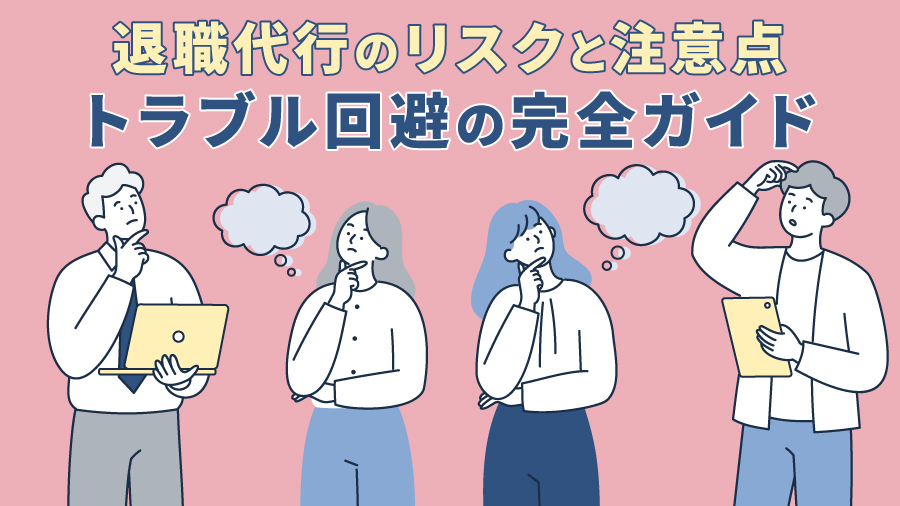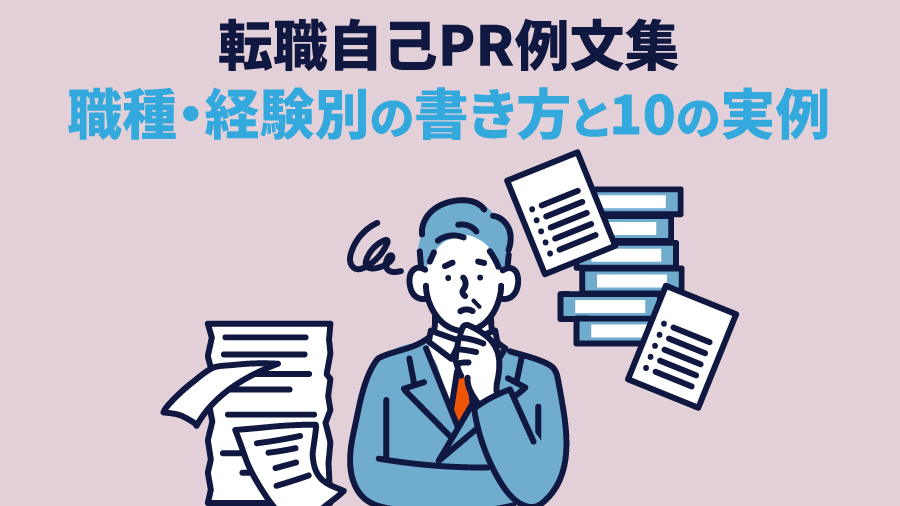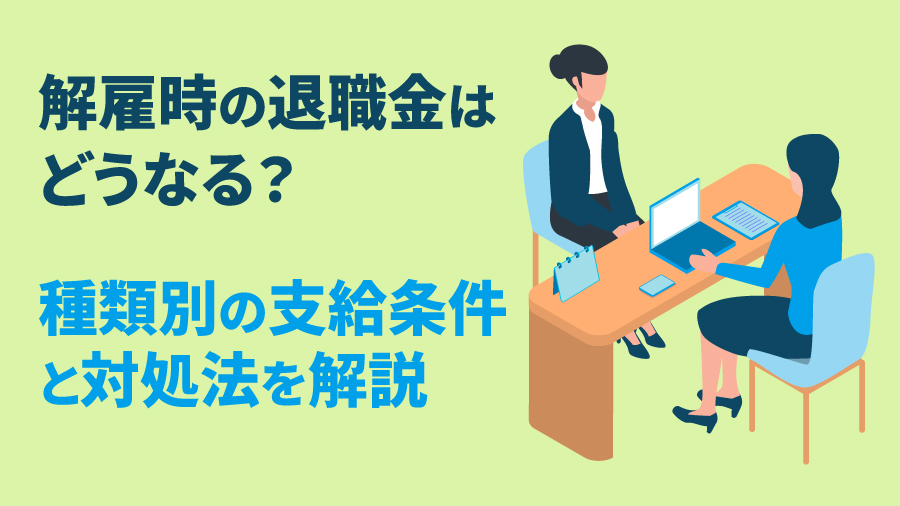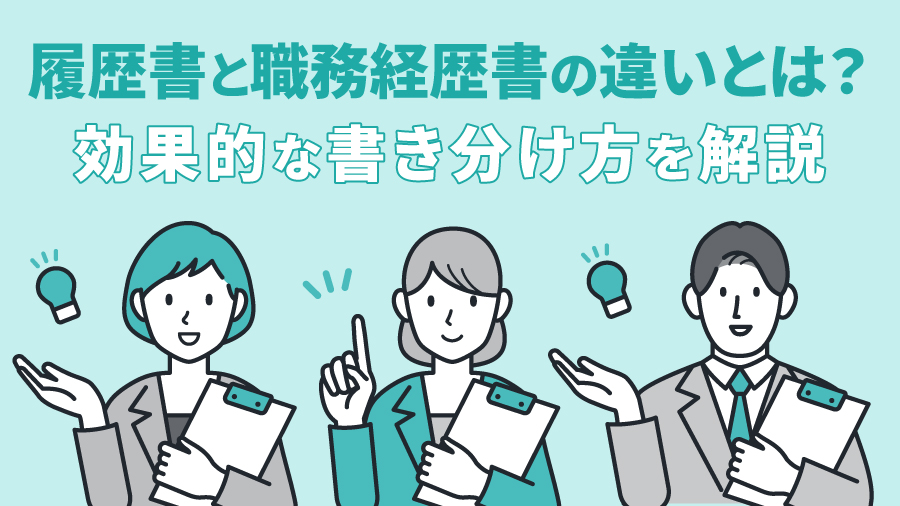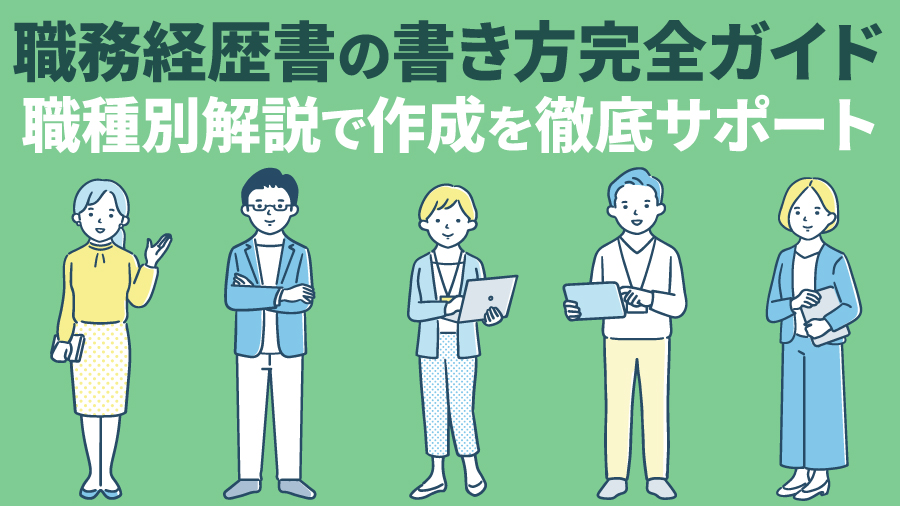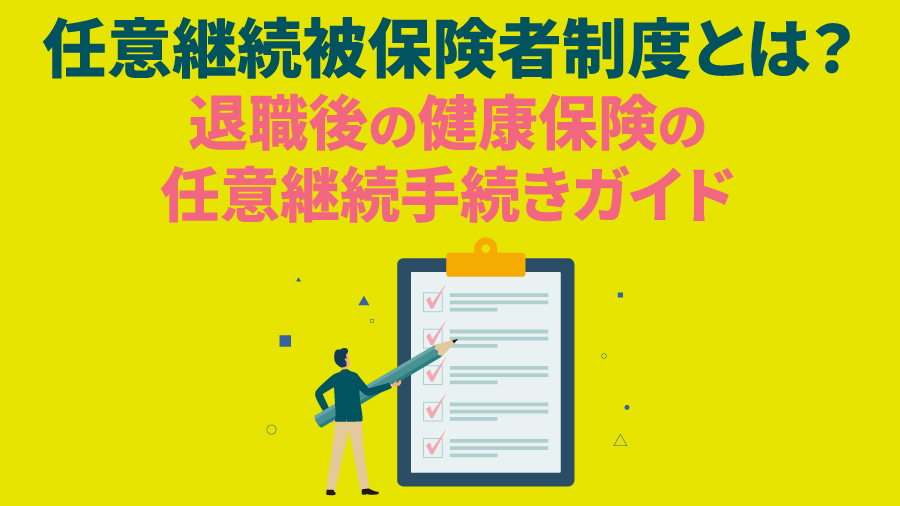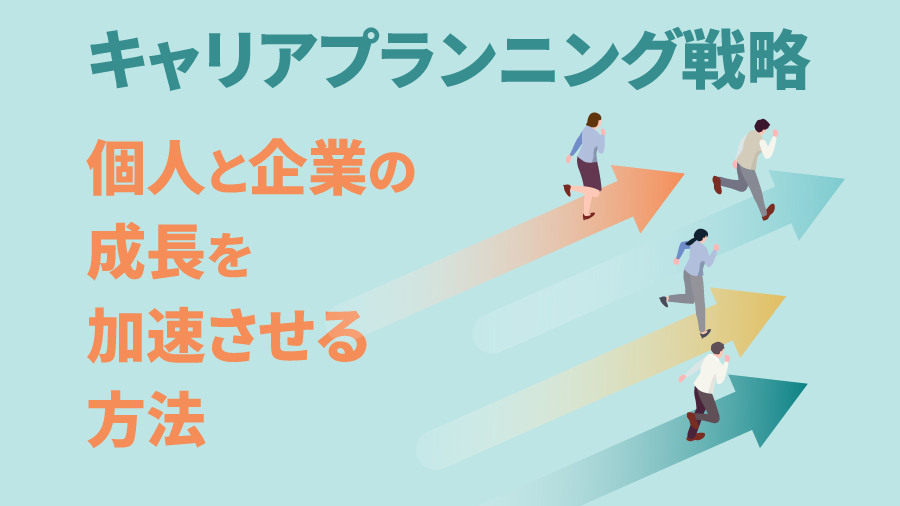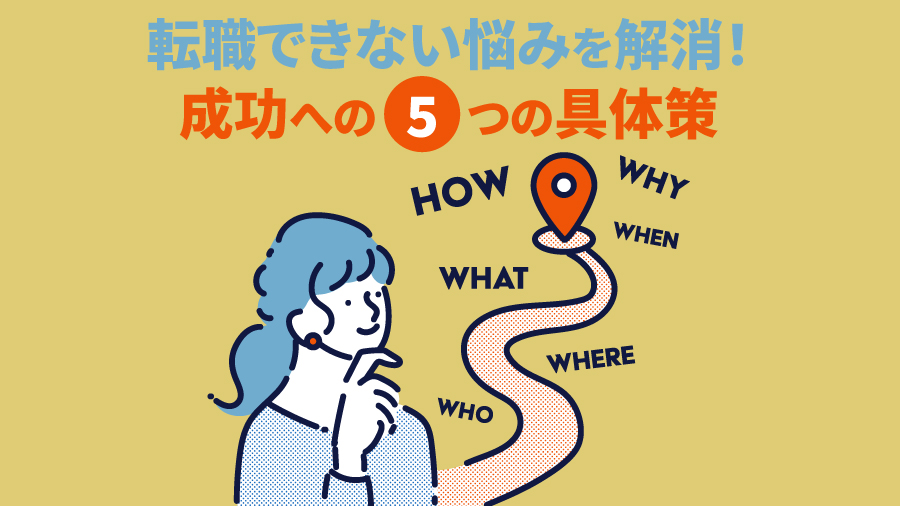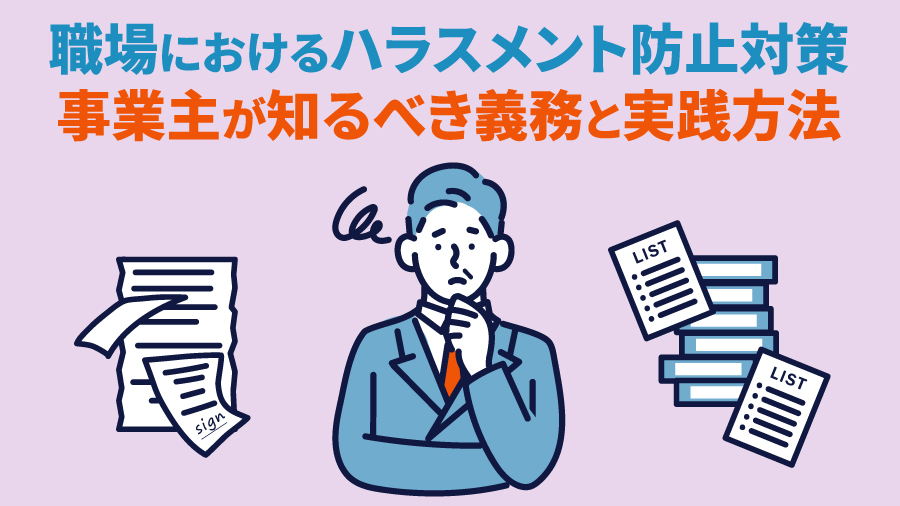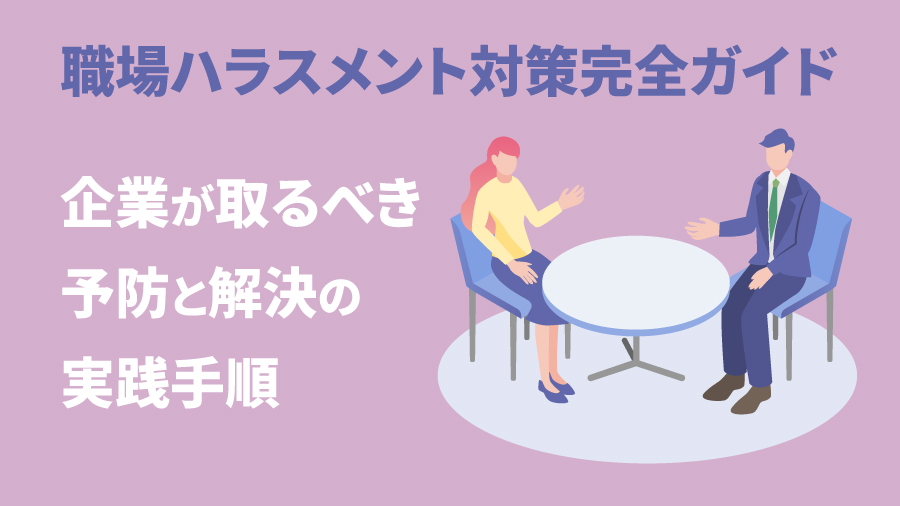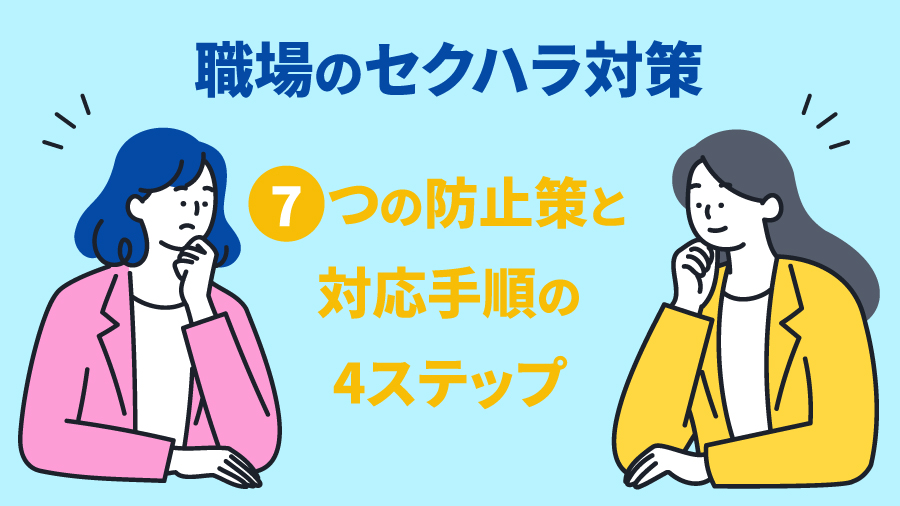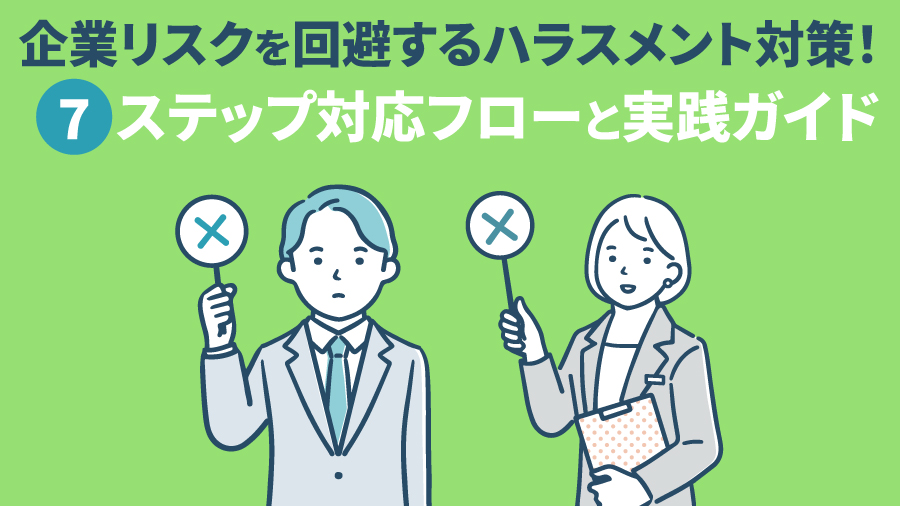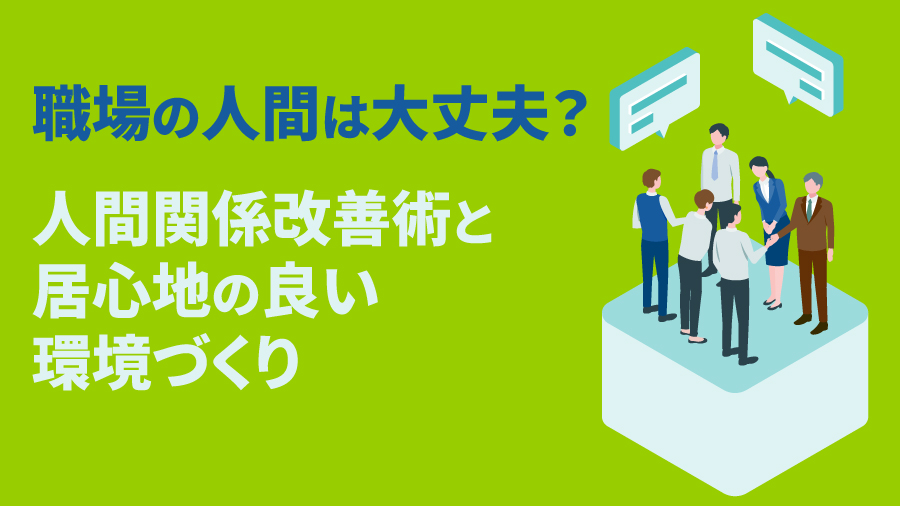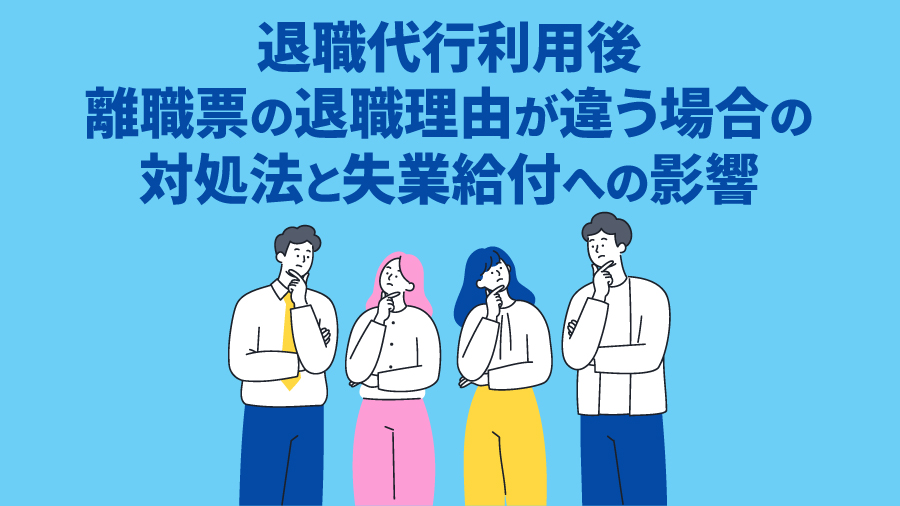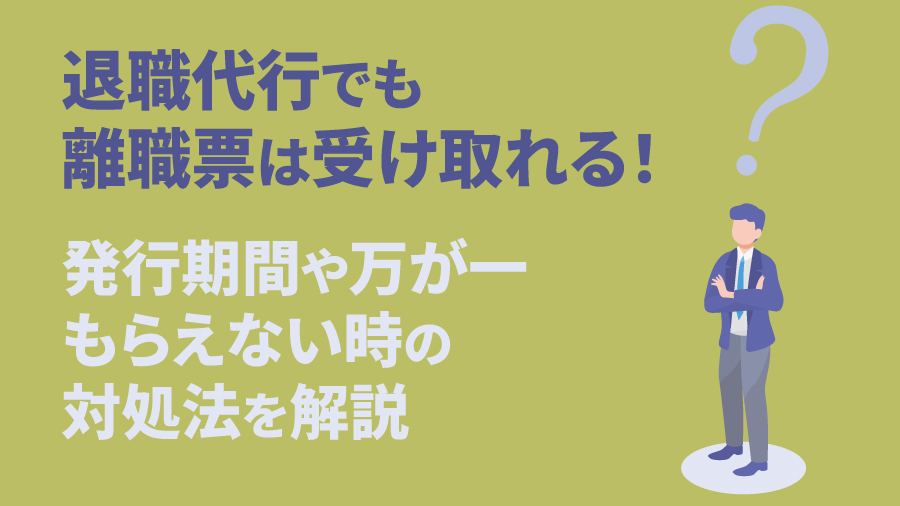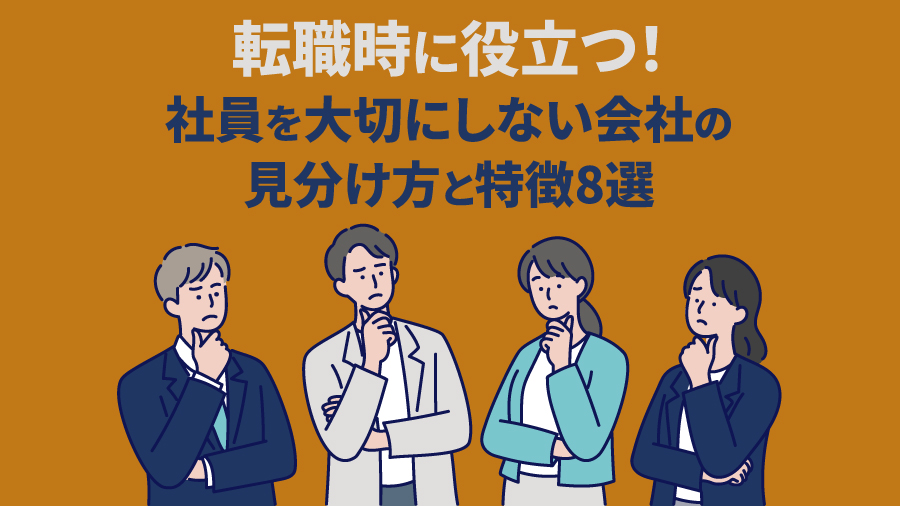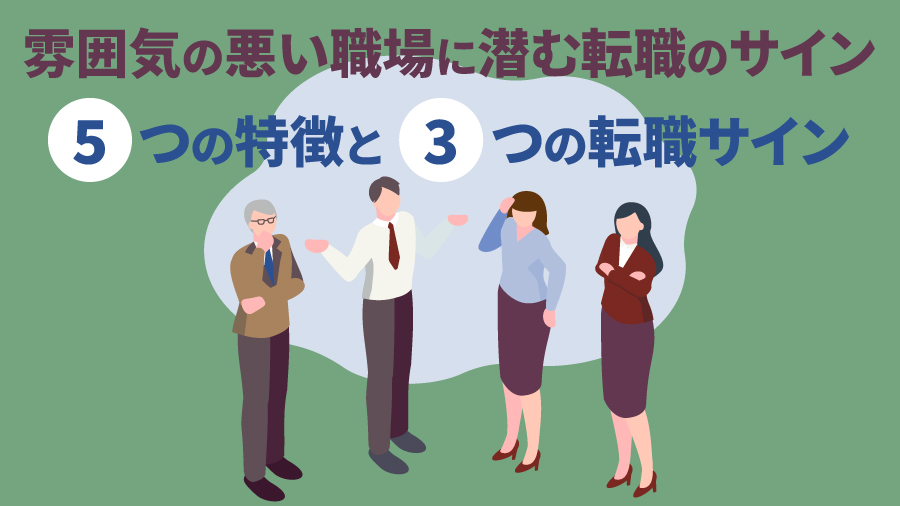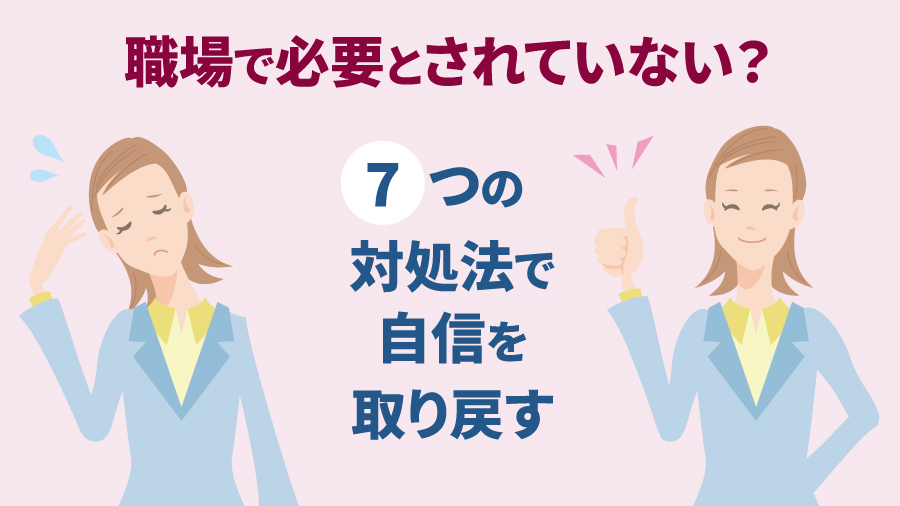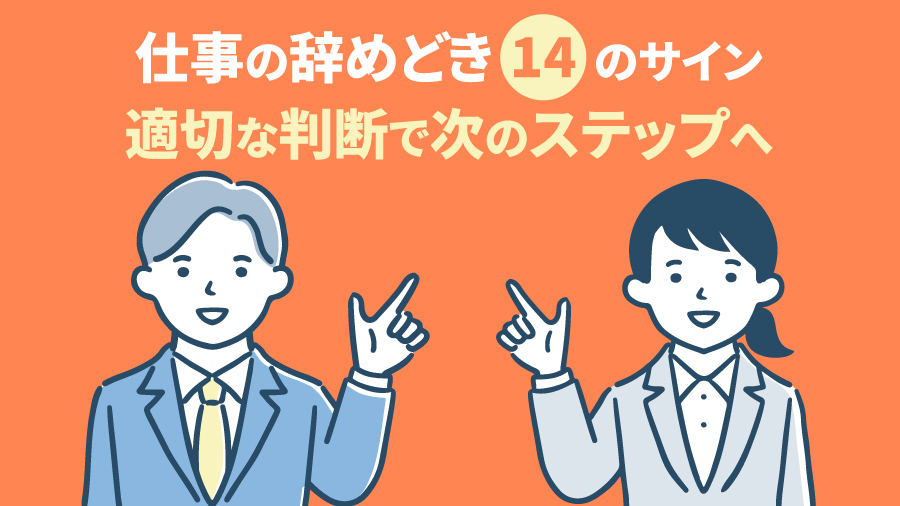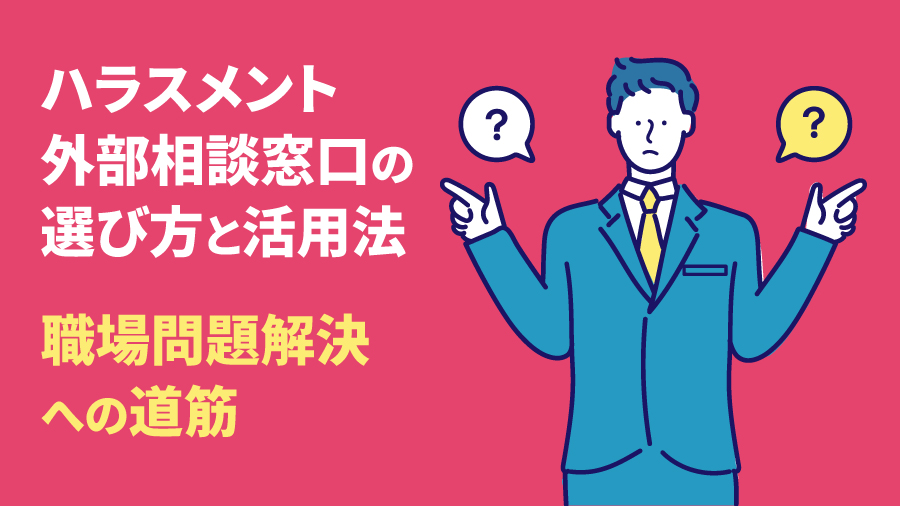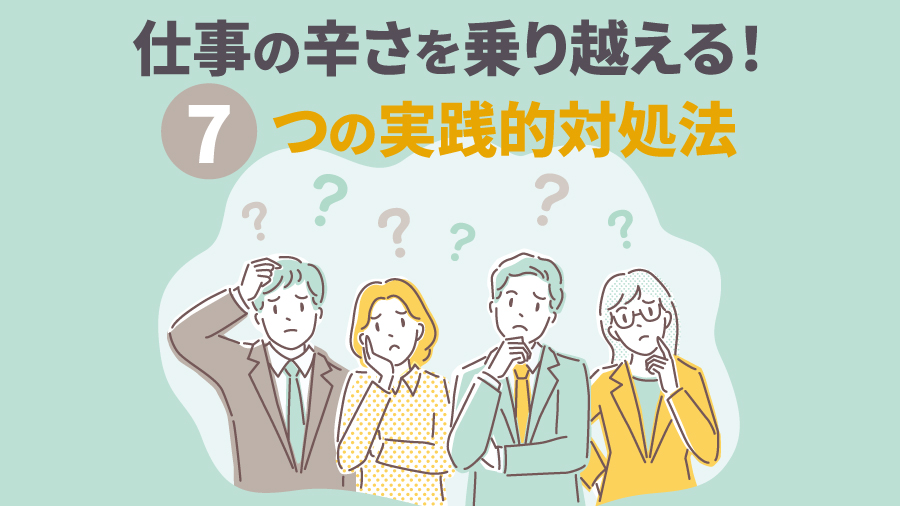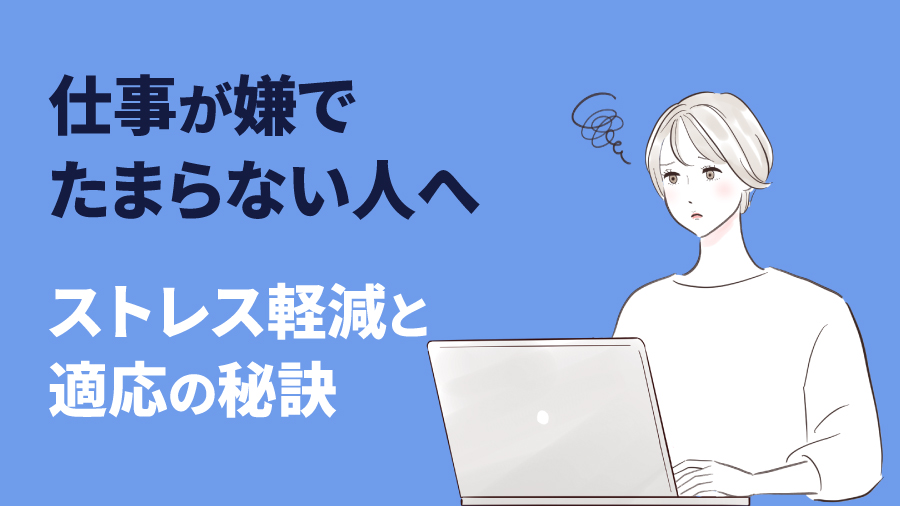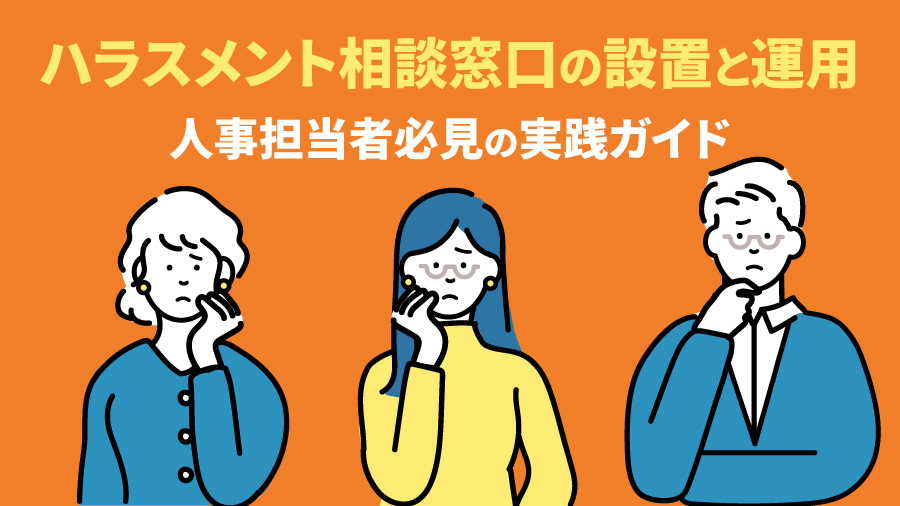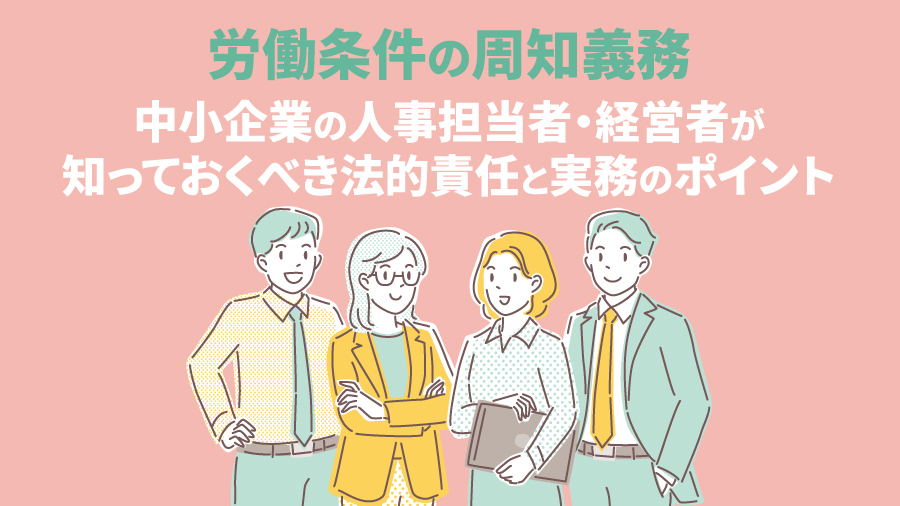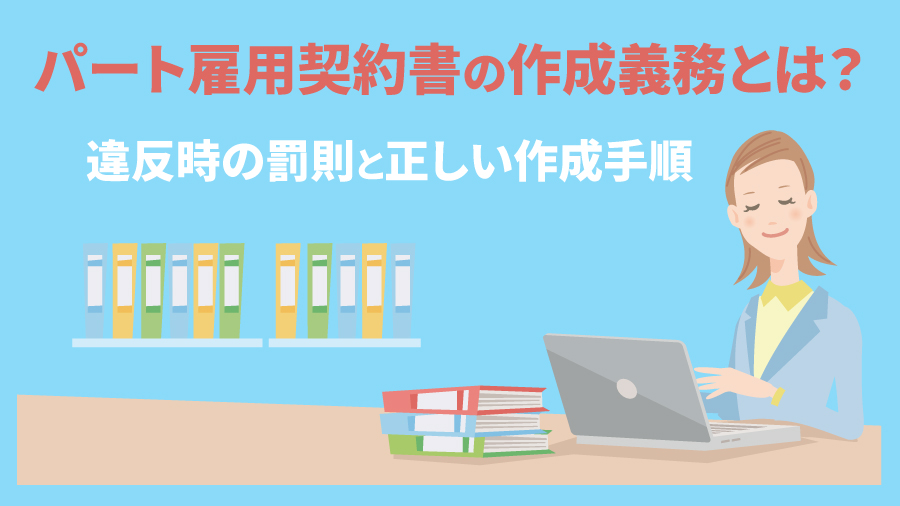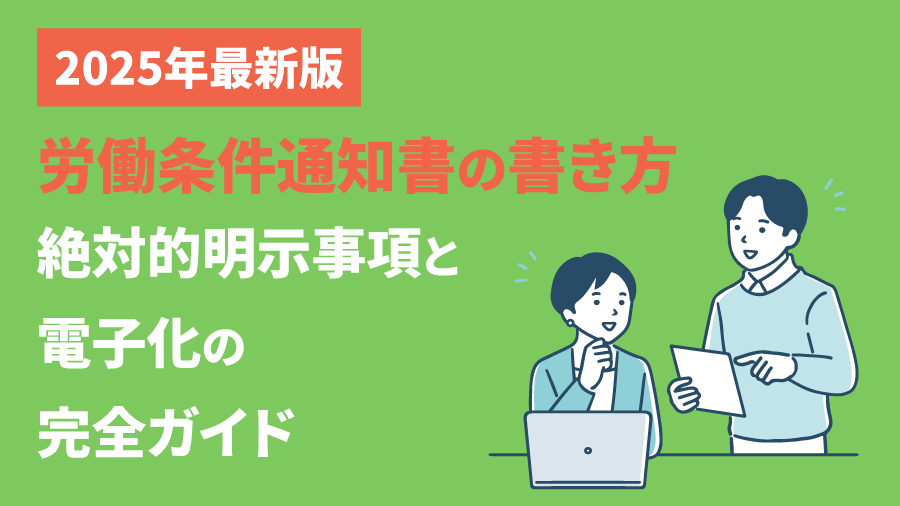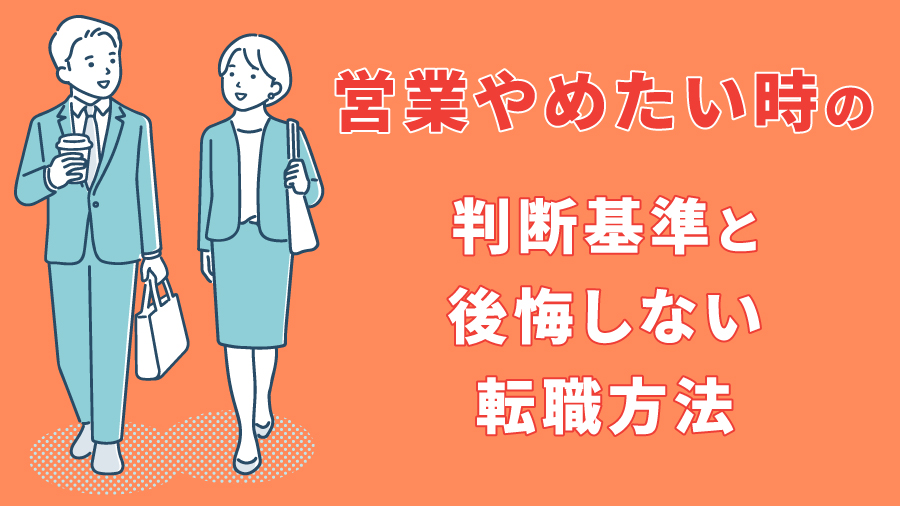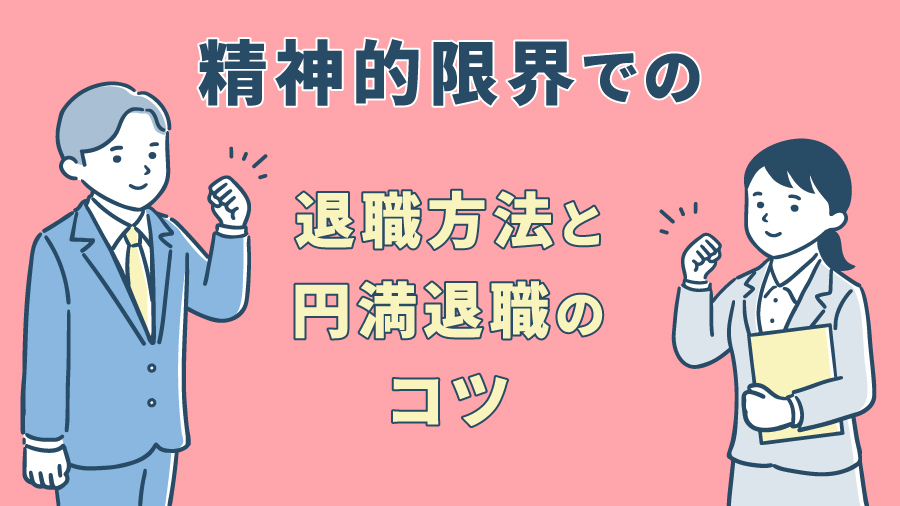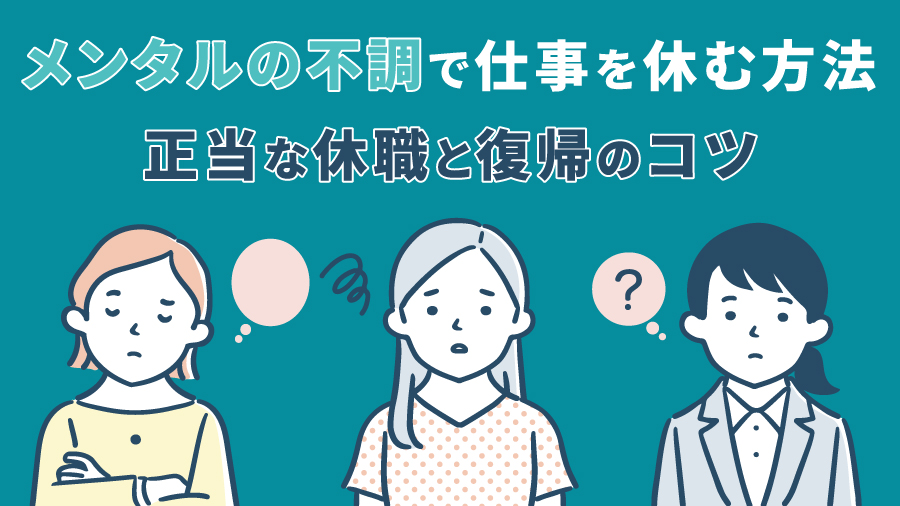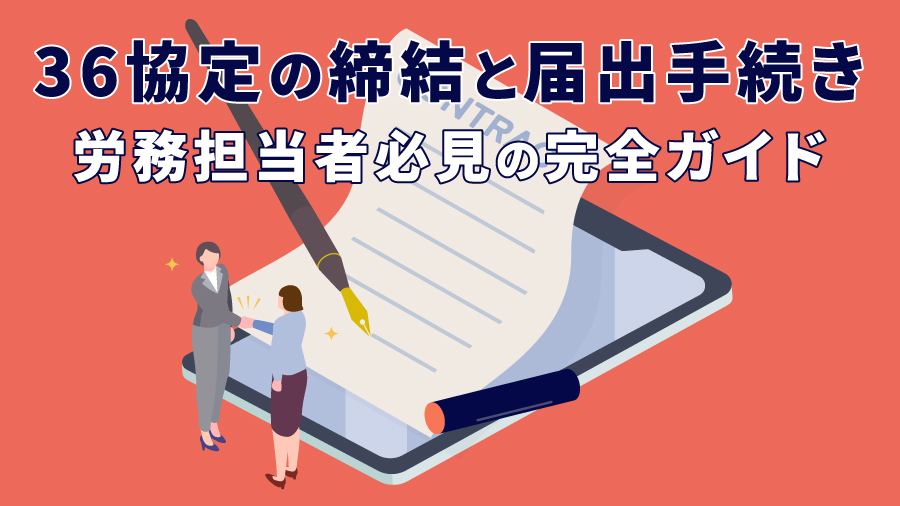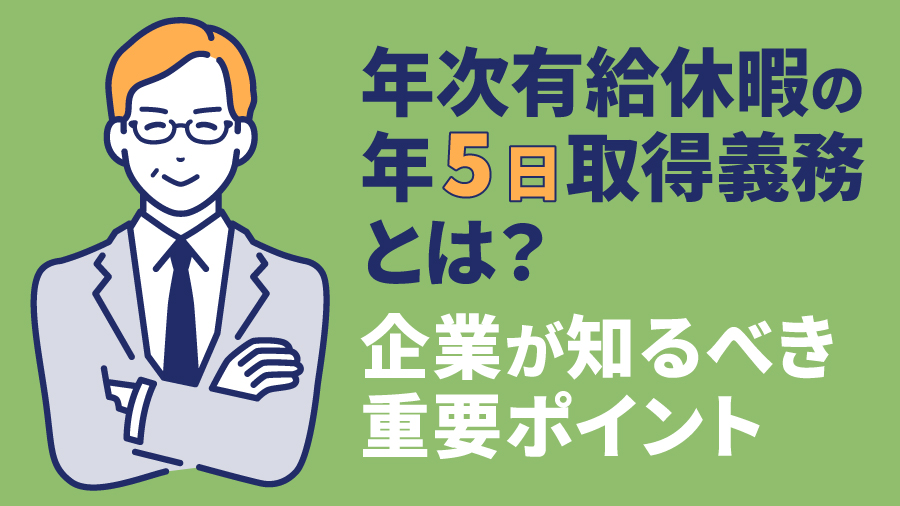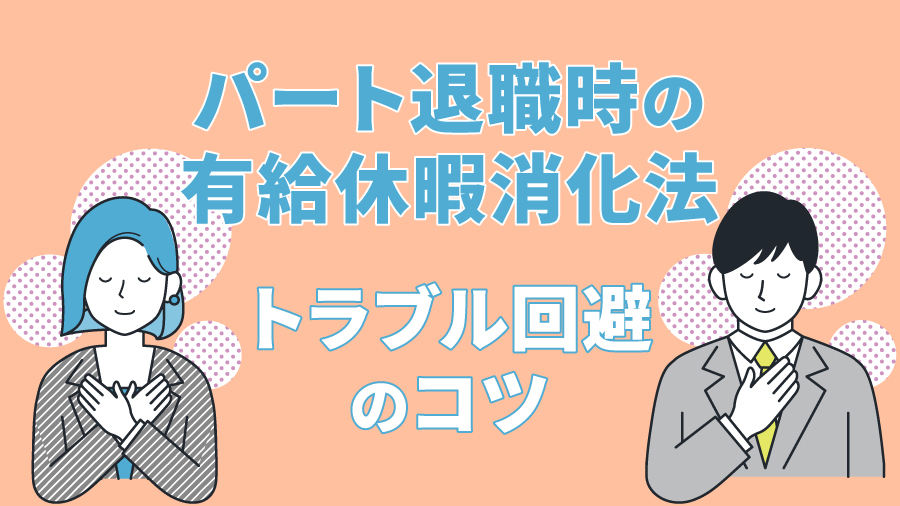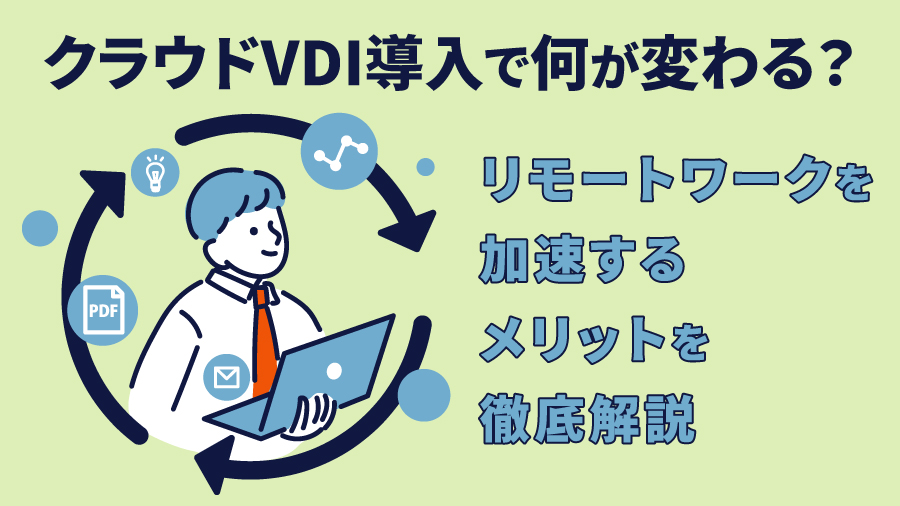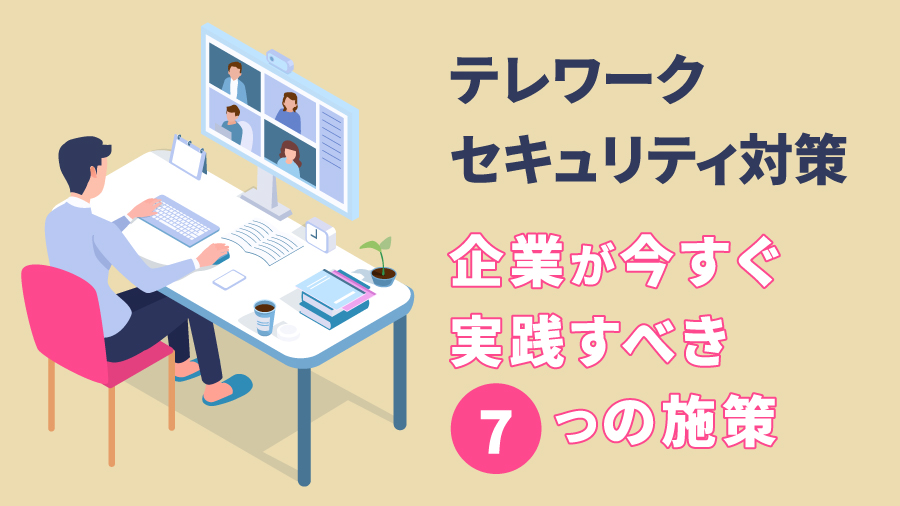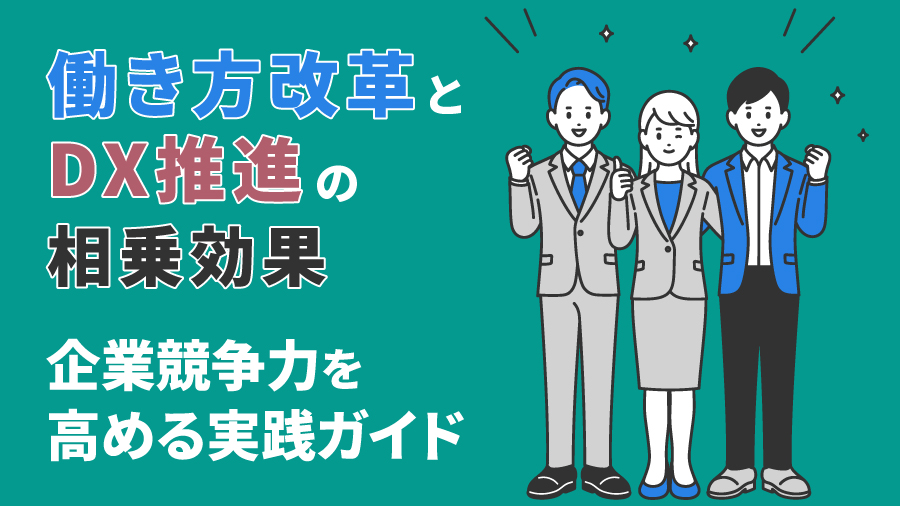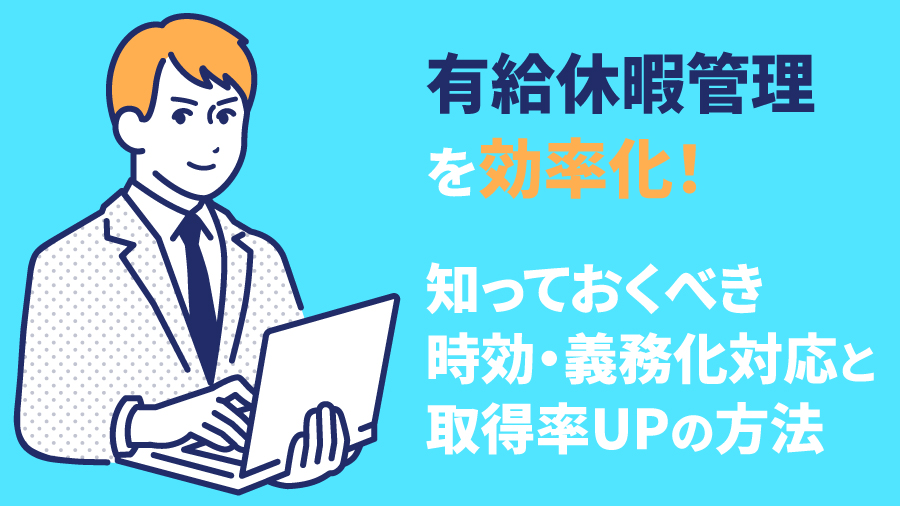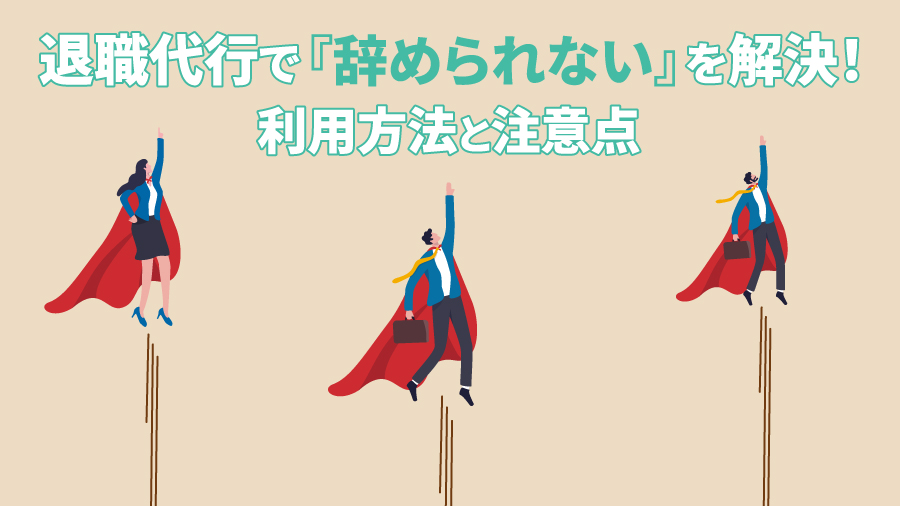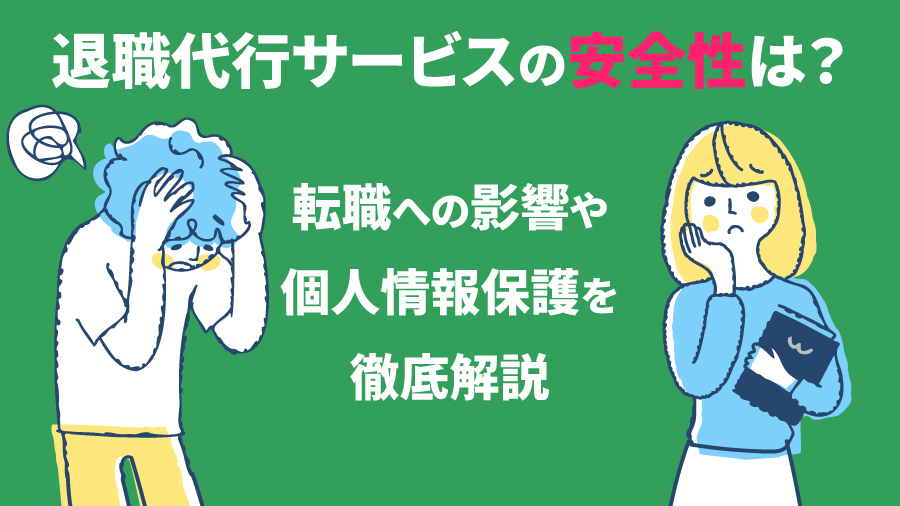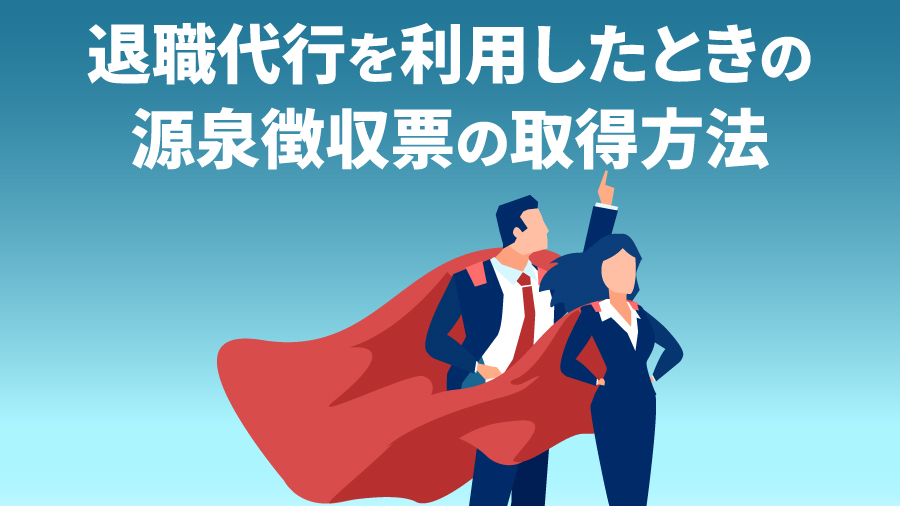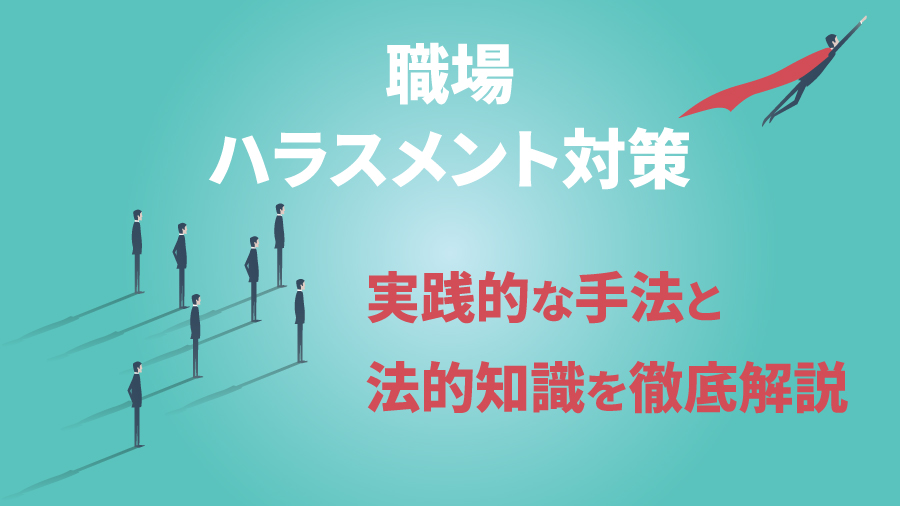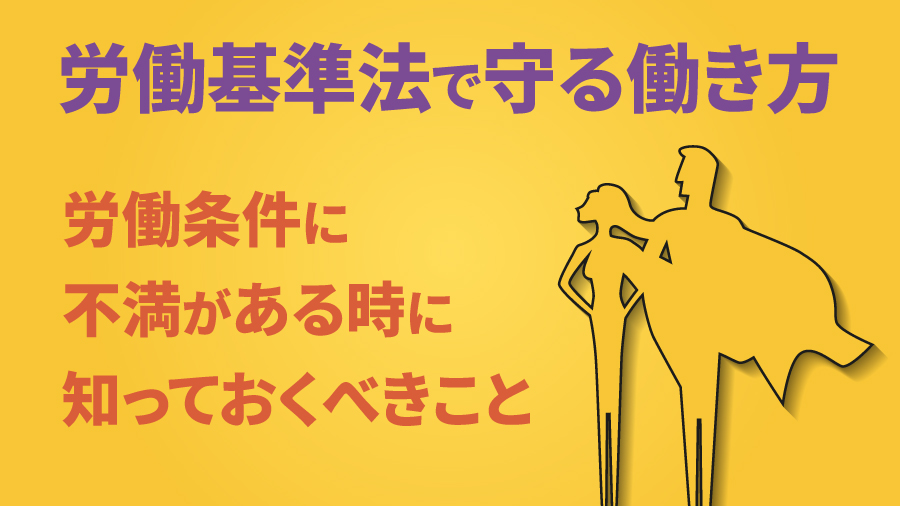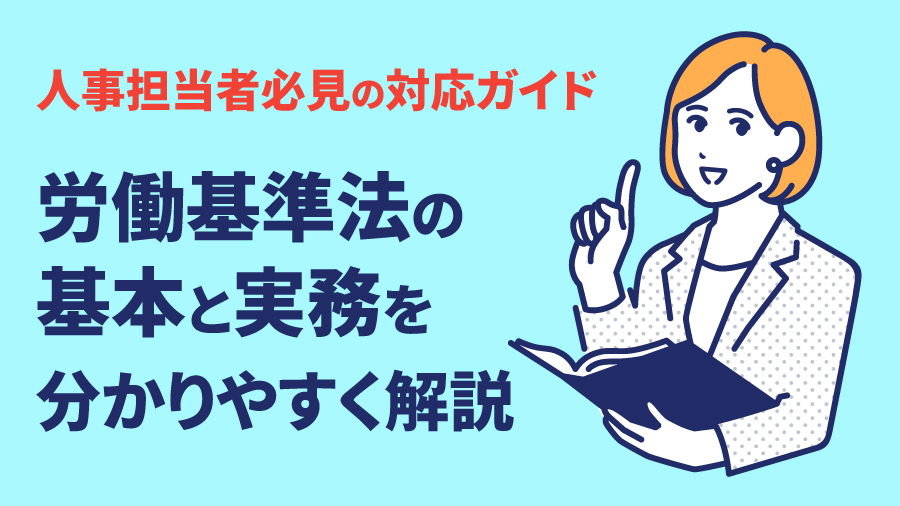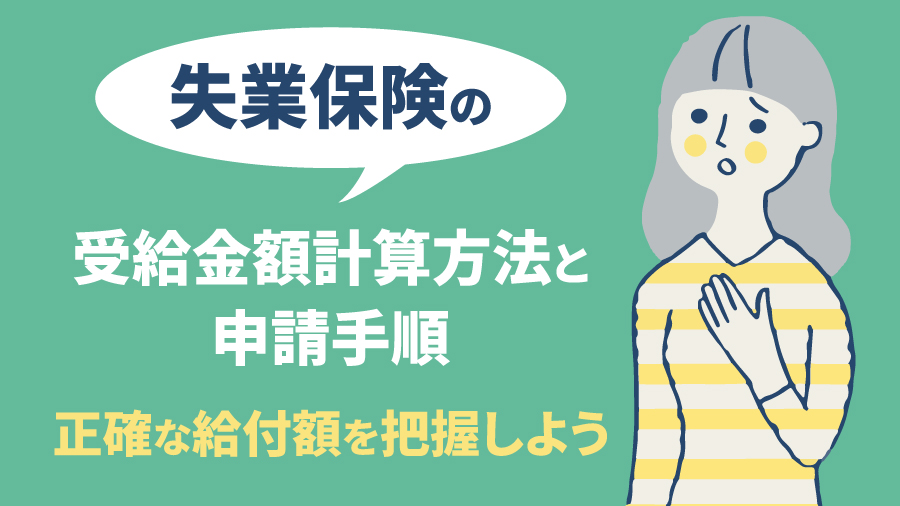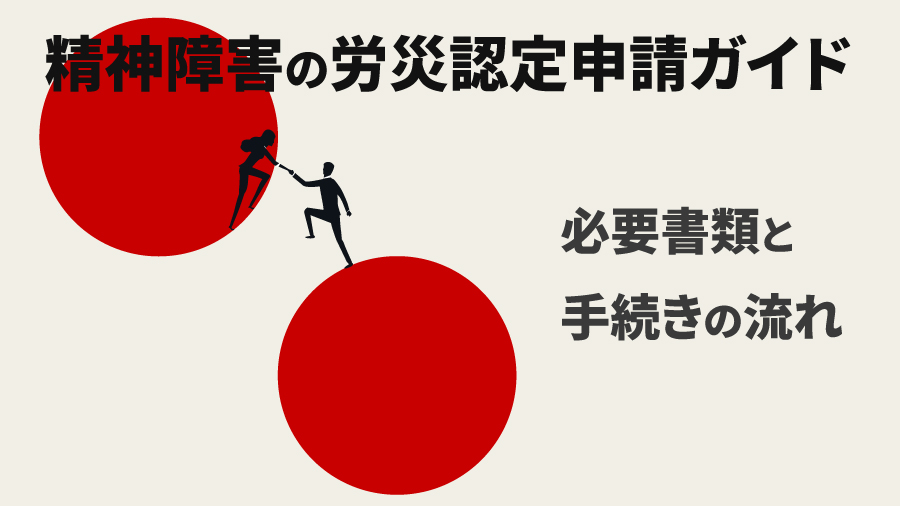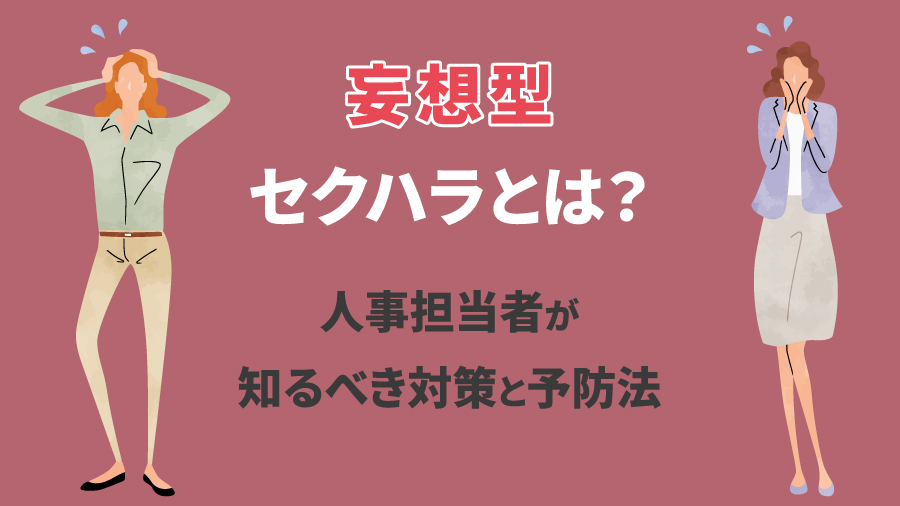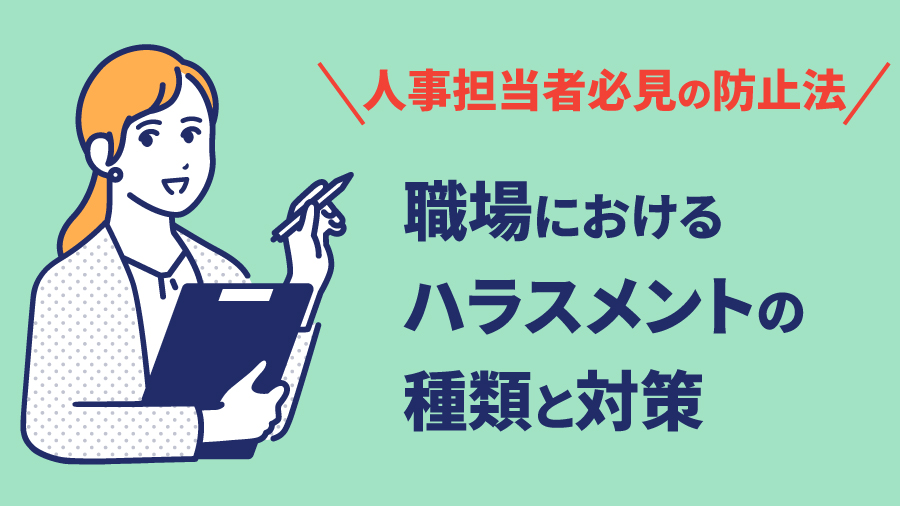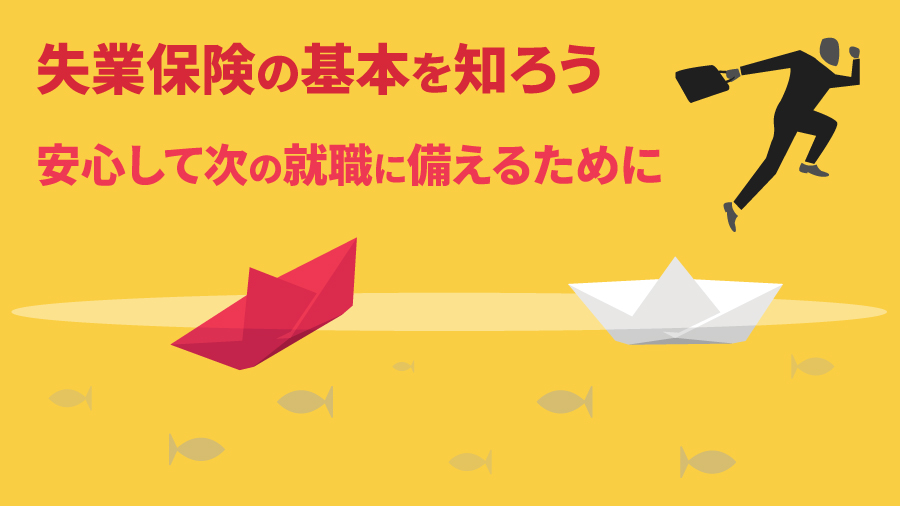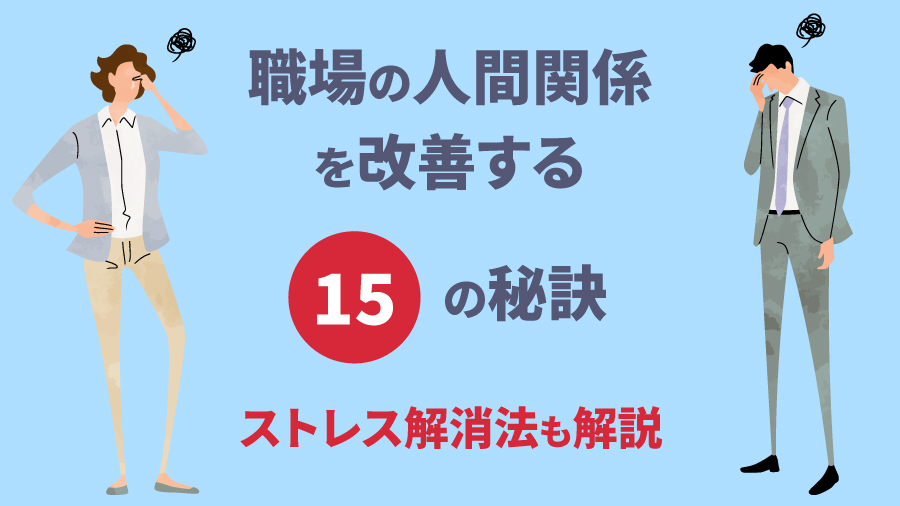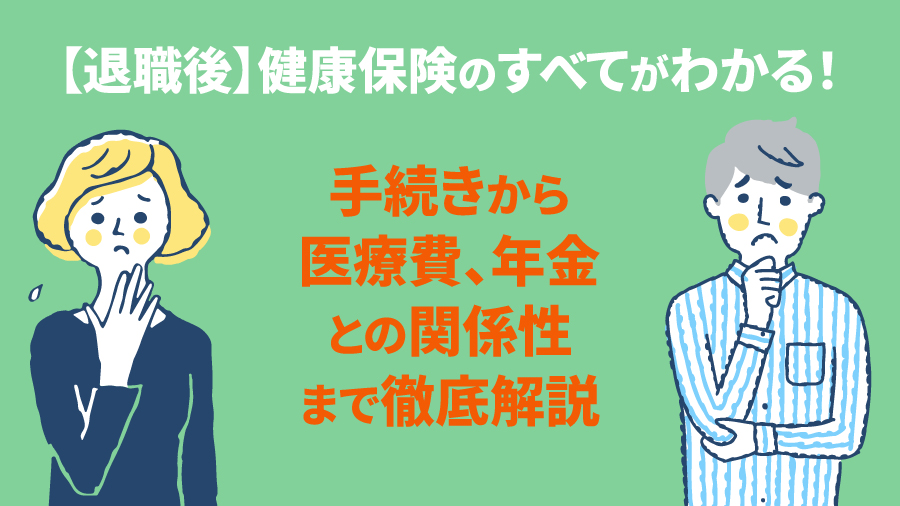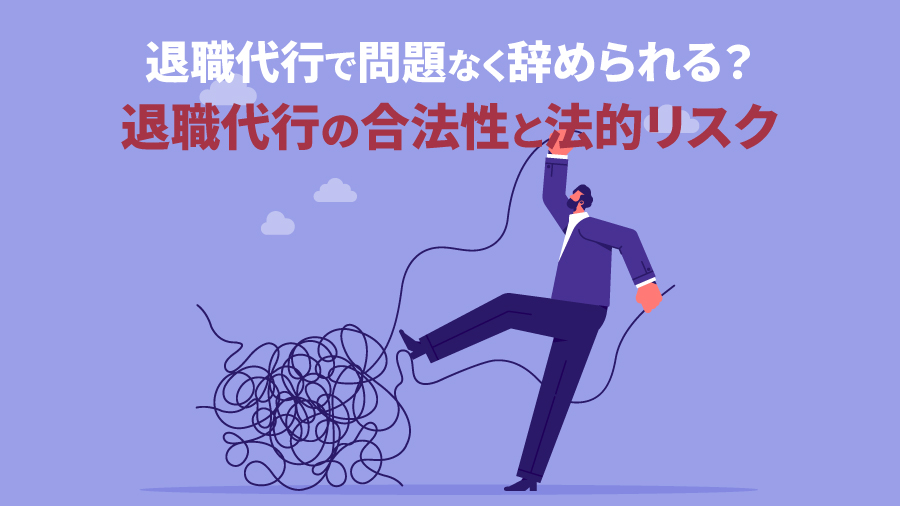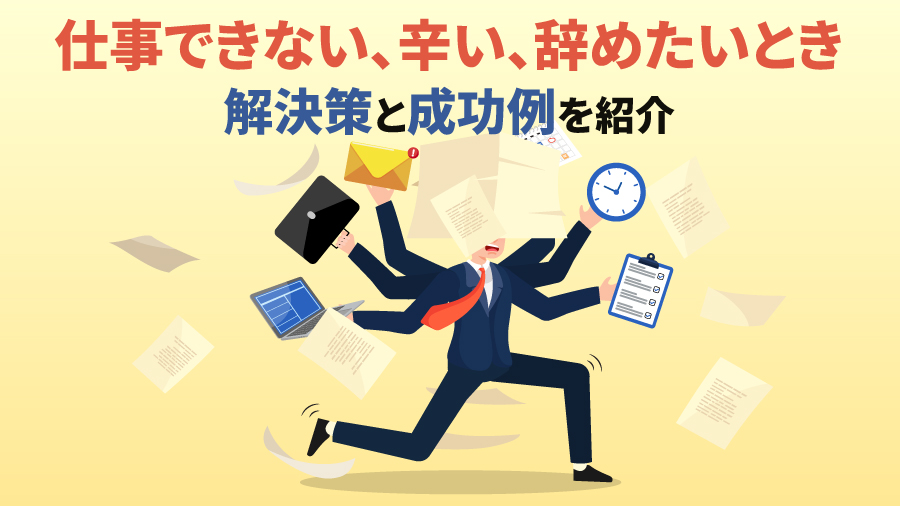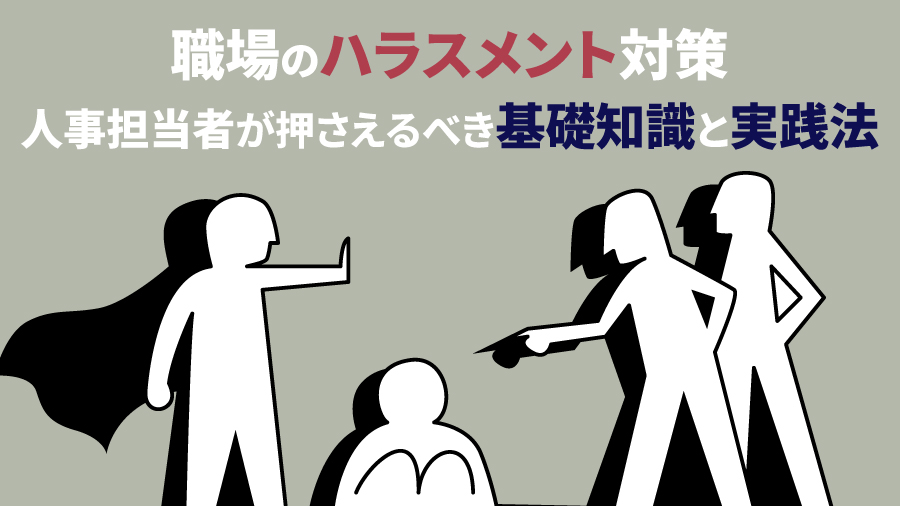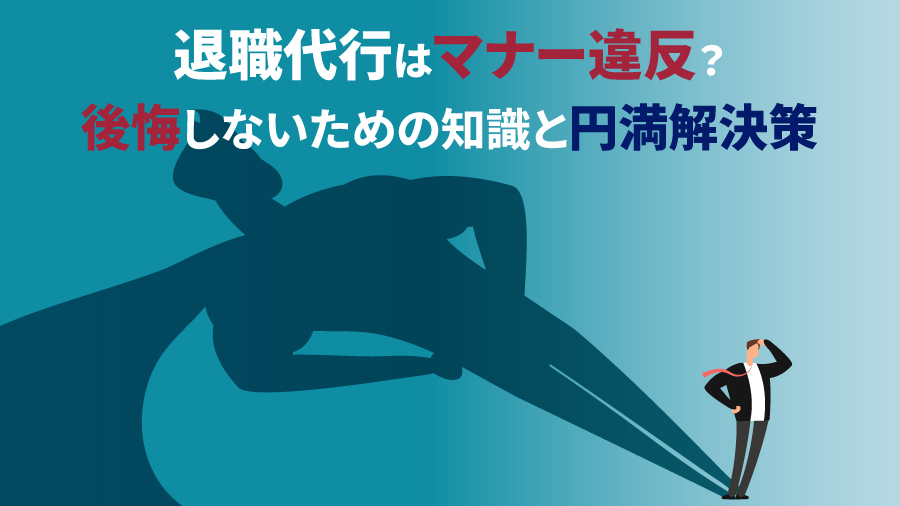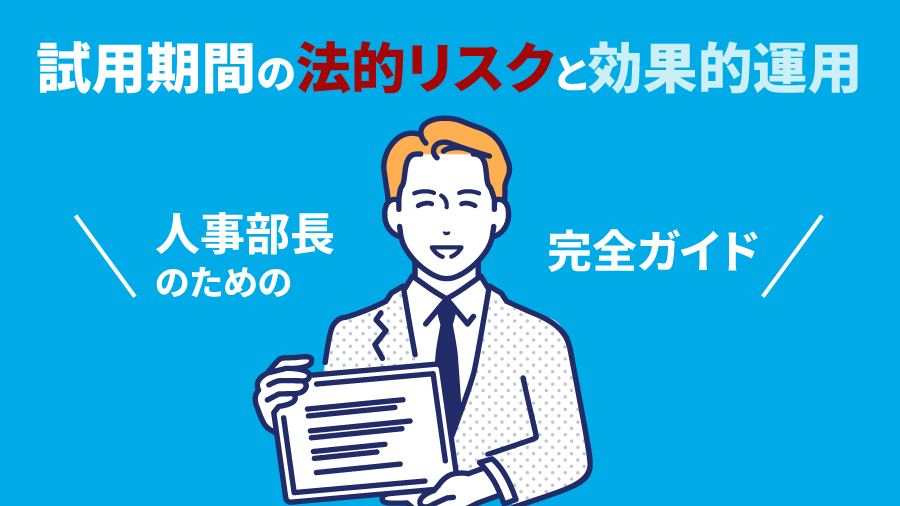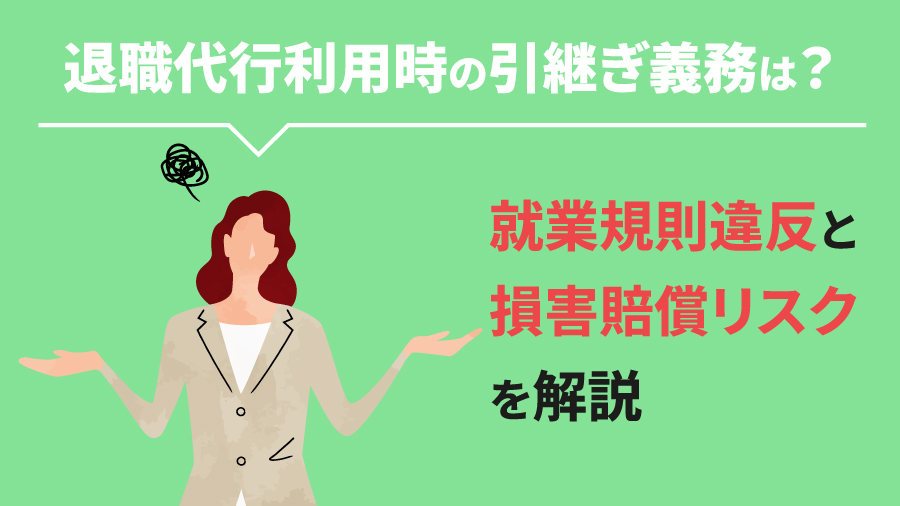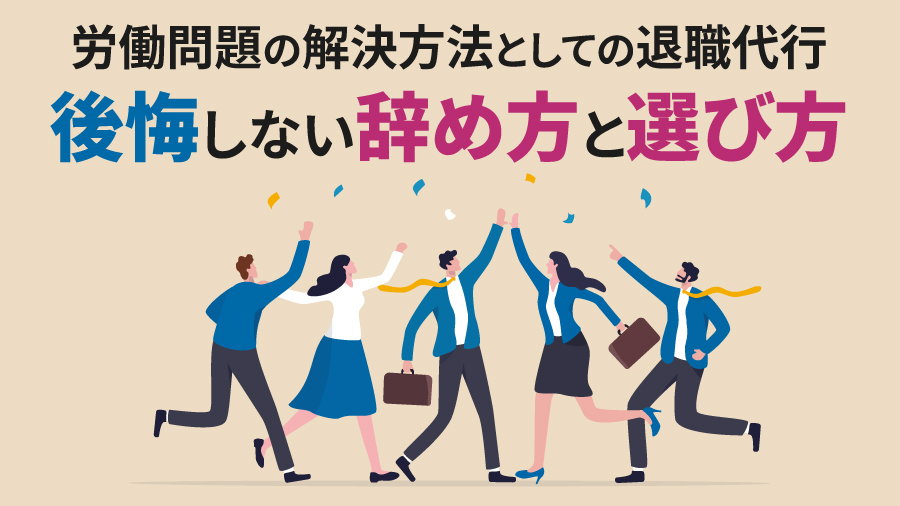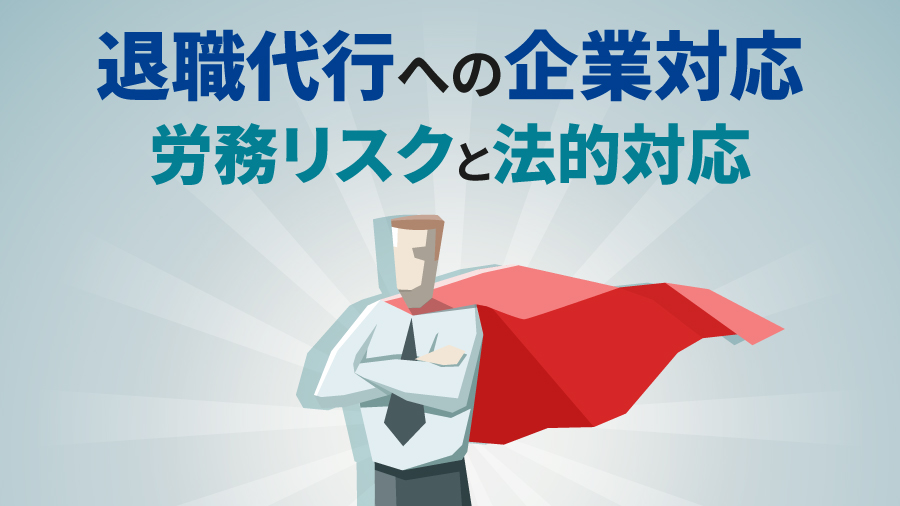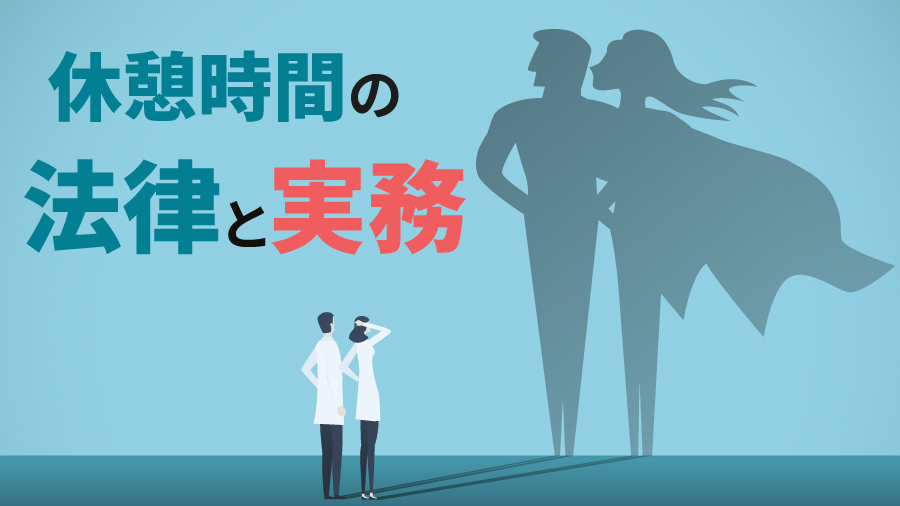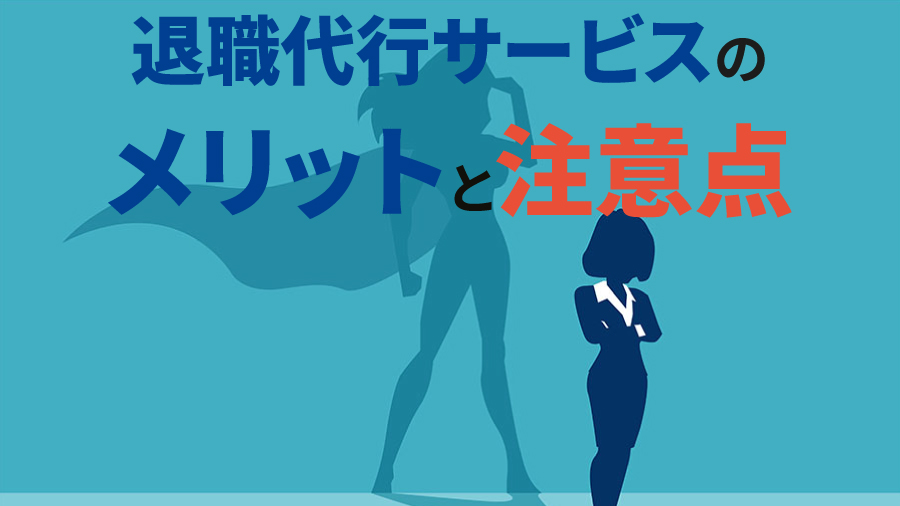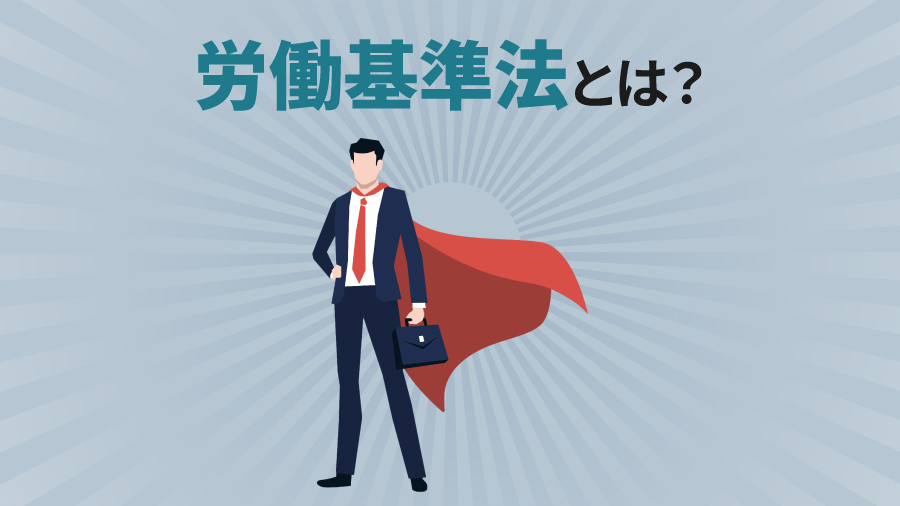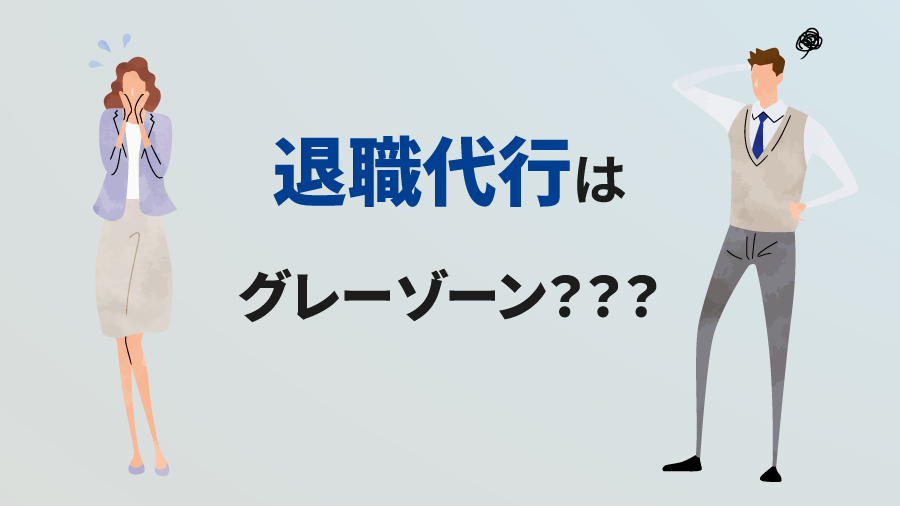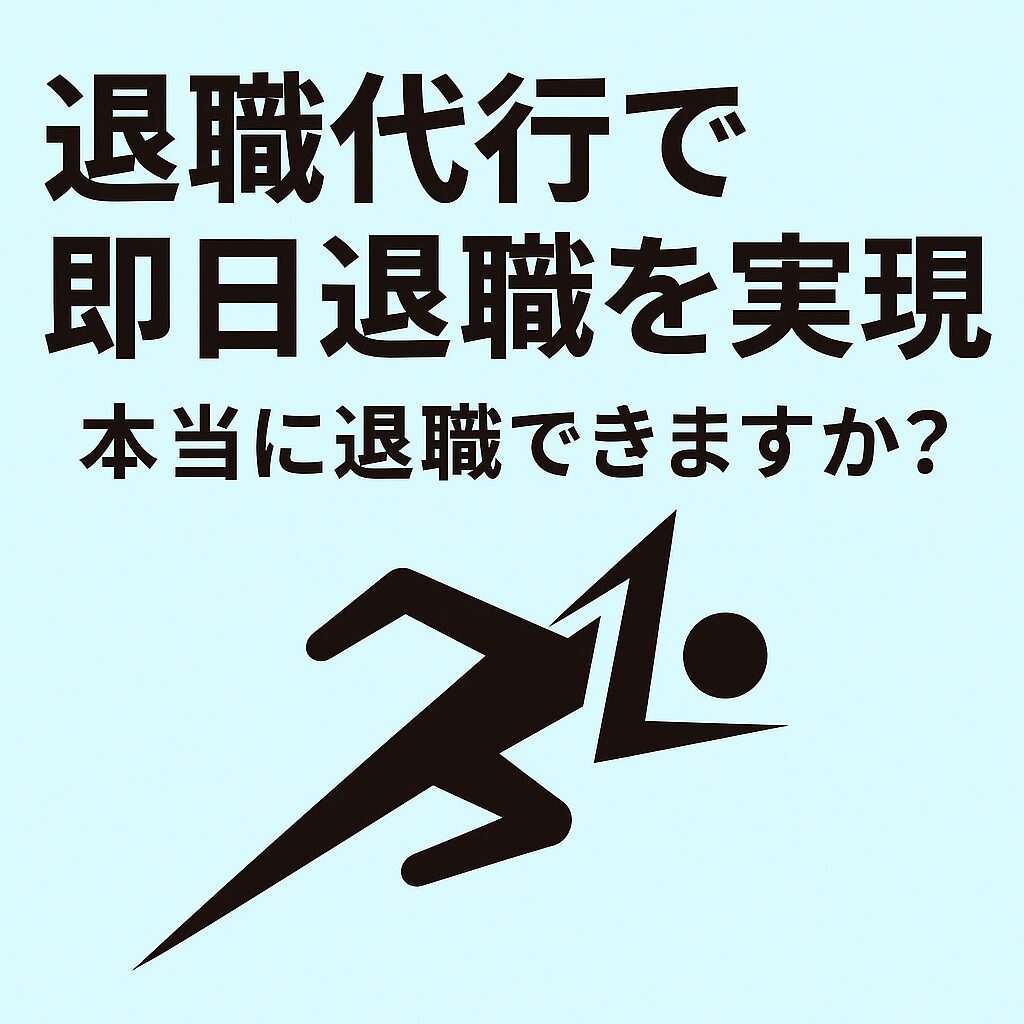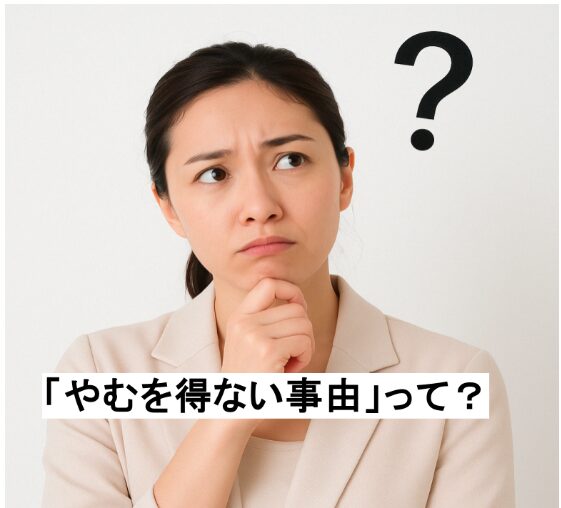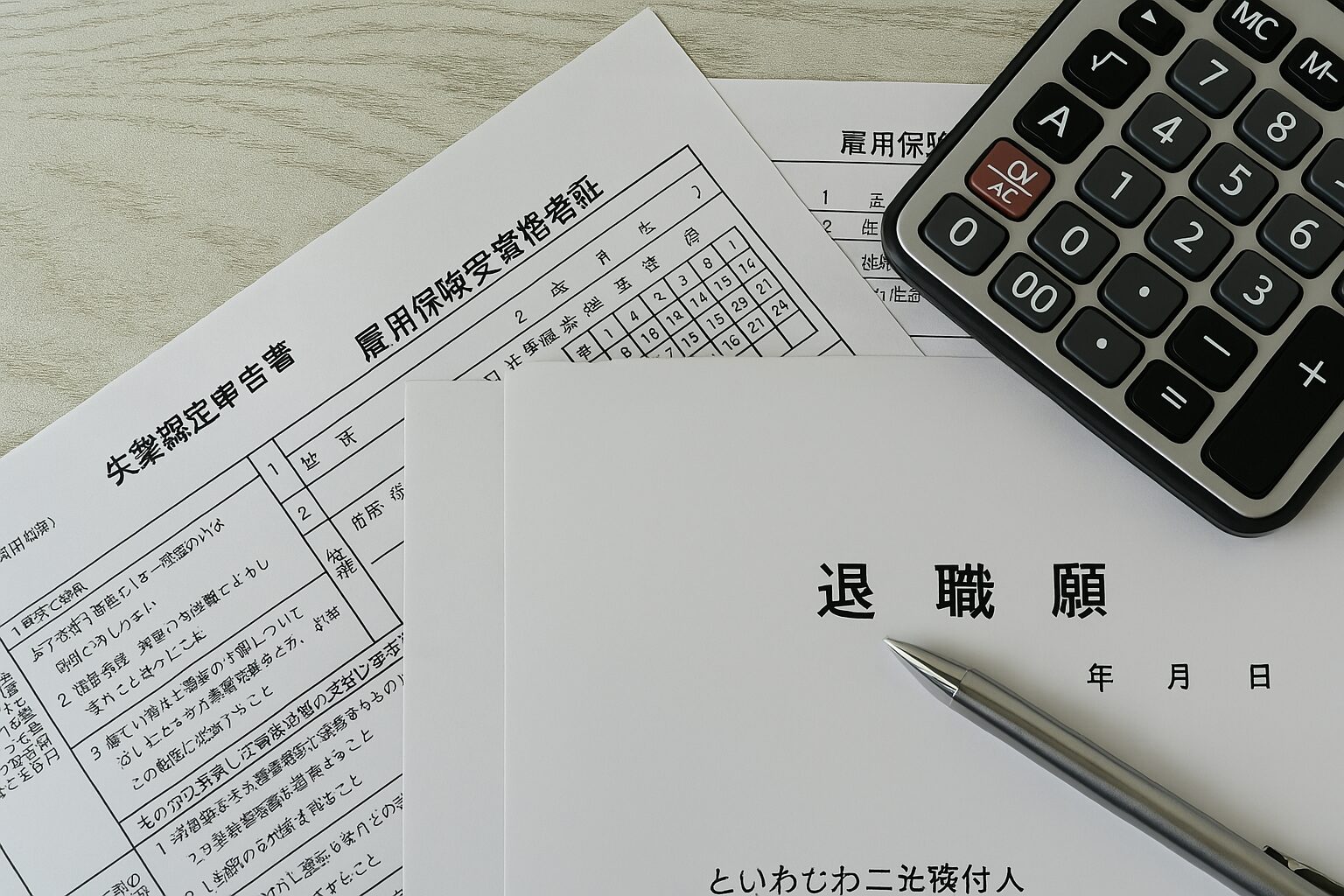-
-
退職代行は甘えじゃない!利用する正当な理由と後悔しないための全知識
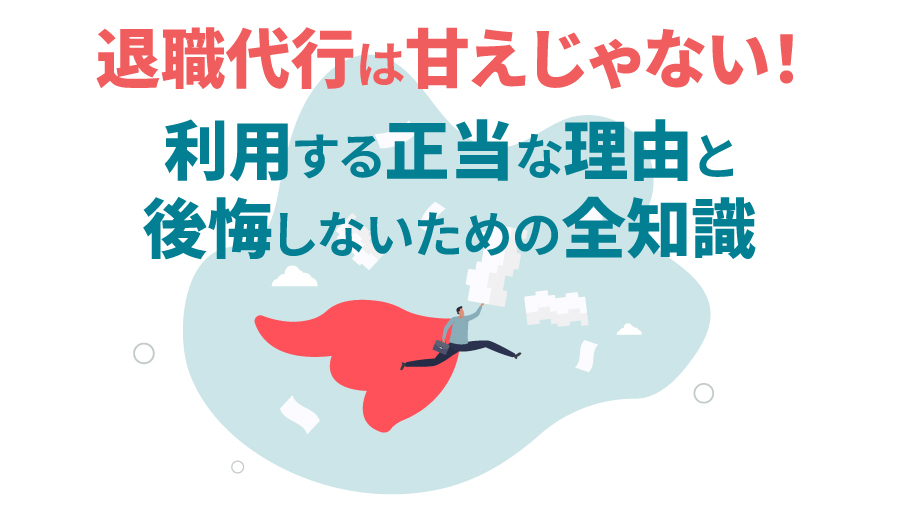
「退職したいけれど、自分で言い出せない…」「退職代行を使うなんて、やっぱり甘えなのかな?」 そんな思いで夜眠れず、スマートフォンで検索を繰り返す日々を過ごしていませんか? 実は、退職代行の利用をためらっている方はあなただけではありません。 「会社に迷惑がかかるかも」「自分で伝えられないのは社会人失格では」——そんな不安と罪悪感を抱えている方は数多くいます。 しかし、それはあなたの責任ではありません。退職代行の利用は、心身を守るための「正当な手段」であり、甘えでも逃げでもないのです。 本記事では、退職代行を利用する正当な理由やメリット・デメリット、実際の体験談、そして罪悪感を和らげる考え方まで、徹底的に解説します
目次退職代行の仕組みと誤解されやすいポイント
退職代行サービスの基本的な流れと役割
退職代行とは、本人に代わって会社へ退職の意思を伝え、退職手続きを進めるサービスです。
利用者が業者に依頼し、業者が会社に連絡することで、本人が直接やり取りせずに退職を進められます。サービス提供者には以下の3種類があります。
- 民間業者(弁護士ではない)
- 労働組合系代行サービス
- 弁護士事務所
法的な交渉(損害賠償請求の対応や未払い賃金の請求など)が必要な場合は、弁護士資格のある業者に依頼する必要があります。
「甘え」「逃げ」という誤解:なぜそう思われがちなのか?
「退職代行は逃げ」「社会人として自分で言えないのは甘え」という批判的な意見を見かけることがあります。しかし、そういった声の多くは、退職代行を必要としない恵まれた環境の中にいる人たちの価値観にすぎません。
退職代行を利用する人は、上司の高圧的な言動やハラスメントにより、精神的に追い詰められた状態にあることが少なくありません。
それは「言えない」のではなく、「言わせてもらえない」「言うと被害を受ける」環境にいるからです。退職代行は合法?法的な位置づけと注意点
退職の意思表示そのものは、労働者の権利として法律で認められています(民法627条)。
つまり、代理人を通じて会社に退職の意思を伝えることも、法的には問題ありません。ただし、退職代行業者が「未払い残業代の交渉」や「損害賠償請求への対応」などを行うと、非弁行為となり違法です。
このため、弁護士でない業者を選ぶ場合は、あくまで「退職の意思の伝達」に限定されているかを確認することが重要です。- 理由1:上司が高圧的・威圧的で退職を言い出せない
- 「辞めたい」と思っても、上司が怖くて言い出せない——これは多くの人が退職代行を考える最初の理由です。
罵倒や理不尽な命令が日常的に繰り返される環境では、退職の申し出すら心身への負担になります。 - 理由2:深刻なハラスメント(パワハラ・セクハラ等)を受けている
- 人格否定や性的発言、無視や嫌がらせなどのハラスメントを受けている場合、もはや職場に「安全」は存在しません。
退職代行は、その環境から速やかに自分を守るための手段となります。 - 理由3:過度な引き止めや脅しにあう可能性がある
- 「辞めたら損害賠償を請求するぞ」「お前のせいで業務が回らない」など、強い引き止めや脅しがある職場では、自力での退職は難航します。
第三者が介入することで、冷静にかつ安全に退職を進められます。 - 理由4:心身の不調で、直接交渉する気力がない
- うつ症状、不眠、食欲不振など、ストレスによって体調を崩している場合、自ら交渉することがさらに悪化を招くこともあります。
退職代行は、そんな方にとって「最後の気力を使わずに済む」手段です。 - 理由5:会社や上司との関係性が極度に悪化している
- 感情的なやり取りや、信頼関係の崩壊などにより、直接のコミュニケーションが成り立たない場合もあります。
代行を通すことで、トラブルを避けた円満な退職が可能になります。 - 理由6:人手不足を理由に退職を不当に拒否される懸念がある
- 「今は辞められない」「後任が決まるまで残れ」など、人手不足を理由に退職を断られるケースもありますが、法律上、これは通用しません。
- 理由7:そもそも会社側とまともに話し合える状況ではない
- 組織としてのガバナンスが崩れていたり、暴言や暴力が常態化している職場では、もはや話し合いでは解決しません。
- 理由8:「自分で言えない」のではなく「言わせてくれない」環境
- 退職の意思を伝えようとしても遮られたり、話を聞こうとしない環境では、もはや退職代行しか道が残されていないという状況も珍しくありません。
退職代行を利用するメリットとデメリット【客観的比較】
- メリット1
- 会社と直接連絡を取らずに済む精神的負担の軽減
- メリット2
- 即日退職や有給消化の交渉を任せられる可能性
- メリット3
- 退職に関する知識がなくても専門家が代行してくれる安心感
- メリット4
- 引き止めやハラスメントから解放される
- デメリット1
- 費用がかかる(相場は2万円〜5万円)
- デメリット2
- 業者選びを間違えるとトラブルの可能性も
- デメリット3
- 一部の会社や同僚からネガティブな印象を持たれる可能性
- デメリット4
- 直接感謝を伝えたい相手に伝えられない可能性
退職代行を使った人のリアルな声と体験談
- 「利用して良かった」と感じるポジティブな体験談
- 「退職を言えずに2年間悩み続けていましたが、退職代行のおかげでようやく一歩踏み出せました。もっと早く知っていれば…」(30代女性・事務職)
- 「少し後悔した」「こうすれば良かった」という体験談と教訓
- 「業者選びを甘く見て後悔しました。結果的に辞められたけど、対応が遅くて不安な時間が長かった…」(20代男性・営業職)
- 退職代行利用後のキャリアや生活の変化
- 多くの利用者が「心が軽くなった」「新しい仕事で自分らしく働けている」と語っています。
精神的・身体的な健康を取り戻したという声も多数あります。
もう悩まない!退職代行利用への罪悪感を解消する方法

- 「会社に迷惑をかける」という考え方への対処法
- 労働契約は対等な契約関係です。労働者が辞める自由も法律で保障されています。
会社の都合よりも、自分の健康と人生を優先して問題ありません。 - 自分の心と体の健康を最優先に考えることの重要性
- 自分を守れるのは自分だけです。限界を超える前に、助けを借りることはむしろ賢明な判断です。
- 退職は労働者の権利であるという事実の再確認
- 退職の意思表示をした時点で、原則として2週間後には退職できます(民法627条)。
「辞めさせない」は通用しません。 - 「逃げ」ではなく「戦略的撤退」と捉える視点
- 戦い続けることだけが正解ではありません。自分を守り、新たな場所で力を発揮するための撤退は、立派な「戦略」です。
FAQ:退職代行に関するよくある質問と回答
- 退職代行を利用したら、会社から訴えられたりしませんか?
- 正当な退職の意思表示であれば、訴えられることはほぼありません。
- 退職代行を使っても、離職票や源泉徴収票はもらえますか?
- はい、法律に基づき会社は発行する義務があります。
- 退職代行業者を選ぶ際のポイントは何ですか?
- 法的対応の可否、料金体系の明確さ、実績や口コミを確認しましょう。
- 費用はどれくらいかかりますか?相場は?
- 平均で2万円〜5万円程度。労働組合系はやや安価、弁護士系は高めです。
- 親や家族にバレずに利用できますか?
- 業者によっては家族宛の連絡配慮も可能。申し込み時に確認を。
まとめ:退職代行はあなたの未来を守るための選択肢の一つ
退職代行の利用は、決して「甘え」ではありません。
むしろ、自分の人生と健康を守るために必要な、正当かつ戦略的な判断です。あなたが今、罪悪感や不安で苦しんでいるなら、まずは「辞めたい」という自分の気持ちを肯定してください。
退職は「新しい自分」へのスタートです。
安心して、次の一歩を踏み出していきましょう。
-