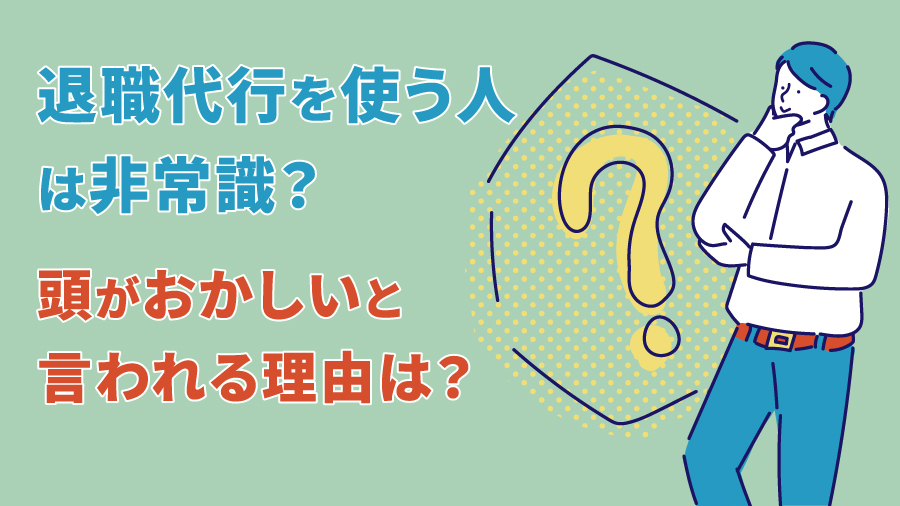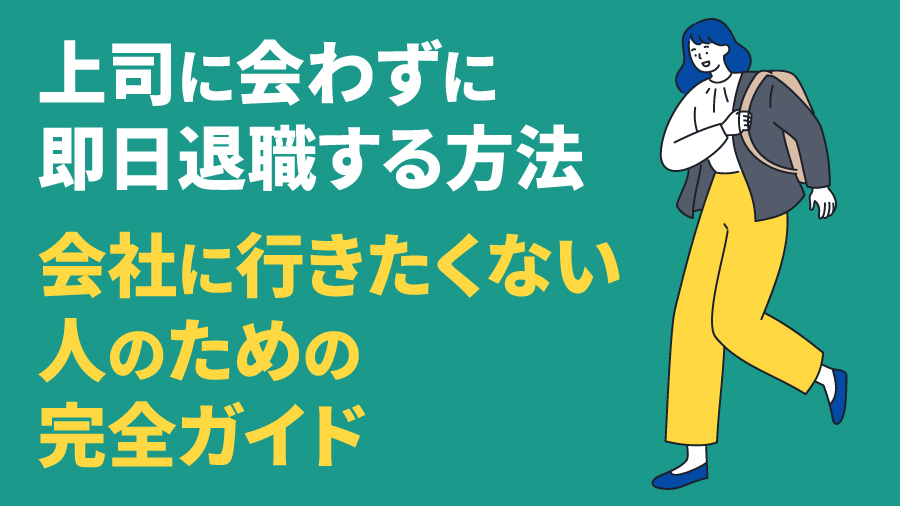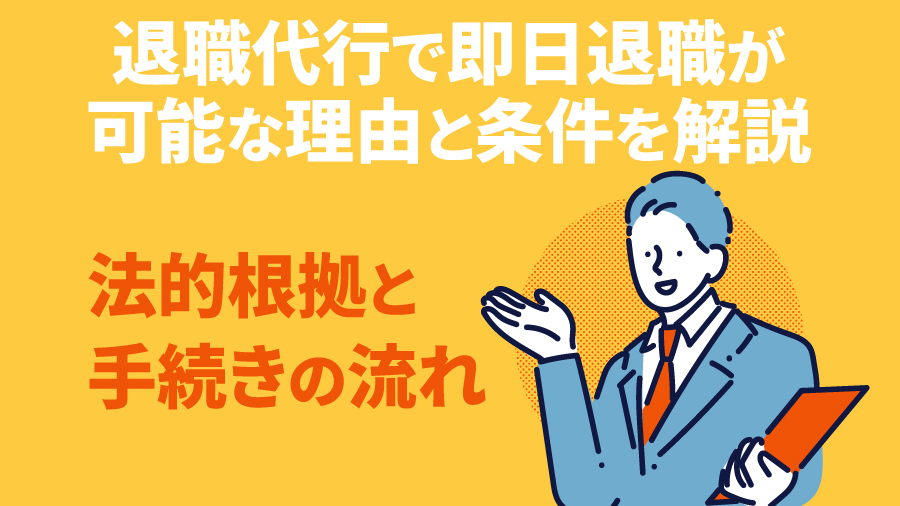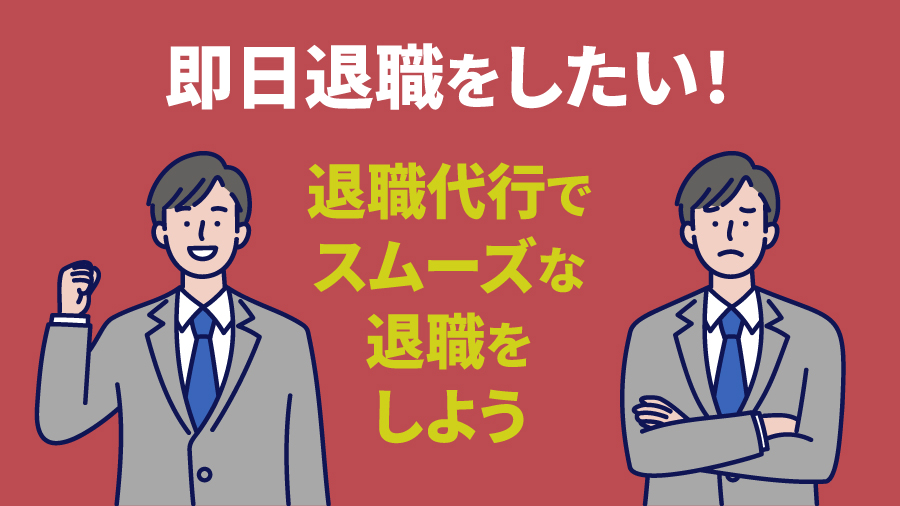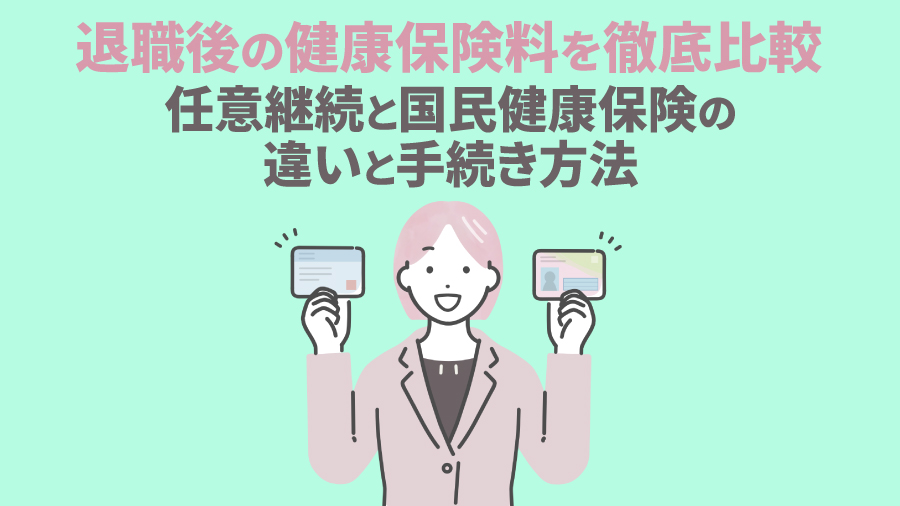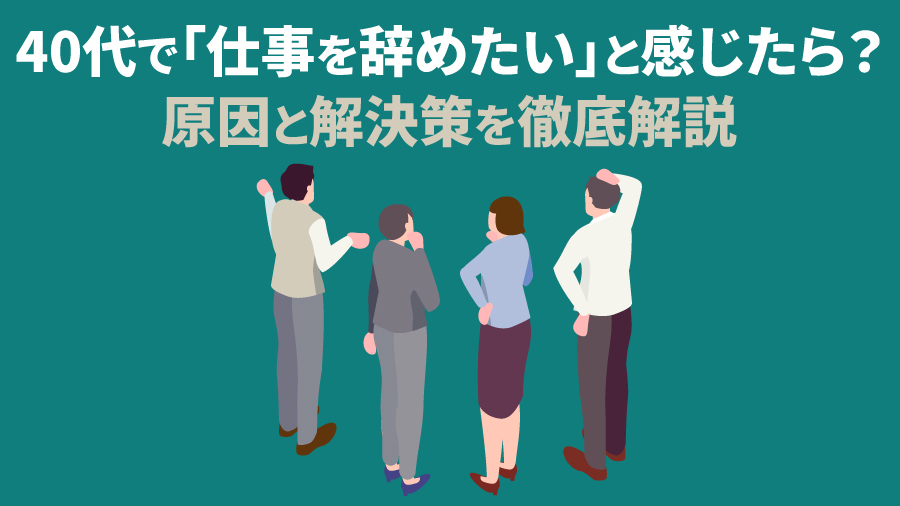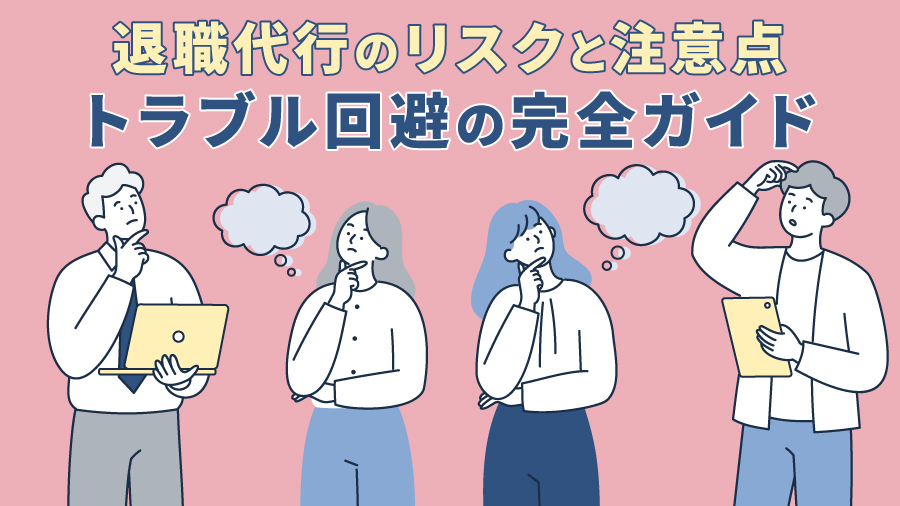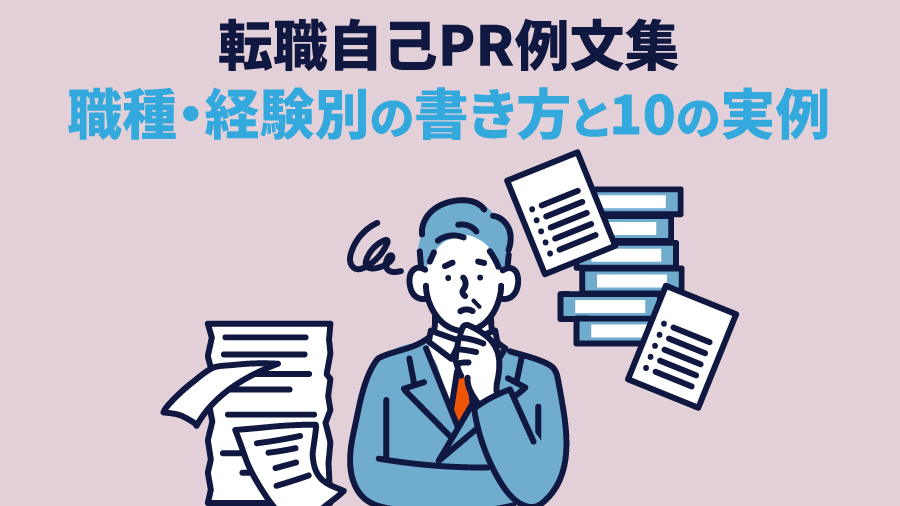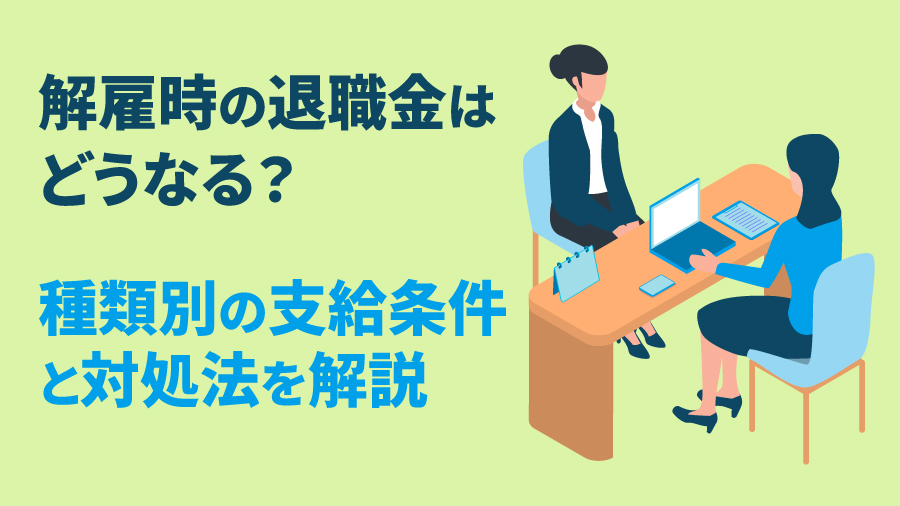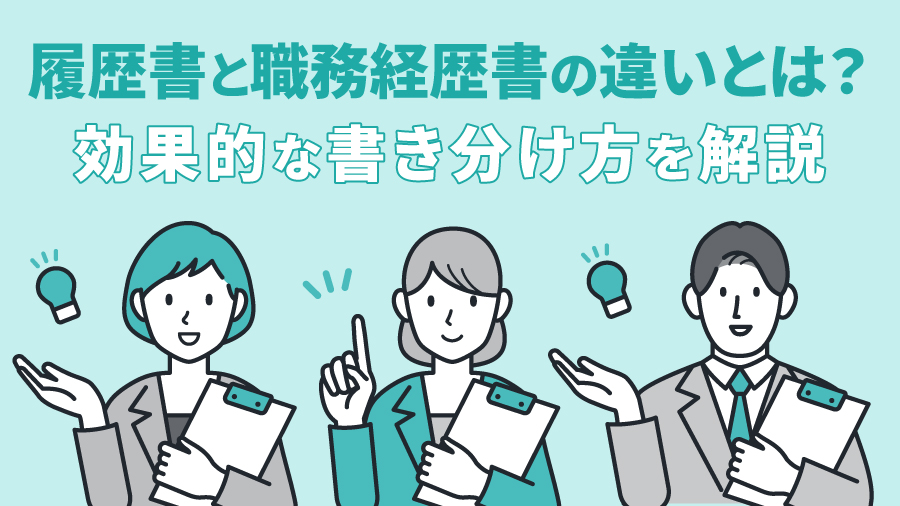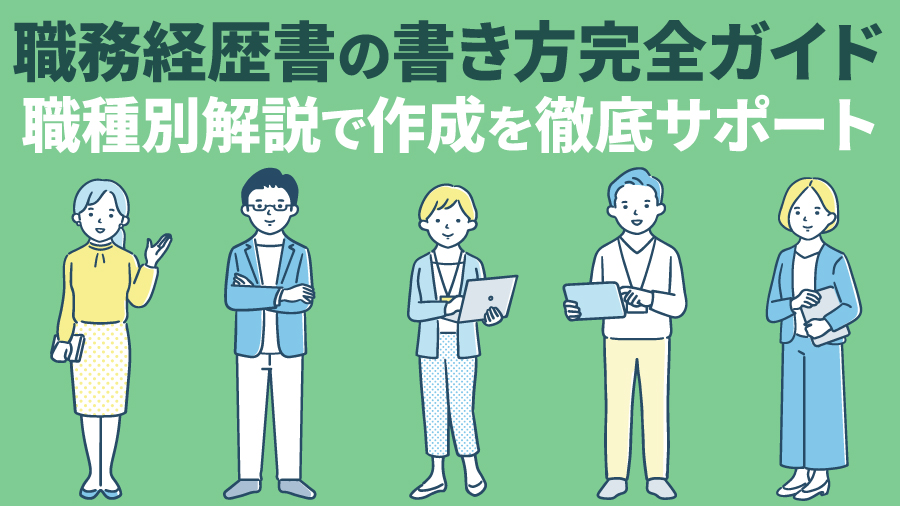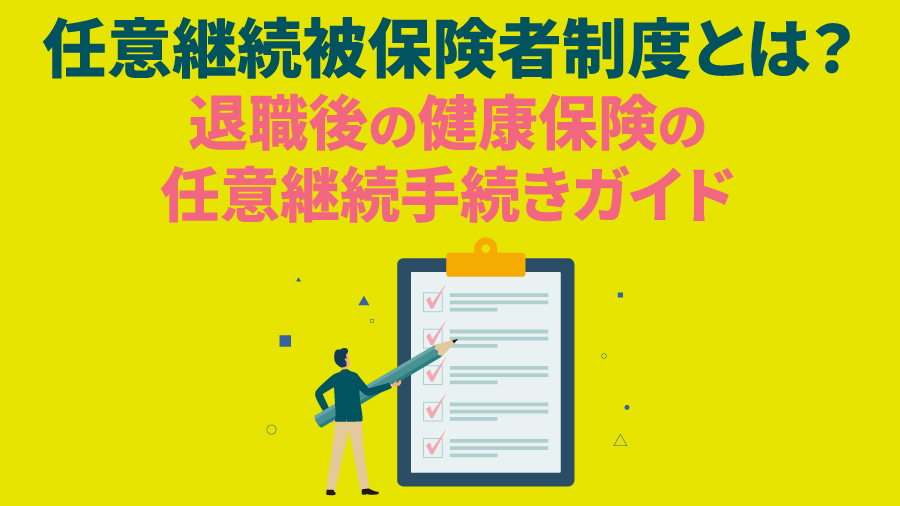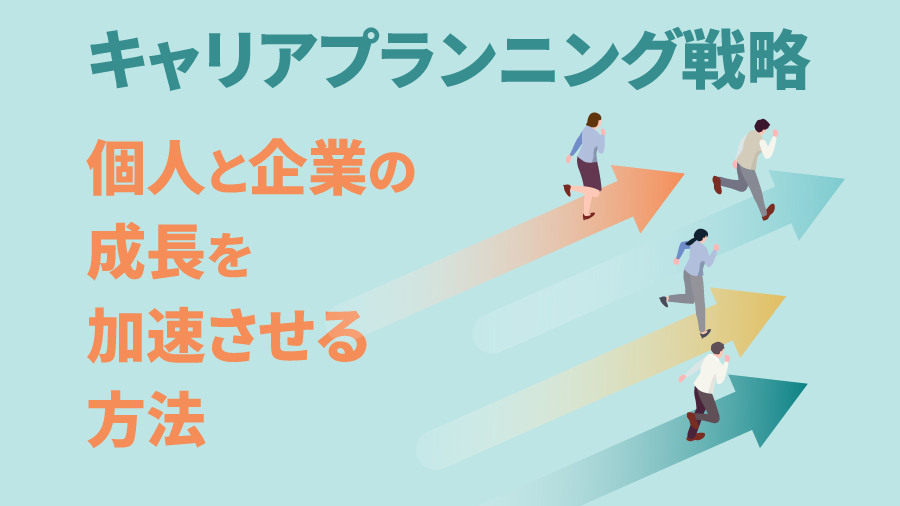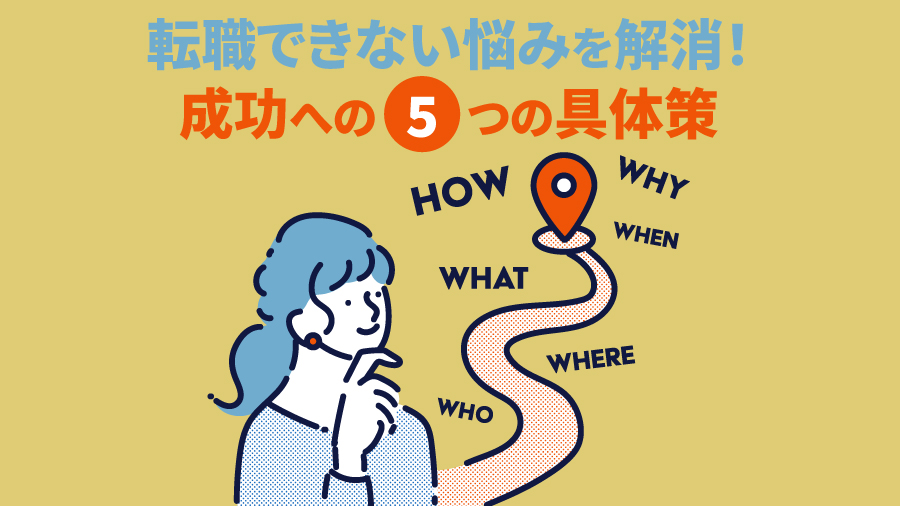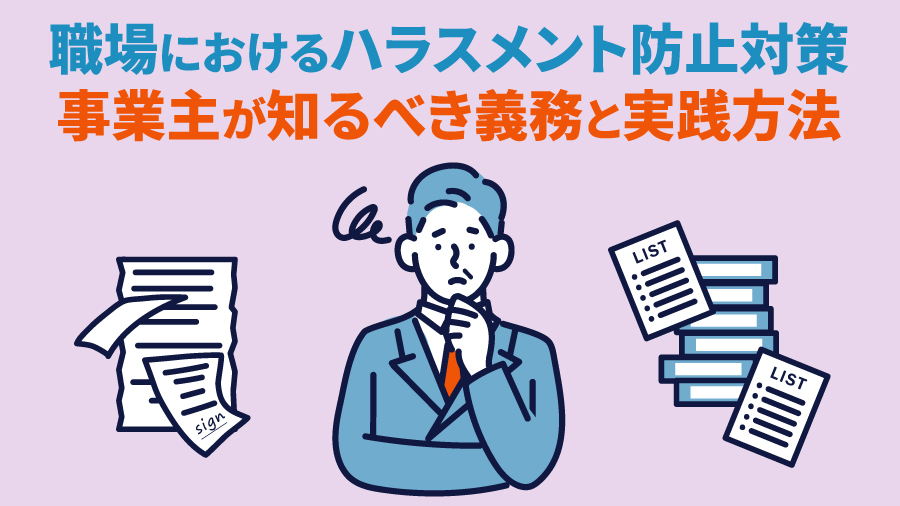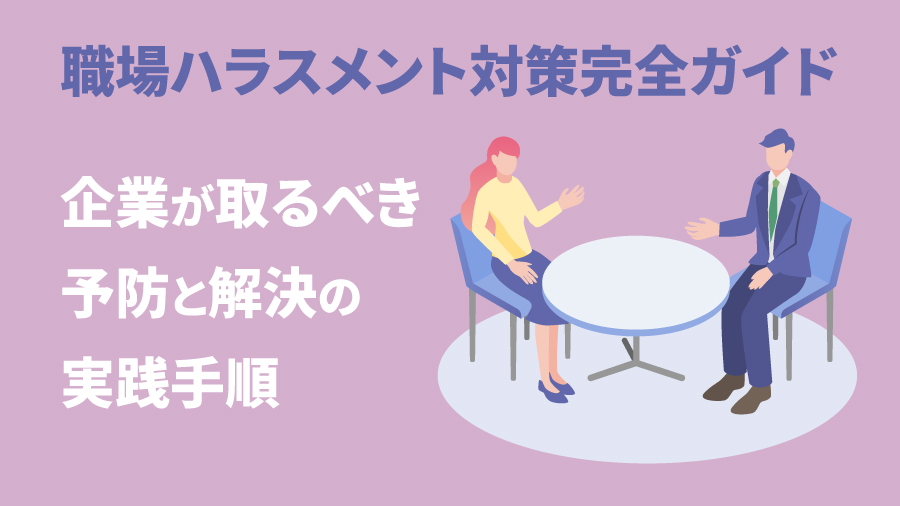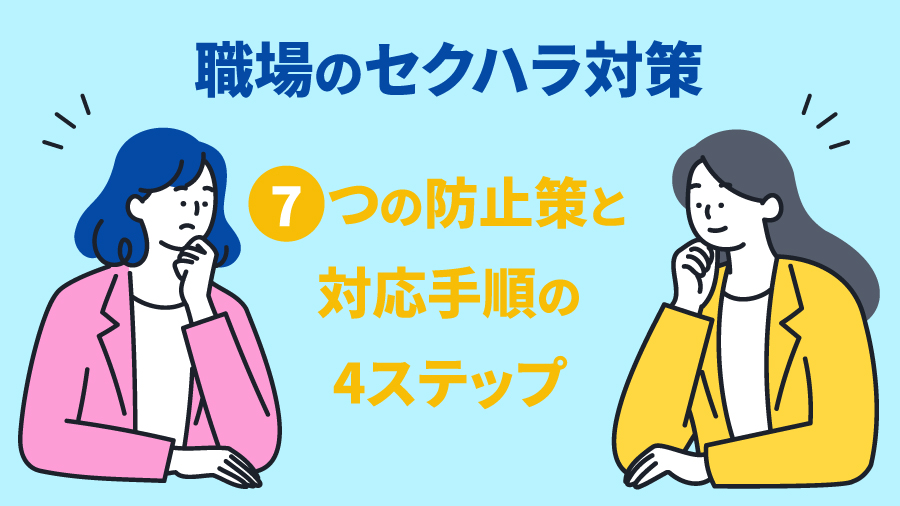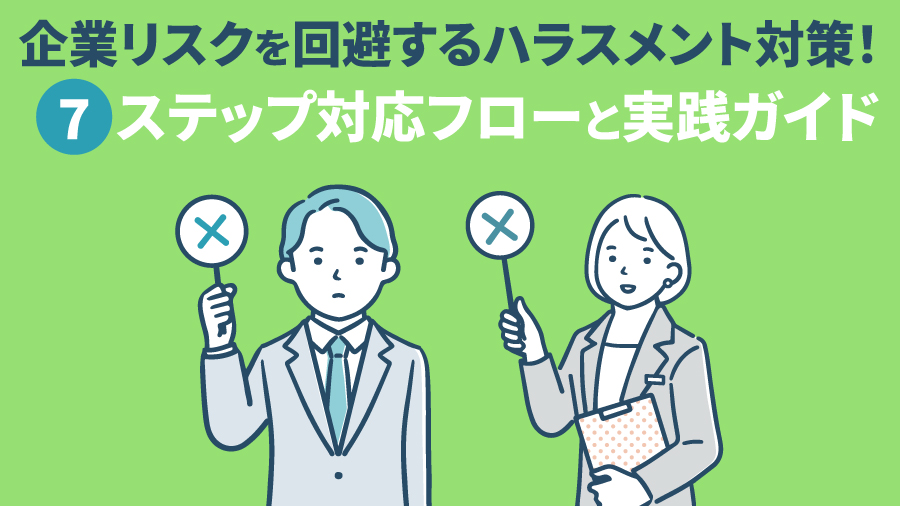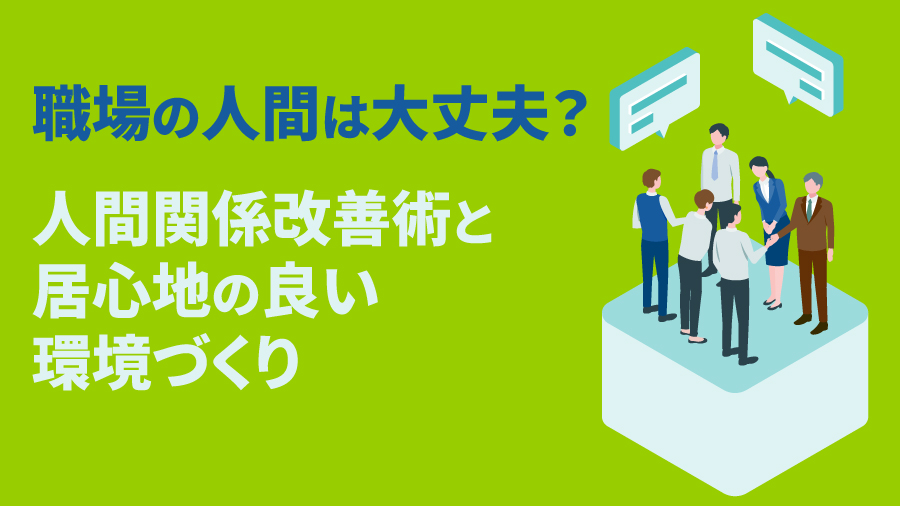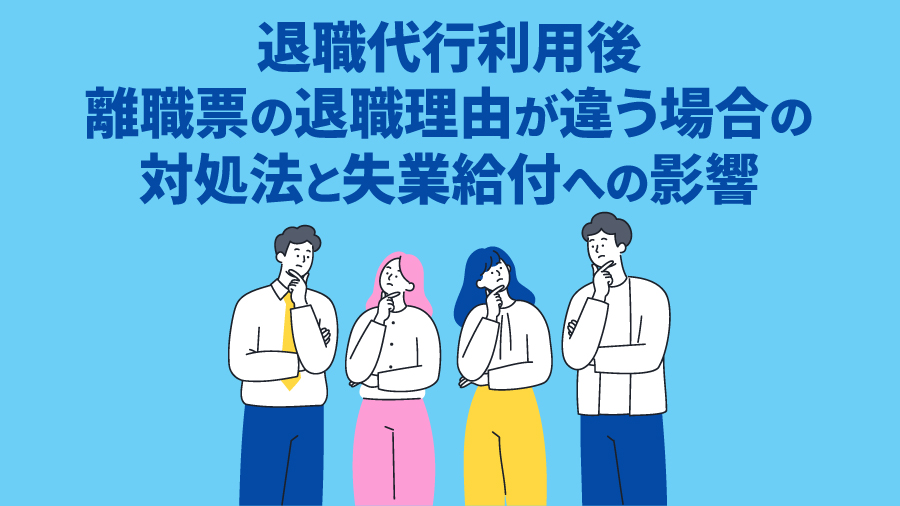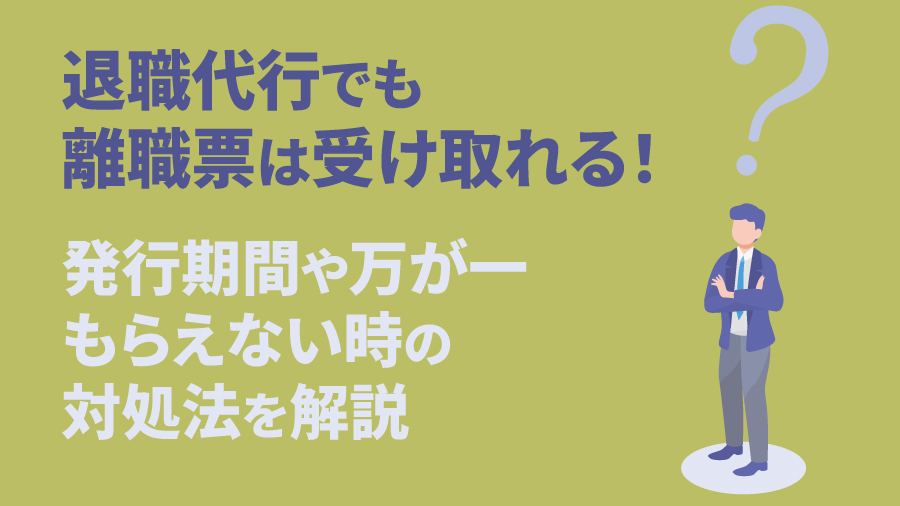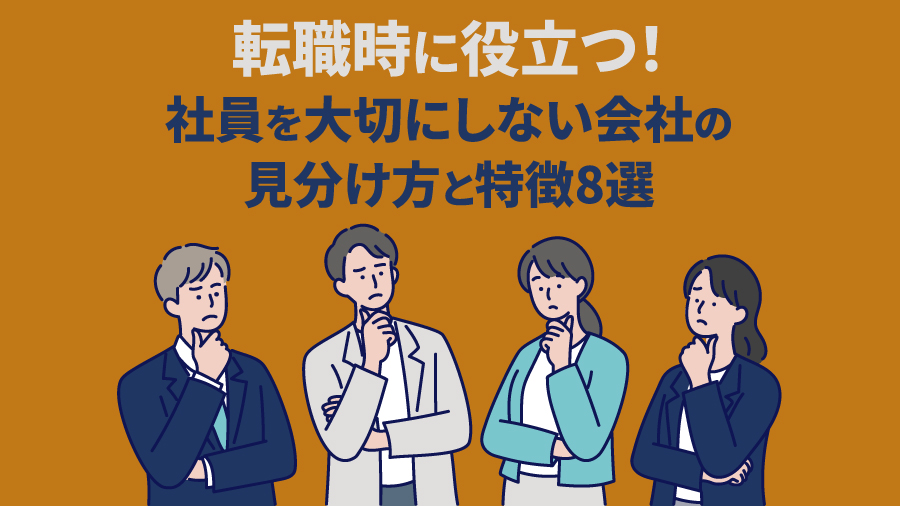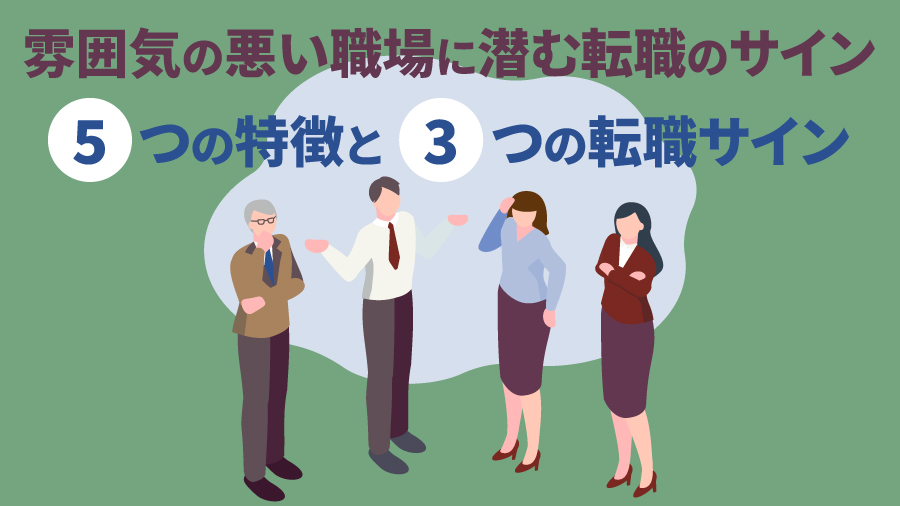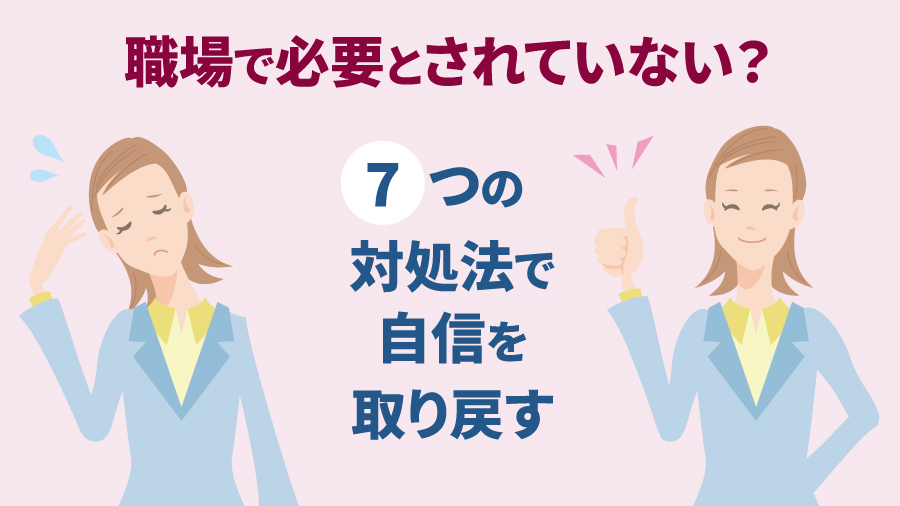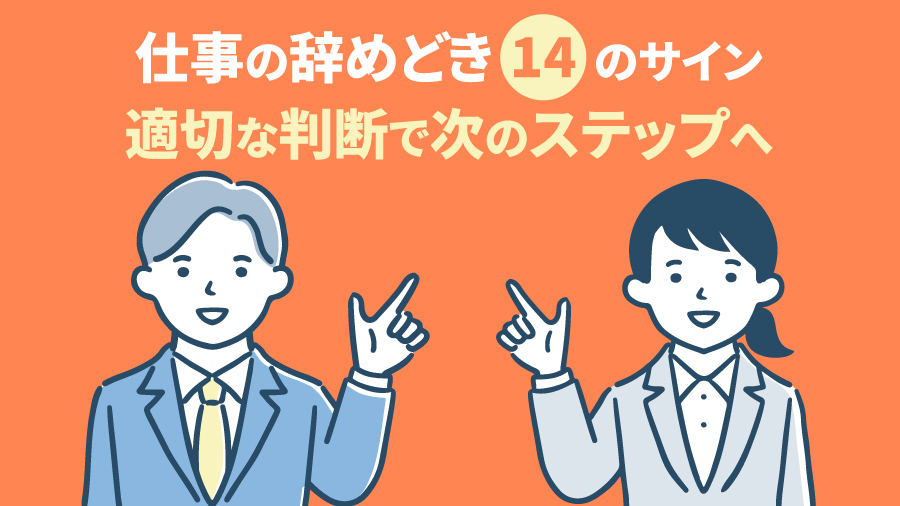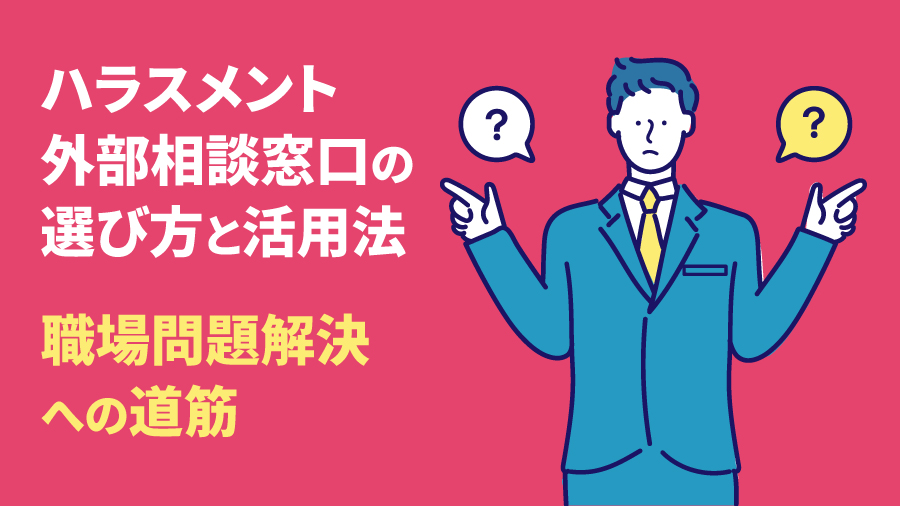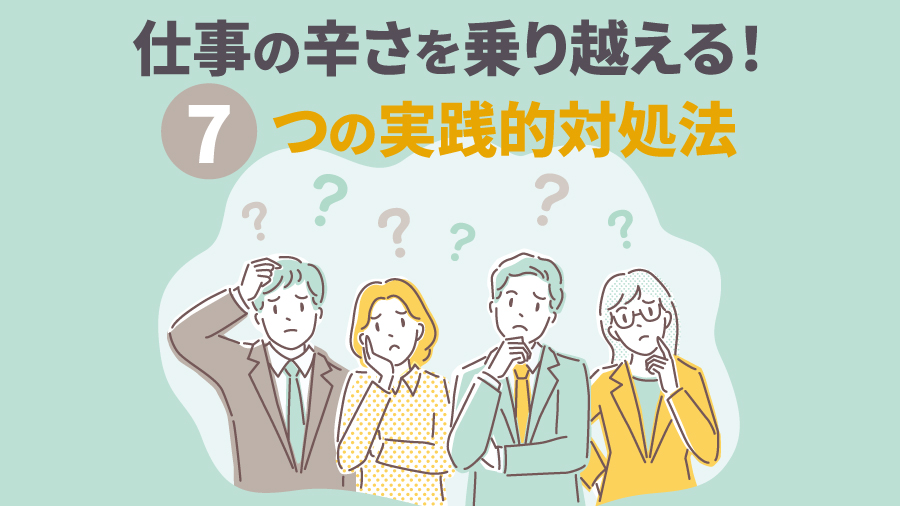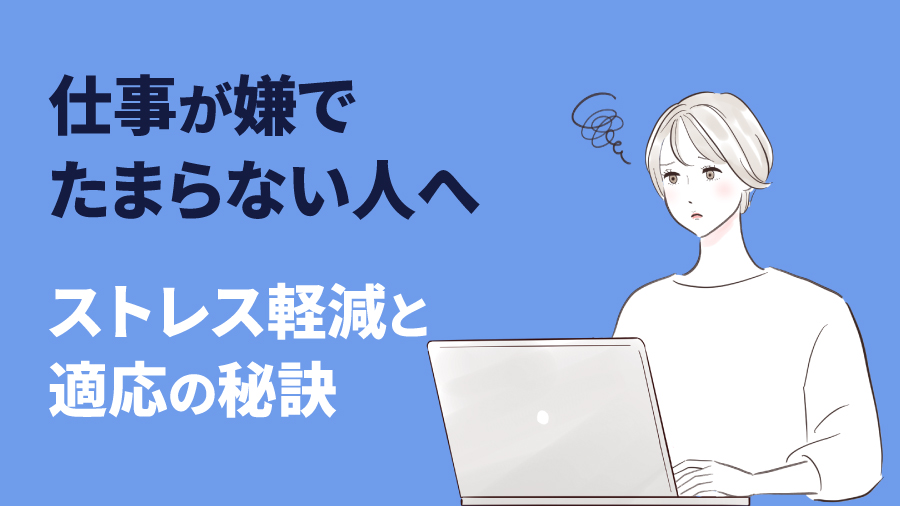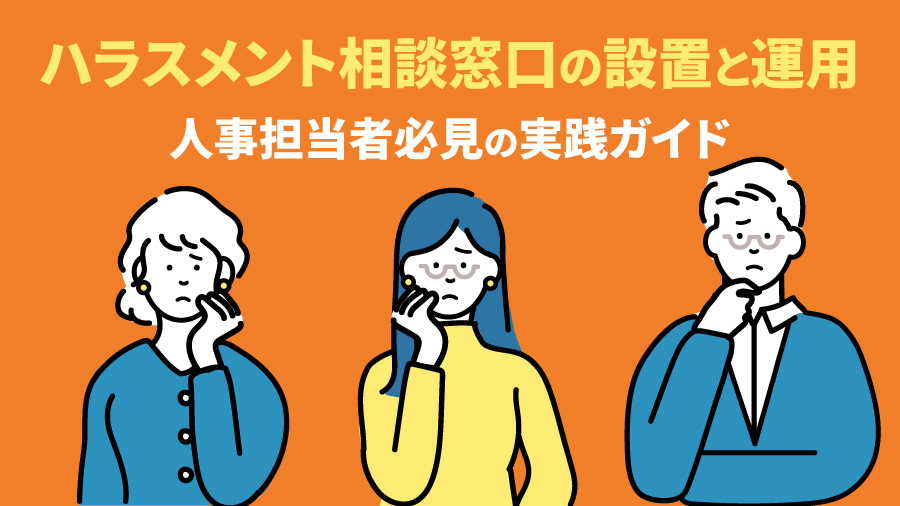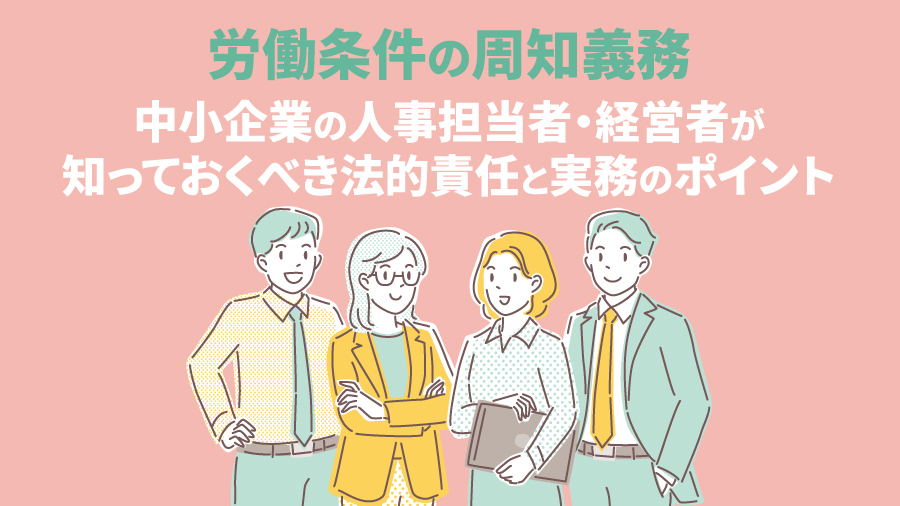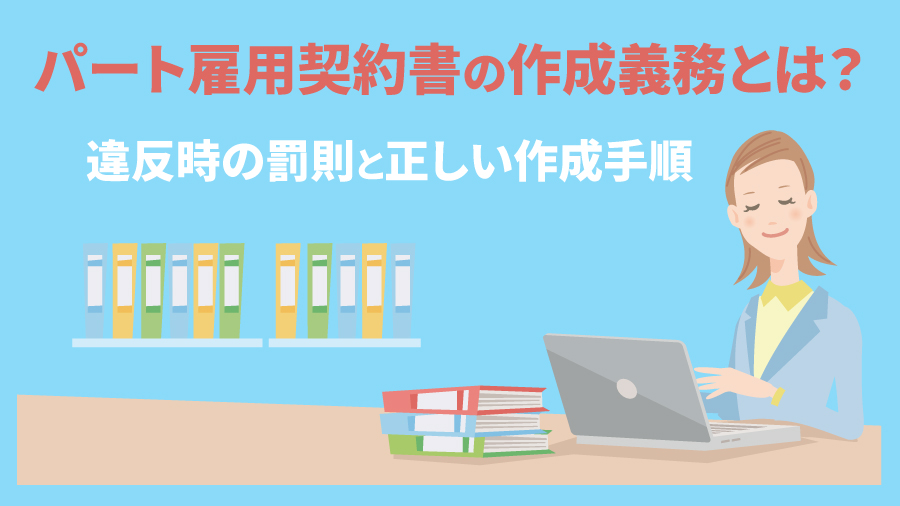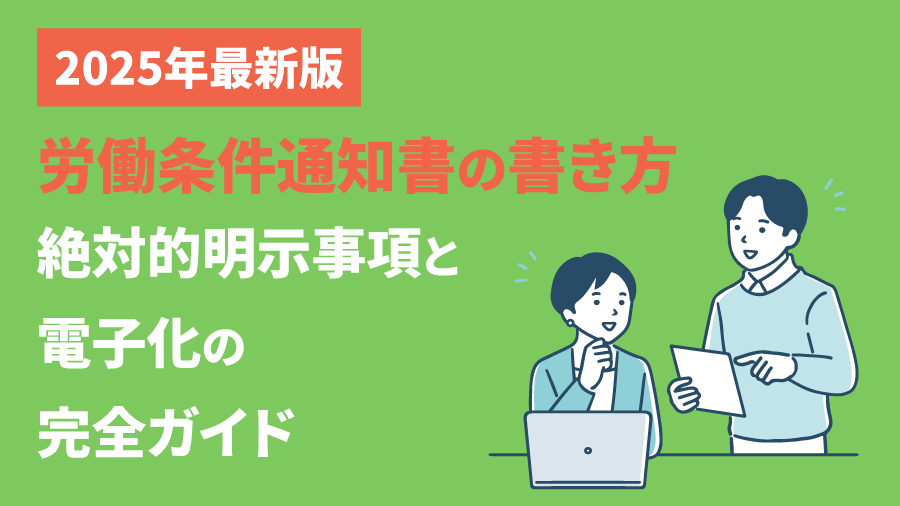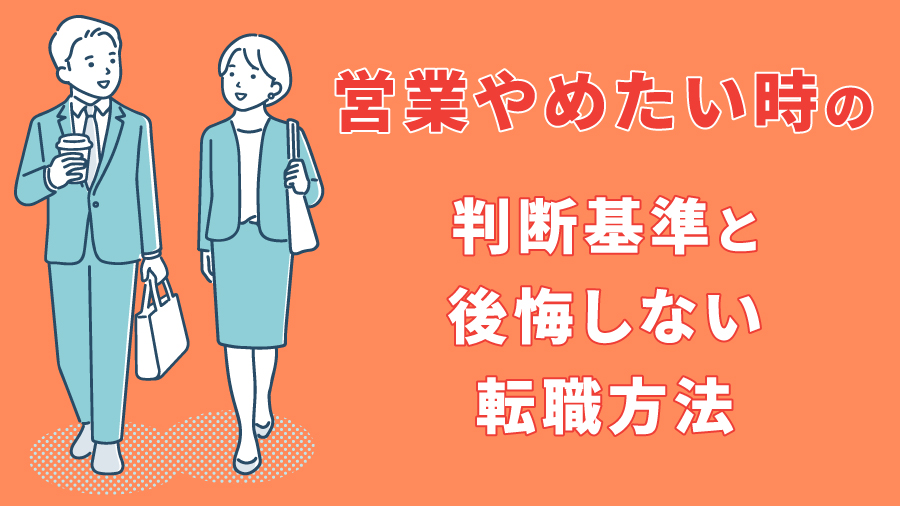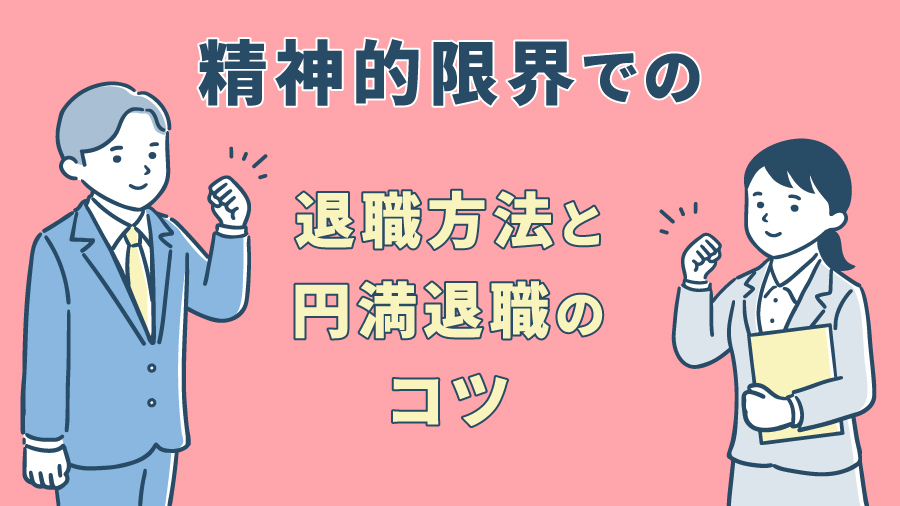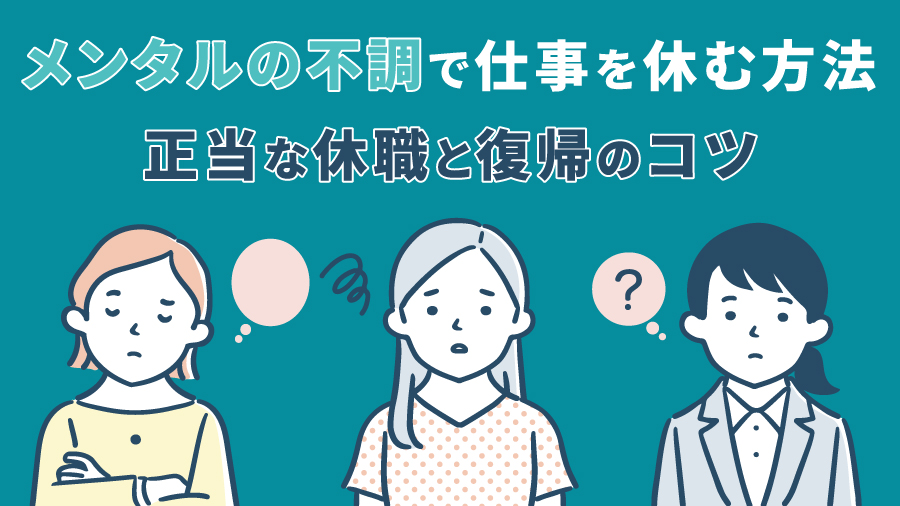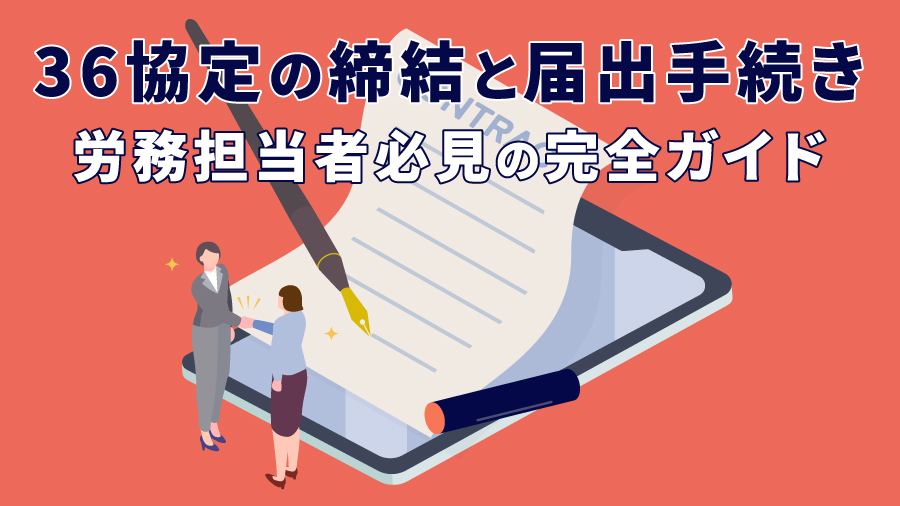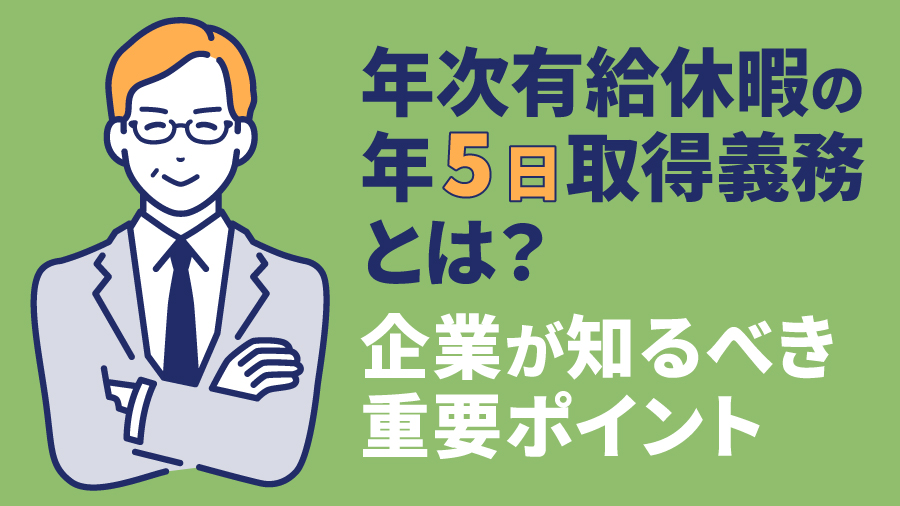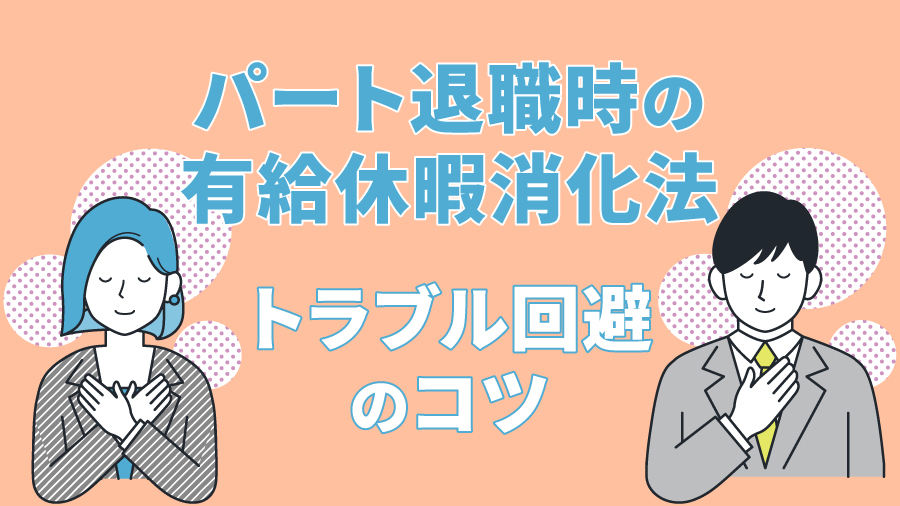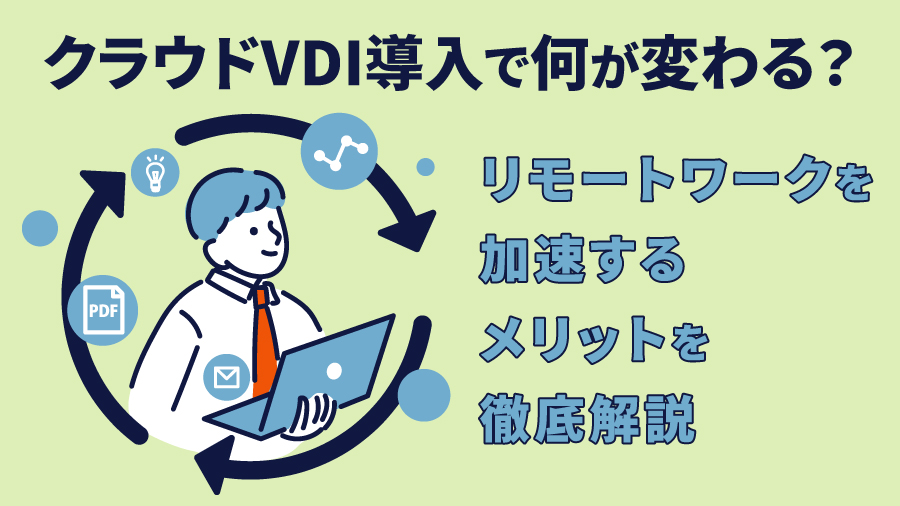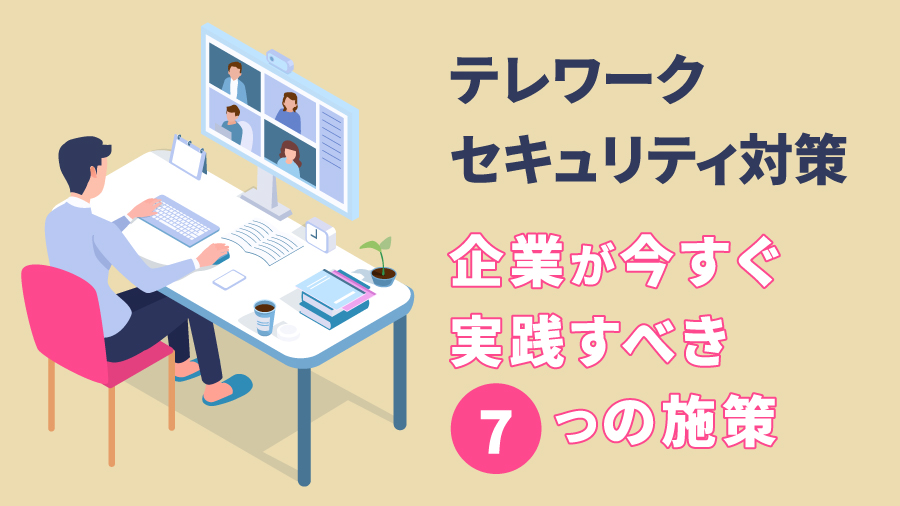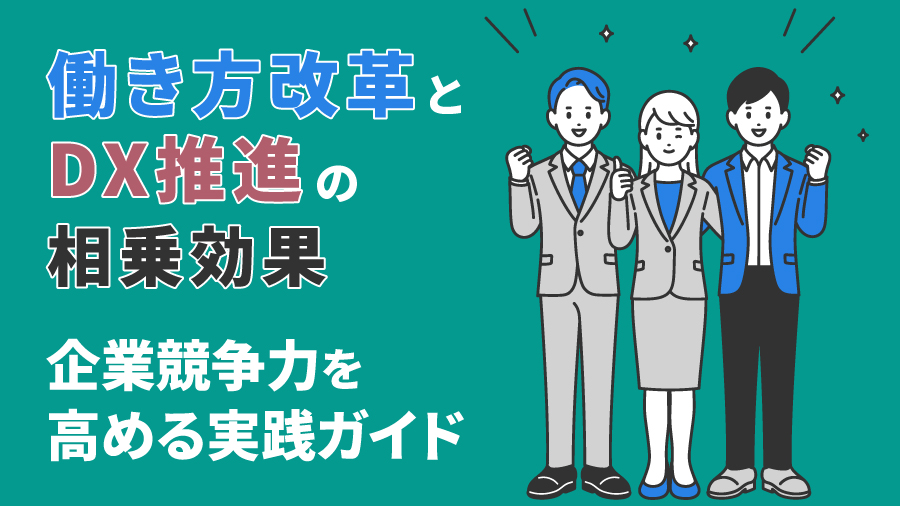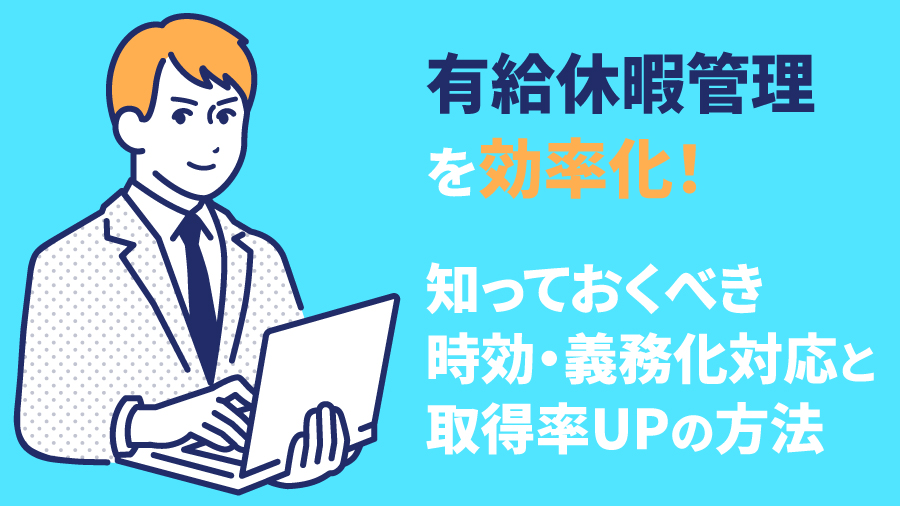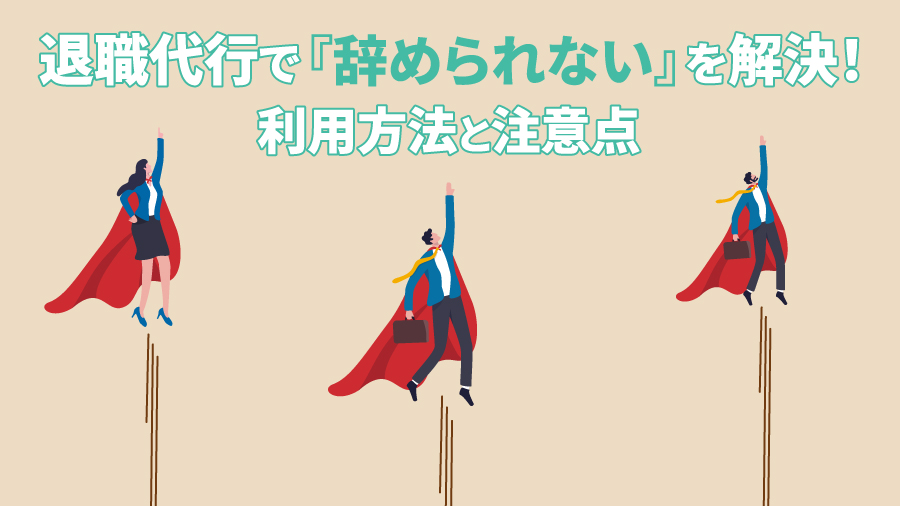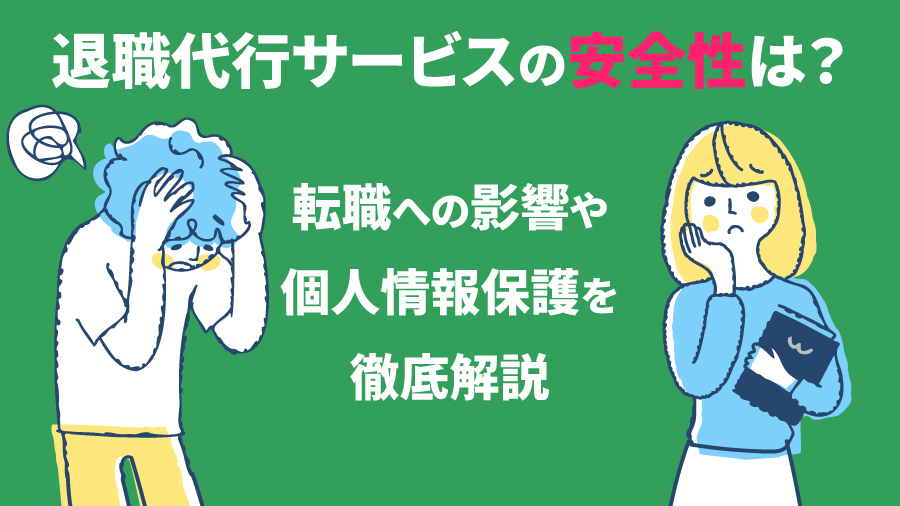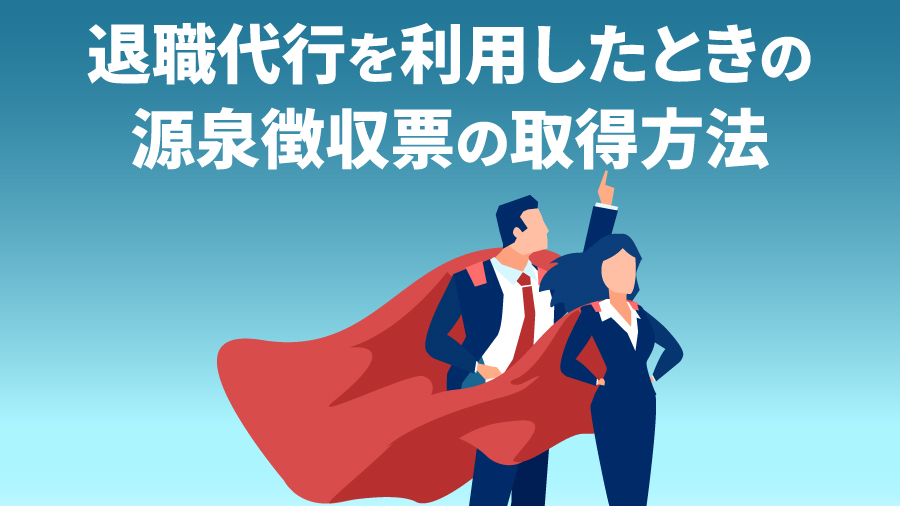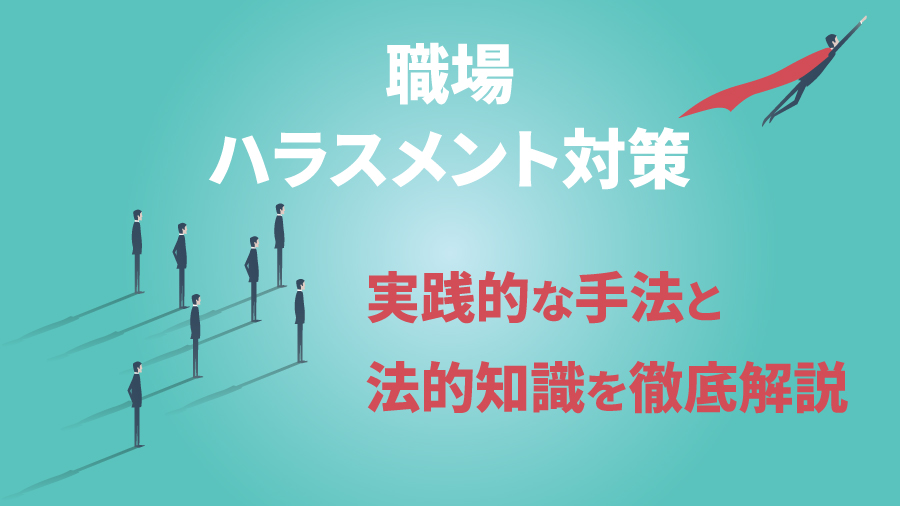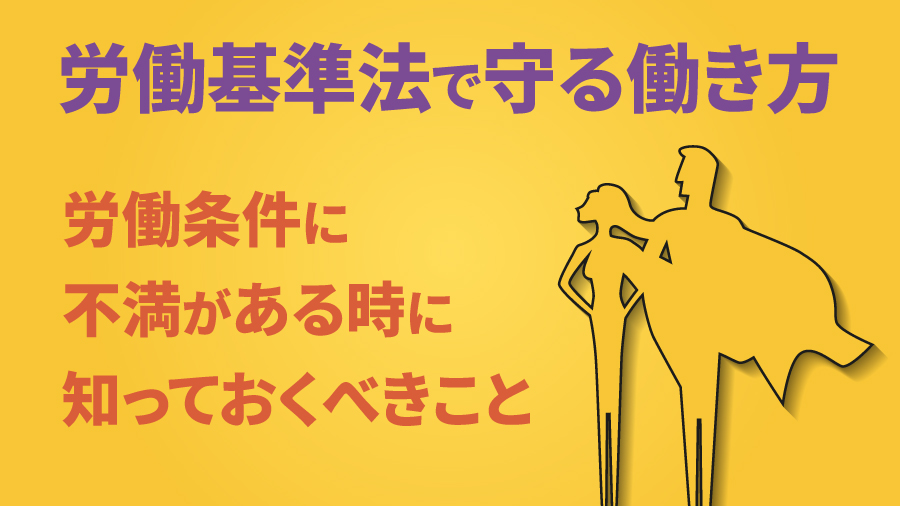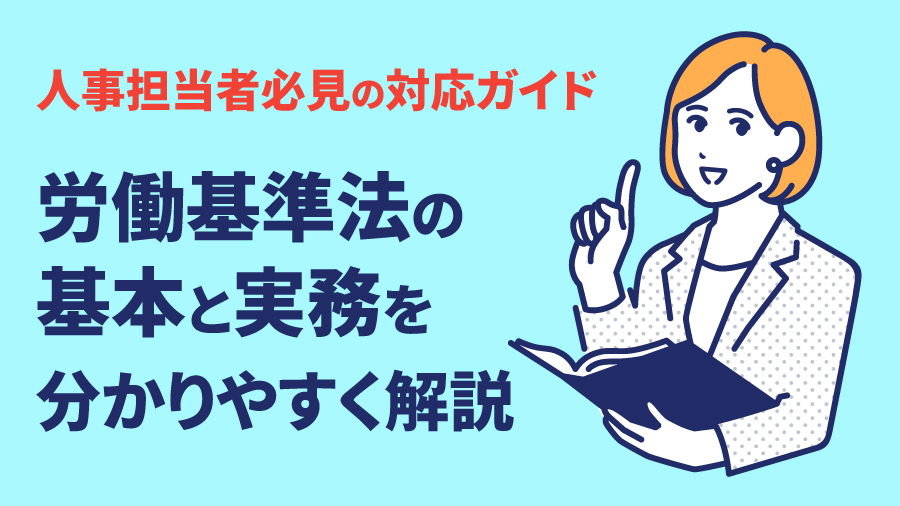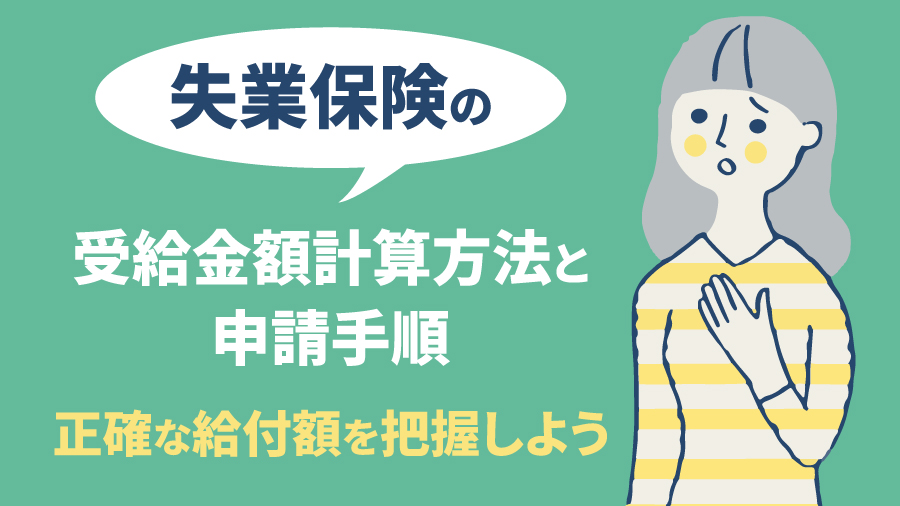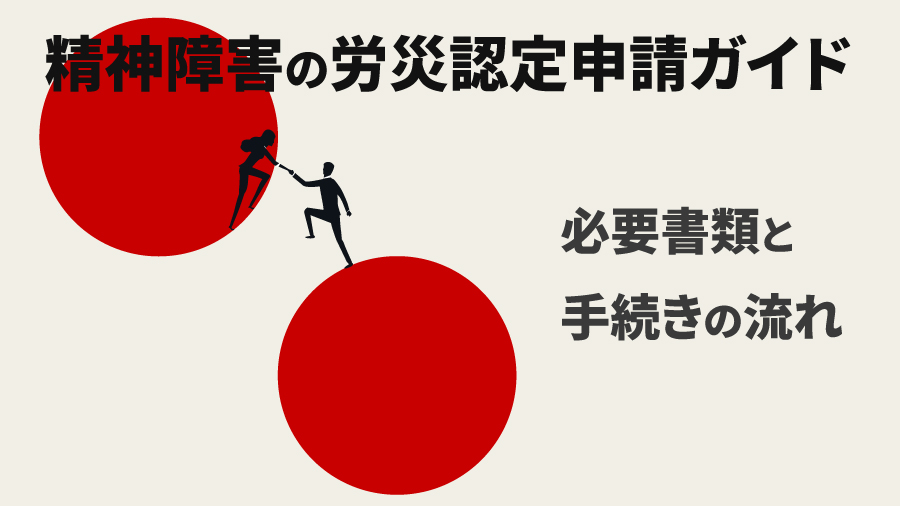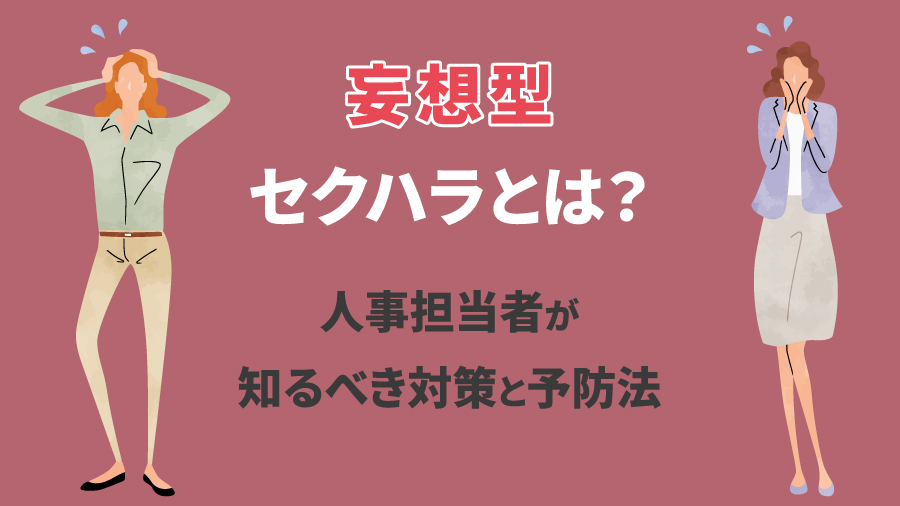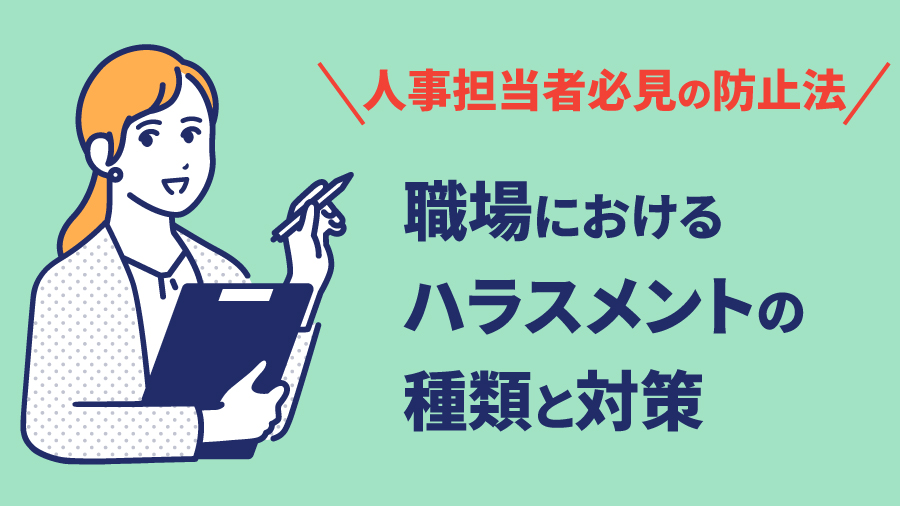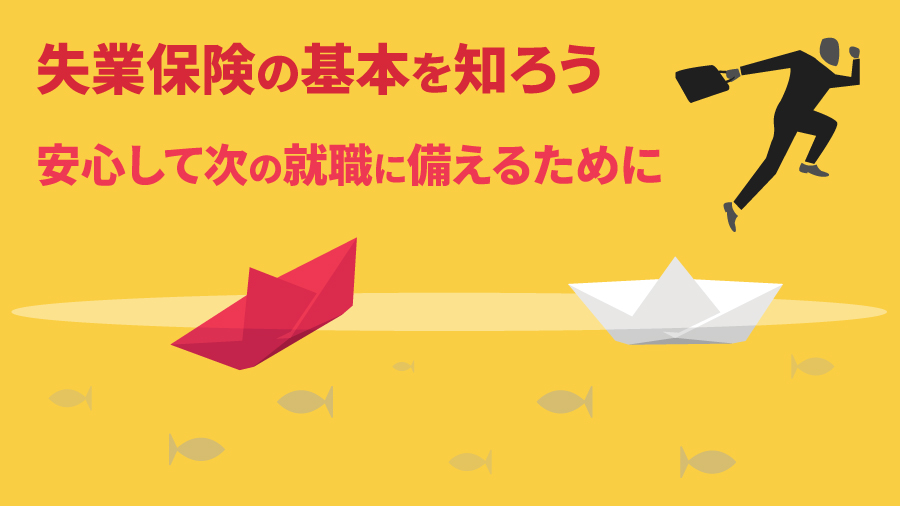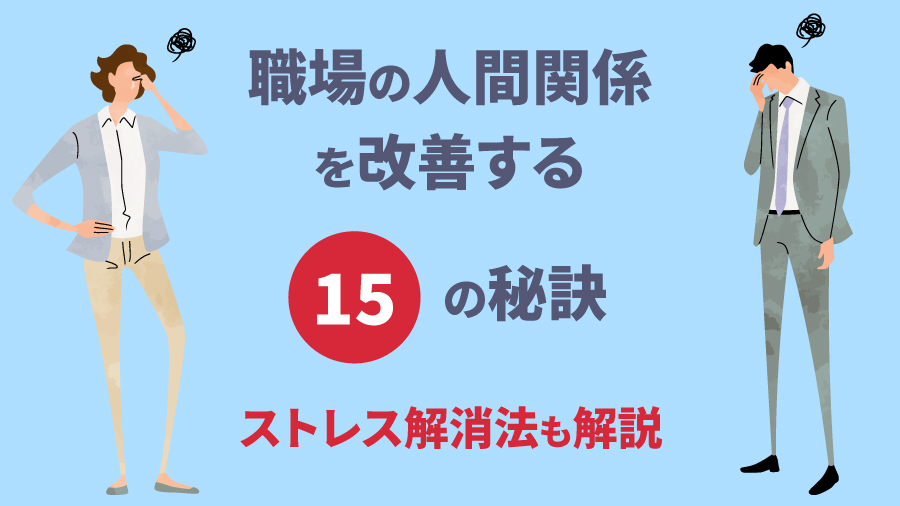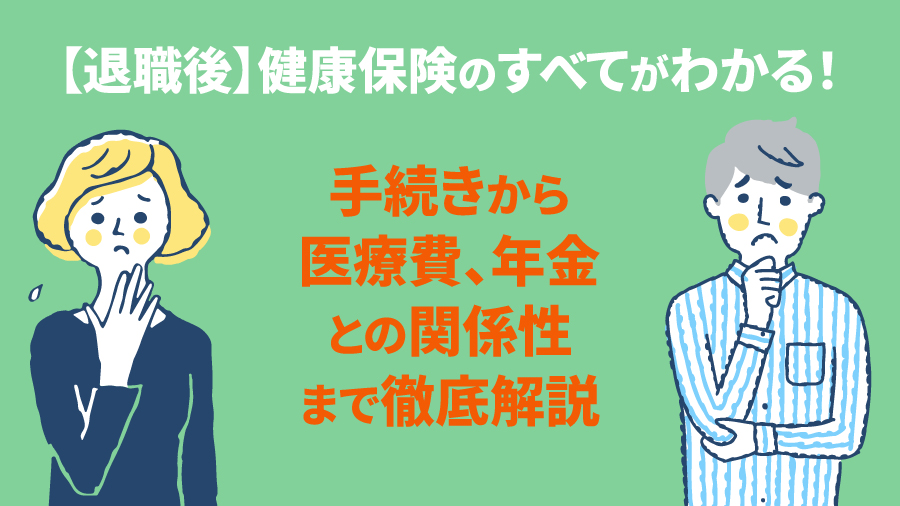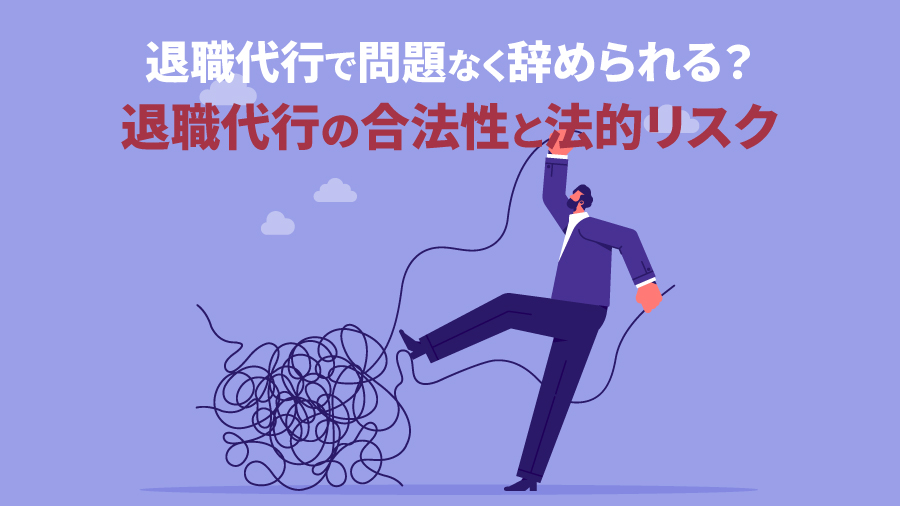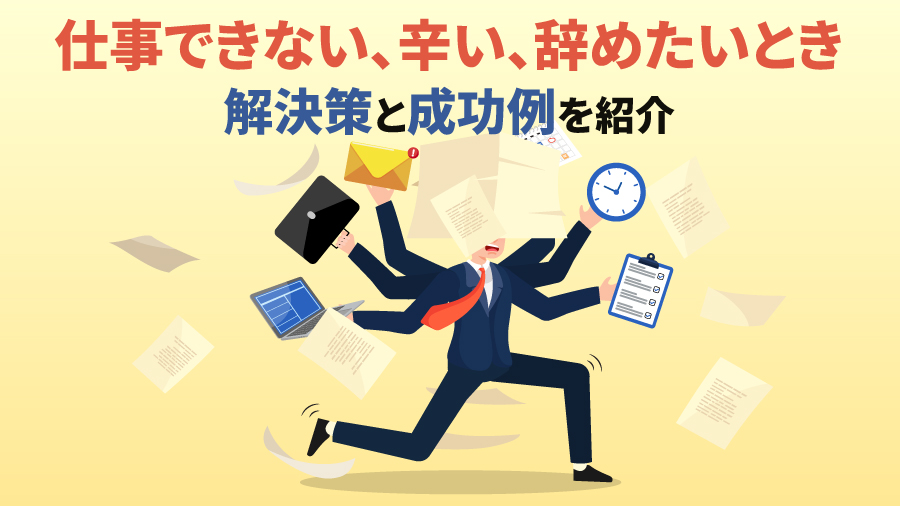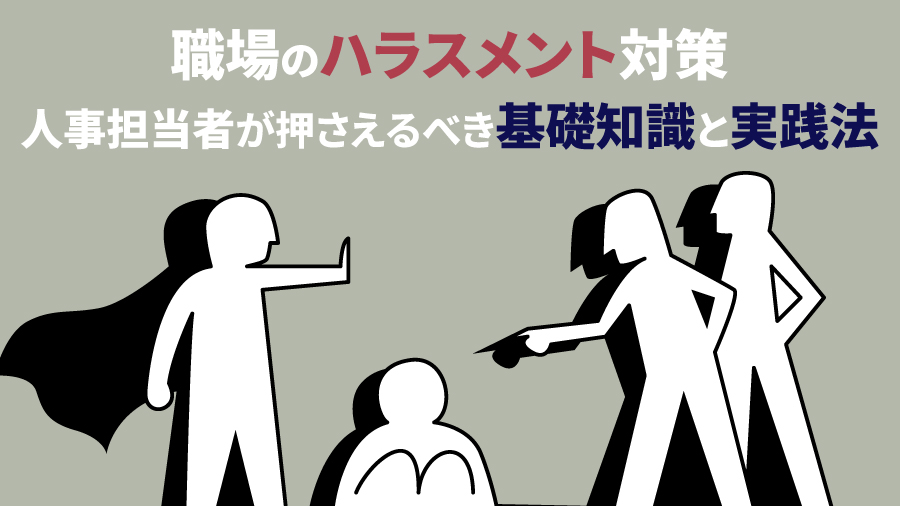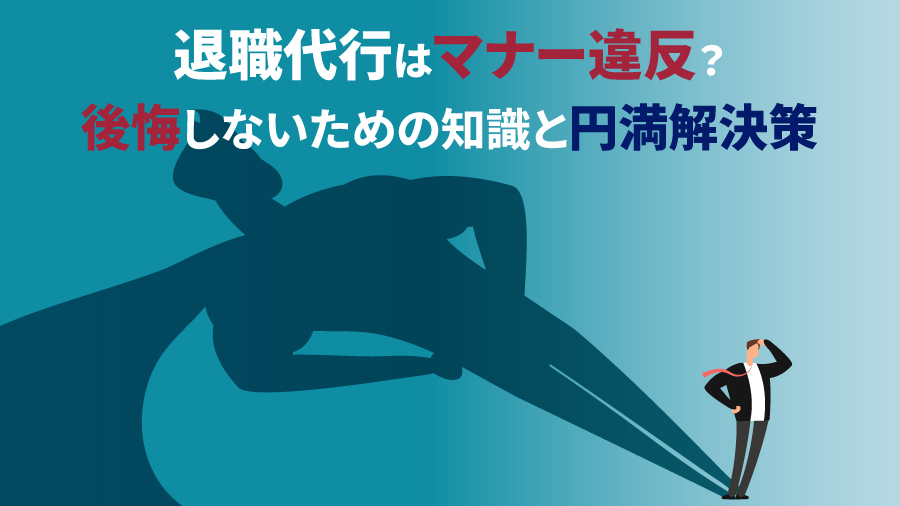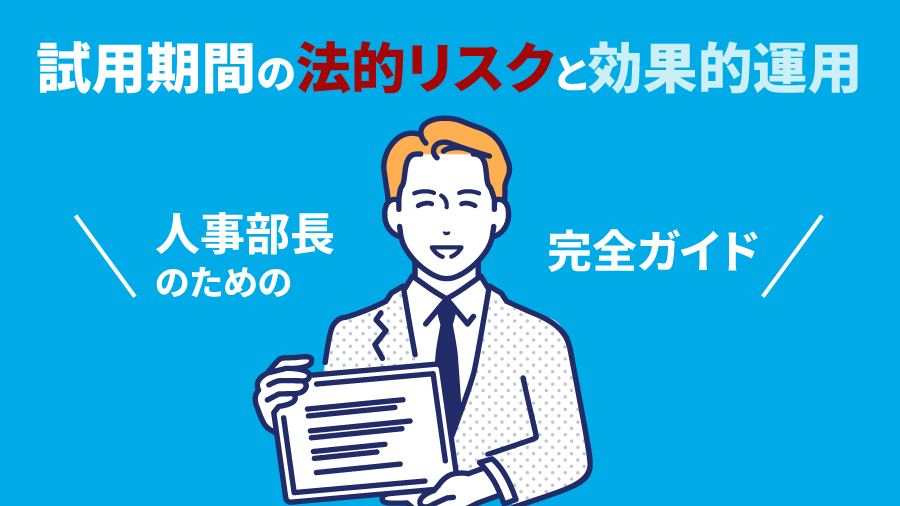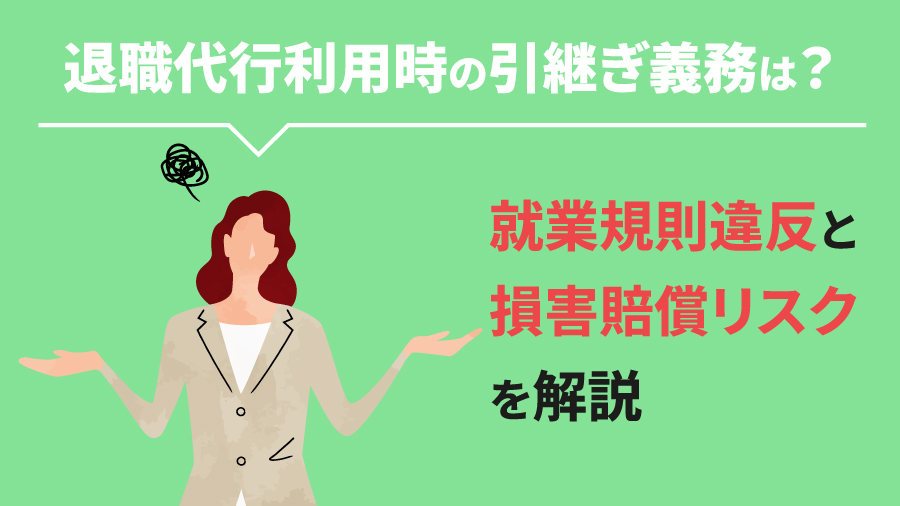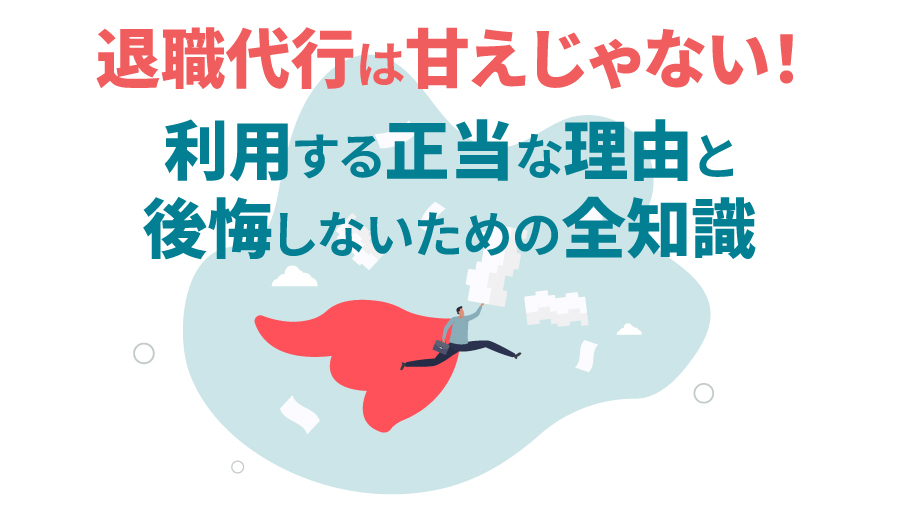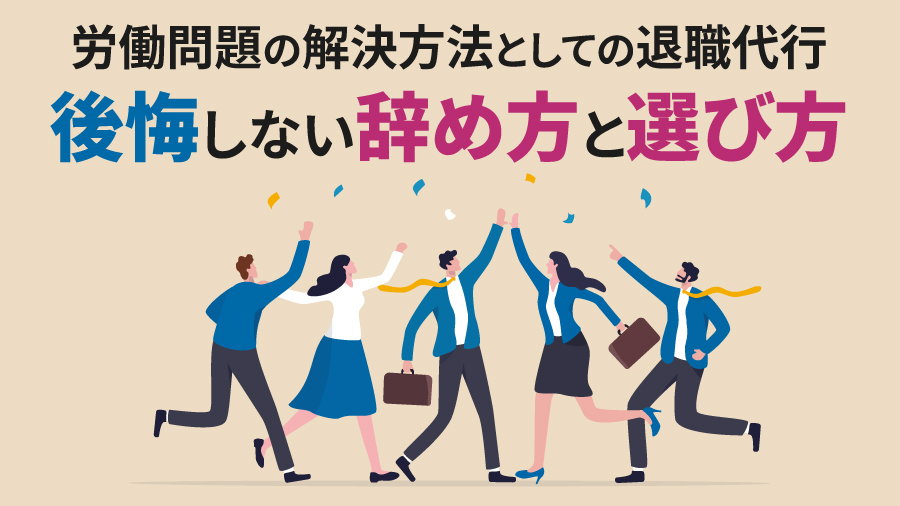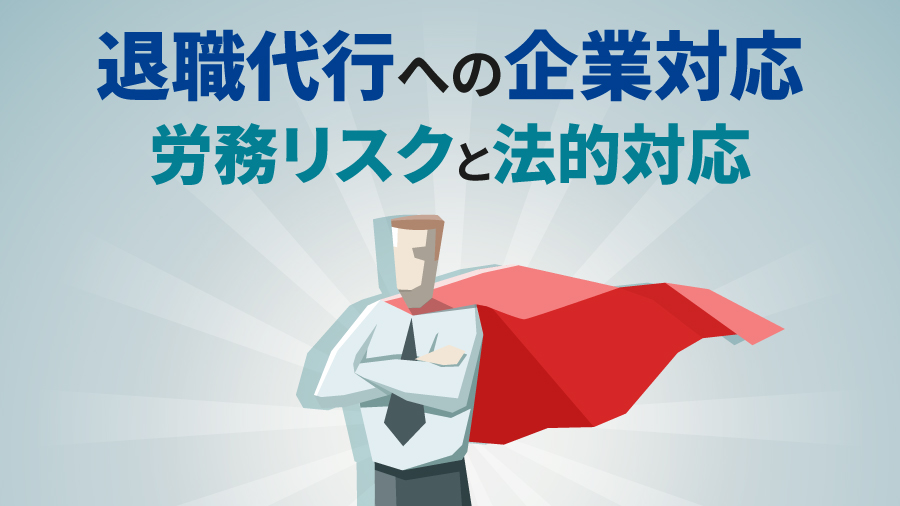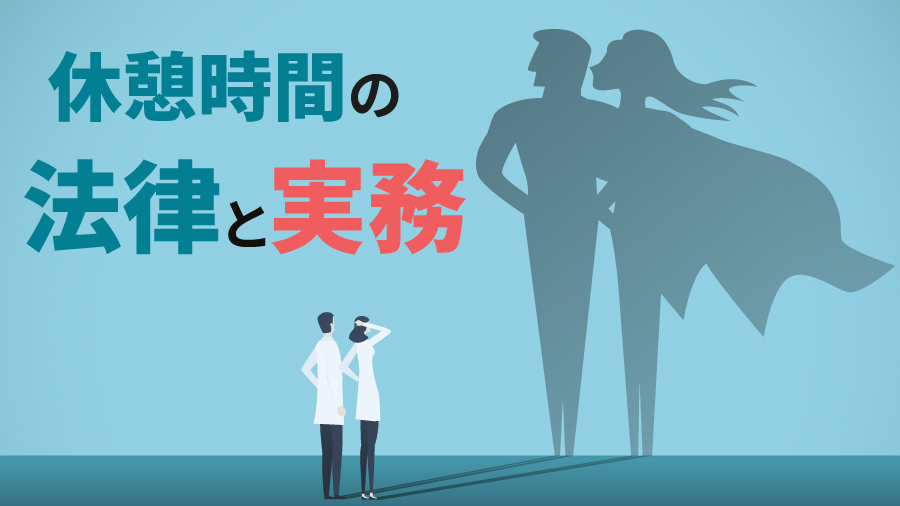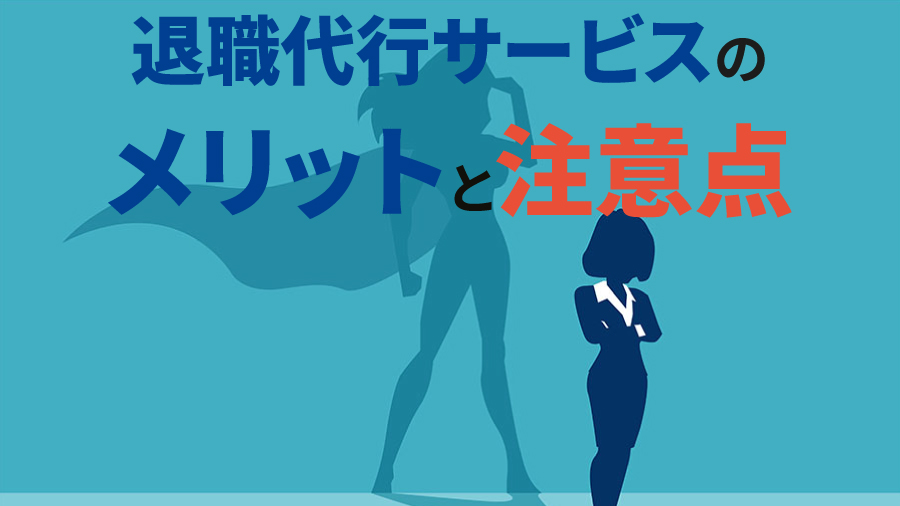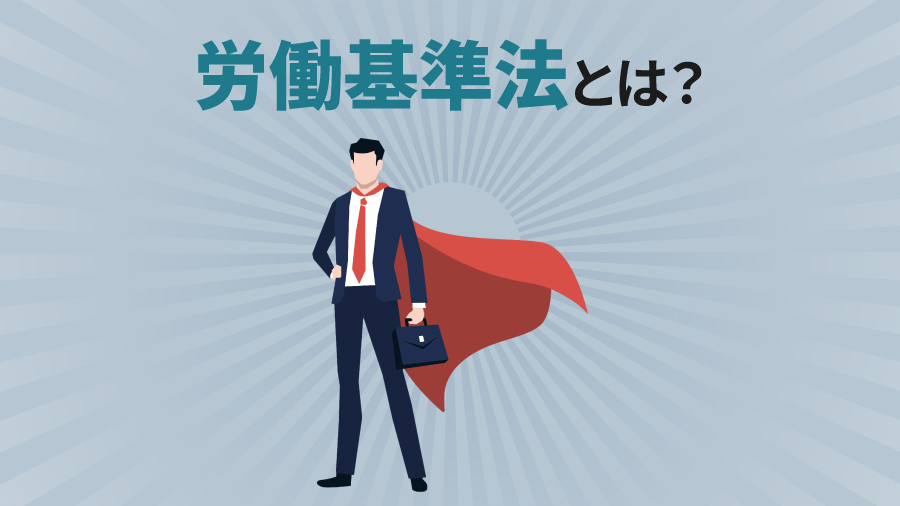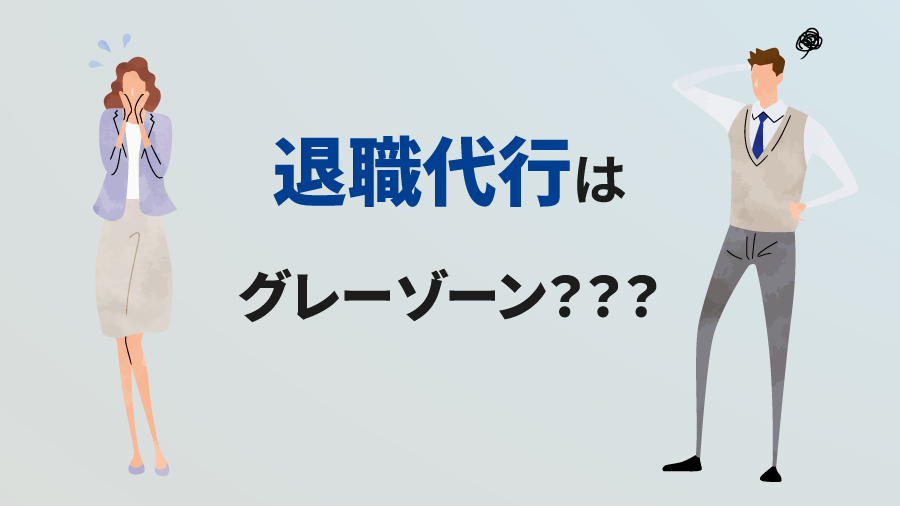-
-
退職代行はやめておけ?やめておけといわれる理由と必要とされる状況
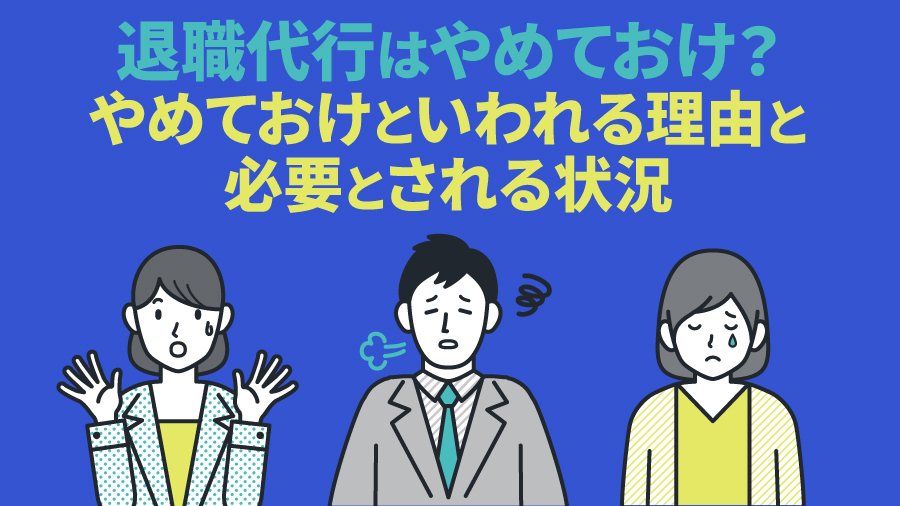
「退職代行はやめとけ」という声を聞いたことがありますか? パワハラや長時間労働で心身ともに限界なのに、退職を言い出せない…そんな状況で退職代行を使いたいけど利用をためらっている。 そんな思いの方も少なくないでしょう。 この記事では、「退職代行はやめとけ」と言われる具体的な理由を理解していきます。さらに、退職代行が理由から状況、退職代行業者の選び方まで詳しくご紹介。この記事を読めば、退職代行を客観的に判断し、あなたにとって最適な退職方法を見つけるヒントが得られるでしょう。
「退職代行はやめとけ」と言われる主な理由
退職方法の多様化に反するように、退職代行の利用に対して「やめとけ」という意見が少なからず存在します。
これらの意見には、費用、キャリアへの影響、人間関係の悪化、トラブルのリスクなどが挙げられます。
これらの理由を理解し、退職代行の利用を検討する際の参考にしてください。費用がかかる:自分でできることにお金を払う必要性
退職代行の利用には、一般的に2〜3万円程度の費用がかかる場合があります(サービス内容により、さらに高額になることも)。
退職手続きは本来自分で行うことも可能なため、費用をかけて代行サービスを利用することに疑問を持つ人もいます。
特に、経済的な負担を考慮すると、退職代行の利用をためらうケースも少なくありません。転職活動や将来のキャリアへの悪影響の可能性
退職代行の利用が、転職活動や将来のキャリアに影響する可能性は否定できません。
企業によっては、退職代行を利用したことをネガティブに捉える場合があり、選考で不利になることも考えられます。
特に、業界が狭い場合や、人間関係や評判が重視される職種では、注意が必要かもしれません。人間関係や感情面での問題:後悔や心残り
退職代行を利用すると、会社との直接的なコミュニケーションが不足し、後悔や心残りが生じることがあります。
特に、お世話になった上司や同僚との人間関係が良好だった場合、何も伝えずに去ることで、退職後にわだかまりが残る可能性も考えられます。
感情的な整理がつかないまま退職すると、新たなスタートに悪影響を及ぼすことも考慮すべき点です。トラブルに発展するリスク:直接連絡や損害賠償請求の可能性
退職代行の利用が、会社とのトラブルに発展するリスクも考慮すべき点です。
会社側が退職代行の利用を認めず、本人に直接連絡を求めてくることがあります。
また、引き継ぎが不十分だったなどの理由で、損害賠償を請求される可能性もゼロではありません(ただし、退職自体を理由とした請求は通常困難です)。
これらのリスクを避けるためには、信頼できる退職代行を選ぶことが重要になります。退職代行が必要とされる正当な状況
退職代行の利用には否定的な意見もありますが、状況によっては非常に有効な手段となり得ます。
パワハラやハラスメントが横行する職場、メンタルや体調不良が深刻な場合、または会社が退職を受け入れない場合など、自分での退職が困難な状況では、退職代行の利用が有効な解決策となるでしょう。
パワハラやハラスメントがある職場環境からの脱出
パワハラやハラスメントが横行する職場では、精神的な負担が大きく、自力での退職が困難な場合があります。
上司に直接退職を伝えること自体が恐怖であるケースも少なくありません。
このような状況では、退職代行を利用することで、加害者や会社と直接やり取りせずに退職できます。
退職代行は、安全かつ迅速に有害な職場環境から離れるための有効な手段です。メンタルヘルスや体調不良に悩んでいる場合の選択肢
メンタルヘルスや体調不良が深刻な場合、退職の手続きを行うこと自体が大きな負担になります。
気力や体力が低下し、会社とのやり取りや書類準備などが困難に感じることもあるでしょう。
退職代行を利用することで、心身の負担を最小限に抑え、スムーズに退職できます。
特に、医師から休職や退職を勧められている場合や、即日退職を希望する場合には、専門家のサポートが有効です。退職の意思を伝えても受け入れてもらえないケース
退職の意思を明確に伝えても、会社側が「後任が見つかるまで待ってほしい」などと強く引き止める、あるいは退職届を受け取らないといったケースがあります。
このような場合、労働者には退職の自由(民法第627条)がありますが、個人で対応するのは困難です。
退職代行は、専門的な知識と経験に基づき、労働基準法などを根拠に退職をサポートします。
退職の権利を適切に行使できるよう支援してくれるでしょう。引き継ぎの長期化や不当な要求に悩まされている場合
退職時に、会社から過剰な引き継ぎ期間を要求されたり、退職日までの不当な業務を指示されたりする場合にも、退職代行が役立ちます。
特に、弁護士や労働組合が運営する退職代行であれば、会社との交渉が可能です。
専門家が間に入ることで、法的な観点から適切な引き継ぎ範囲や期間について会社と話し合い、不当な要求にも毅然と対応します。
これにより、精神的なストレスを軽減し、円滑な退職が期待できます。退職代行の利用状況
近年、退職代行サービスの利用者は年々増加しており、社会的にも徐々に認知されるようになってきました。
特に、20〜30代の若い世代を中心に、「円滑かつ法的に問題のない方法で退職したい」というニーズが高まっており、「心身の安全を守る合理的な選択」として受け入れられつつあります。SNSや口コミを通じて実際に利用した人の体験談も広まり、「やめとけ」といった否定的な声があっても、それ以上に「助かった」「もっと早く使えばよかった」といった前向きな声も多く見られます。
退職代行は、決して逃げではありません。
むしろ、自分の人生を前に進めるための一歩として、多くの人に選ばれている正当な手段なのです。退職代行利用者の実際の体験談
退職代行を実際に利用した人々の声は、サービスの実態を知り、利用を検討する上で非常に参考になります。
ここでは、成功事例に利用のきっかけを交えて紹介します。事例 1:きっかけ・ブラック企業からの脱出(25歳・男性)
新卒で入社したIT企業で長時間労働を強いられ、退職の申し出も却下され続けていたAさんは、退職代行サービスを利用。
わずか1週間で退職手続きが完了し、ワークライフバランスの取れた新しい職場に転職しました。事例 2:きっかけ・パワハラ上司からの解放(28歳・女性)
広告代理店で上司からの激しいパワハラに悩んでいたBさんは、退職代行サービスを利用。
専門家が適切に対応し、スムーズに退職。
現在は、自分の強みを活かせる新しい職場で活躍しています。事例 3:きっかけ・会社への気遣い(27歳・女性)
長年勤めた日本企業を辞めて海外で働くことを決意したDさんは、会社への気遣いから直接言い出せずにいましたが、退職代行サービスを利用することでスムーズに退職手続きを完了。
現在、はニューヨークの広告代理店で自分の可能性を広げています。事例 4:退職を申し出ることへの負い目(29歳・男性)
大手メーカーで働きながら自身のビジネスアイデアを温めていたEさんは、会社への負い目から退職を切り出せずにいましたが、退職代行サービスを利用してスムーズに退職手続きを完了。
現在は、自身のスタートアップ企業を軌道に乗せ、急成長を遂げています。退職後のキャリアと精神的変化
退職代行を利用して退職した人々は、その後、心身の健康を取り戻し、新たなキャリアをスタートさせているケースが多く見られます。
一時的な不安や罪悪感を感じる人もいますが、結果的に自身の健康や将来のために良い選択だったと捉えていることが多いようです。
退職代行は、困難な状況から抜け出し、新たなスタートを切るための有効な手段となり得ます。まとめ:あなたにとって最適な退職方法を選ぶために
退職代行は、「やめとけ」という意見がある一方で、パワハラやメンタル不調、引き止めなどで自力での退職が困難な状況にある人にとっては、非常に有効な選択肢となり得ます。
重要なのは、退職代行のメリット(精神的負担の軽減、迅速な退職実現など)とデメリット(費用、キャリアへの影響懸念、トラブルリスクなど)を十分に理解し、ご自身の状況や優先順位と照らし合わせて検討することです。
-