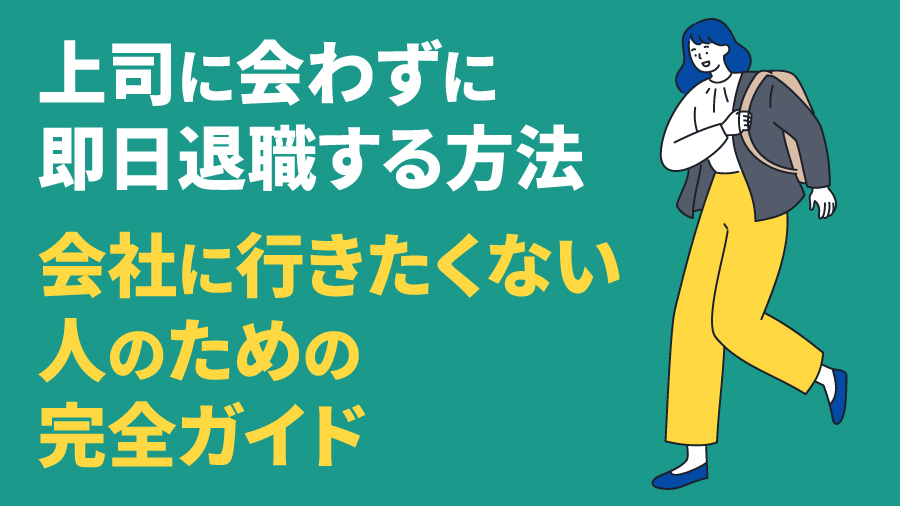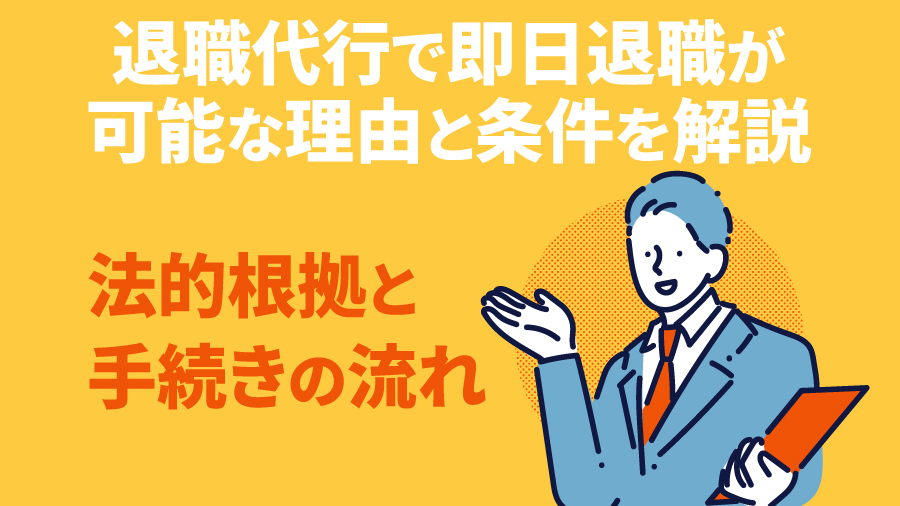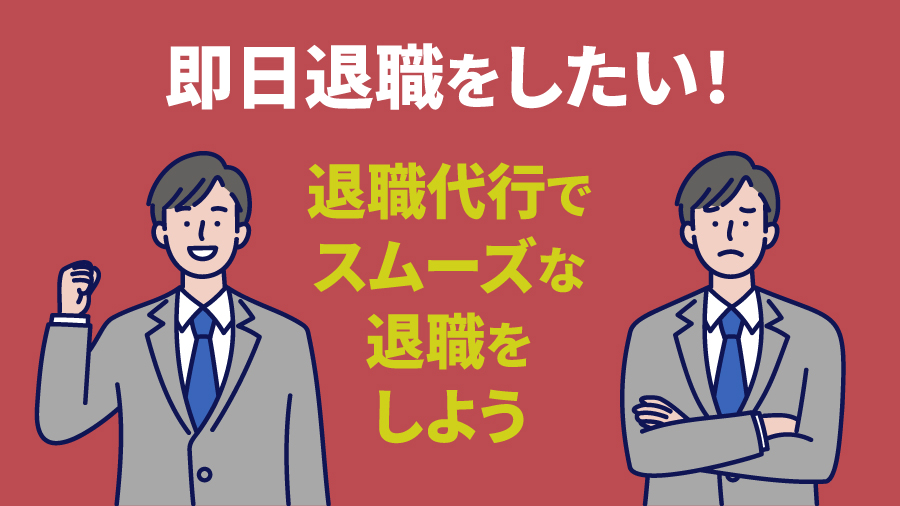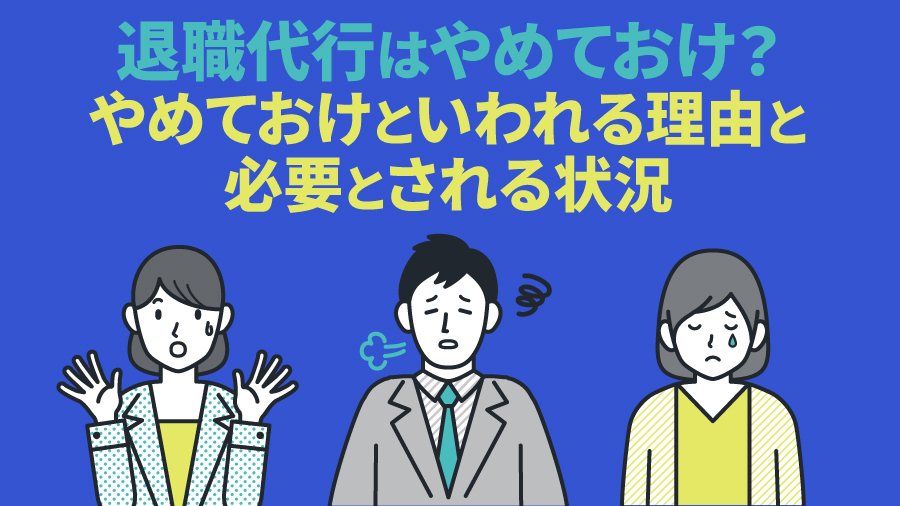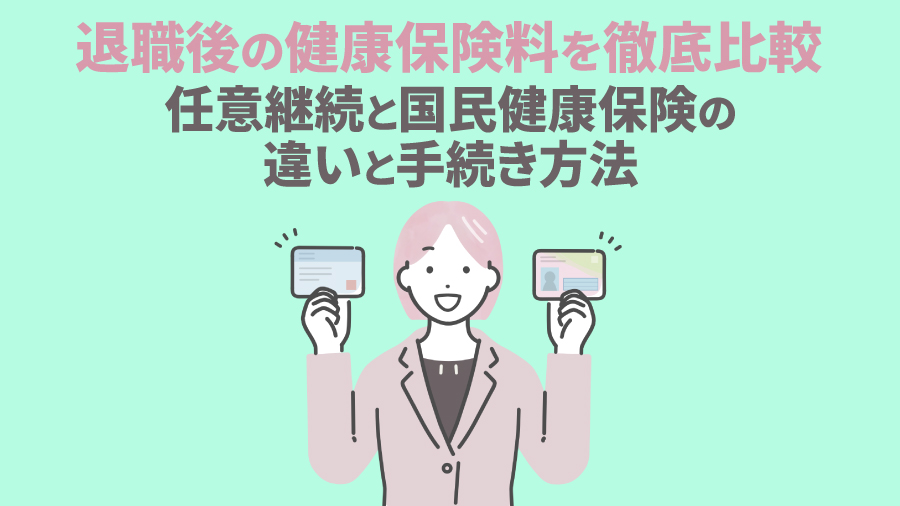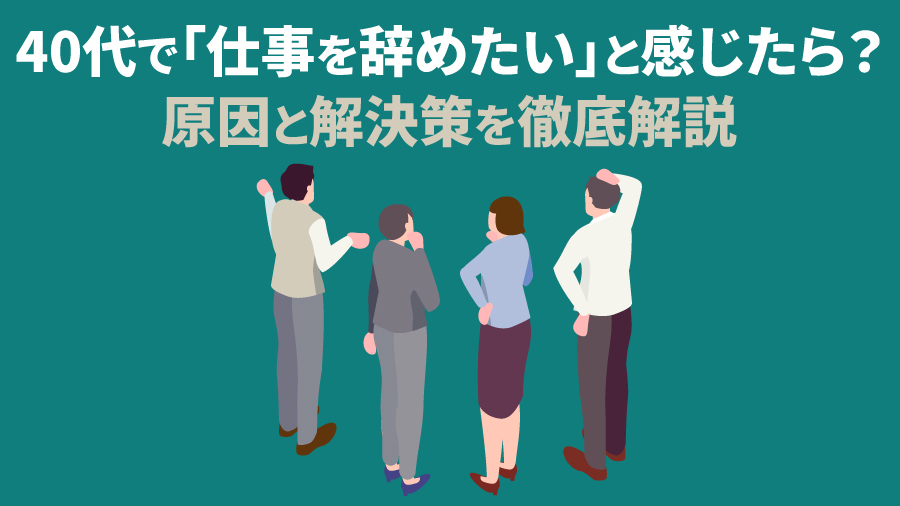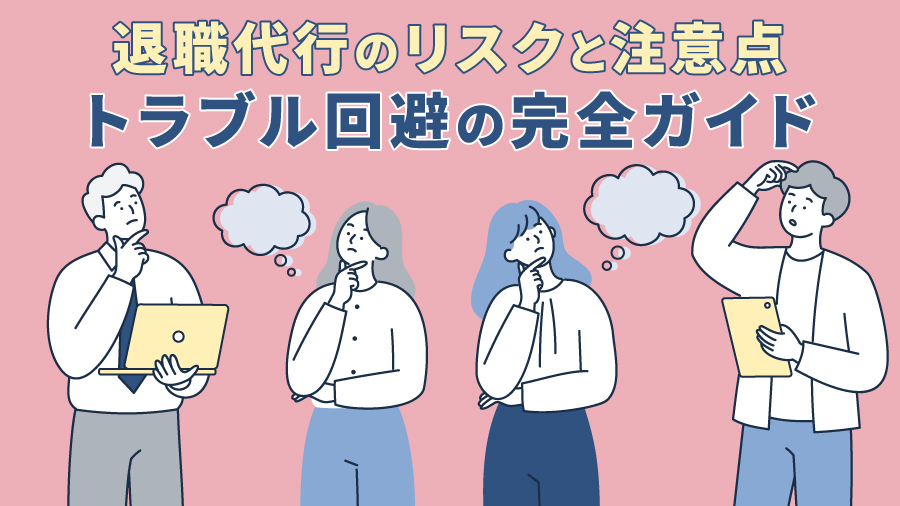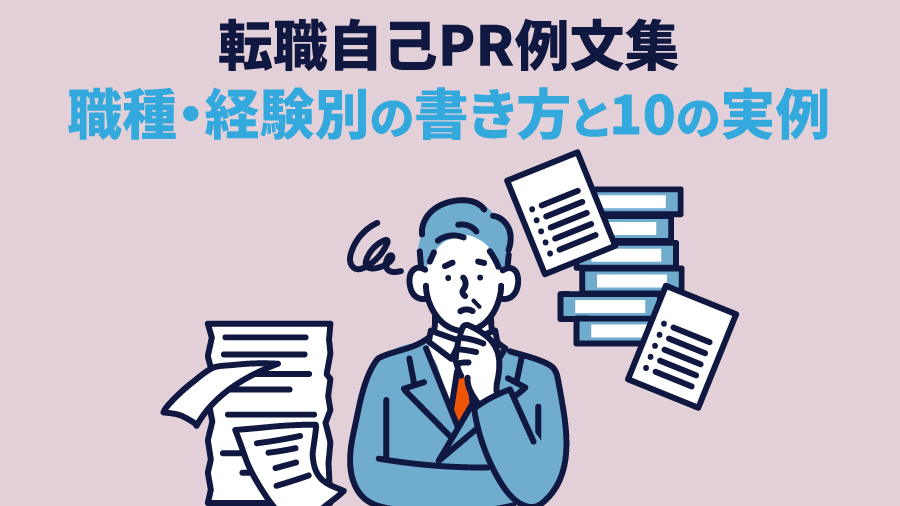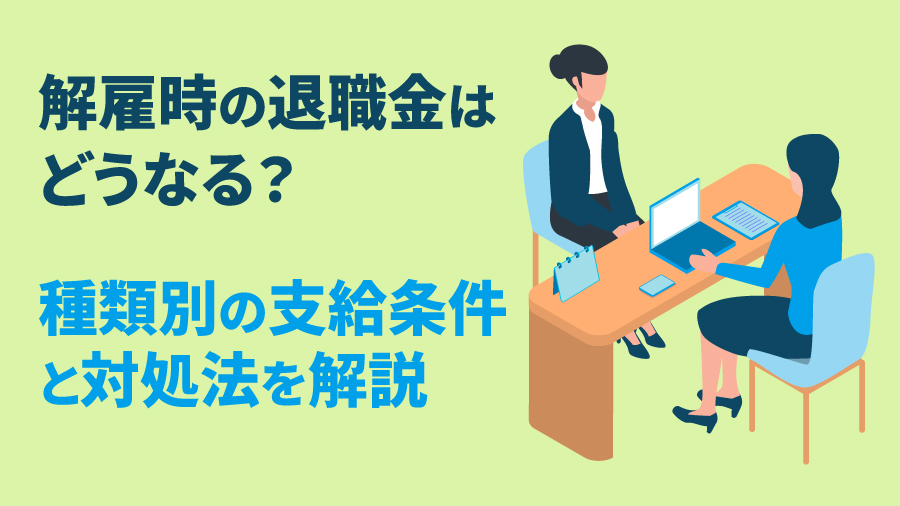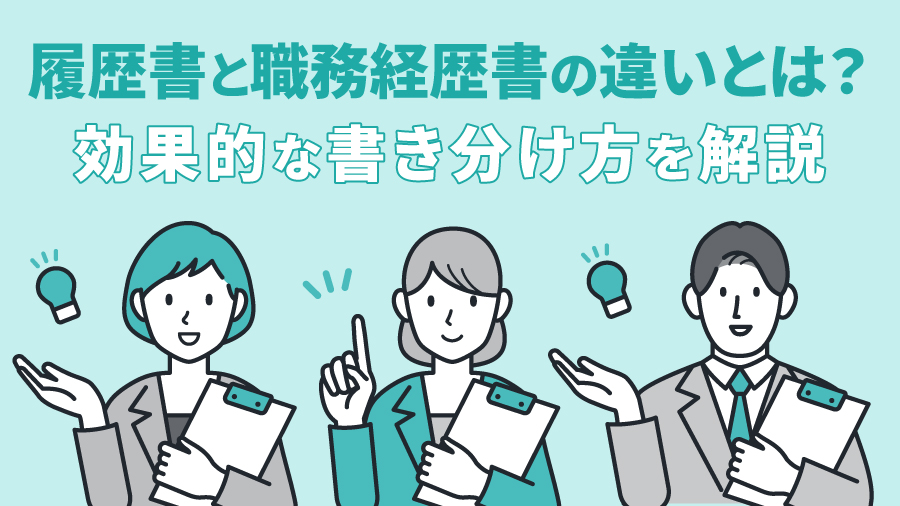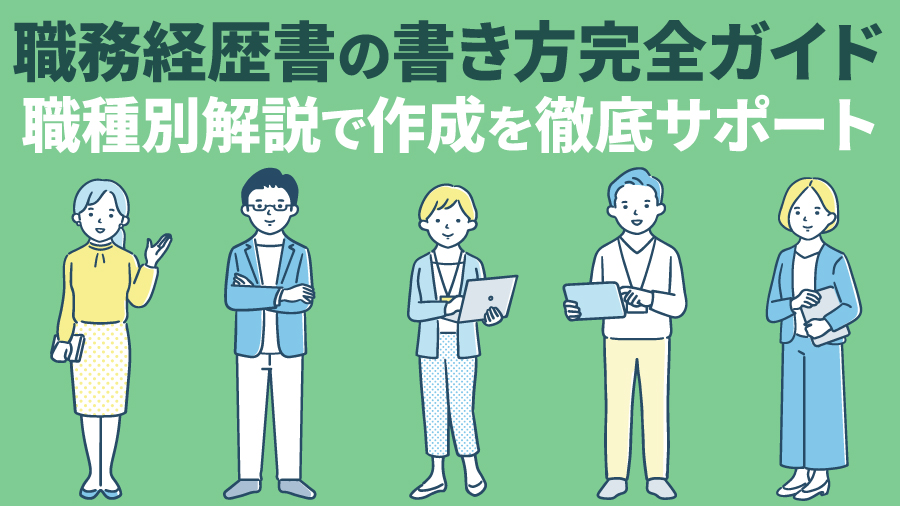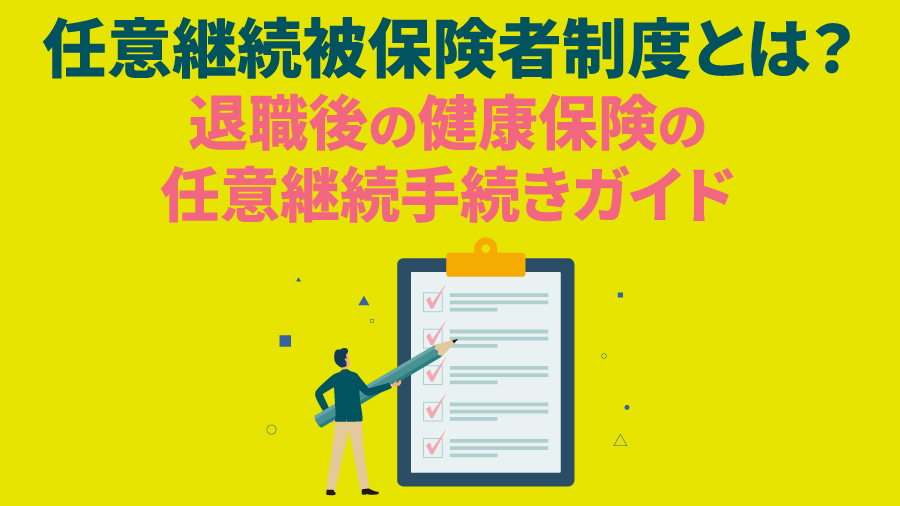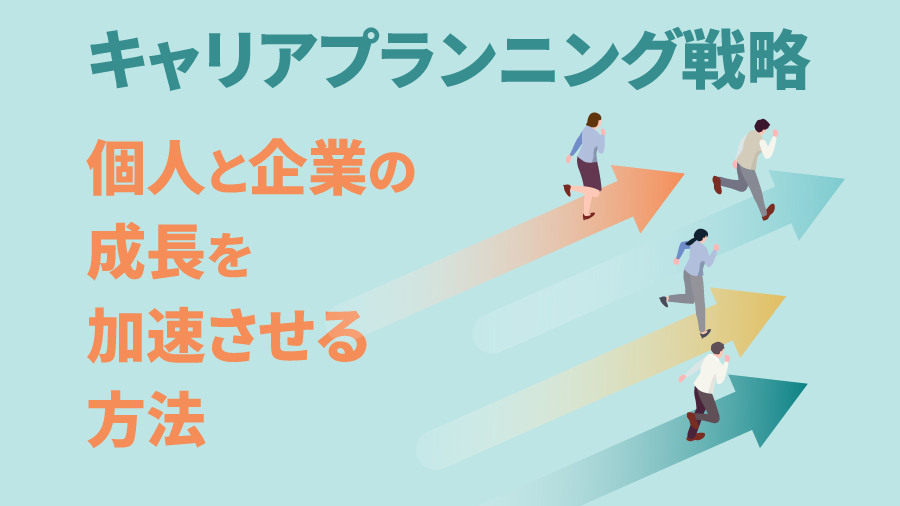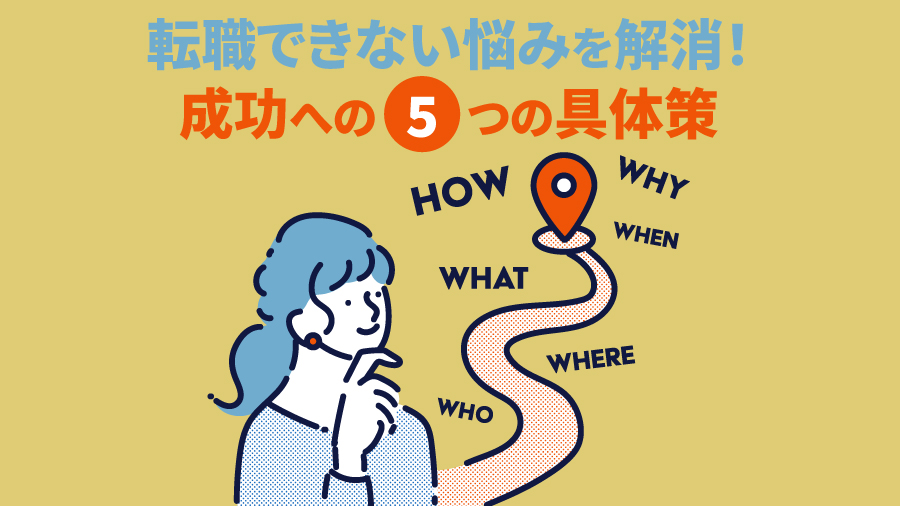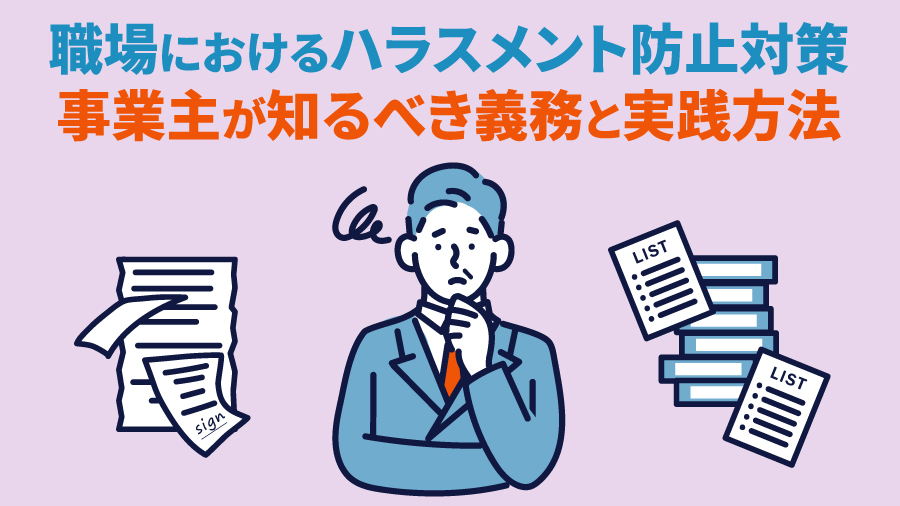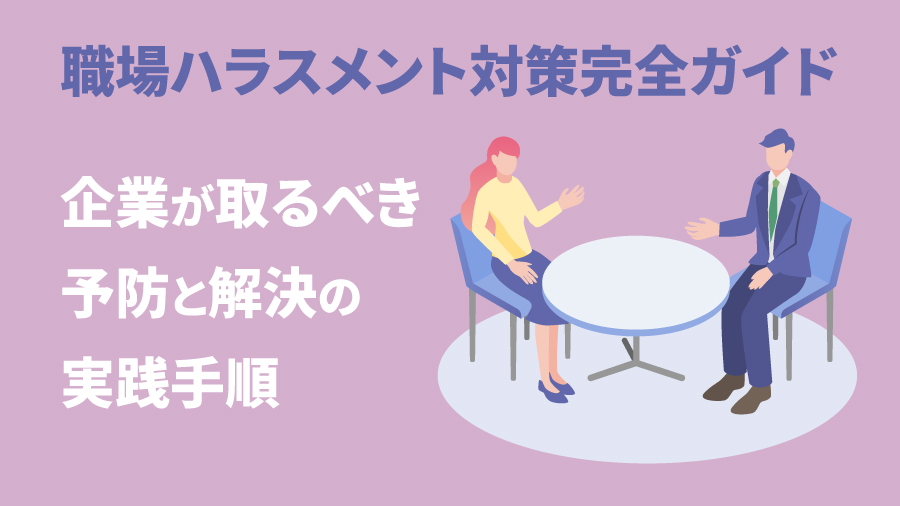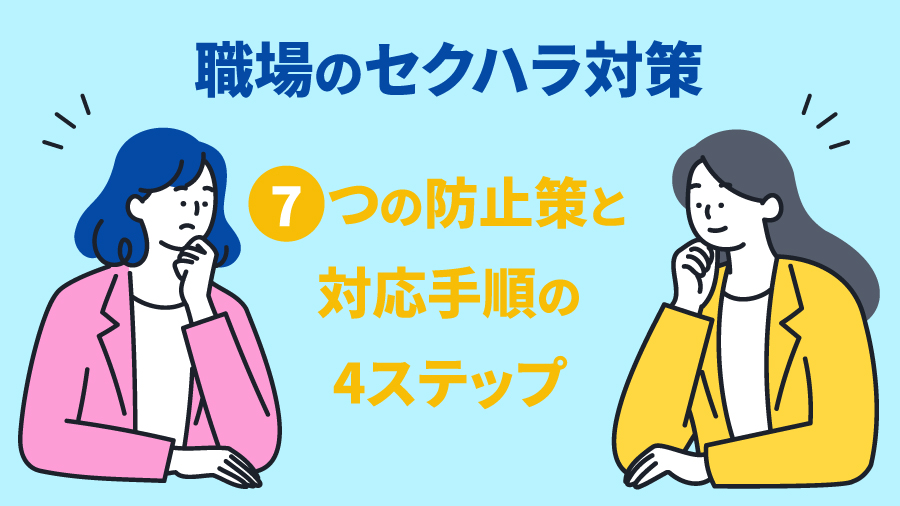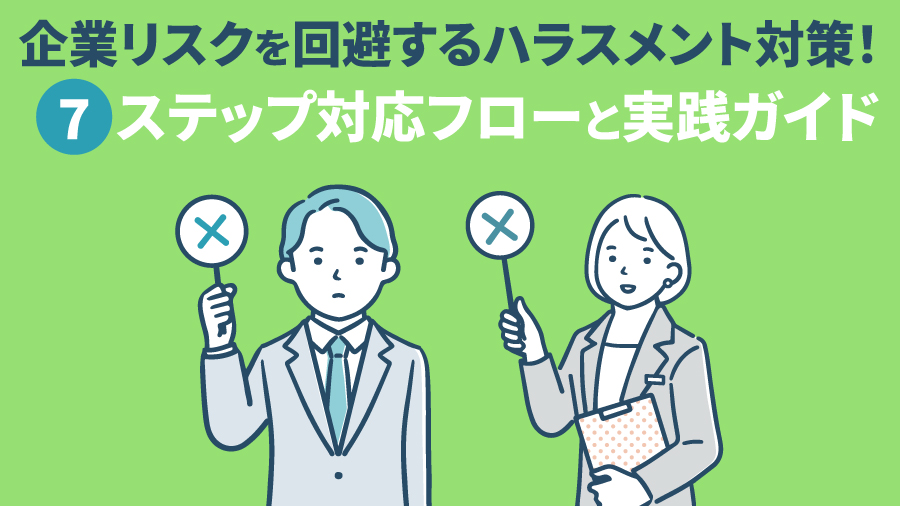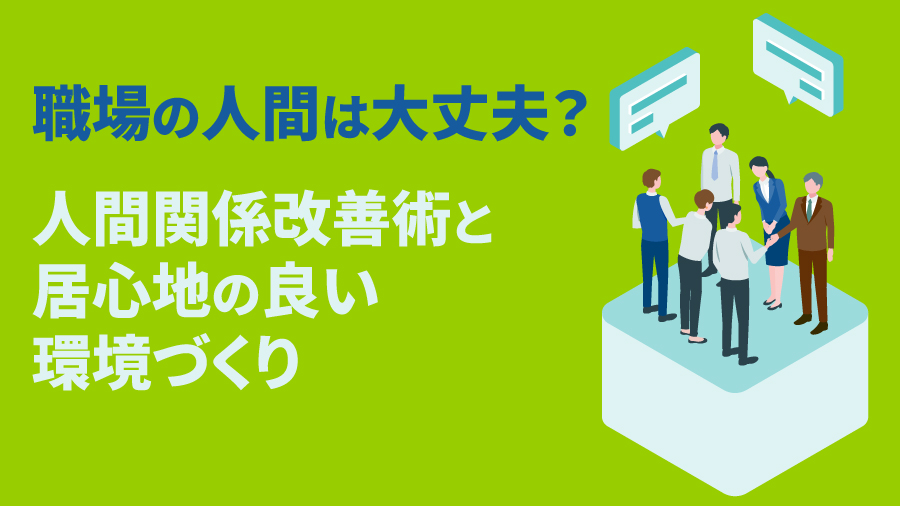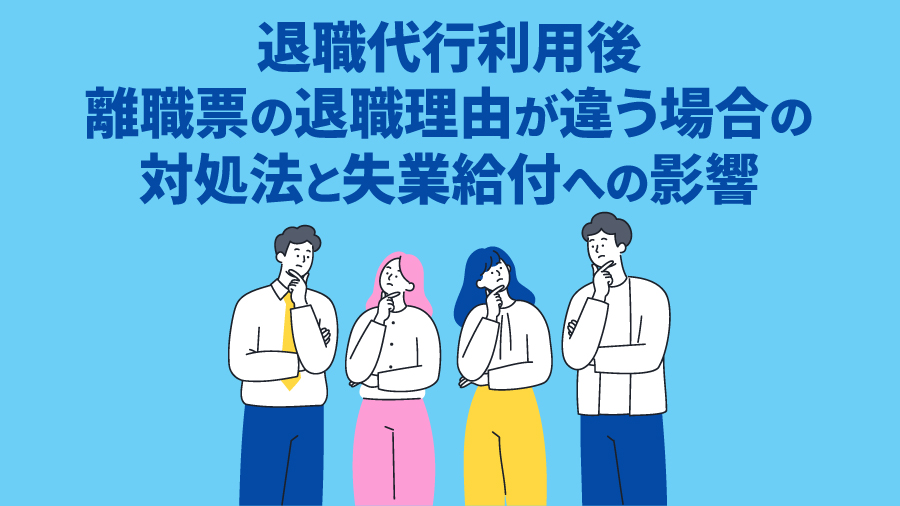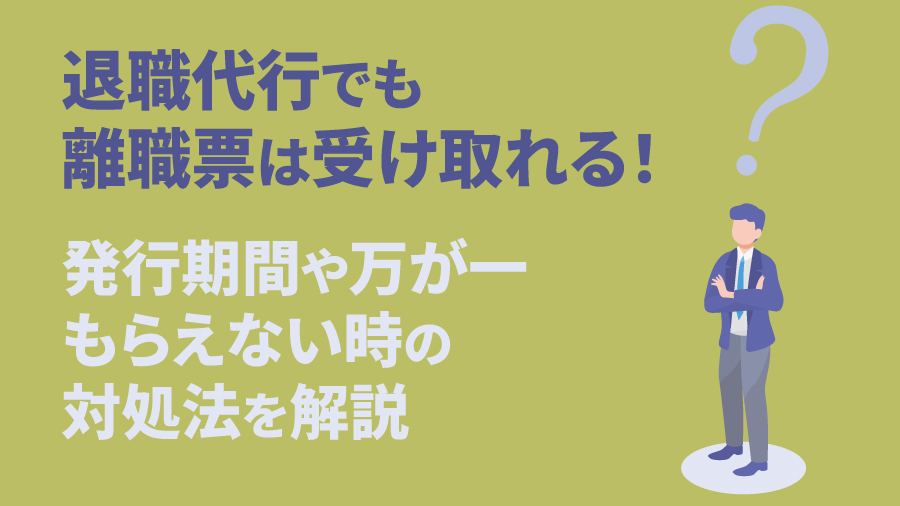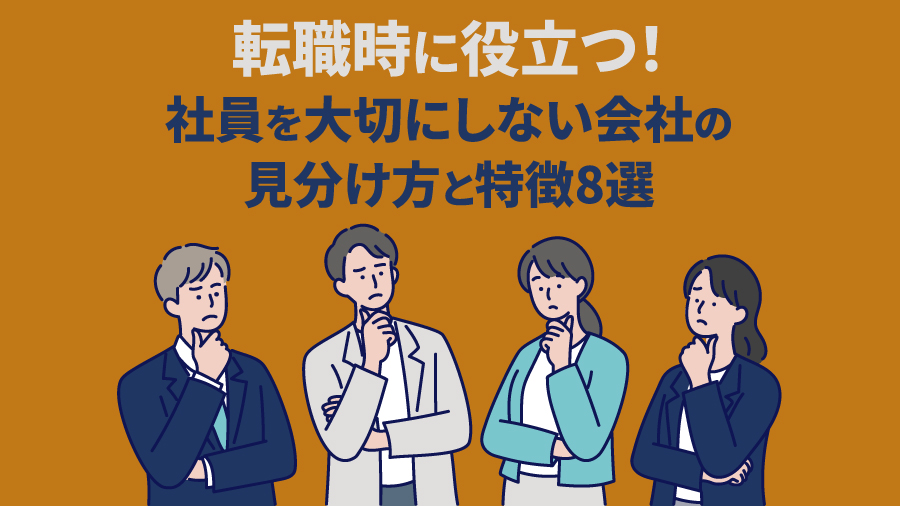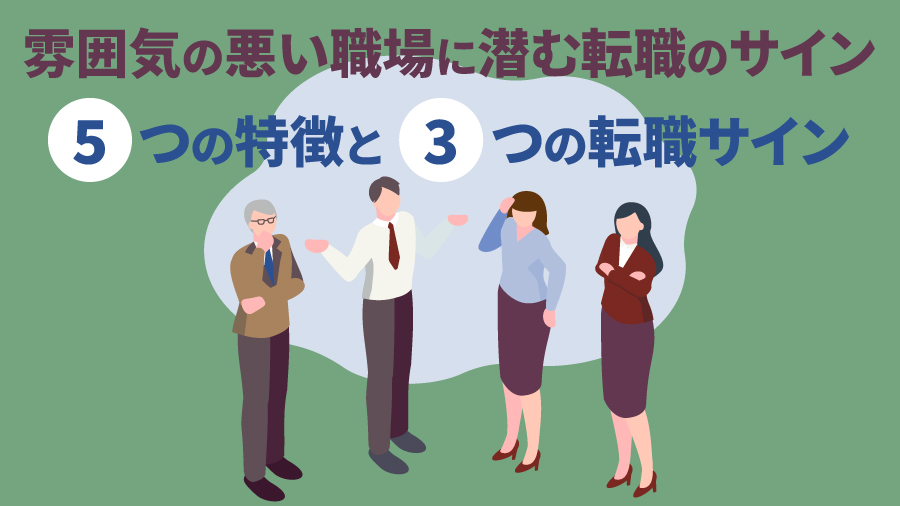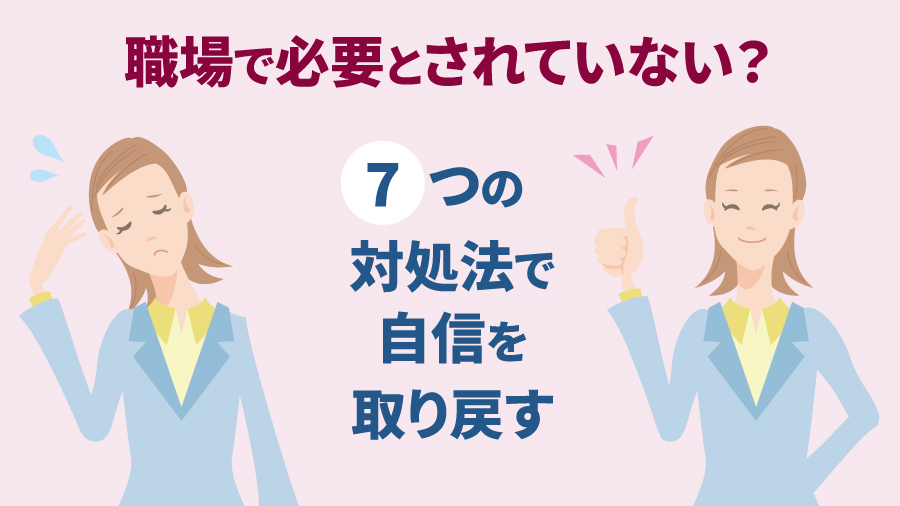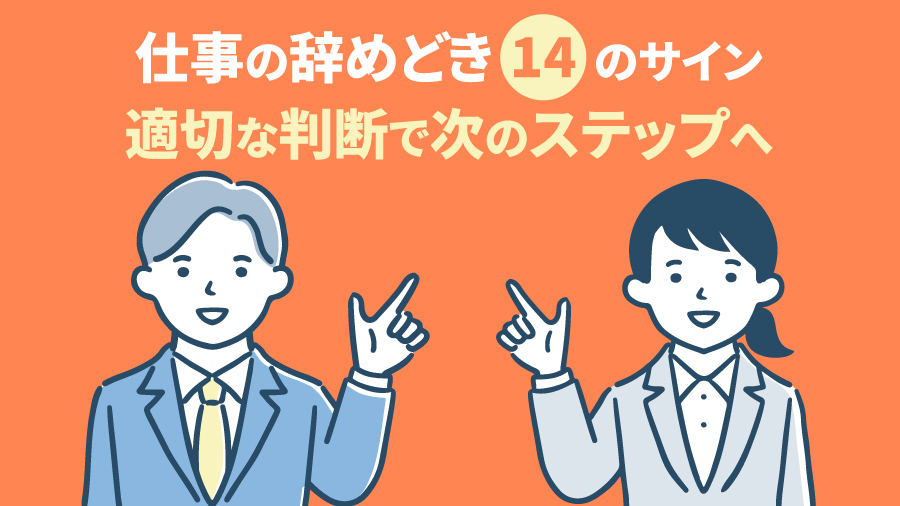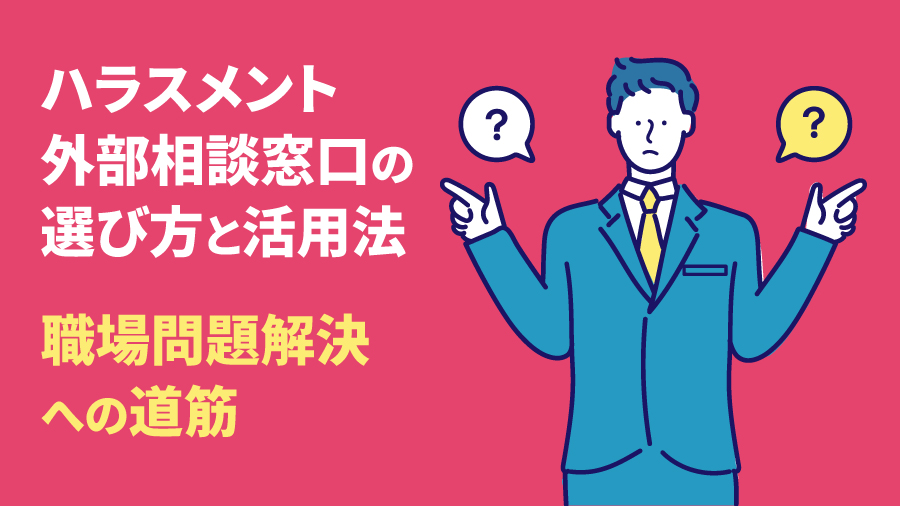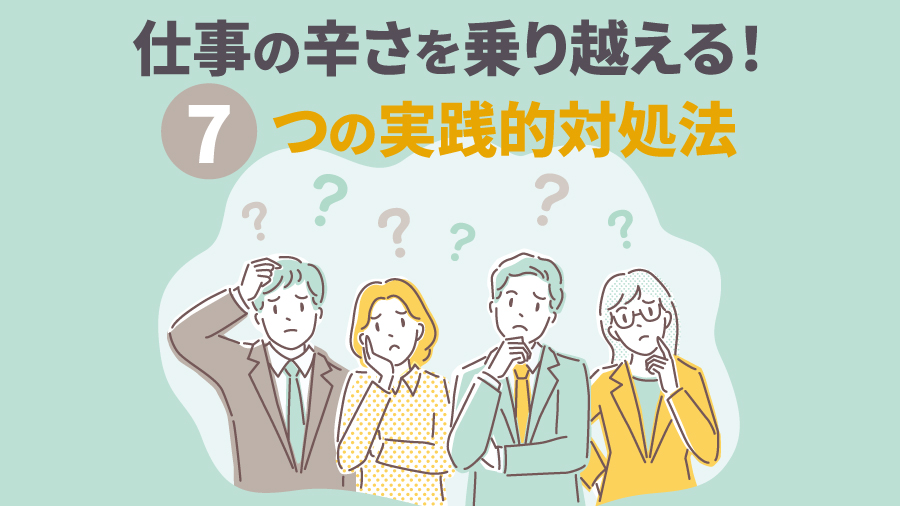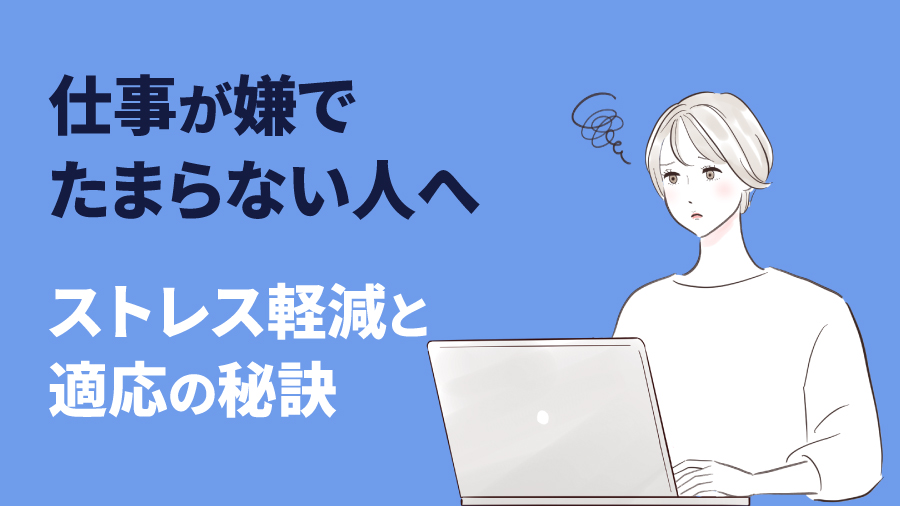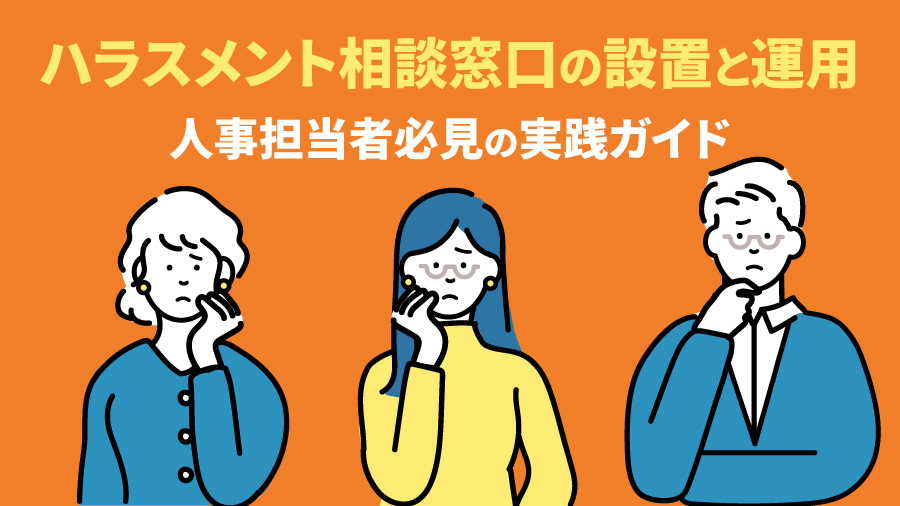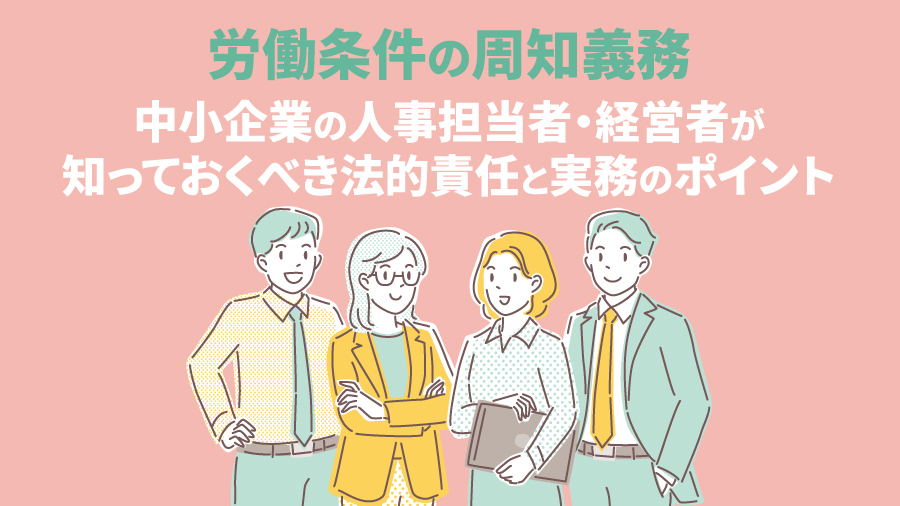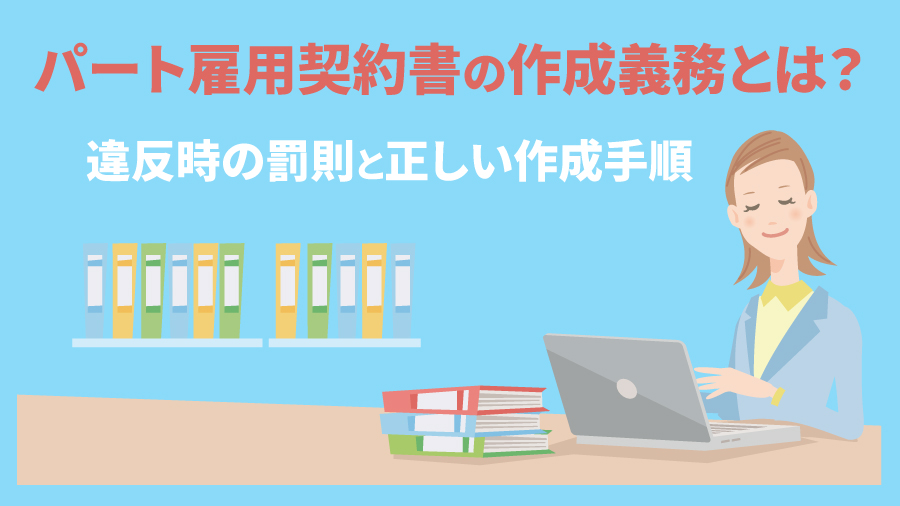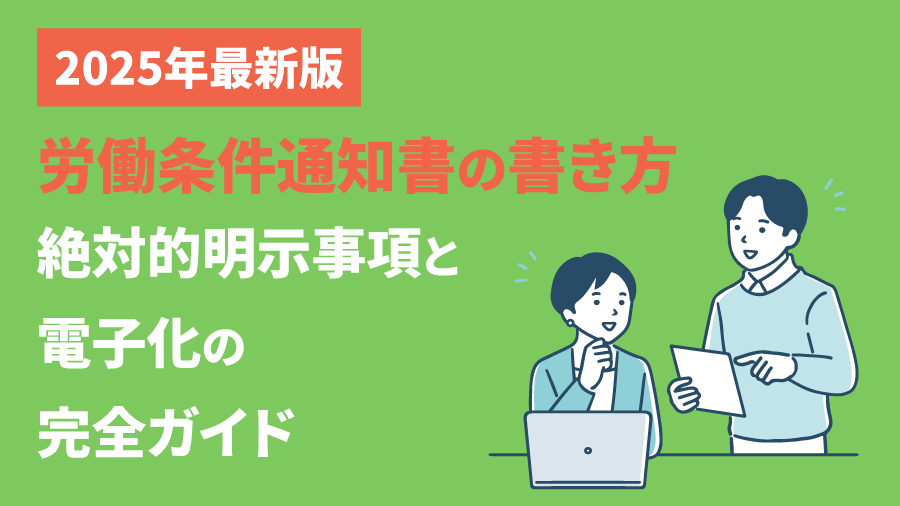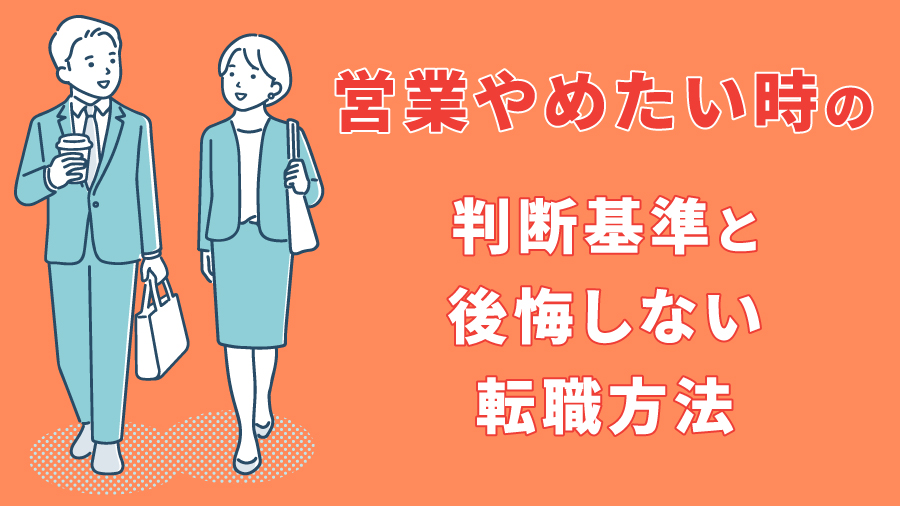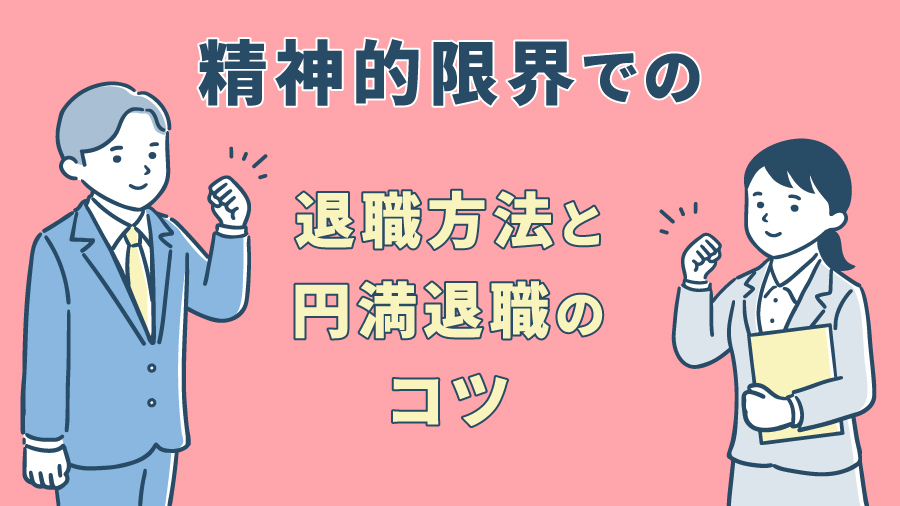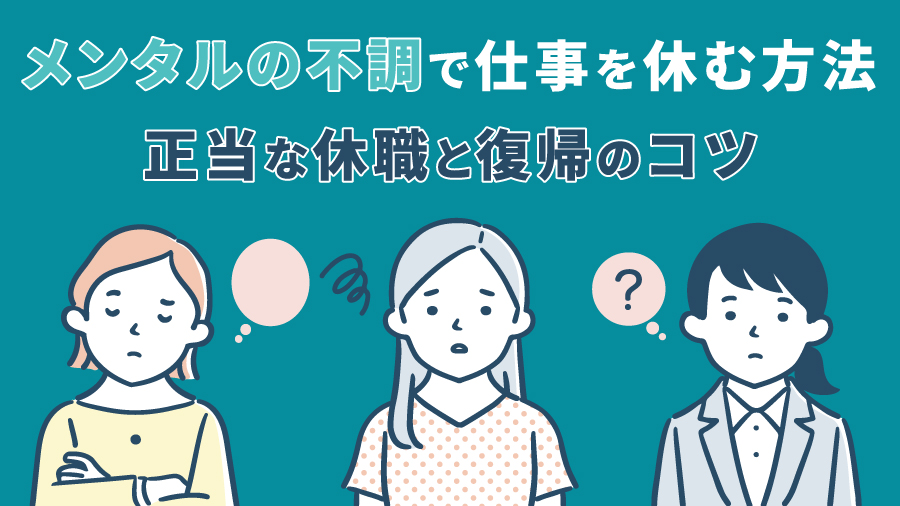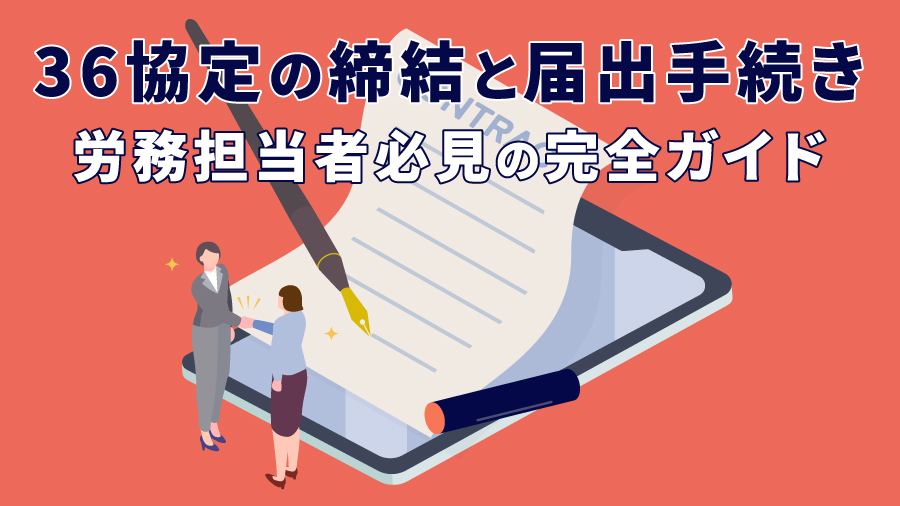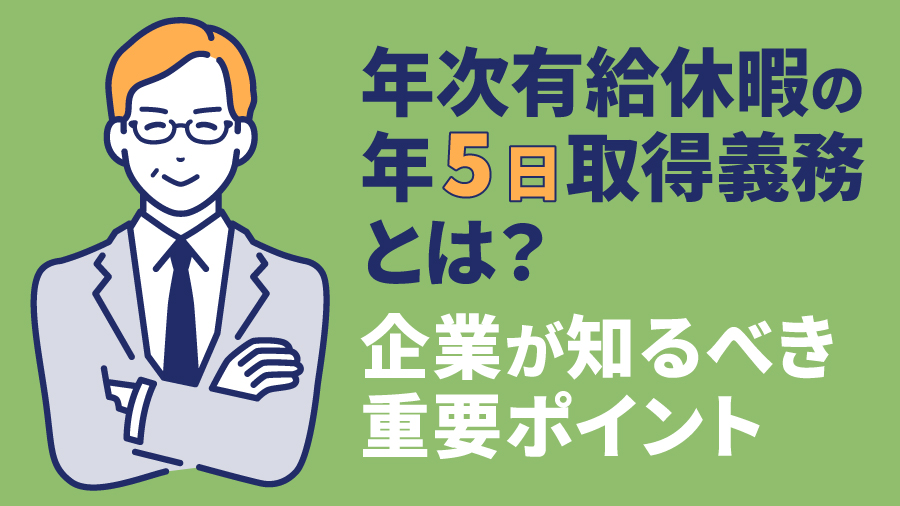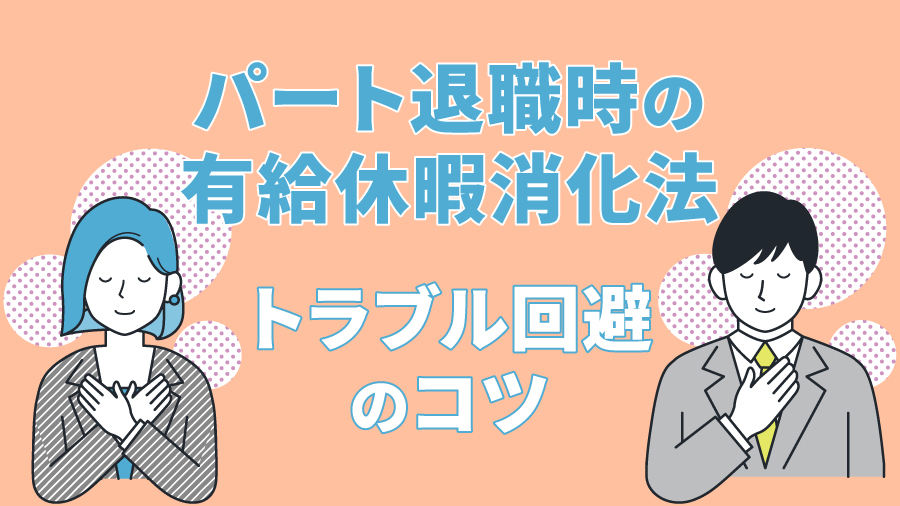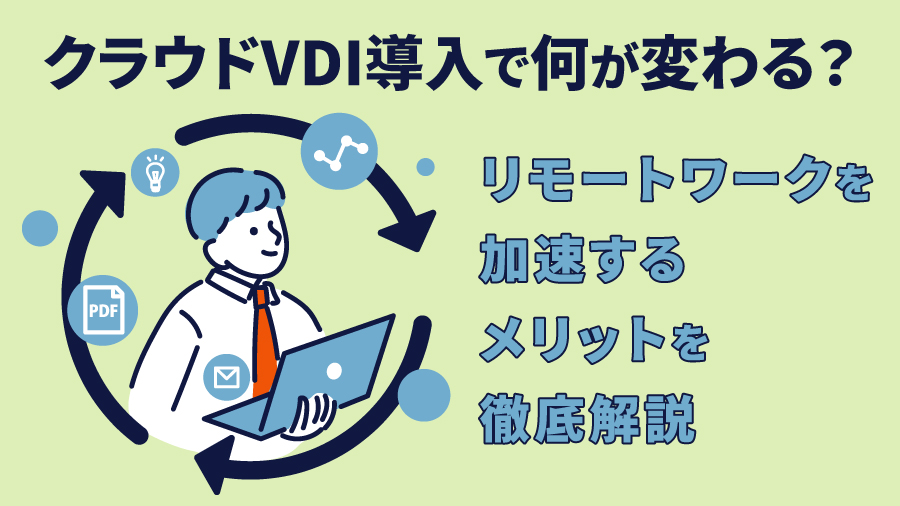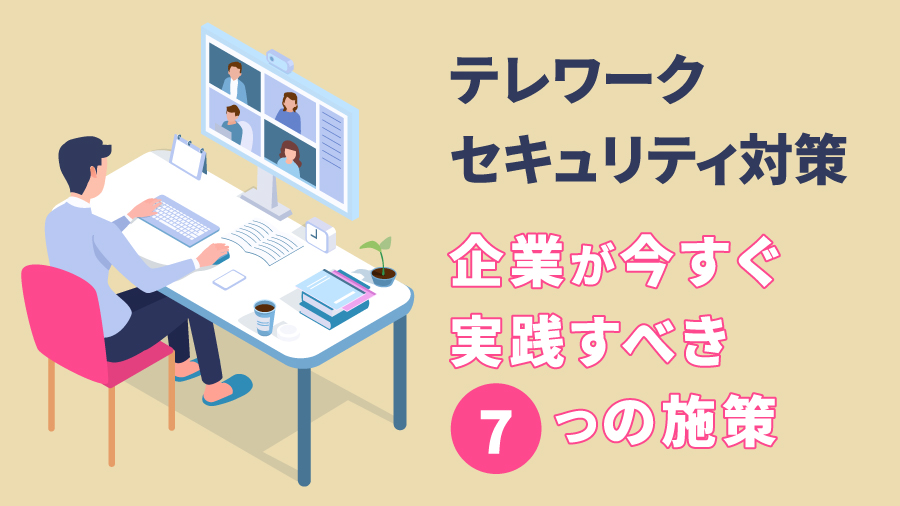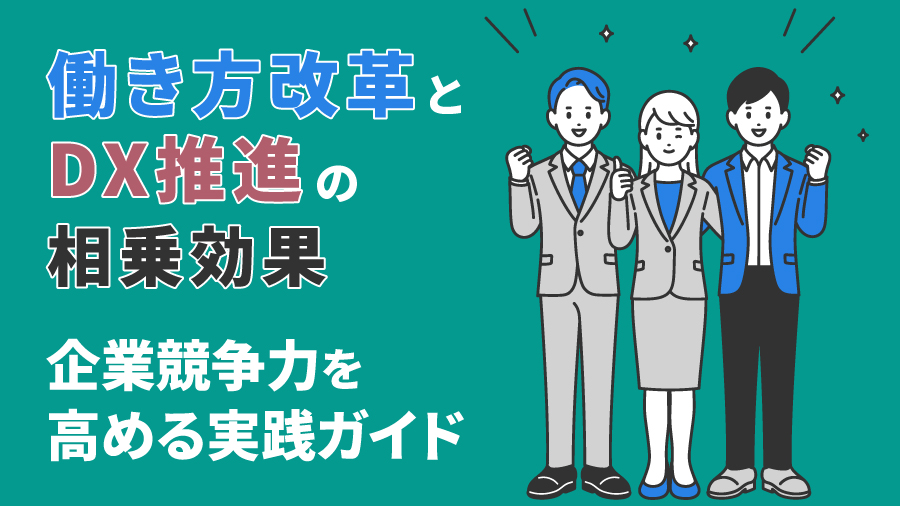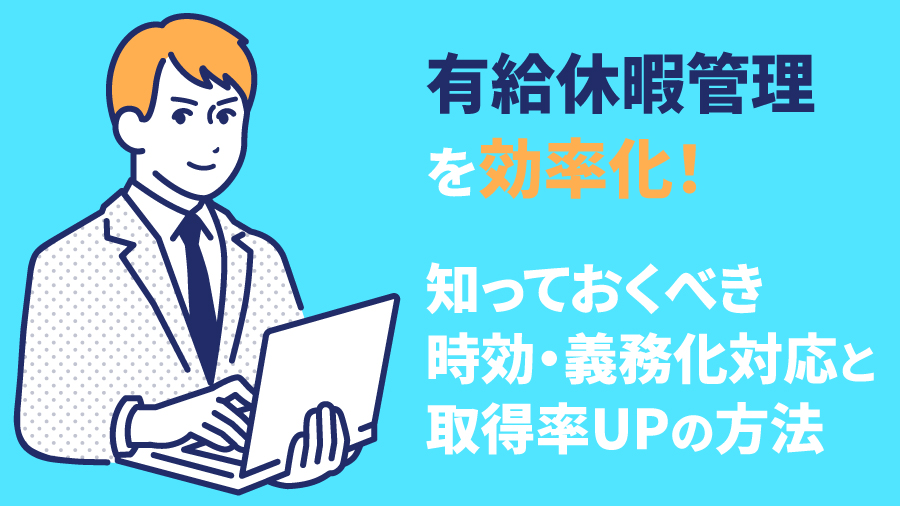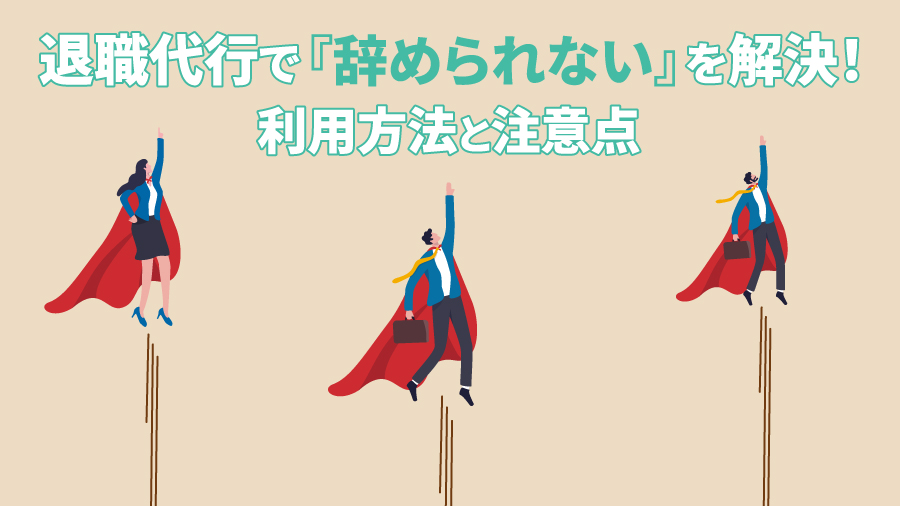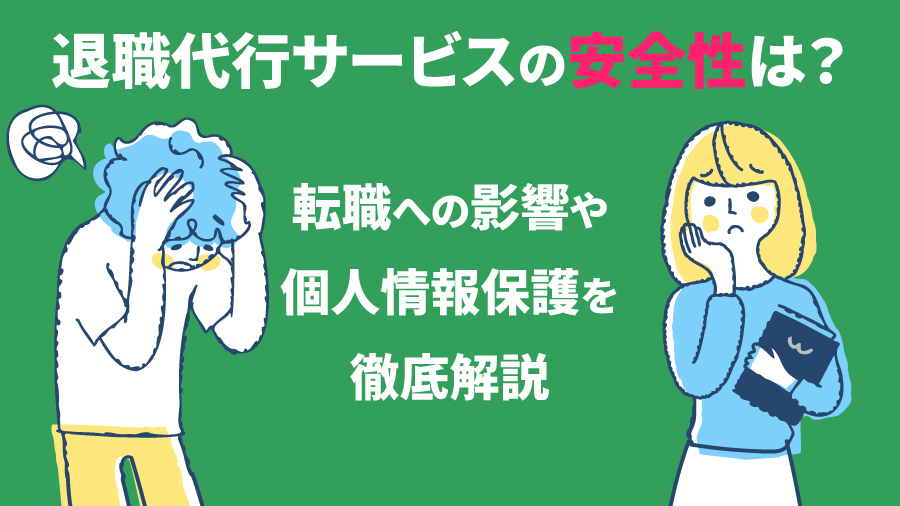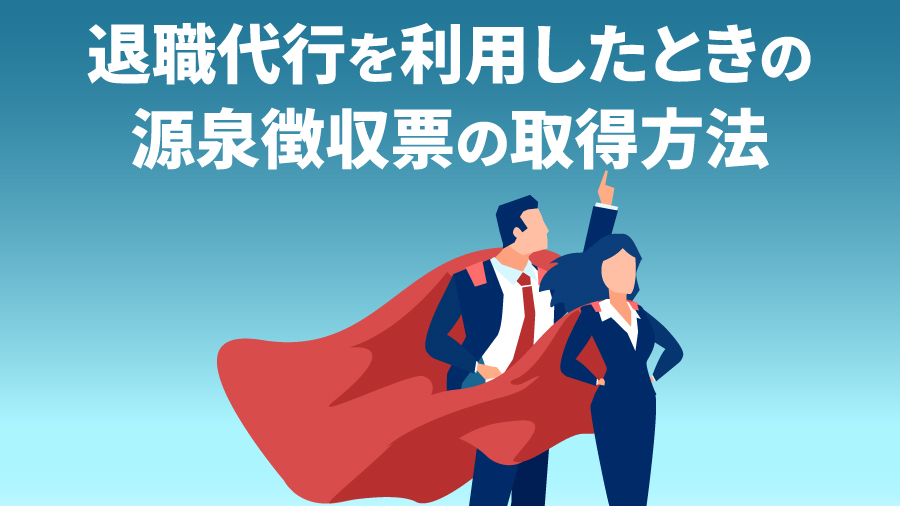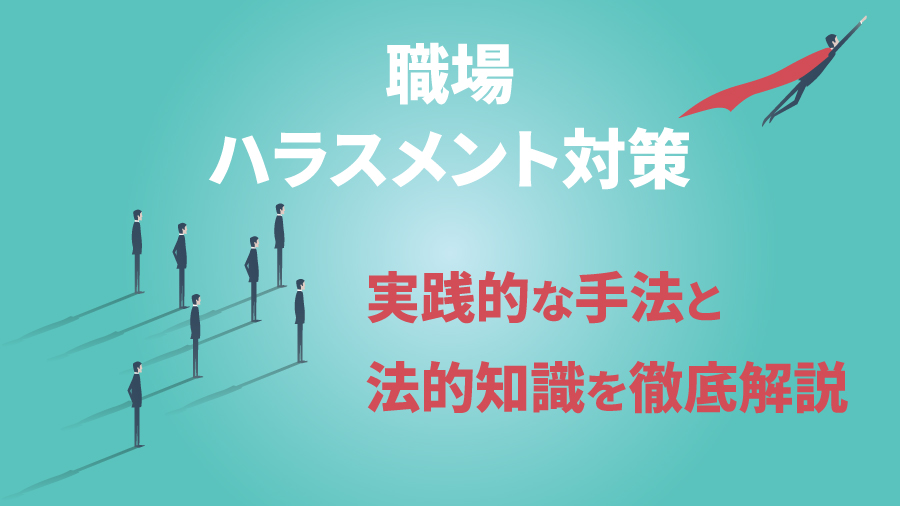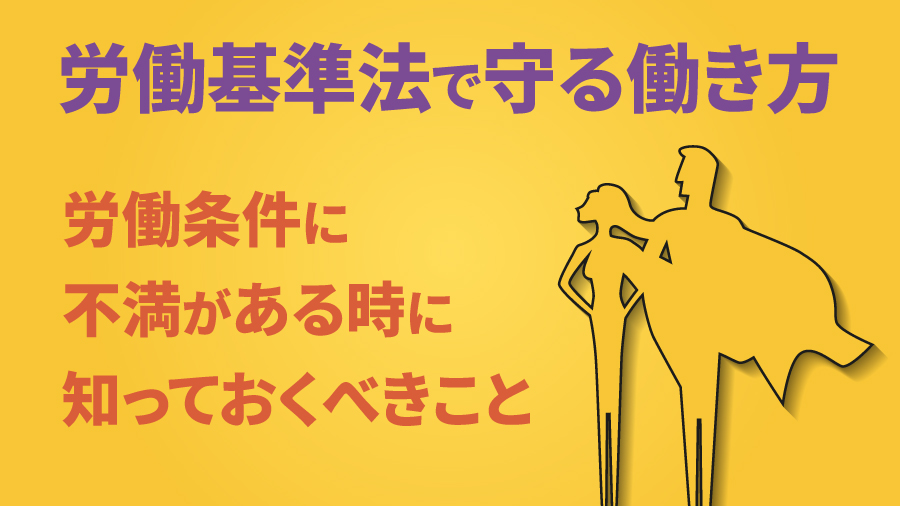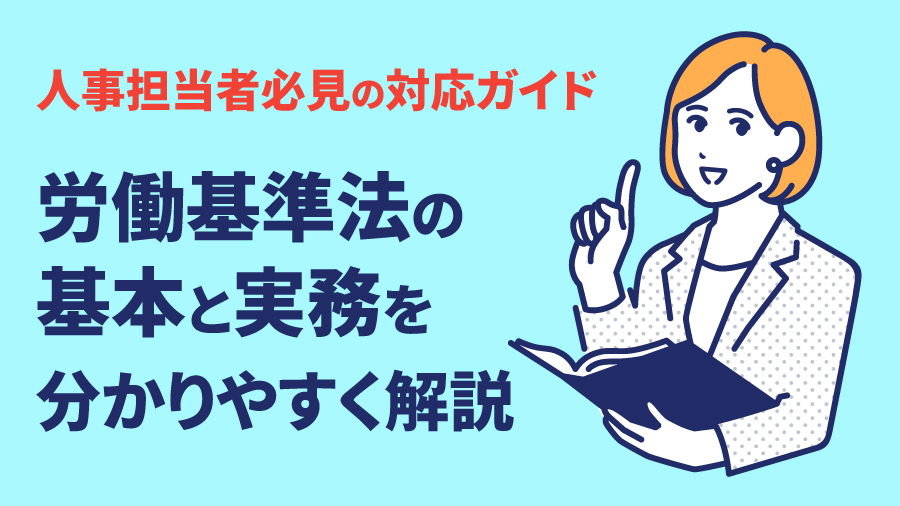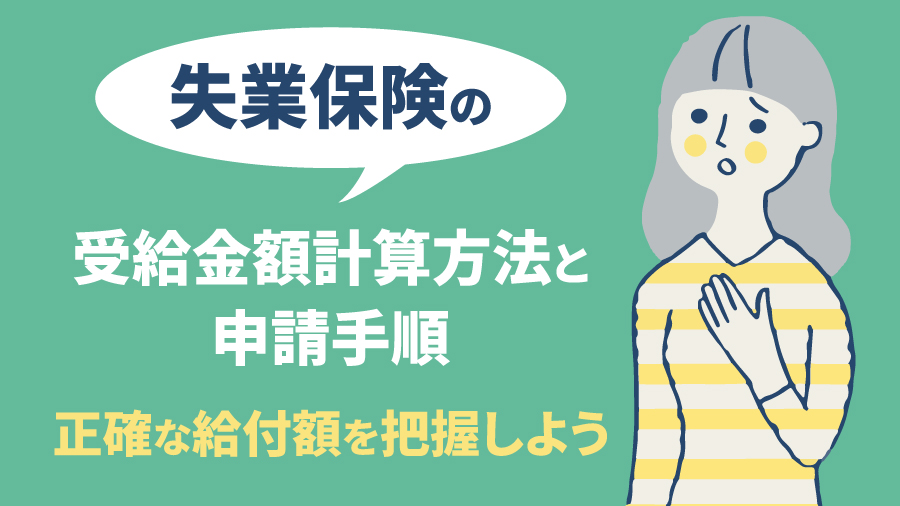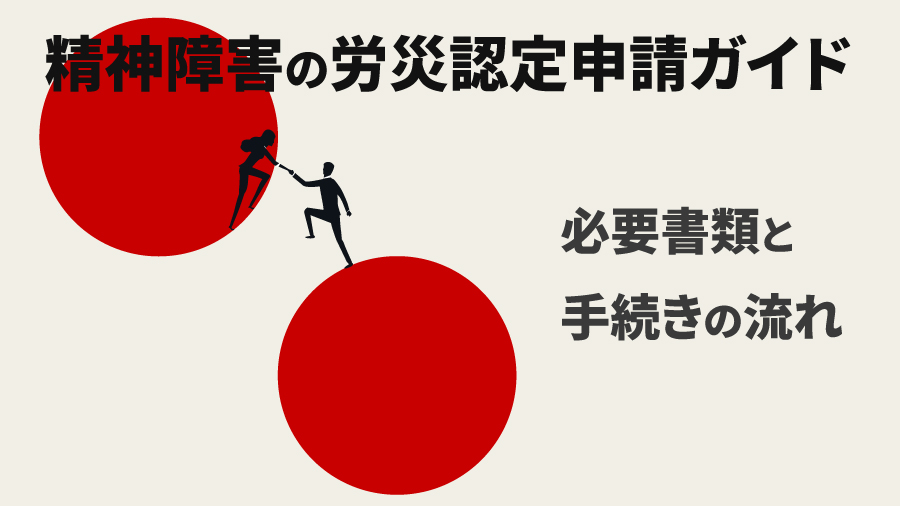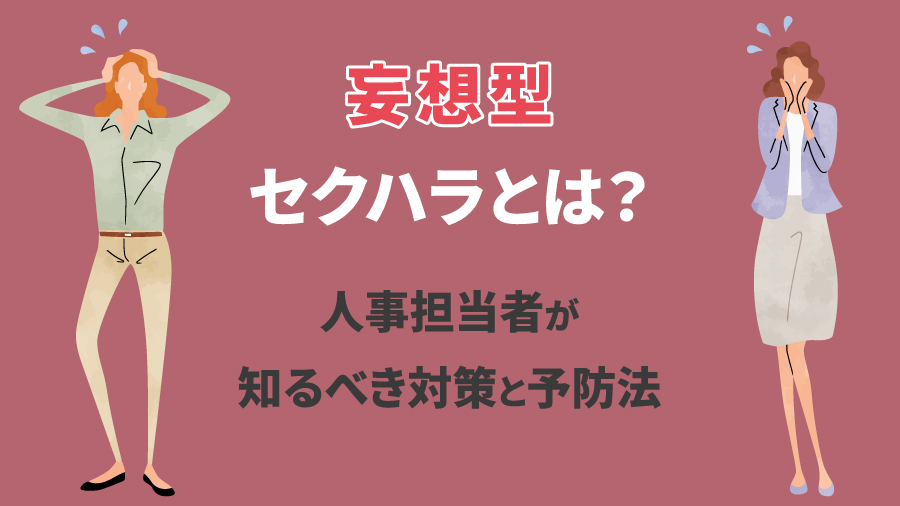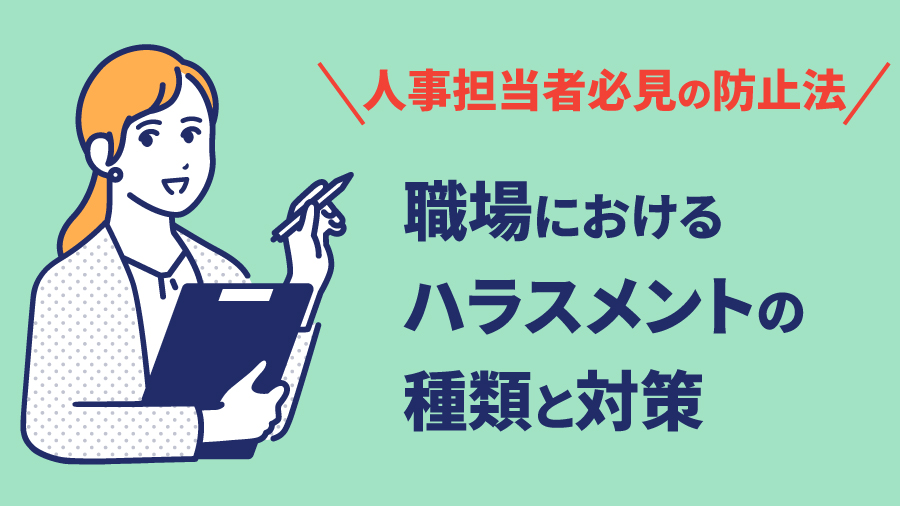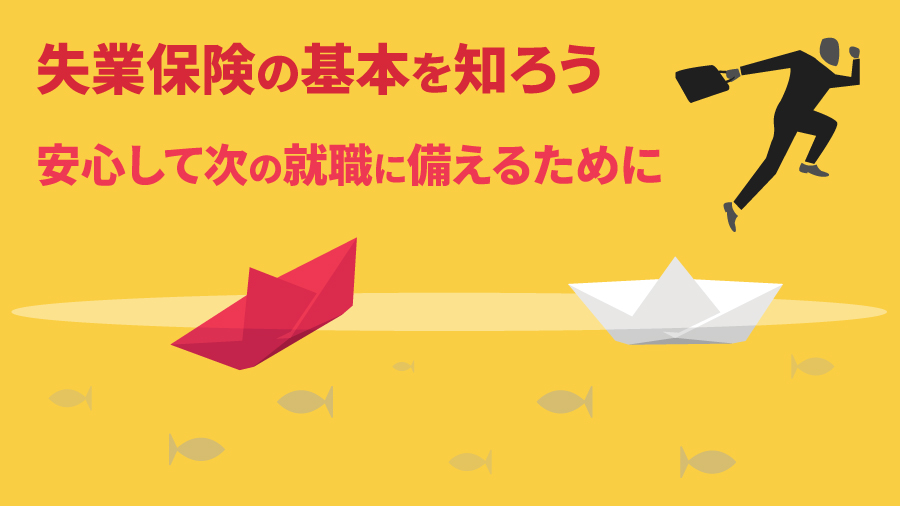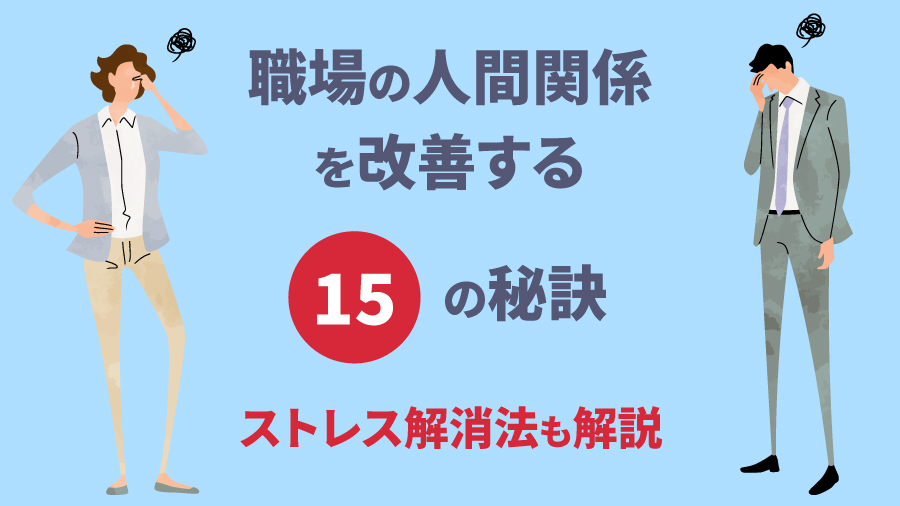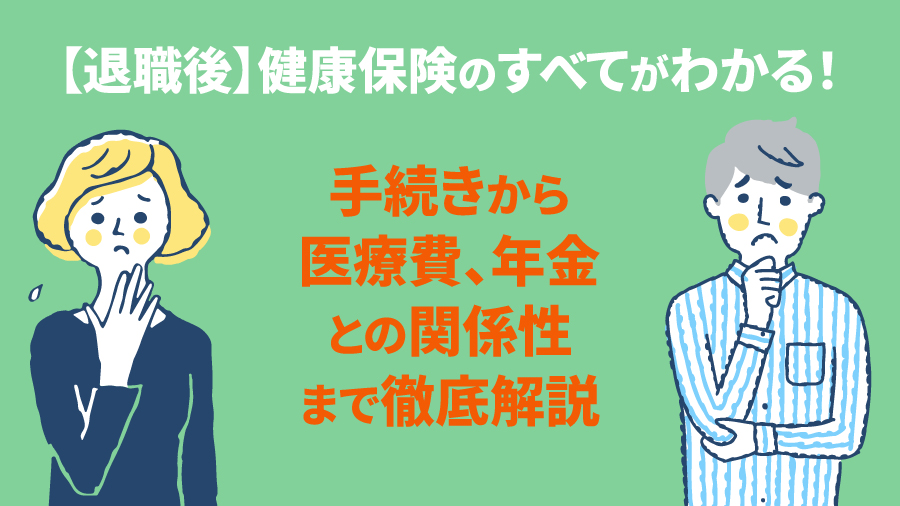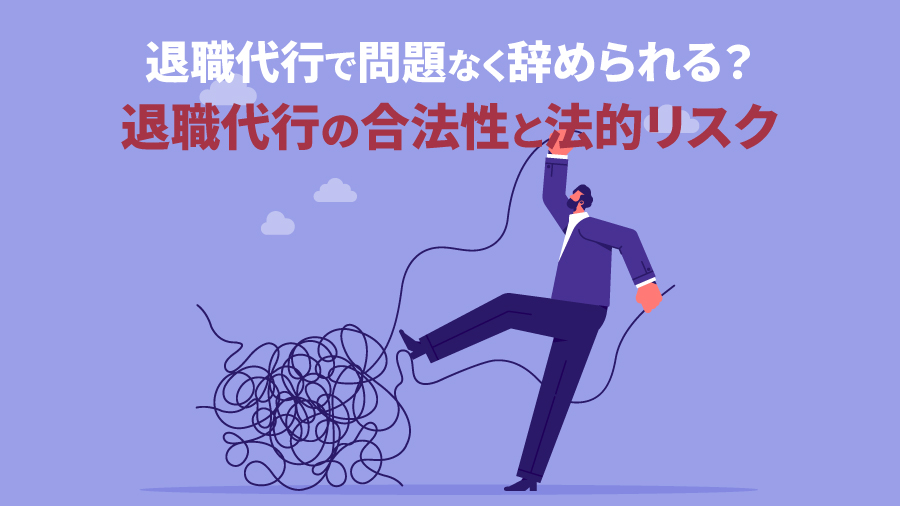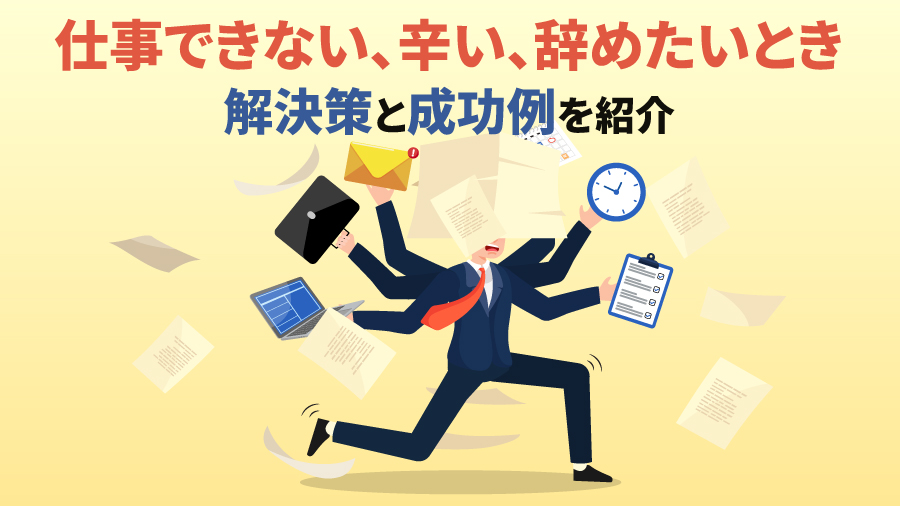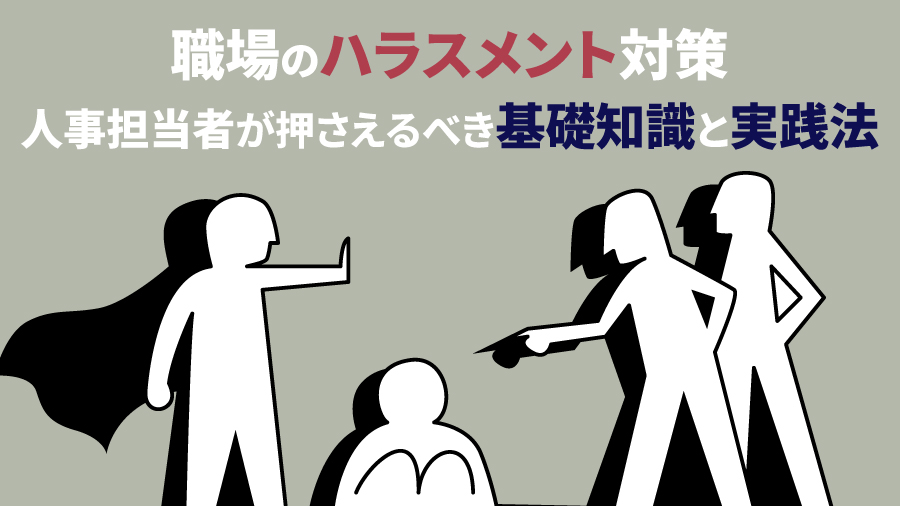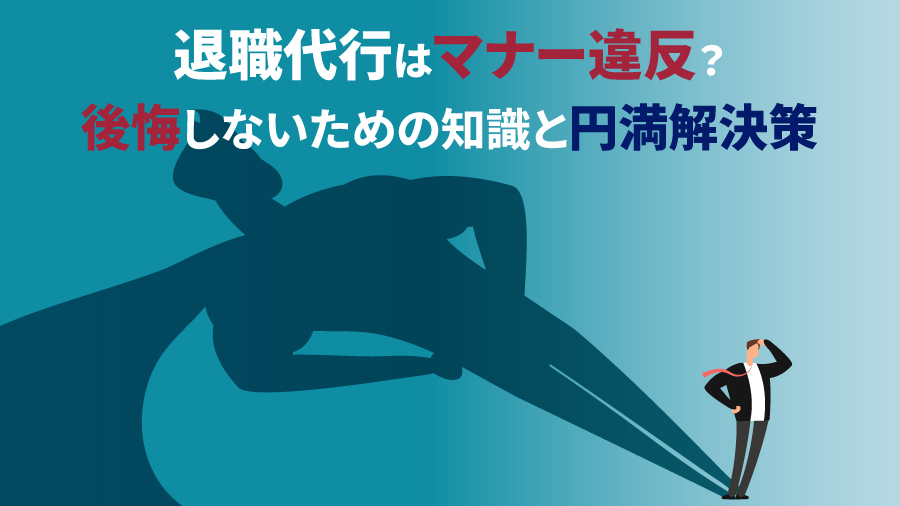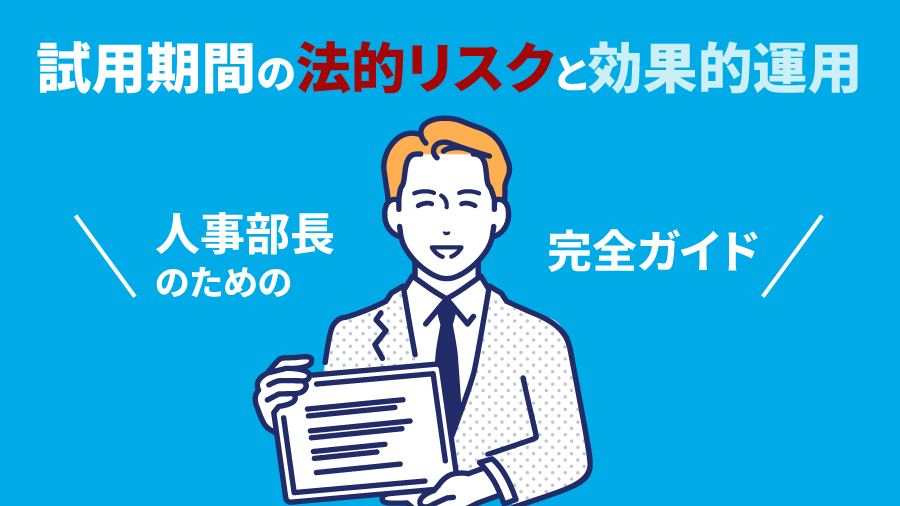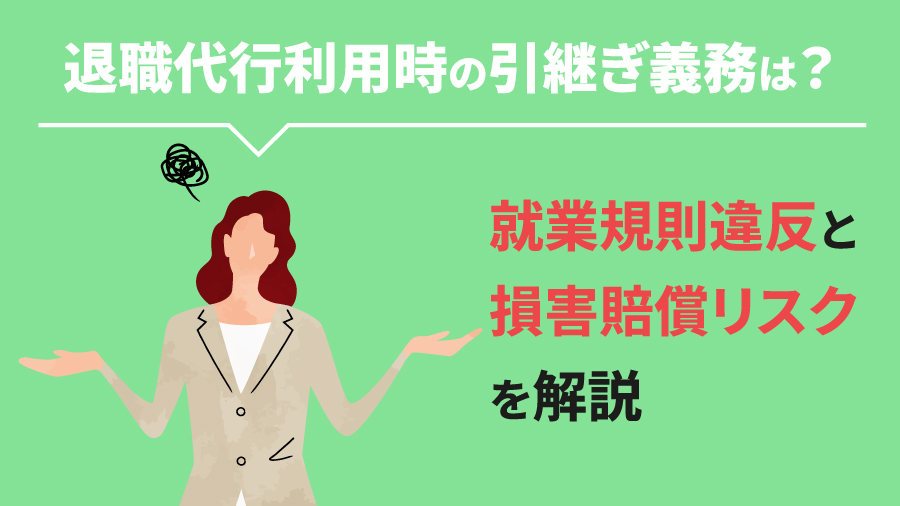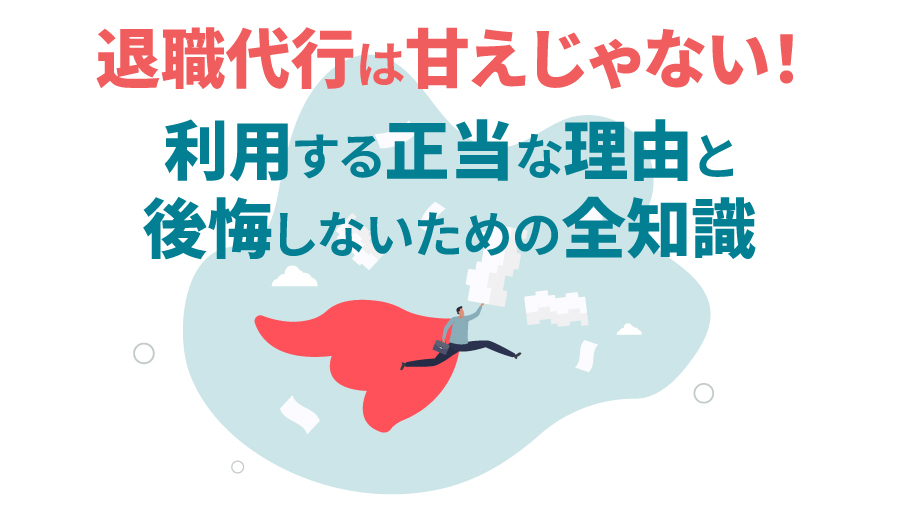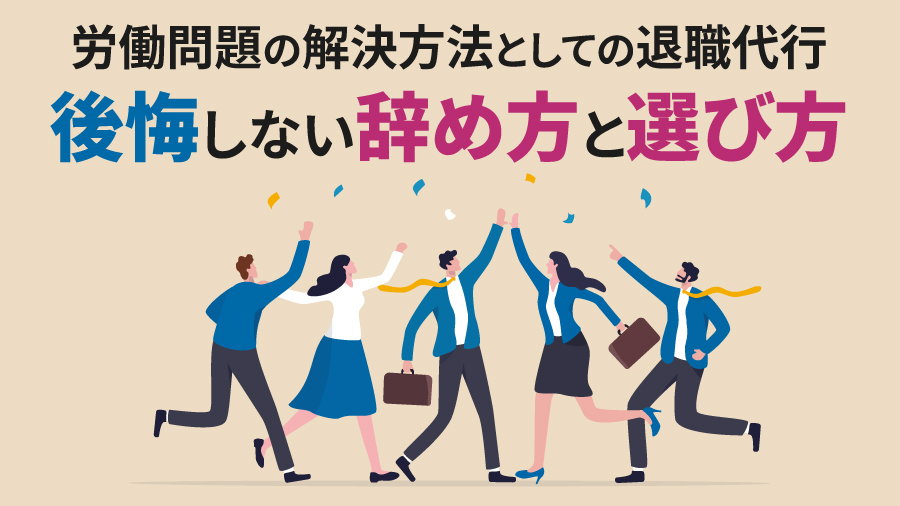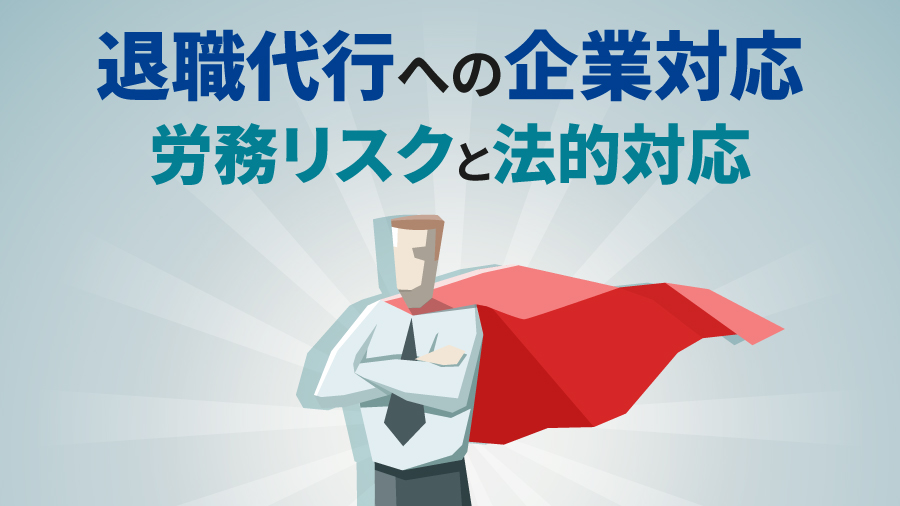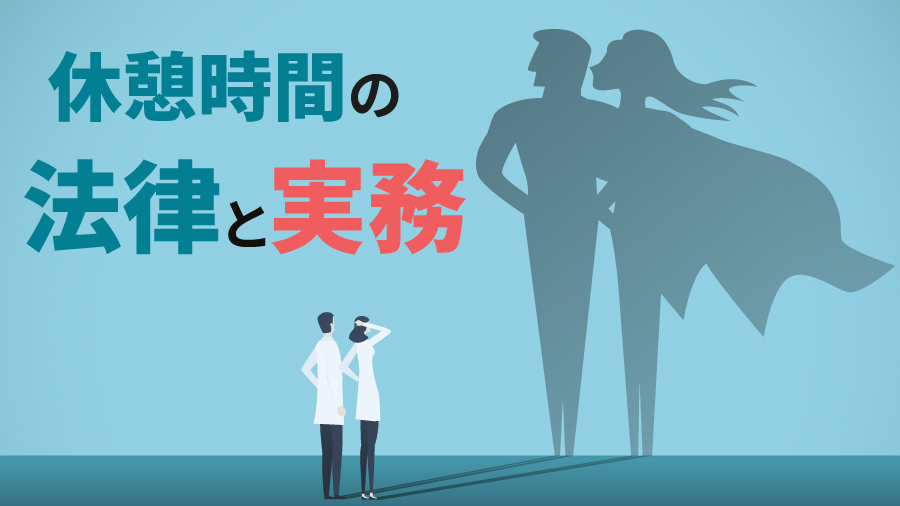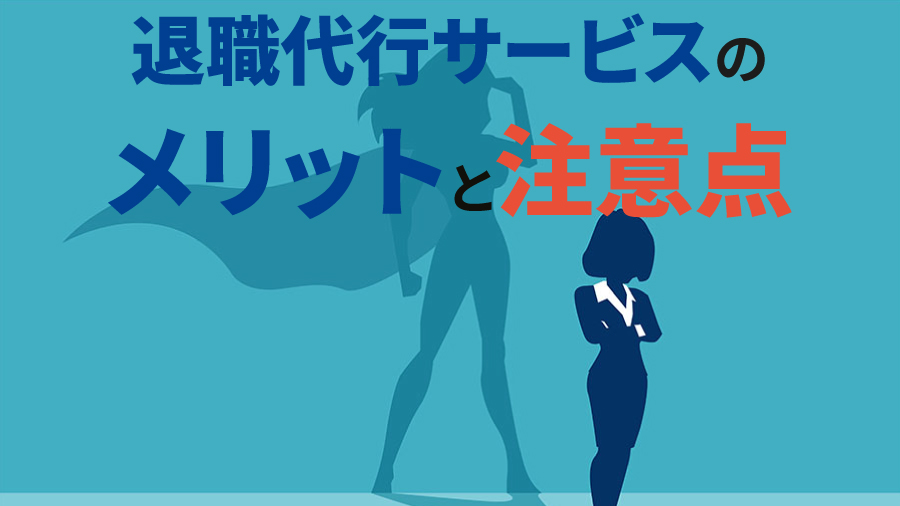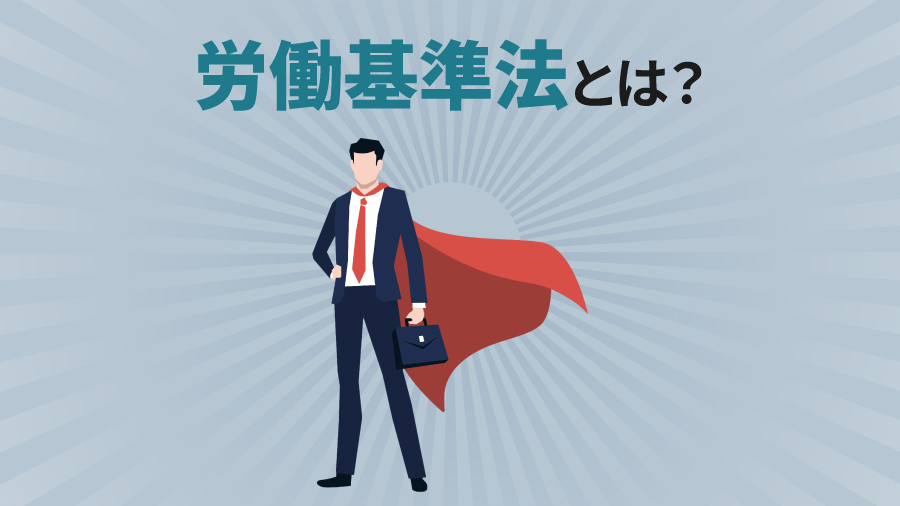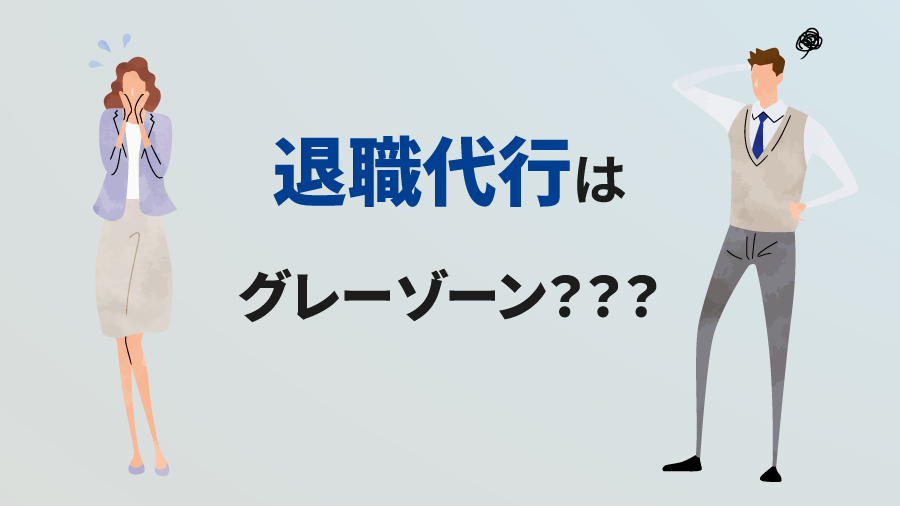-
-
精神障害の労災認定事例|成功と不支給のケースから学ぶポイント

近年、職場のストレスから精神障害を発症し、労災認定を求めるケースが増加しています。しかし、労災認定の可否は状況によって異なり、認定される場合もあれば、不支給となる場合もあります。本記事では、実際の労災認定事例を通じて、認定されたケースと不支給となったケースの違いや、労災認定の成功率について詳しく解説します。労災申請を検討している方が、適切な判断と準備を行うための参考となれば幸いです。
目次精神障害の労災認定とは
精神障害の労災認定とは、業務に起因する強い心理的負荷によって発症した精神疾患に対して、労働者災害補償保険法に基づき補償を受けられる制度のことです。
具体的には、うつ病や適応障害、PTSDなどが対象とされており、近年では社会的な認知も進みつつあります。この章では、労災認定の仕組みや判断基準について情報を整理します。
労災認定の基本的な流れ
労災認定を受けるためには、まず労働基準監督署に対して申請を行う必要があります。
申請には、医師の診断書、業務上の出来事に関する記録、本人の陳述書、就労記録など、多くの資料が必要です。これらをもとに、厚生労働省が定める「心理的負荷評価表」に照らして、精神障害の発症と業務との因果関係を評価します。
調査は詳細かつ慎重に進められ、必要に応じて事業所への聞き取り調査や追加書類の提出を求められることもあります。審査の結果、労災と認められれば、医療費や休業中の賃金補償などが給付され、生活の安定を図ることが可能になります。
精神障害が労災認定されるための要件
労災認定されるためには、以下の3つの要件を満たすことが必要です。
1つ目は、対象となる精神障害であること。
これは医師の診断に基づき、うつ病、適応障害、急性ストレス障害、PTSDなどが該当します。2つ目は、発症前に業務による強い心理的負荷が存在したこと。
これには長時間労働、パワハラ、重大なトラブル対応などが含まれます。そして3つ目は、私生活上の要因よりも業務の影響が大きかったと客観的に判断されることです。
これらの要件は、発症までの期間や出来事の性質を含め、個別に精査されるため、証拠の整理と専門家の支援が重要です。認定されたケースの紹介
実際に労災が認められた事例を知ることで、どのような状況が「業務による強い心理的負荷」と評価されるのかを具体的に把握することができます。
この章では、パワーハラスメントや長時間労働といった代表的なケースを紹介し、それぞれが認定された理由を明らかにしていきます。パワーハラスメントによるうつ病の認定事例
営業職の男性社員が、上司から長期間にわたり厳しい叱責や人格否定を伴う発言を受け続け、精神的に追い詰められた結果、うつ病を発症したケースです。
このケースでは、本人が録音していた音声や、当時の日報、さらに同僚の証言などがパワーハラスメントの実態を裏付ける証拠となりました。
医師の診断書にも「職場の人間関係による継続的ストレスが発症要因である」と明記されており、これらを総合的に評価した結果、労災認定が下りました。長時間労働による適応障害の認定事例
IT業界で働く女性社員は、半年以上にわたって月100時間を超える残業を継続し、さらに休日出勤も常態化していました。
徐々に睡眠障害や抑うつ状態を呈するようになり、最終的に適応障害と診断。彼女のケースでは、PCのログオン・ログオフ履歴やタイムカード、勤怠管理システムの記録が長時間労働の証拠として採用されています。
また、医師の所見では「過労による慢性的な疲労とストレスが直接的な原因」と記されており、業務との因果関係が明確であると判断されました。不支給となったケースの紹介
労災申請が却下された事例を知ることも、認定されるためのポイントを知るうえで非常に有効です。
この章では、業務外の要因が大きく影響したケースや、証拠が不足していたために不支給となった具体的な事例を紹介します。業務外の要因が影響したと判断された事例
40代の男性会社員が、うつ病を発症して労災を申請しましたが、調査の結果、離婚による家庭内トラブルや親族の介護など、私生活における強いストレス要因が認められました。
また、業務上の重大な出来事についても曖昧で、心理的負荷評価表のスコアも低かったため、業務との直接的な関係性が認められませんでした。証拠不十分で認定されなかった事例
製造業の女性社員が、職場の人間関係の悪化と業務の過重による適応障害を主張。
しかし、具体的な証拠が乏しく、勤務時間の記録や医師の診断書の内容も曖昧であったことから、労働基準監督署は因果関係を立証できないと判断しました。労災認定の成功率とその背景
労災申請がどれほどの割合で認定されているのかを把握することは、申請を検討する際の大切な判断材料となります。
この章では、最新の統計データに基づき、精神障害における労災認定の成功率と、その背景にある理由について解説します。最新の労災請求件数と認定率
厚生労働省の発表によれば、精神障害による労災申請件数はここ数年で急増しており、特に若年層や女性労働者からの申請も増えています。
とはいえ、厚生労働省の統計によれば、精神障害に関する労災申請の認定率は近年30%前後で推移しており、決して高いとは言えません。認定率が低い理由とその対策
認定率が伸び悩む背景には、心理的負荷の客観的証明が難しいこと、業務と私生活のストレスの区別がつけにくいことが挙げられます。
録音、メール、メモ、診断書などの組み合わせが必要であり、社労士や弁護士に相談することで、申請の完成度を高めることも期待できます。労災申請のポイントと注意点
精神障害に関する労災申請は、適切な準備と理解がなければ認定されるのは難しい制度です。
この章では、申請を成功させるために押さえておきたい証拠の収集方法や、実際の手続きの流れ、注意すべきポイントを詳しく解説します。必要な証拠の収集方法
証拠として重視されるのは、業務上の出来事を裏付ける客観的な資料です。
勤務時間を示す勤怠表やPCログ、上司とのやり取りの記録、相談履歴や診療録、また第三者の証言など、複数の角度から心理的負荷を示すことで、因果関係が明確になります。申請手続きの流れと注意点
申請の流れとしては、まず医療機関で診断を受け、必要書類をそろえたうえで、労働基準監督署へ労災請求書を提出します。
調査期間中には追加資料の提出を求められることもあり、申請から結果が出るまでに数カ月を要するケースもあります。まとめ:精神障害で労災認定を目指すために必要な備えとは
精神障害の労災認定には、制度への正しい理解と適切な準備が欠かせません。
認定された事例には、「証拠が明確」「業務との関連性が説明可能」「医師の所見が的確」といった条件がそろっています。逆に、不支給事例では証拠があいまいであったり、個人的な要因と業務上のストレスの区別が不明確なことが原因です。
申請を検討している方は、まず自身の状況を冷静に整理し、客観的な事実として残せる資料を意識的に残していくことが求められます。加えて、信頼できる第三者への相談や、経験豊富な専門家への依頼も有効です。
精神的な負担を抱えながら一人で対処することは困難です。自分自身を守るためにも、準備を怠らず、適切な手段を講じていく姿勢が大切です。
-