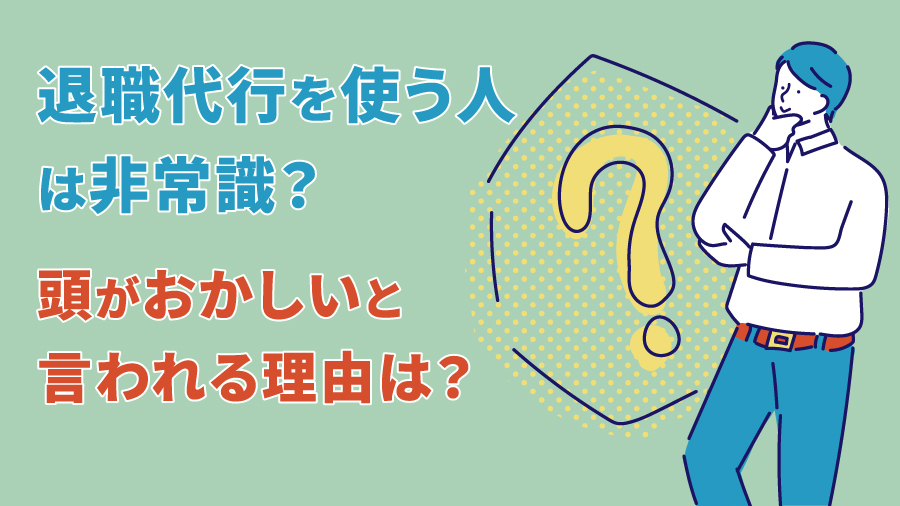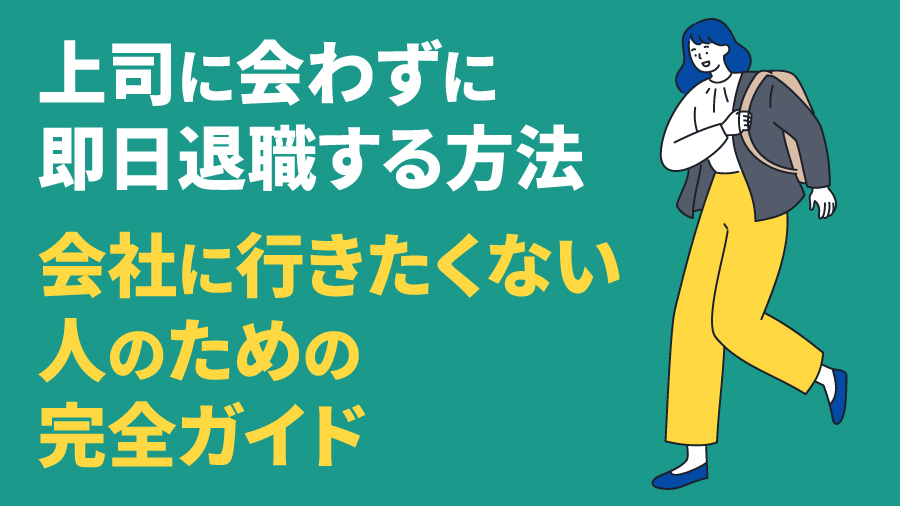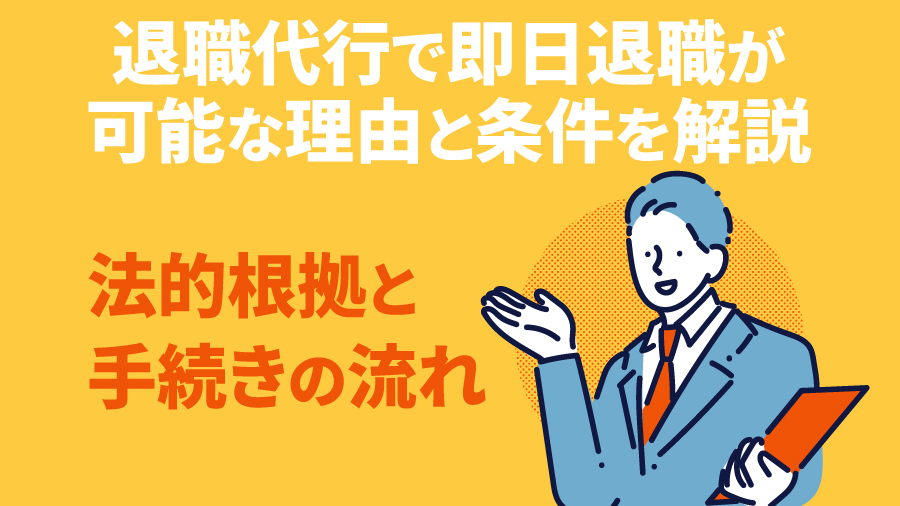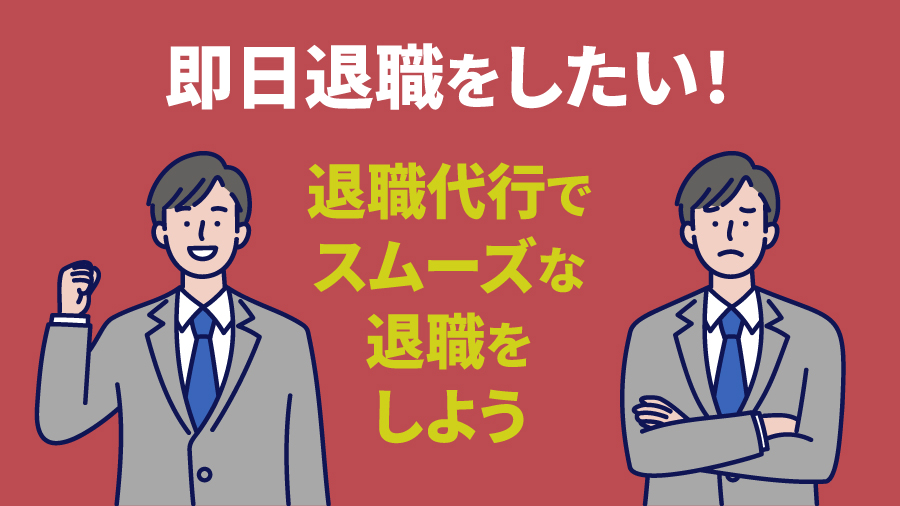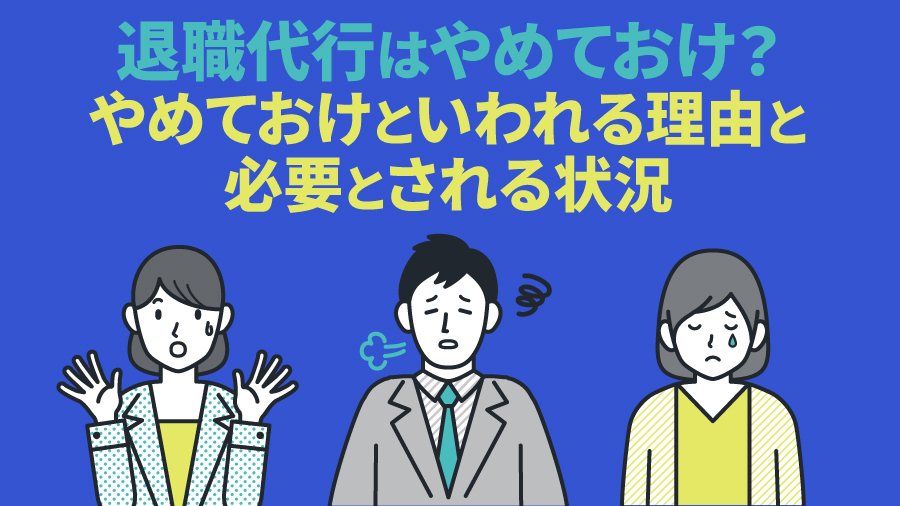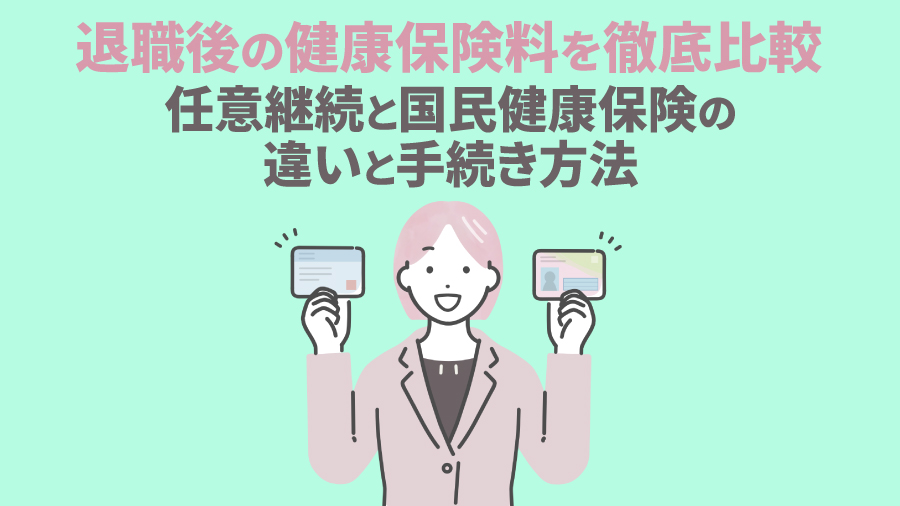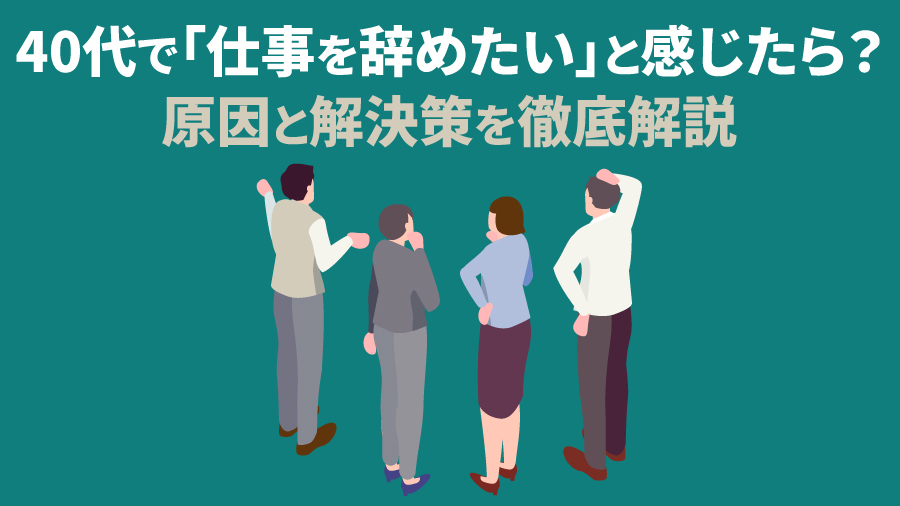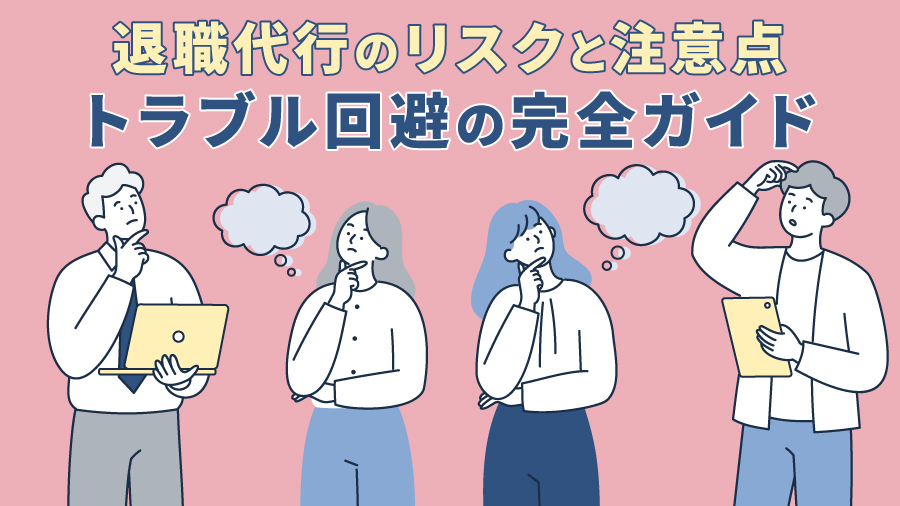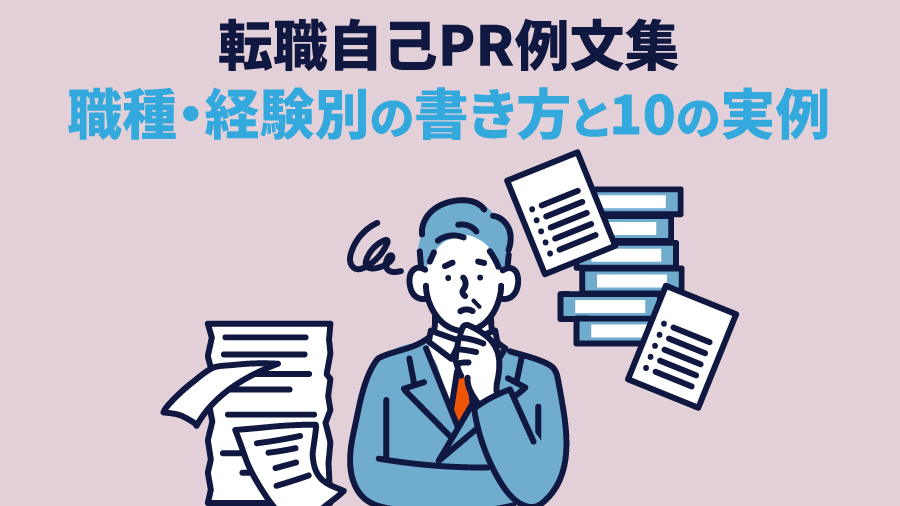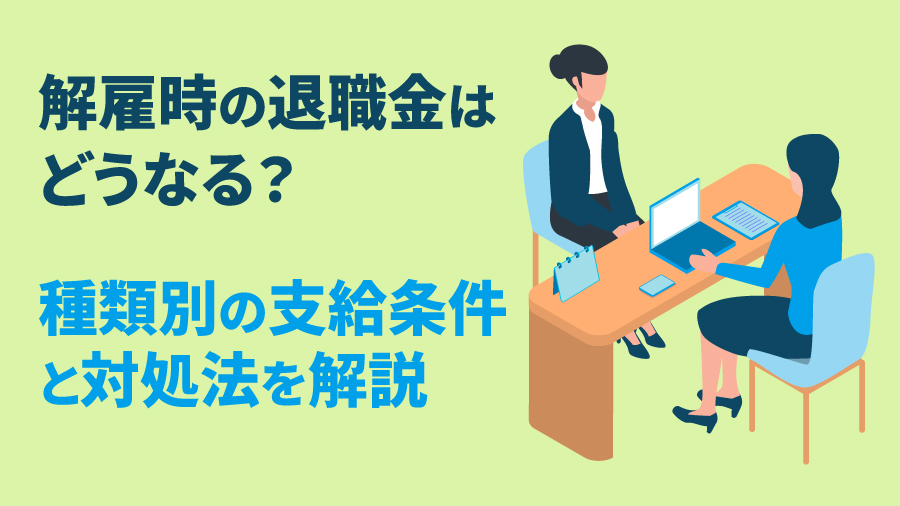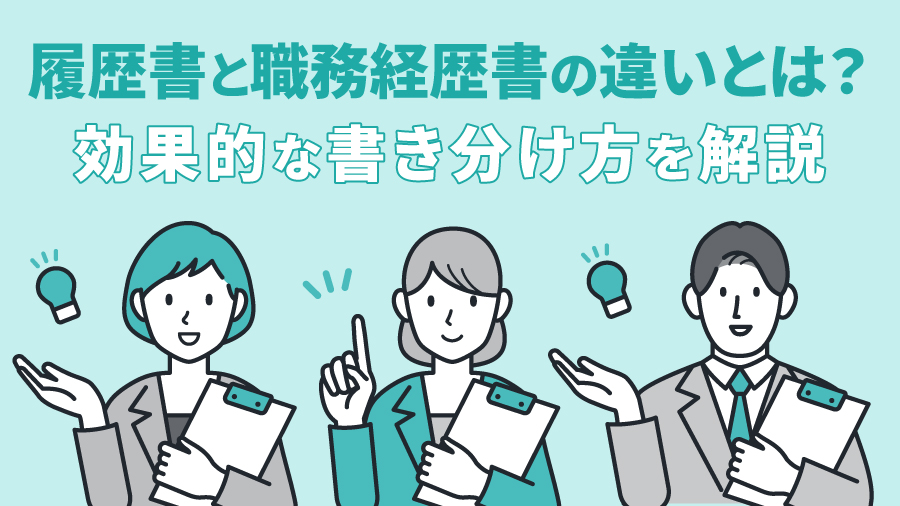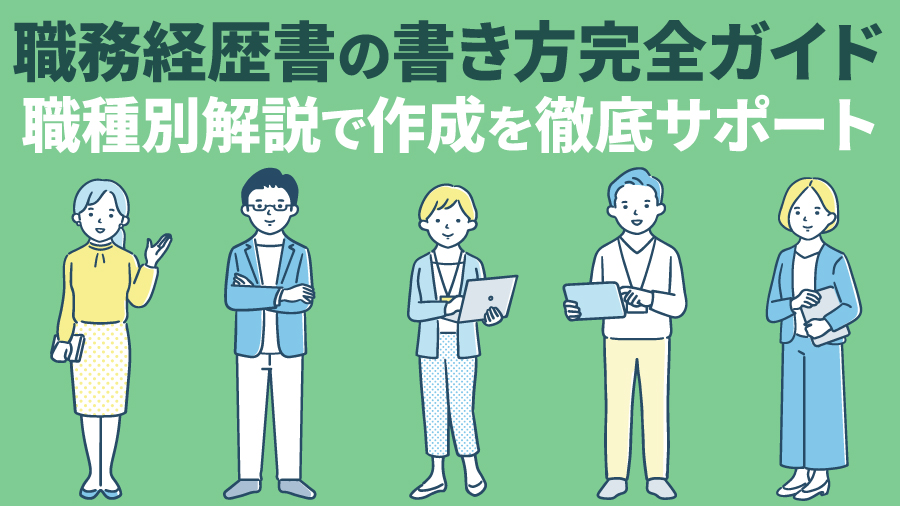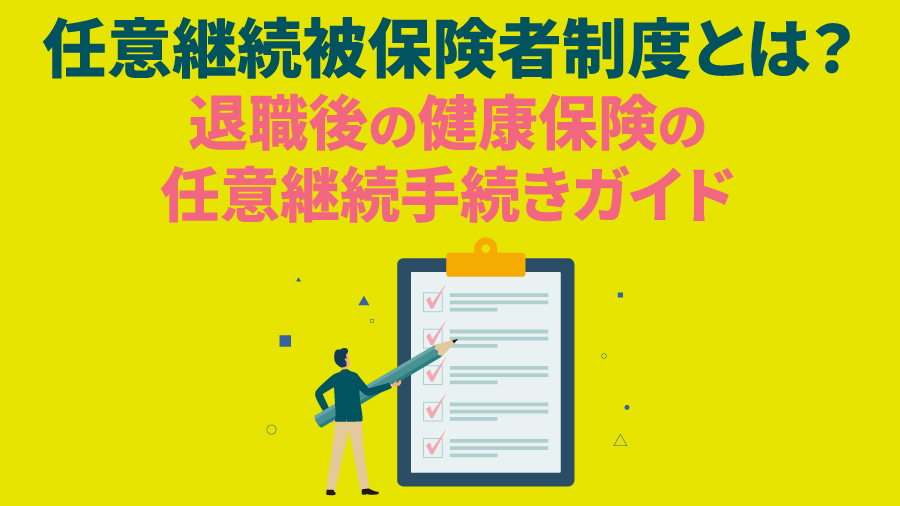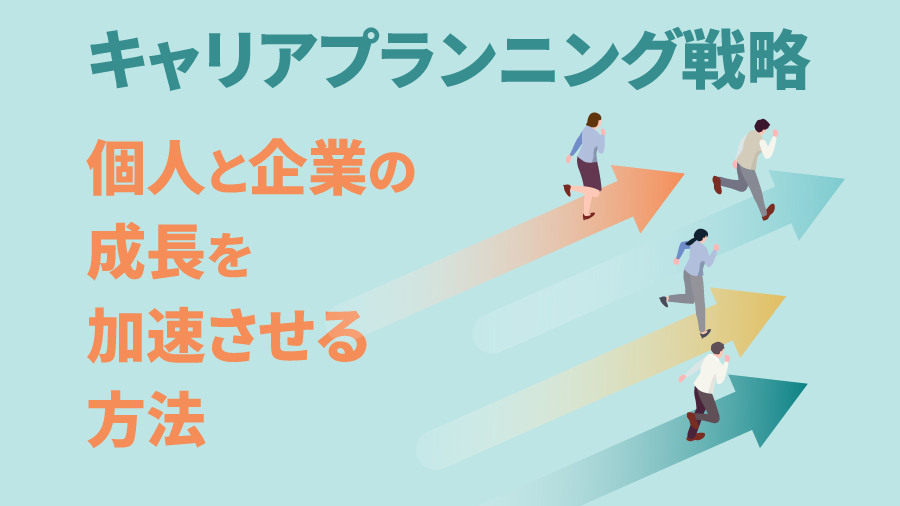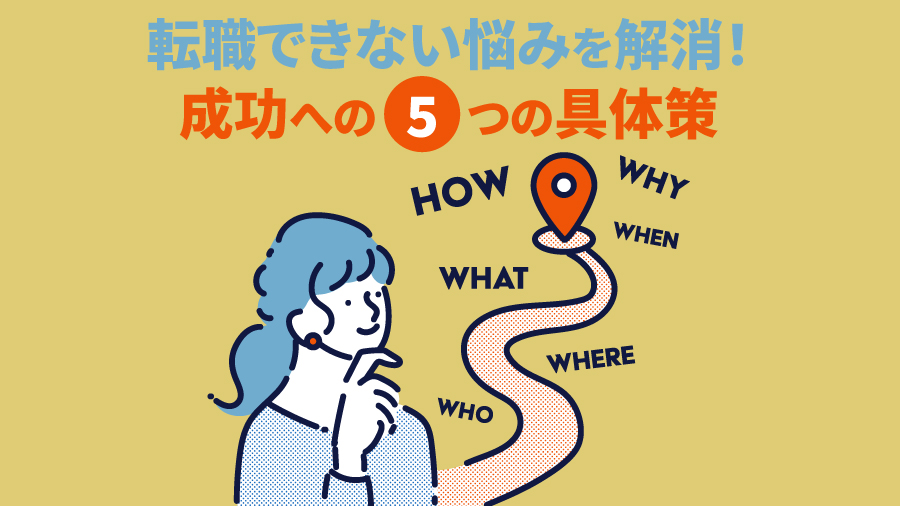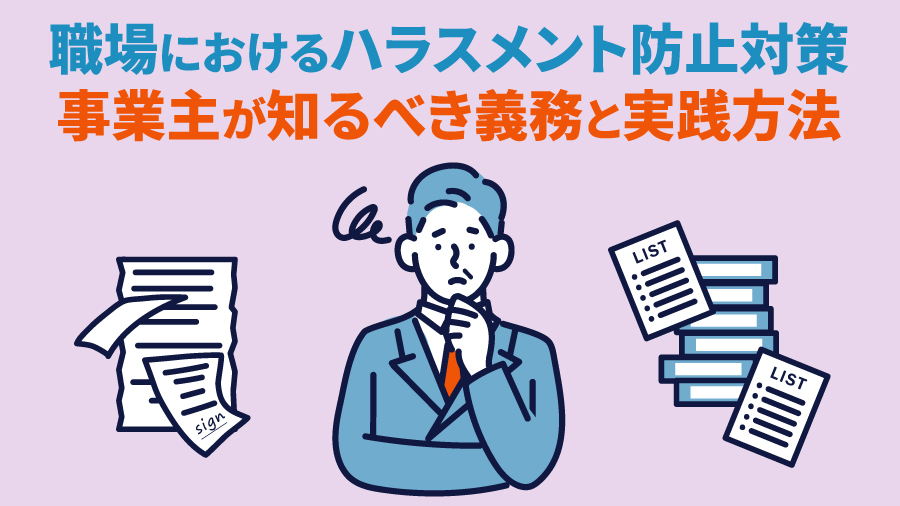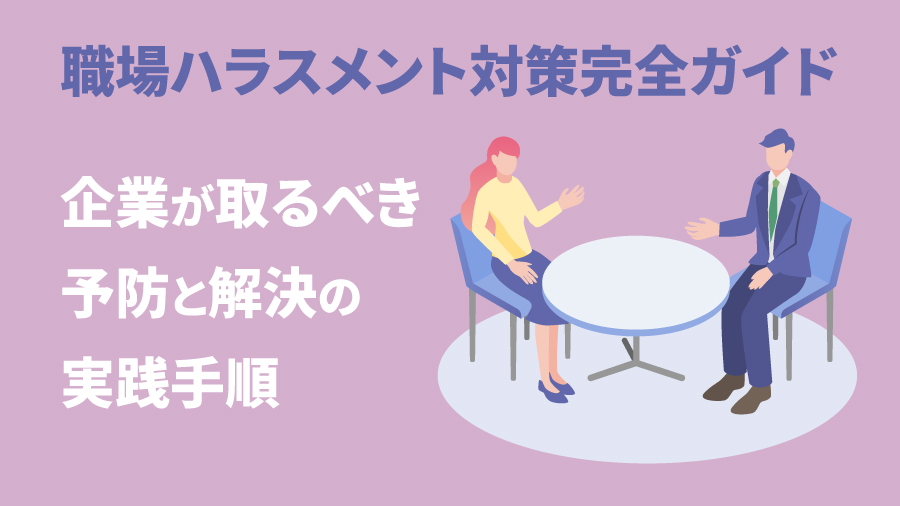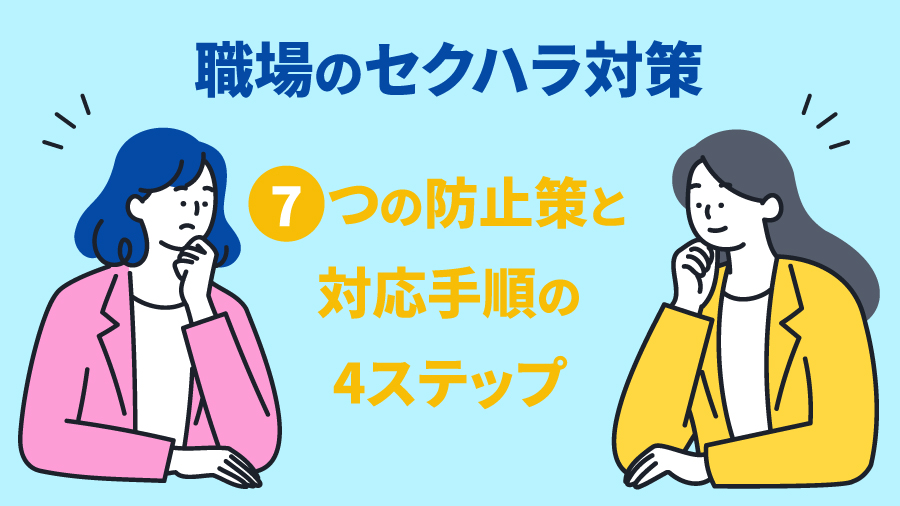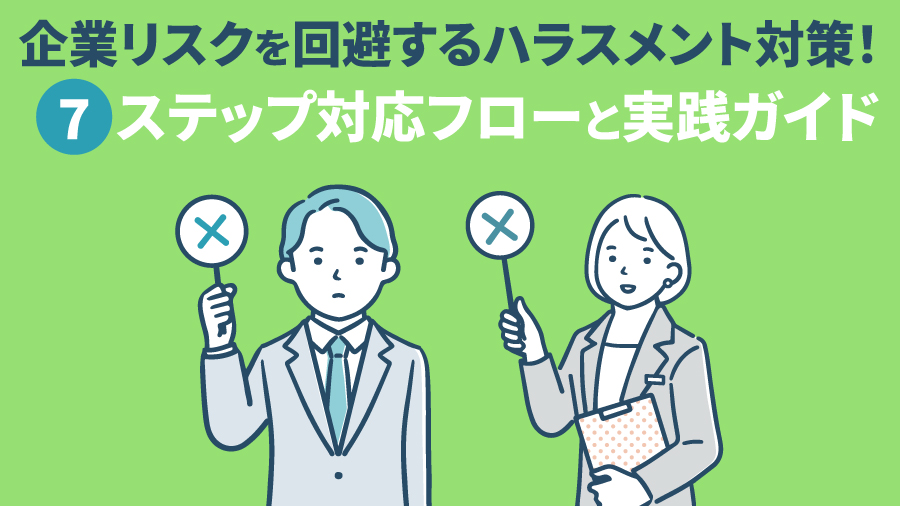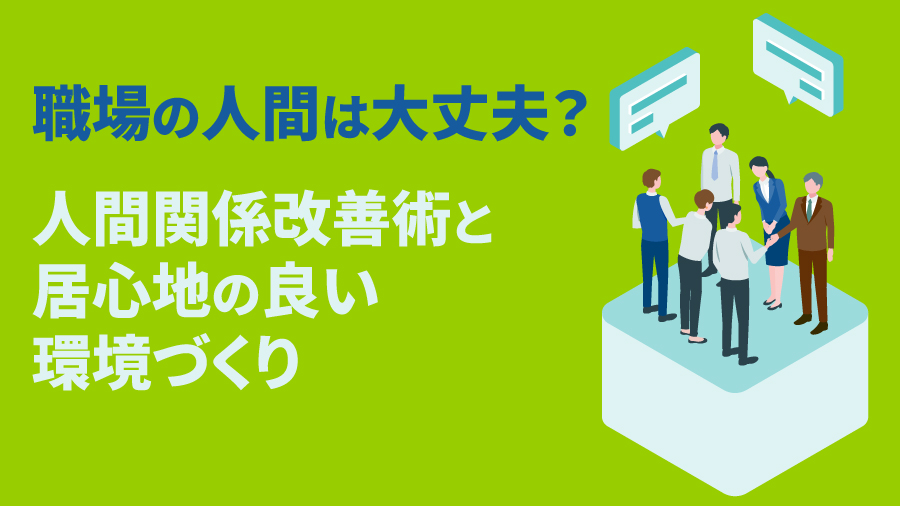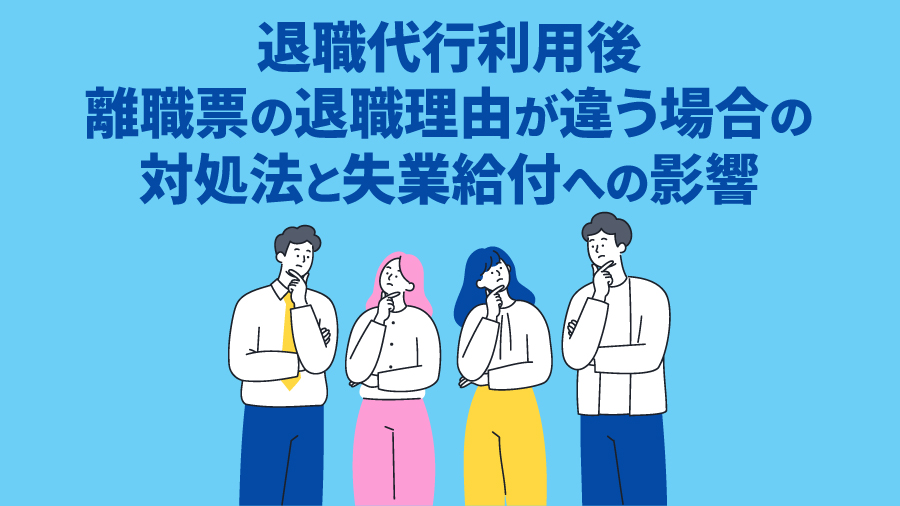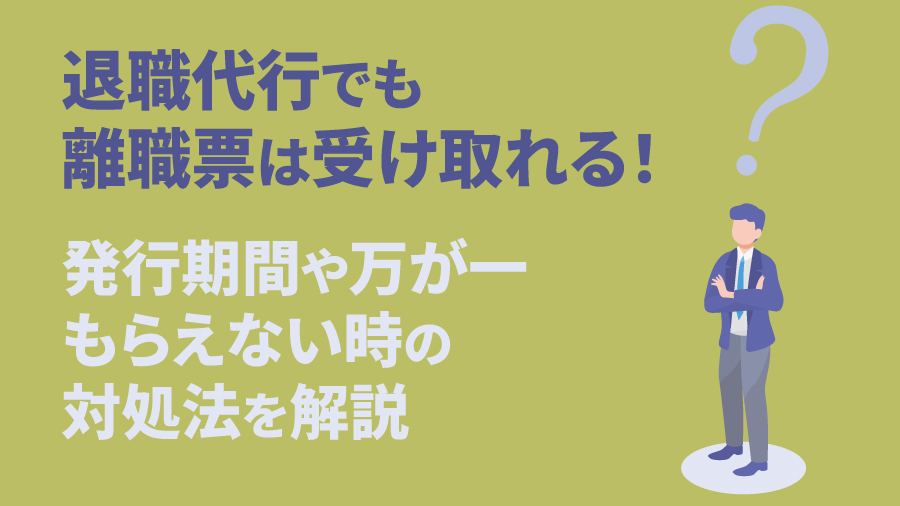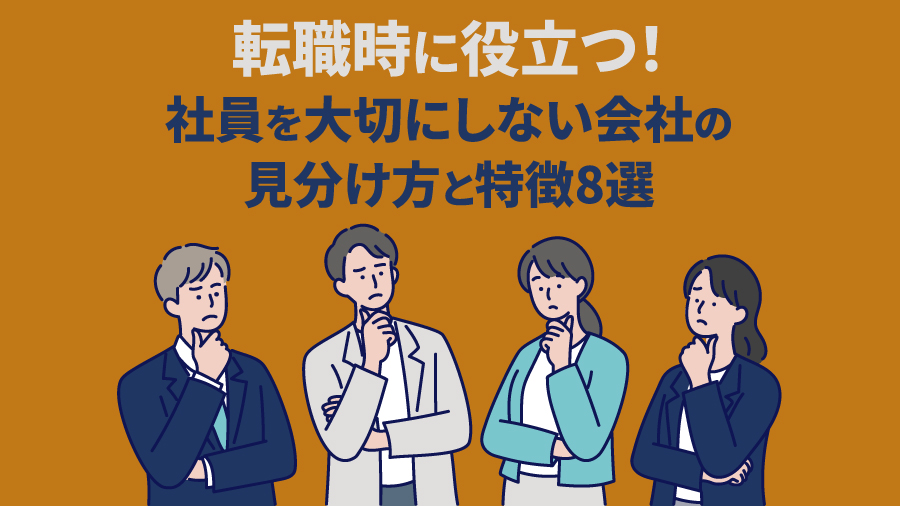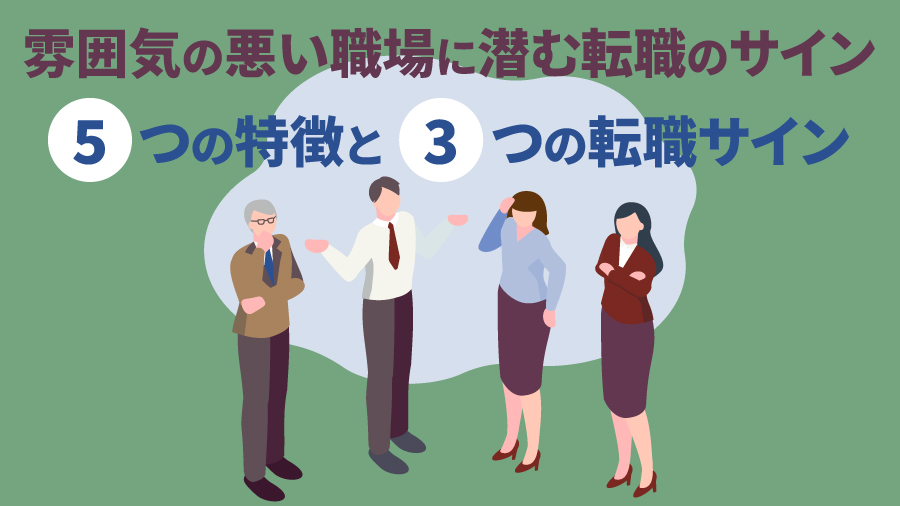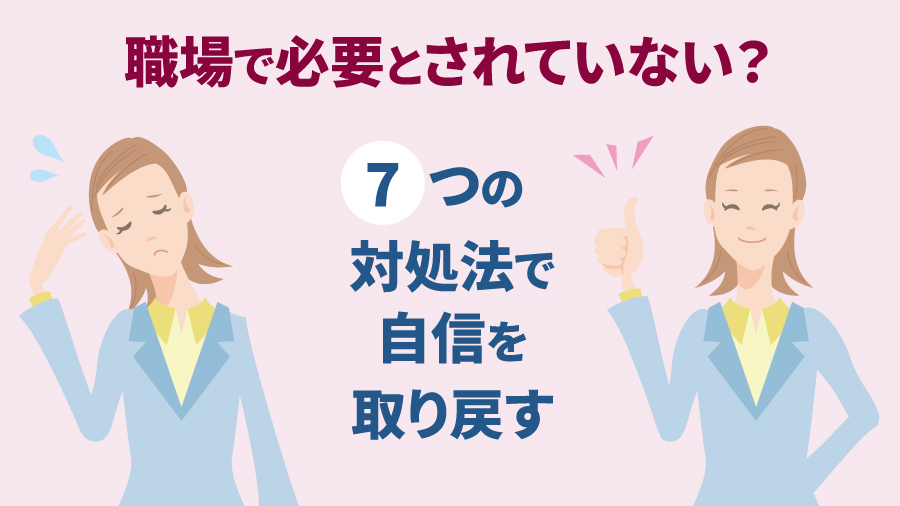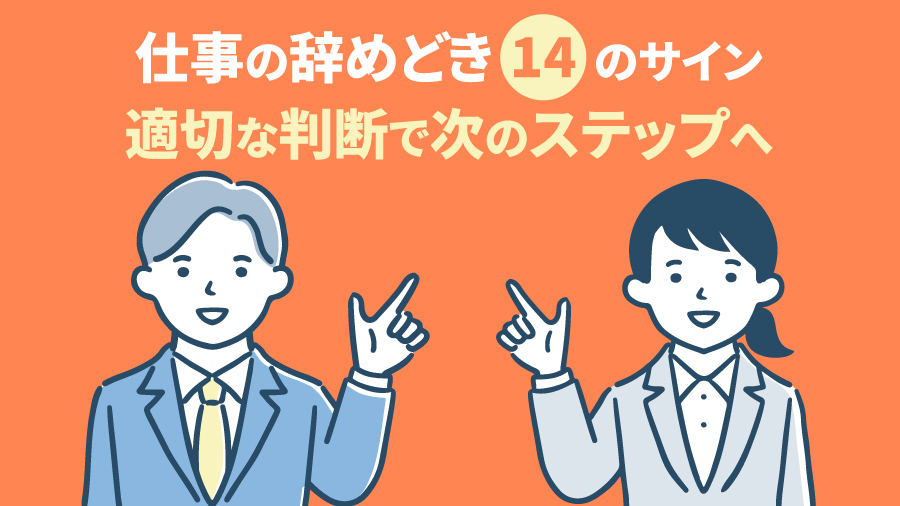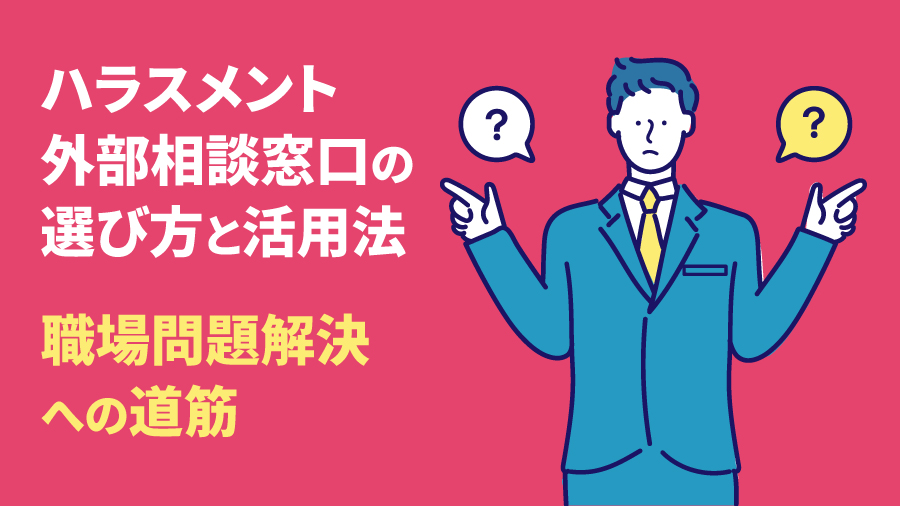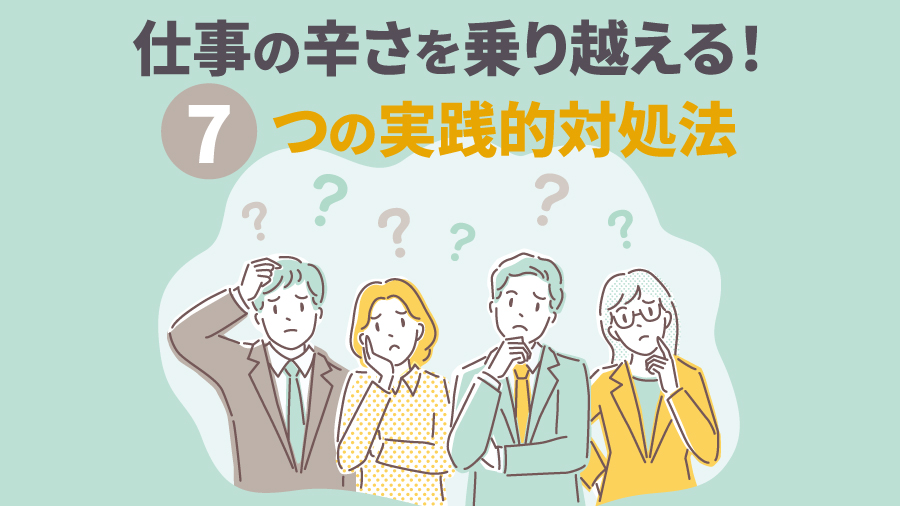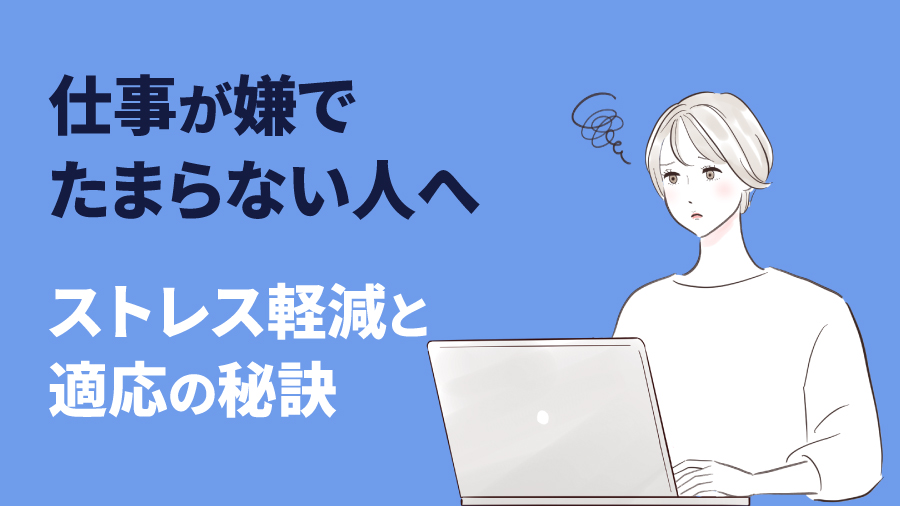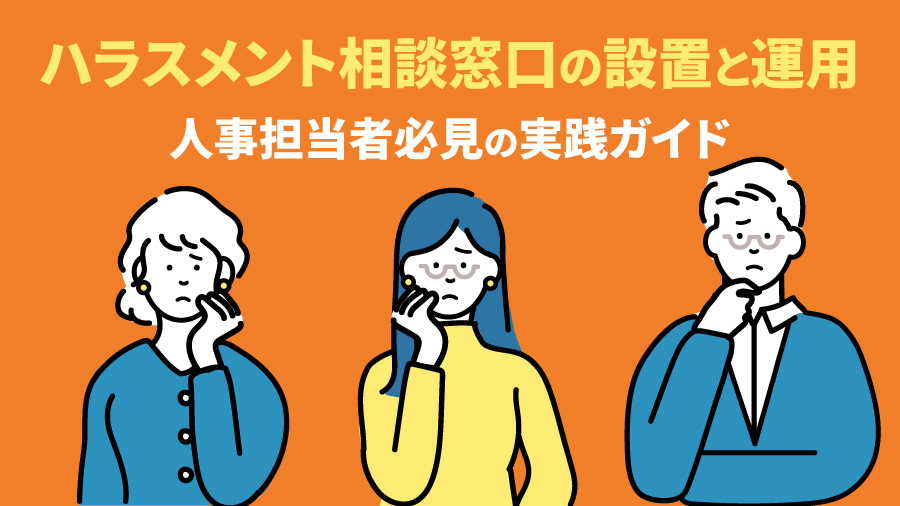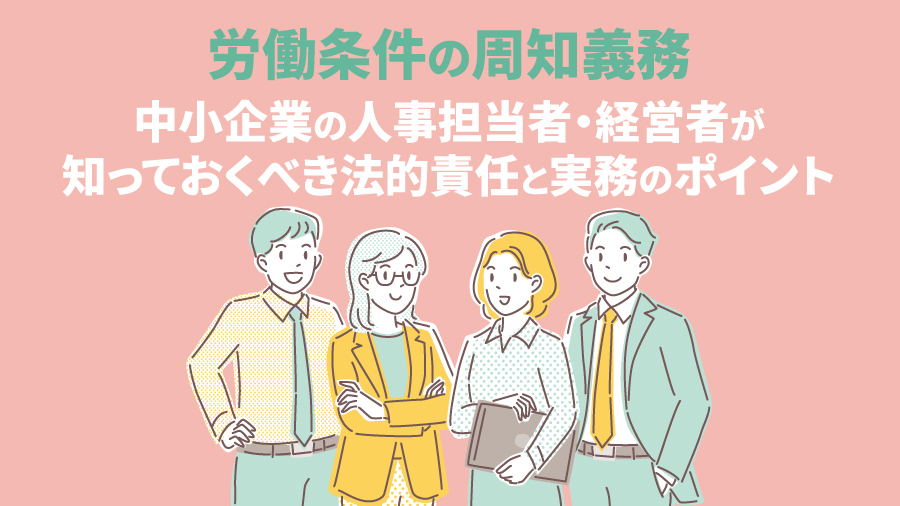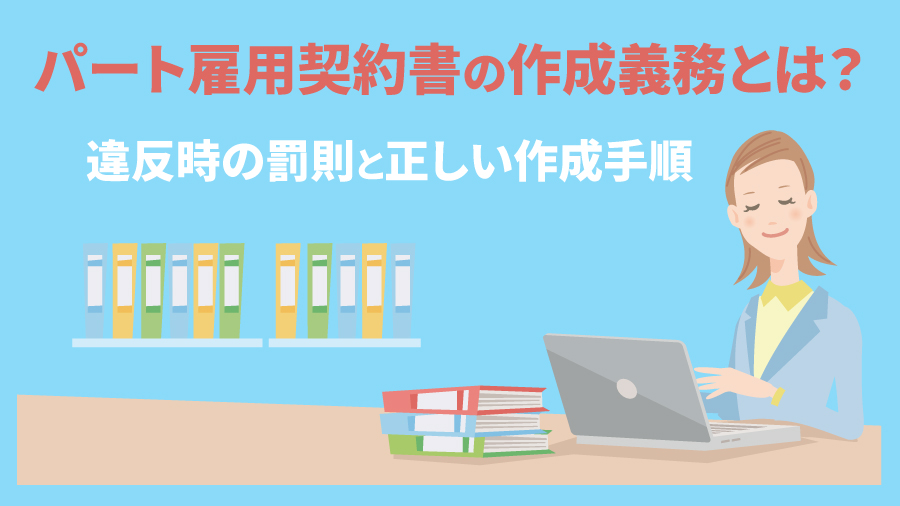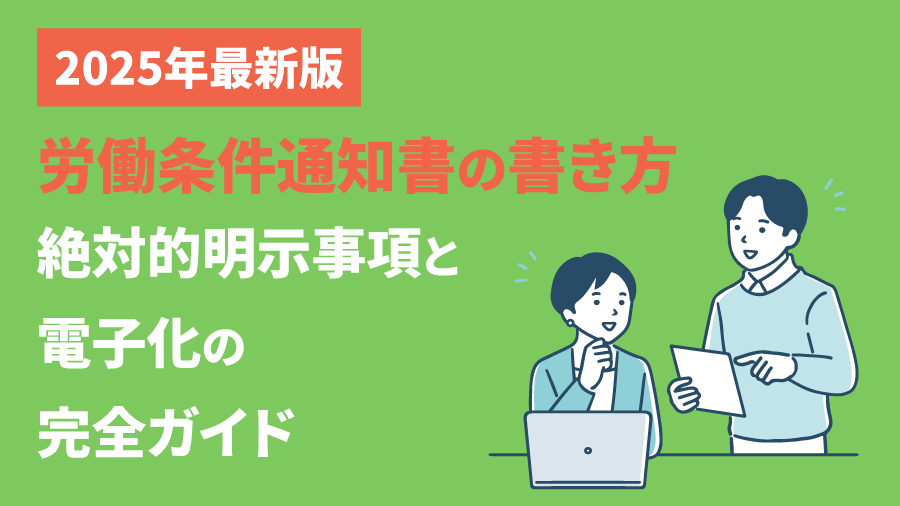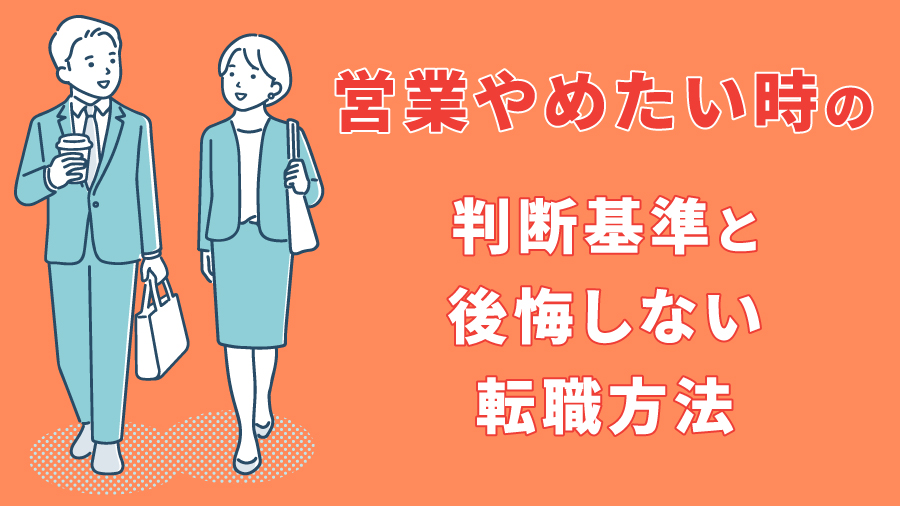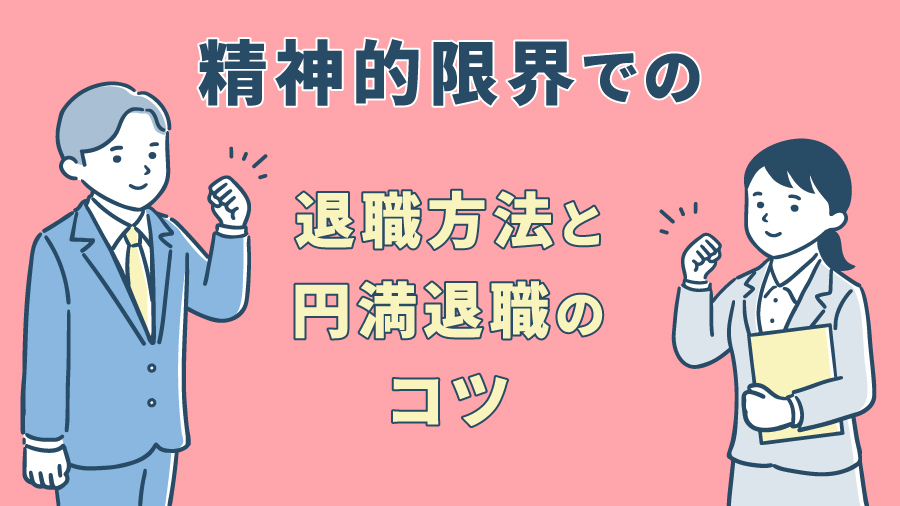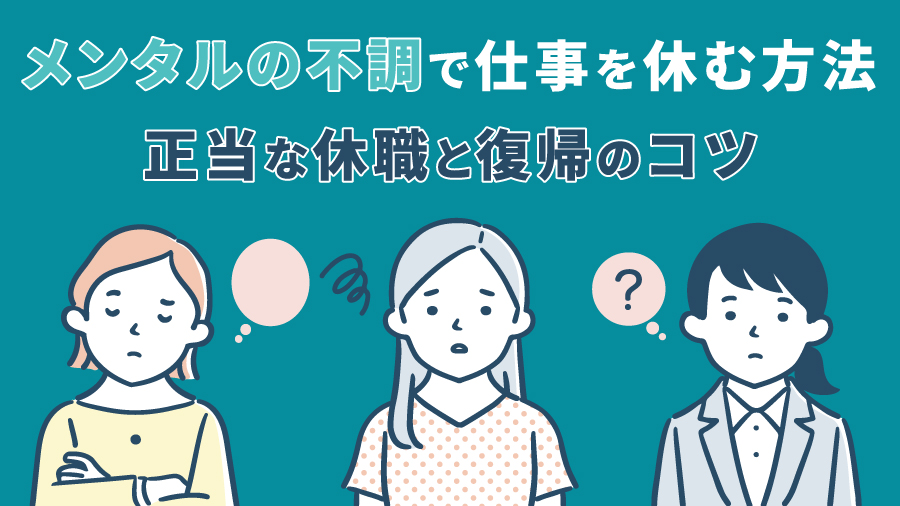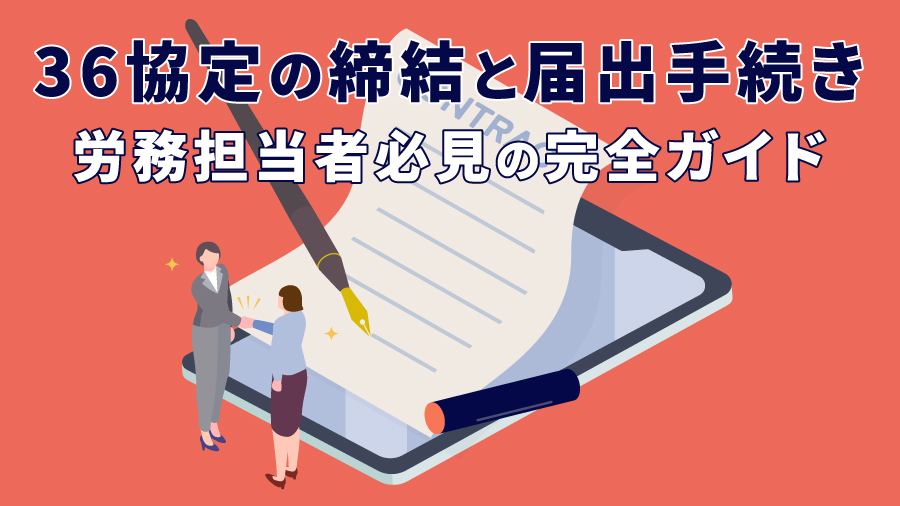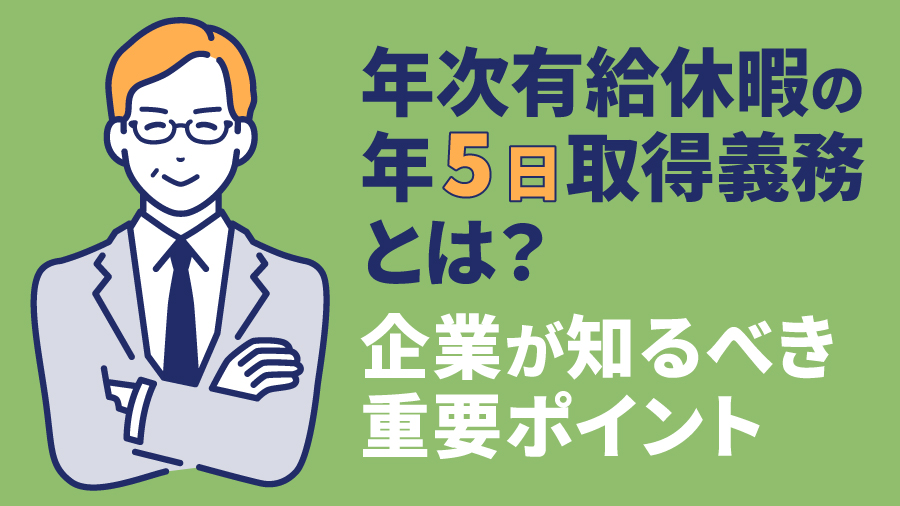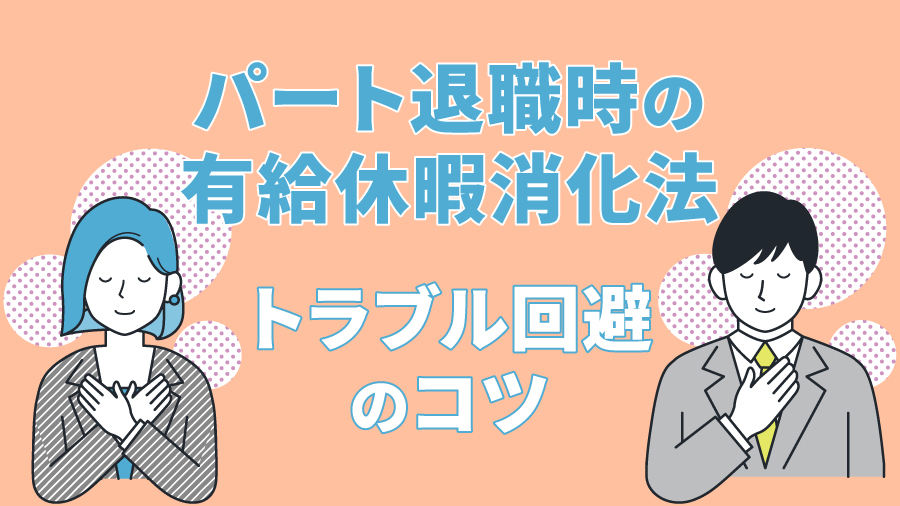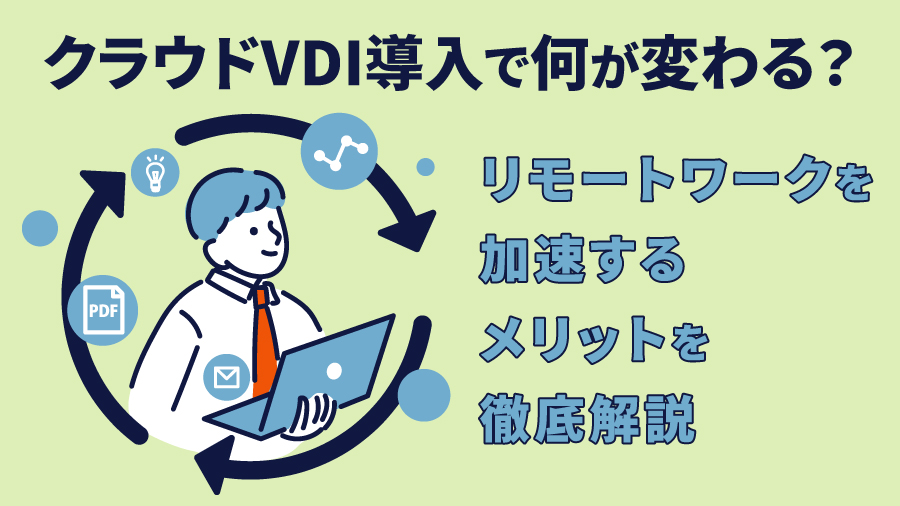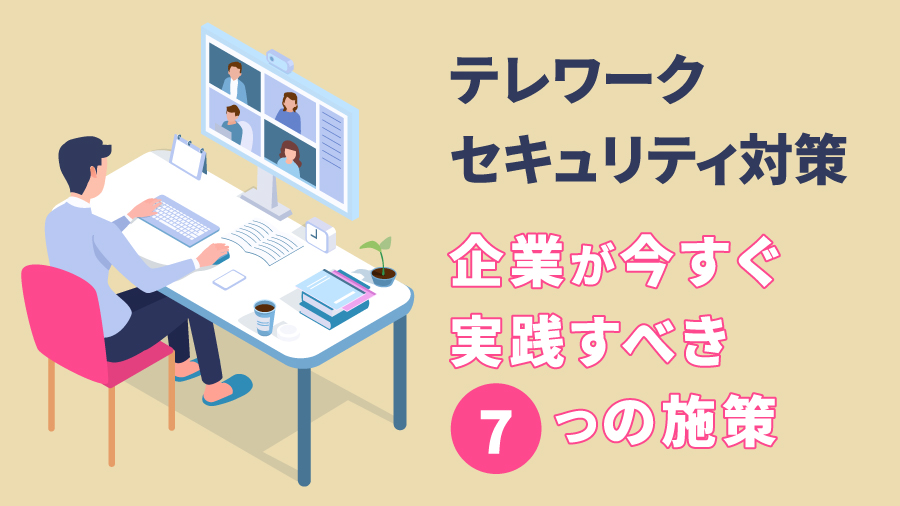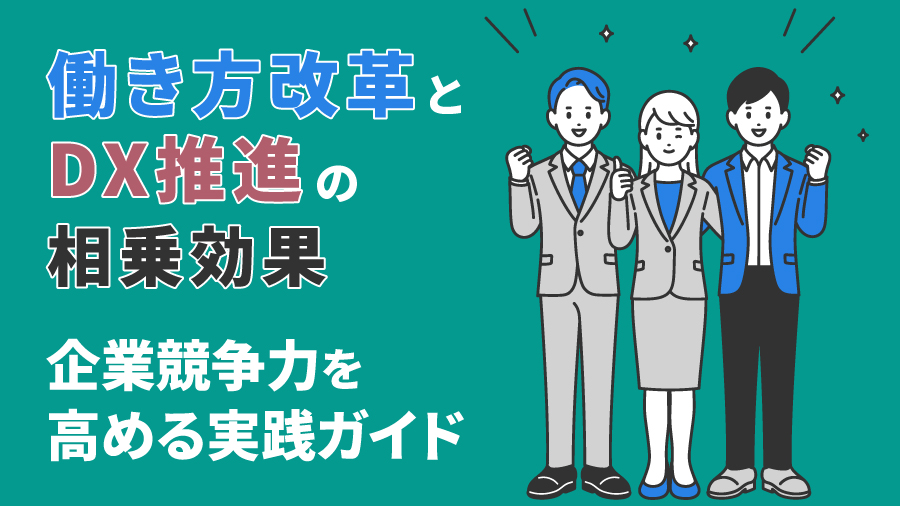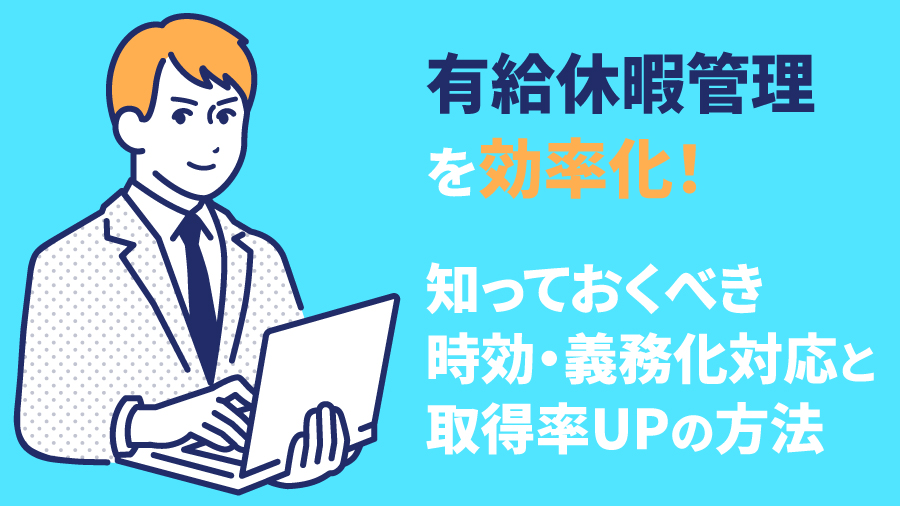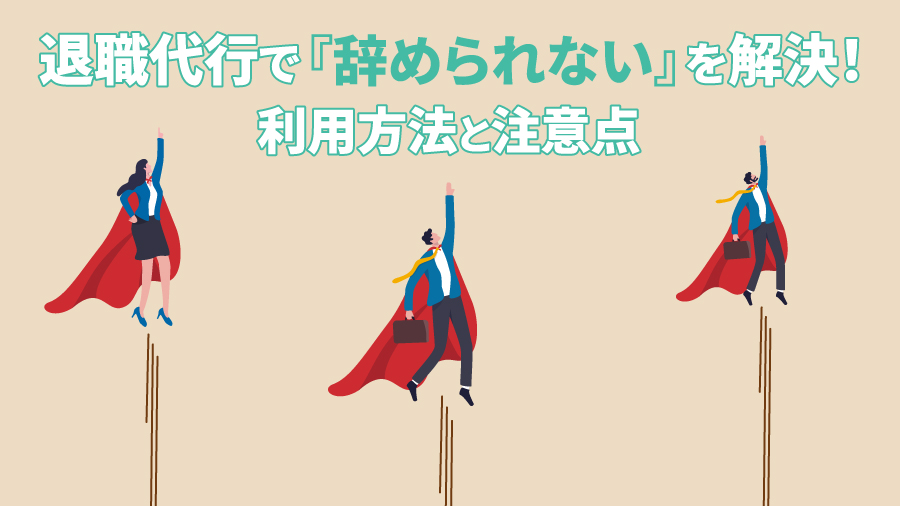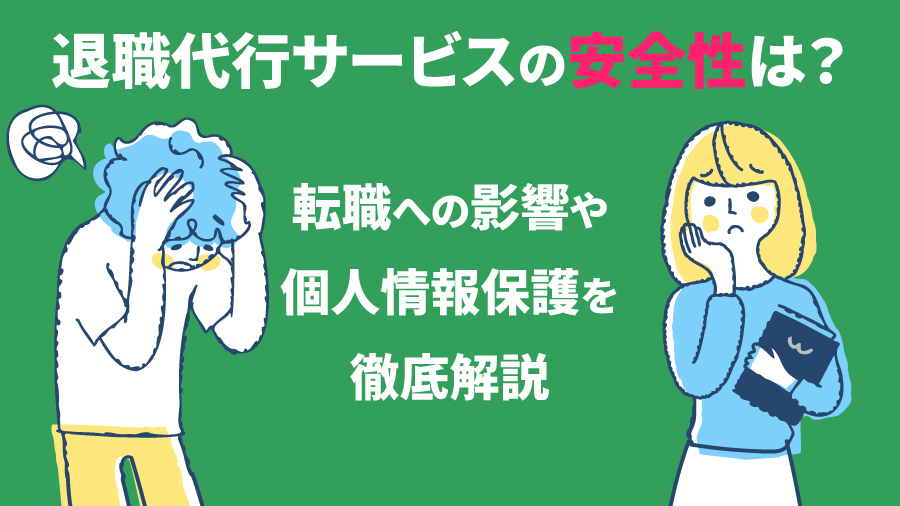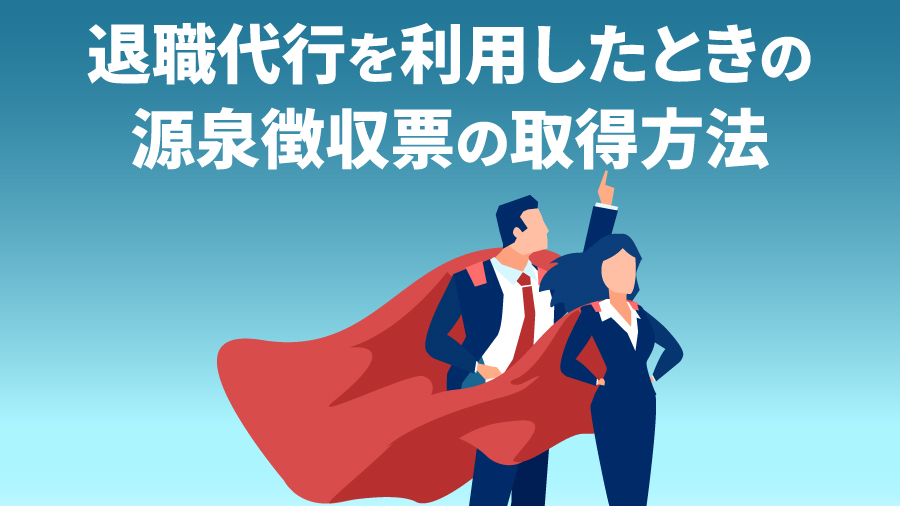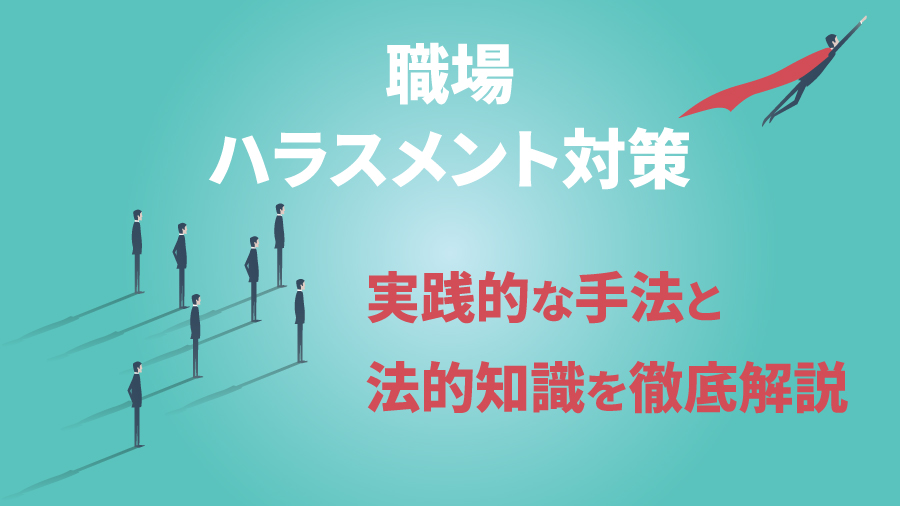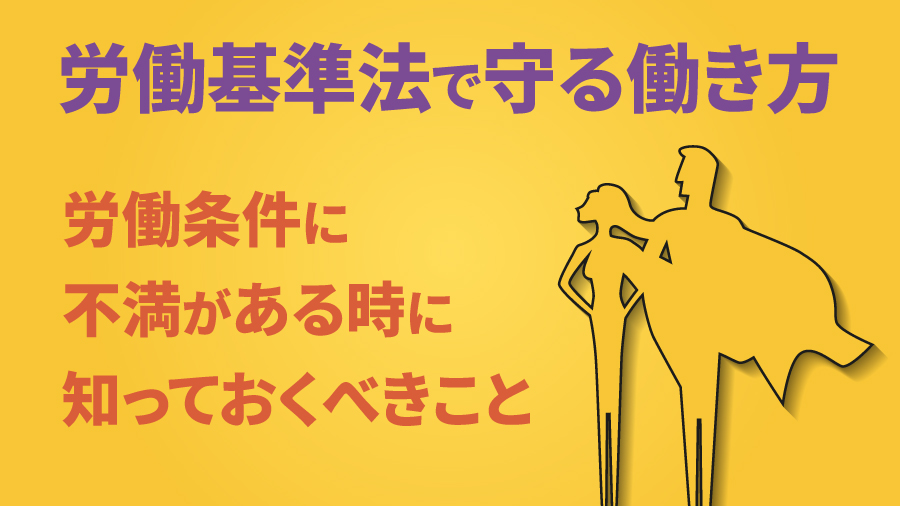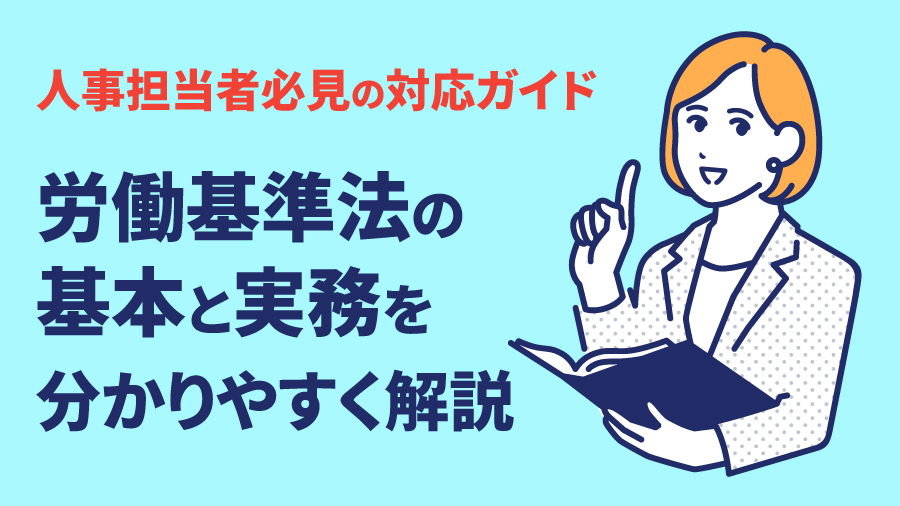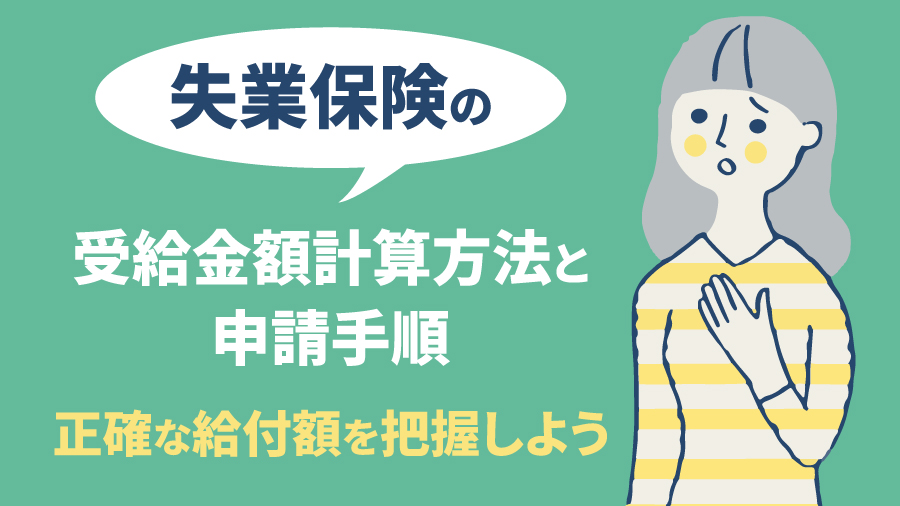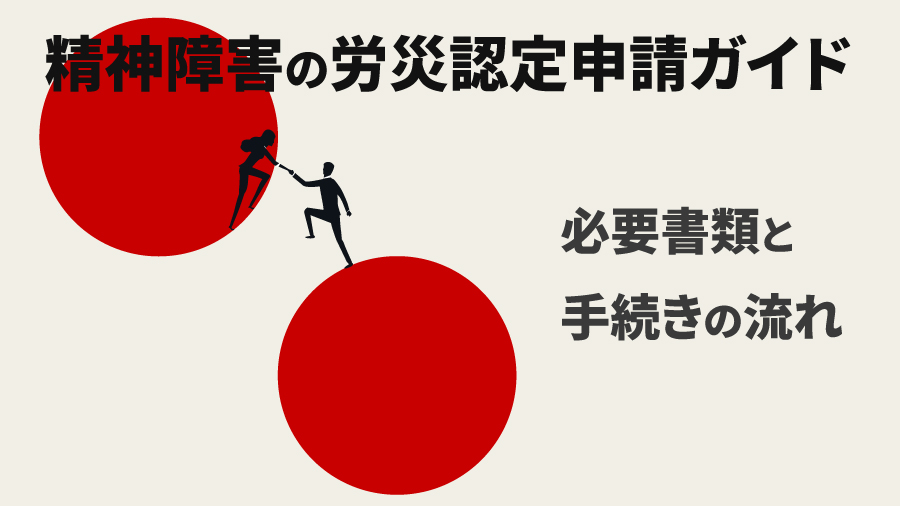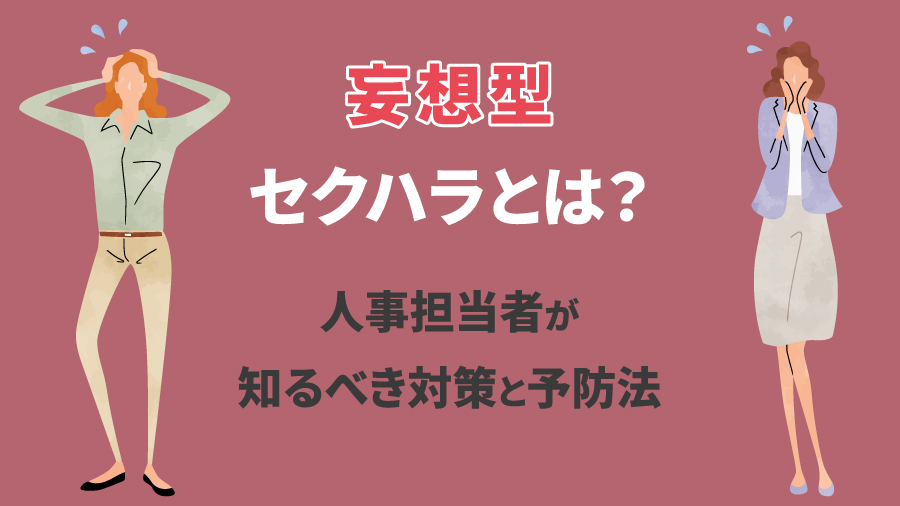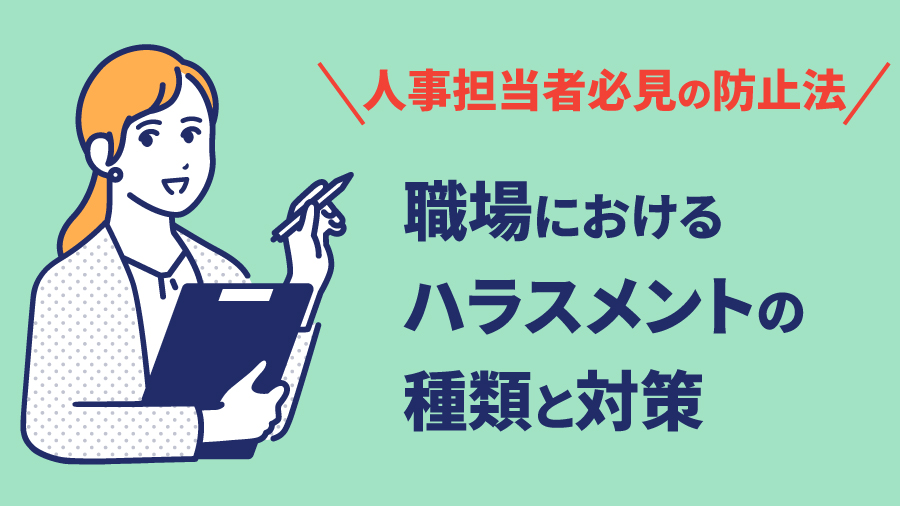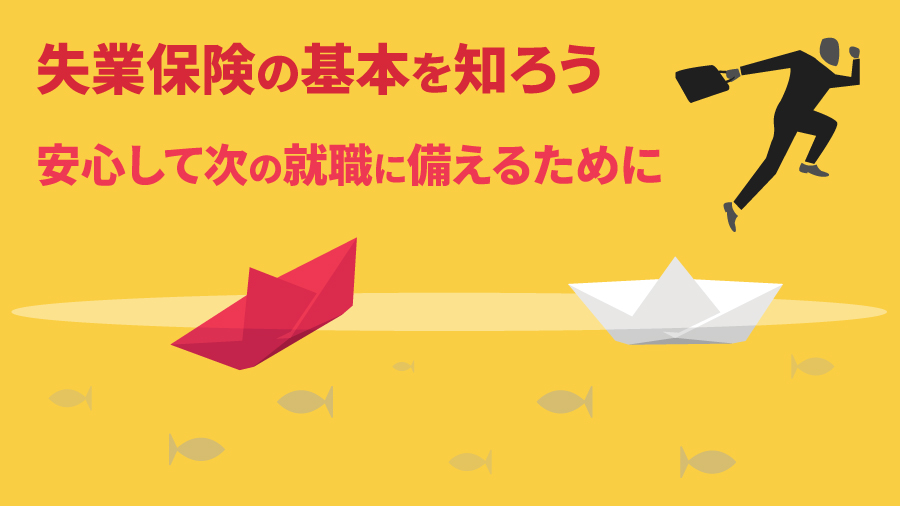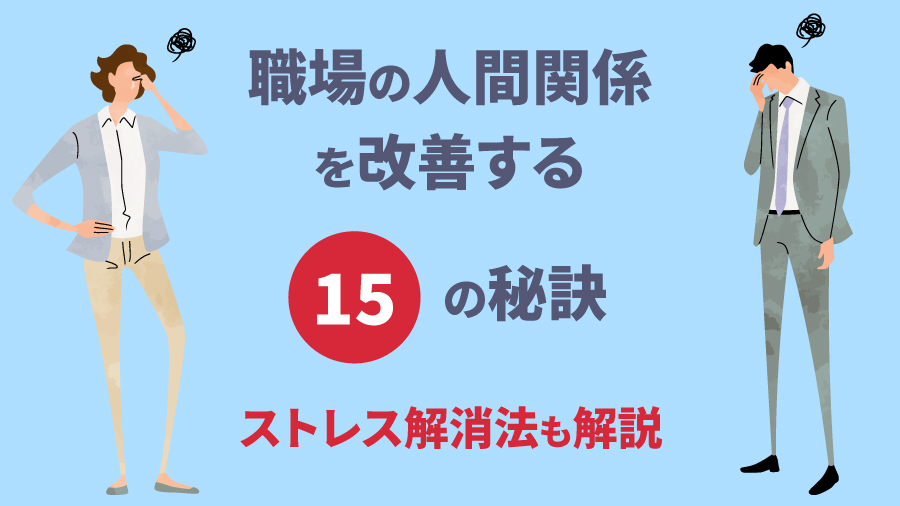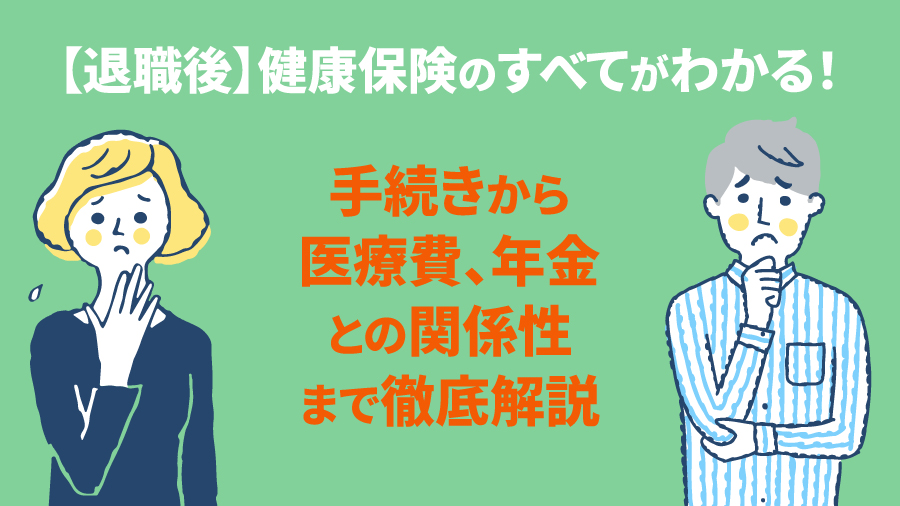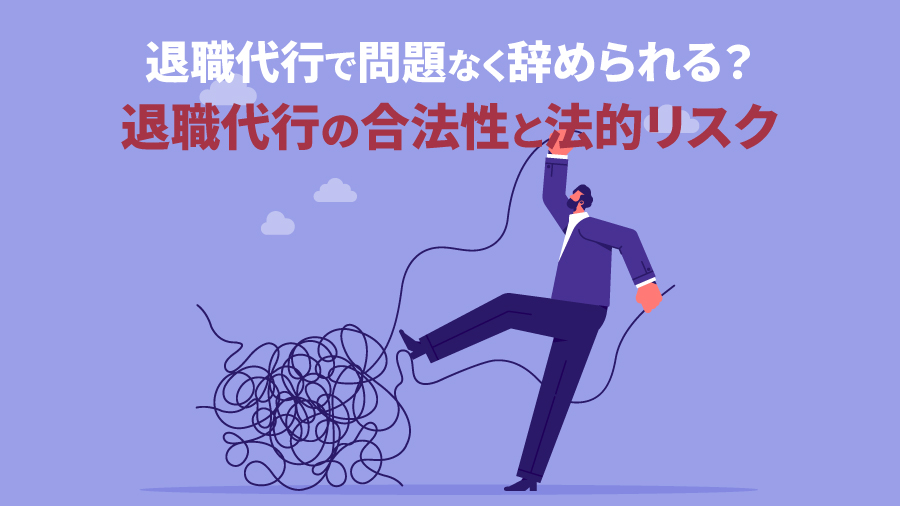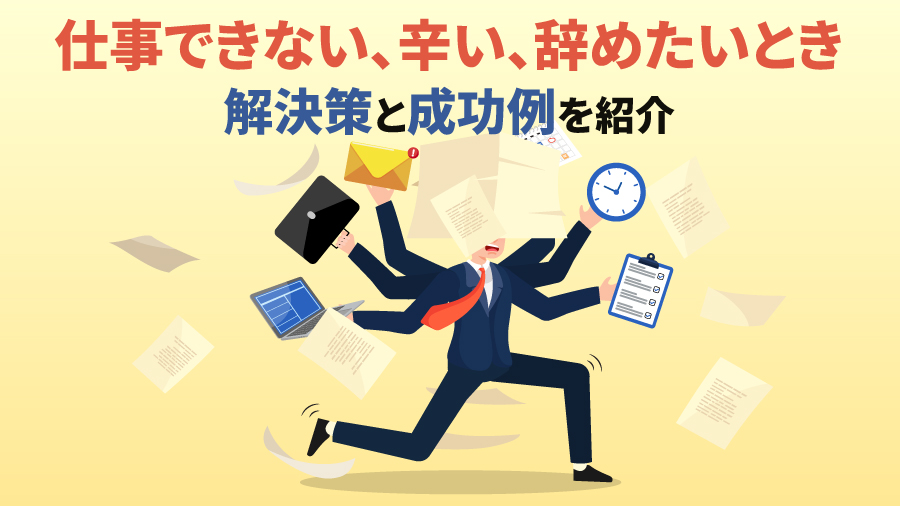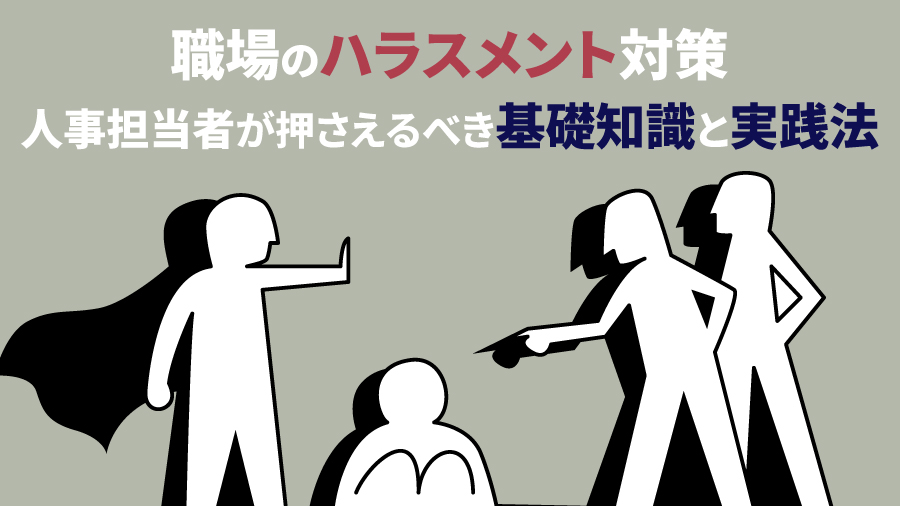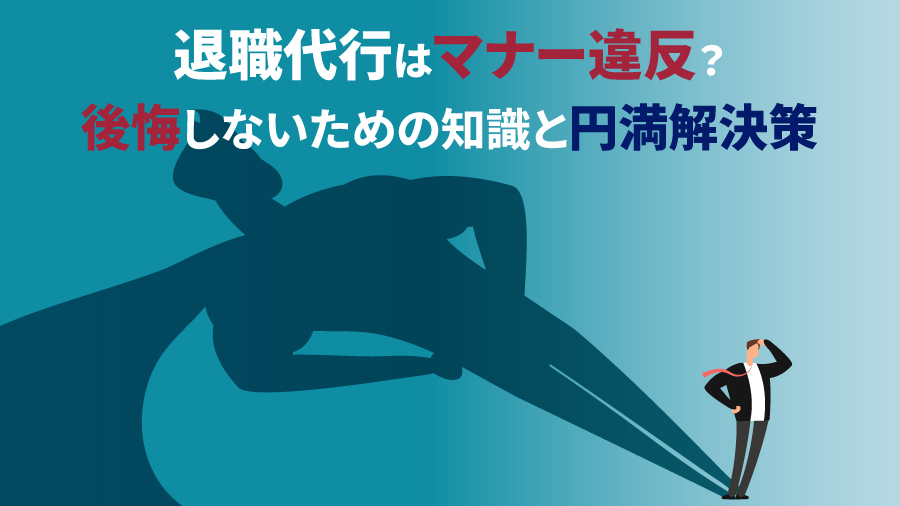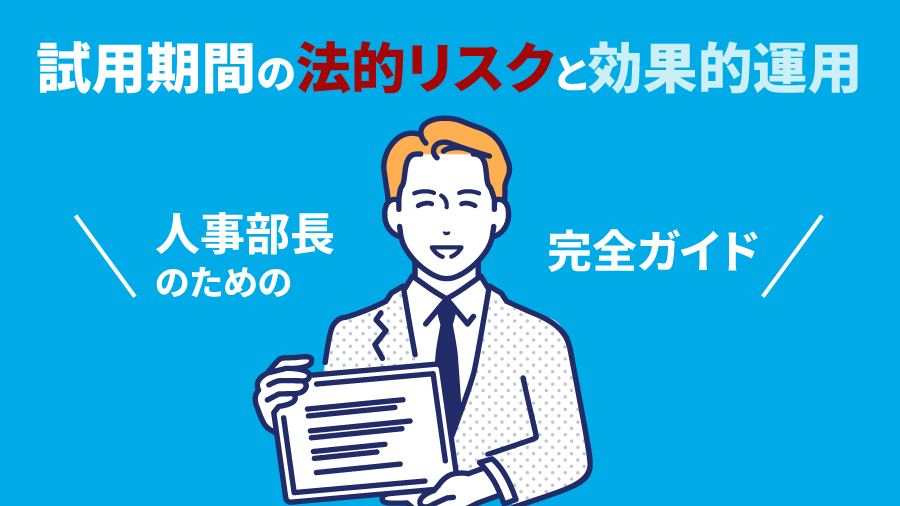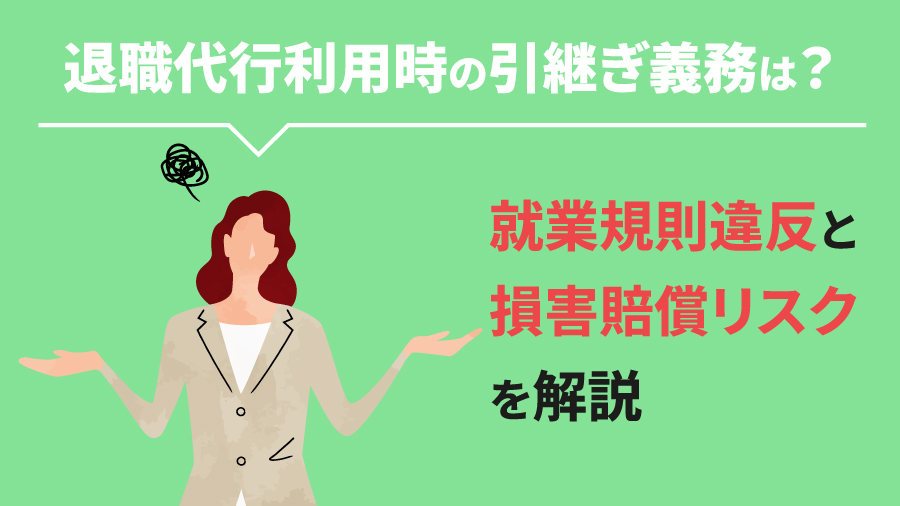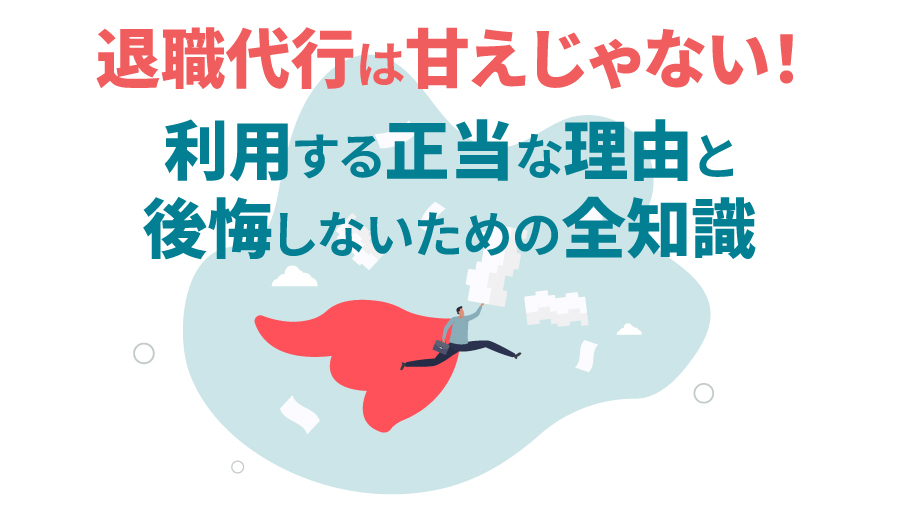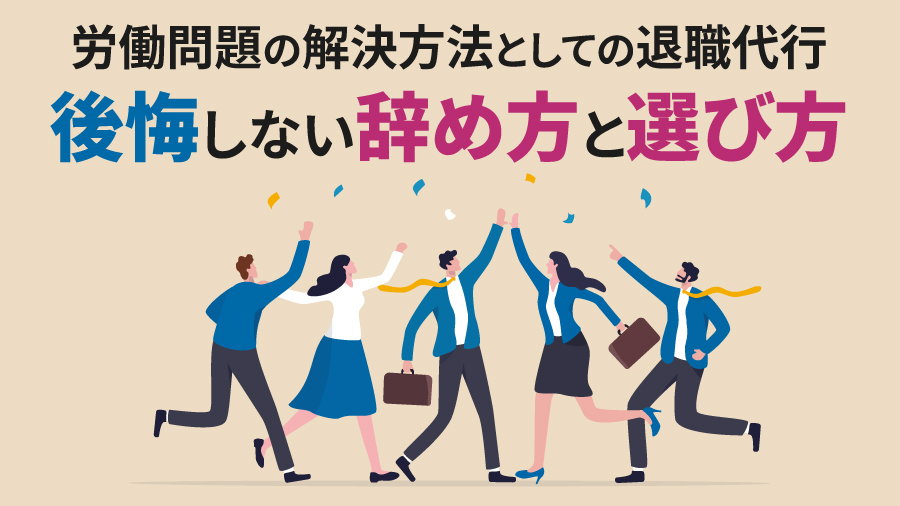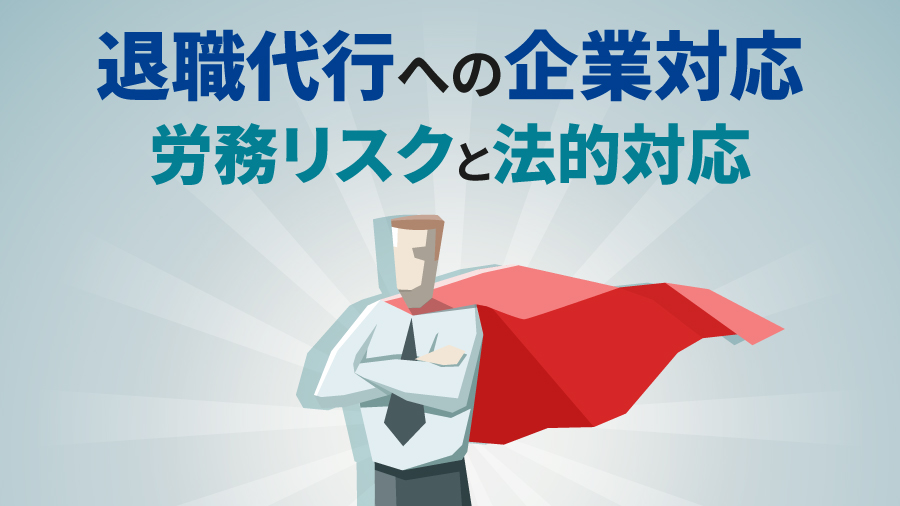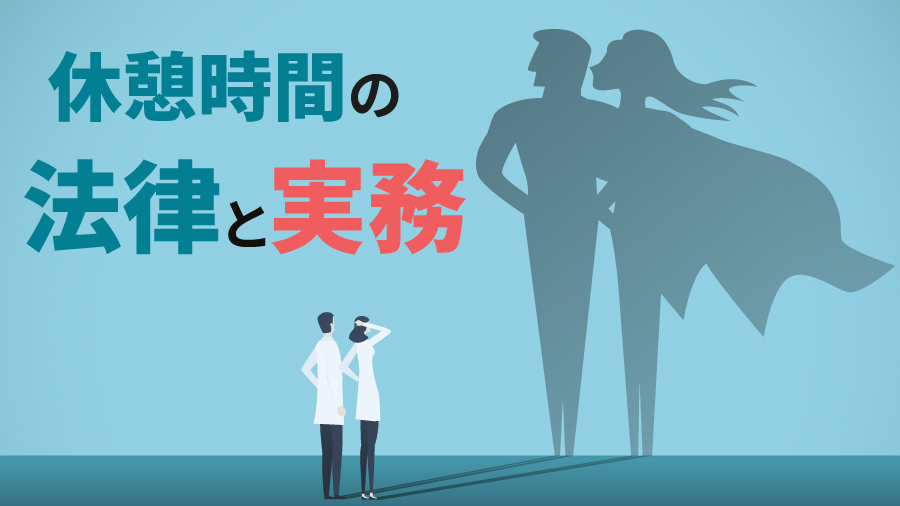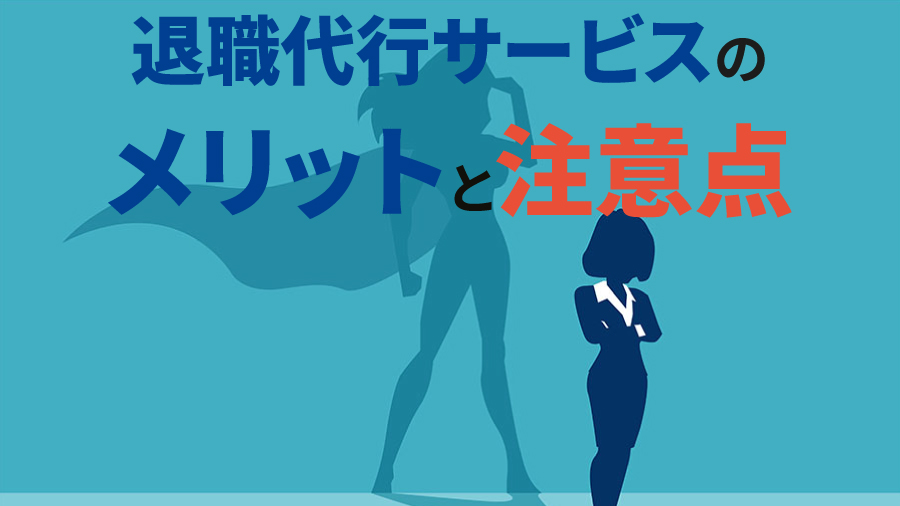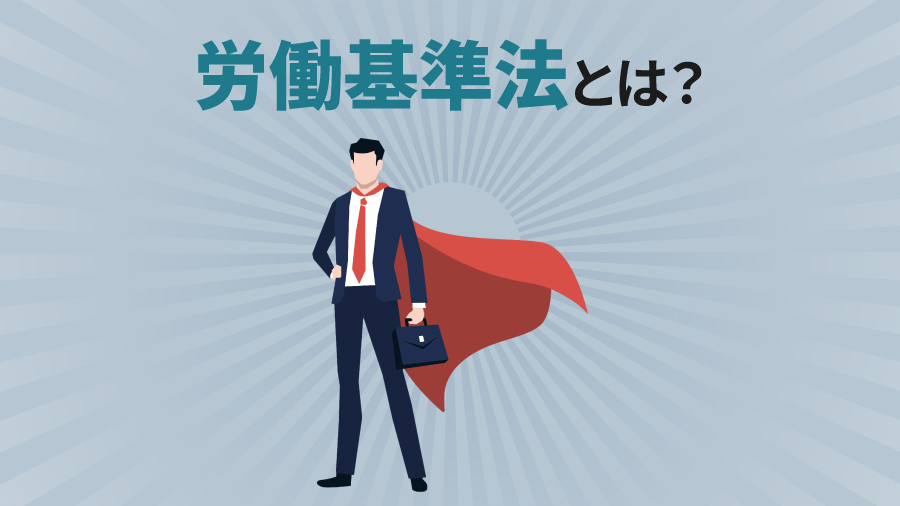-
-
退職代行はグレーゾーン?違法性とトラブル回避のポイント
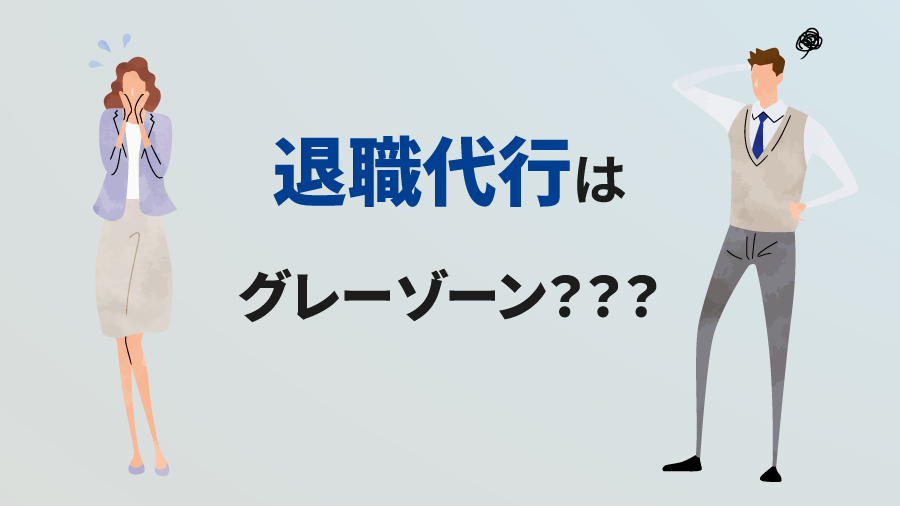
退職代行の利用は違法ではありませんが、非弁行為に該当する可能性があるため注意が必要です。精神的に限界を感じ、すぐにでも退職したいと考える方にとって、退職代行は有効な手段となり得ます。しかし、法的なリスクやトラブルを避けるためには、信頼できる業者の選定が重要です。本記事では、退職代行の合法性やグレーゾーンとされる理由、トラブルを回避するためのポイントについて詳しく解説します。
目次退職代行のグレーゾーンとは?
退職代行サービスは、退職を希望する従業員にとって心強い味方となる一方、その業務内容や運営方法によっては法的な問題を指摘されることがあります。
では、具体的にどのような点が「グレーゾーン」と見なされ、場合によっては違法と判断されてしまうのでしょうか。
この章では、退職代行サービスが抱える可能性のある法的な問題点、特に「非弁行為」との関連性や、利用者が安心してサービスを選ぶための注意点について詳しく掘り下げていきます。グレーゾーンといわれる理由
退職代行サービスが「グレーゾーン」といわれる主な理由は、弁護士法第72条に抵触する可能性があるためです。
この法律は、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を行うこと(非弁行為)を禁じています。退職代行サービスにおいて、業者が単に本人の退職の意思を会社に「伝える」だけであれば、これは「使者」の役割とみなされ、一般的には合法とされています。
しかし、会社側が退職を拒否したり、未払い賃金や有給休暇の消化、退職時期などについて交渉が必要になったりした場合、退職代行業者によるこれらの「代理交渉」は非弁行為にあたる可能性があります。
法的なリスクとその回避方法
- 交渉の範囲
- 退職代行業者が本人に代わって会社と交渉を行うことは、原則として弁護士資格を持つ者か、労働組合法上の団体交渉権を持つ労働組合でなければできません。一般的な退職代行業者がこれらの交渉を行うと、違法となるリスクがあります。
- トラブル対応
- 会社との間で何らかの法的トラブル(例:損害賠償請求)が発生した場合、弁護士資格のない退職代行業者は対応できません。
- 業者の種類
- 退職代行サービスを提供する業者には、民間企業、労働組合、弁護士事務所などがあります。提供できるサービスの範囲は、その業者の法的立場によって異なります。弁護士や労働組合が運営するサービスであれば、交渉や法的な対応も期待できますが、民間企業の場合は「意思を伝える」範囲に限定されることが一般的です。
したがって、退職代行サービスを利用する際には、どこまでのサービスを期待するのか、その業者がどのような法的資格を持っているのかを事前に確認することが非常に重要です。
単に退職の意思を伝えてほしいのか、それとも交渉まで含めて依頼したいのかによって、選ぶべき業者が変わってきます。
安易に依頼すると、かえってトラブルが複雑化する可能性もあるため、注意が必要です。退職代行を利用する際の注意点
退職代行は有効な手段である一方、業者選定や契約条件に関して注意を怠ると、法的トラブルやサービス不履行のリスクを抱えることになります。
ここでは、信頼できる代行業者を見極めるための視点と、利用に際して押さえておきたい要点を解説します。信頼できる業者の選び方
退職代行業者を選ぶ際には、次のような基準を確認する必要があります。
- 運営主体が明確である(弁護士事務所・労働組合など)
- 実績や利用者の口コミ・評判に信頼性がある
- ホームページに料金体系や対応範囲が具体的に記載されている
特に、労働問題の対応力を持つ業者を選ぶことで、退職後のトラブルに発展するリスクを抑えられます。
ランキングサイトや比較記事だけでなく、第三者評価も参考にするのが賢明です。料金体系とサービス内容の確認
料金が不明瞭な業者との契約は避けるべきです。初回提示額が安くても、後から追加費用が発生する例もあります。契約前には以下を確認してください。
- 料金の内訳(基本料金・追加費用)
- 支払い方法と返金条件
- サービスの範囲(連絡代行の範囲、即日対応の可否)
あらかじめ明示された料金体系で、費用対効果が見合っているかを確認することで、後悔しない選択が可能になります。
プライバシー保護と秘密厳守
退職代行の利用を会社や家族に知られたくない場合、秘密保持が徹底されているかが重要です。
業者によっては、個人情報の管理体制が甘く、情報漏洩のリスクがあります。
以下の点に注目してください。- プライバシーポリシーの明記
- 個人情報保護の社内体制
- 契約内容に秘密保持条項があるか
秘密厳守を掲げ、プライバシー保護を強化している業者であれば、安心して利用できます。
退職代行利用後のトラブルを防ぐために
退職代行の利用は退職の意思表示に留まるため、退職後に発生するトラブルへの対処法もあらかじめ理解しておく必要があります。
退職後の対応に不安を感じる方に向けて、トラブルを防ぐ方法を具体的に解説します。退職後の会社からの連絡対応
退職後に会社から直接連絡が来るケースがありますが、弁護士または労働組合と連携している退職代行業者を利用していれば、原則として業者が対応を代行してくれる場合があります。
業者との契約時に、退職後のアフターサポート範囲を確認しておくと安心です。退職届や会社支給品の返却など、形式的なやりとりが必要な場合もありますが、すべてを個人で対応する必要はありません。
事前に書類のやりとりについても相談し、業者に対応を一任することで精神的負担を大幅に軽減できます。損害賠償請求への対処法
退職を理由に損害賠償請求を受ける事例は極めて稀ですが、万が一のケースに備えた対策が必要です。
民法上、正当な理由なく突然退職することによって会社に損害が発生した場合でも、実際に損害が証明されない限り賠償が認められることはほとんどありません。それでも不安がある場合には、退職手続きを弁護士が監修・対応する退職代行サービスを選ぶことで、法的な正当性を確保しながらスムーズな退職が実現できます。
トラブルに発展した場合の相談体制があるかどうかも、業者選定のポイントになります。再就職への影響と対策
退職代行を利用したことが履歴書や面接で直接的に不利になることは基本的にありません。
しかし、前職の退職理由について尋ねられる場面では、「体調不良による判断」や「冷静に状況を見極めた結果の選択」といった、前向きかつ事実に即した説明を準備しておくことが望ましいです。再就職支援や履歴書添削、面接対策など、アフターケアを提供する退職代行業者も存在します。
再就職を意識するなら、こうしたサポート体制が整っている業者を選択すると安心です。安心して退職代行を利用するためのチェックリスト
退職代行サービスの利用は人生の重要な選択です。
後悔やトラブルを避けるために、事前に確認しておくべきポイントをチェックリスト形式で整理しました。
信頼できるサービスを選び、安心して退職を迎えるための判断材料としてください。利用前に必ず確認すべき契約事項
契約を結ぶ前に確認しておくべき具体的なポイントは次の通りです。
- 契約書の有無と内容の明確さ
- 利用規約やキャンセルポリシーの明記
- 料金の内訳(基本料金・追加費用)
- 返金保証の有無とその条件
- サービス提供時間と即日対応の可否
- 担当者との連絡手段と対応スピード
これらを事前に確認し、納得のいく形で契約を進めることがトラブルを防ぐ第一歩となります。
よくある質問(FAQ)
退職代行を利用する際によく寄せられる疑問に対して、法的根拠や実例に基づいて明確にお答えします。
不安を解消し、納得して利用するための参考にしてください。- 退職代行を使うのは違法ではないの?
- 退職の意思を会社に伝えるだけであれば違法ではありません。問題となるのは、報酬を得て会社と交渉する「代理交渉」で、これは弁護士法第72条に基づき非弁行為とされる可能性があります。弁護士が運営するサービス、または労働組合が行う交渉であれば合法とされています。
- 会社にバレたり、訴えられたりしない?
- 退職の意思表示自体に法的問題はないため、訴えられることは非常に稀です。仮に損害賠償請求されたとしても、裁判で企業側が正当性を証明するのは困難です。適法な業者を選べば、連絡も代行されるため、会社との直接接触も避けられます。
- 即日退職はできるの?
- 可能です。民法上、原則として2週間前の申告が必要ですが、精神的な理由や体調不良など「やむを得ない事由」がある場合は、即日退職も認められる可能性があります。退職日が退職通知日から2週間後の日付けとなる場合もございますが、当日から出社せずに手続きを完了させるケースは多数あります。ご安心ください。いますぐ退職したいと考えている方は、今すぐ相談してみてください。
まとめ:退職代行は正しく選べば安心して使える手段
退職代行サービスは、退職の意思を安全かつ確実に伝えるための有効な選択肢です。
特に精神的なストレスを感じている場合、自力での手続きが困難なケースでは大きな助けになります。ただし、業者の選定を誤ると、非弁行為による違法性や、退職後のトラブルといったリスクに直面する可能性もあります。
弁護士や労働組合が運営するサービスを選び、契約条件を十分に確認した上で利用することで、安心して退職を進めることができます。退職は人生の節目です。
この記事を通じて正しい知識と判断基準を身につけ、精神的・法的に安全な退職を実現してください。
-