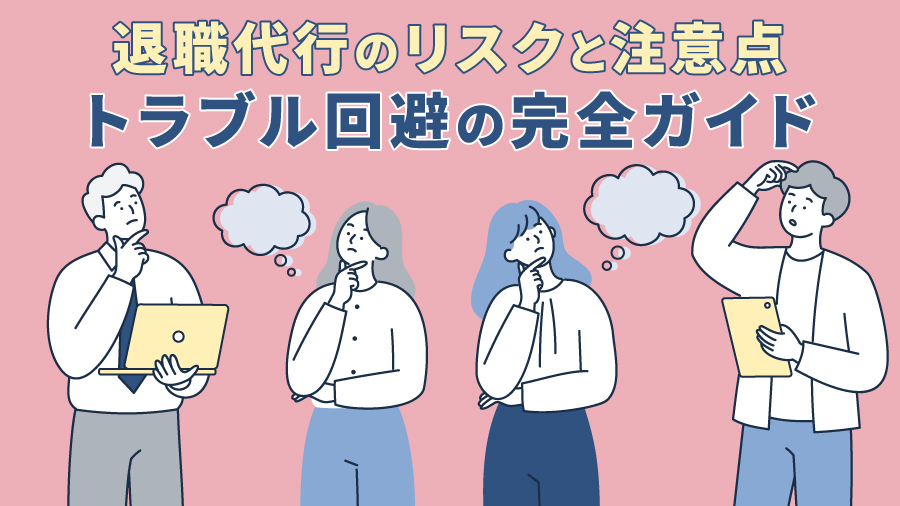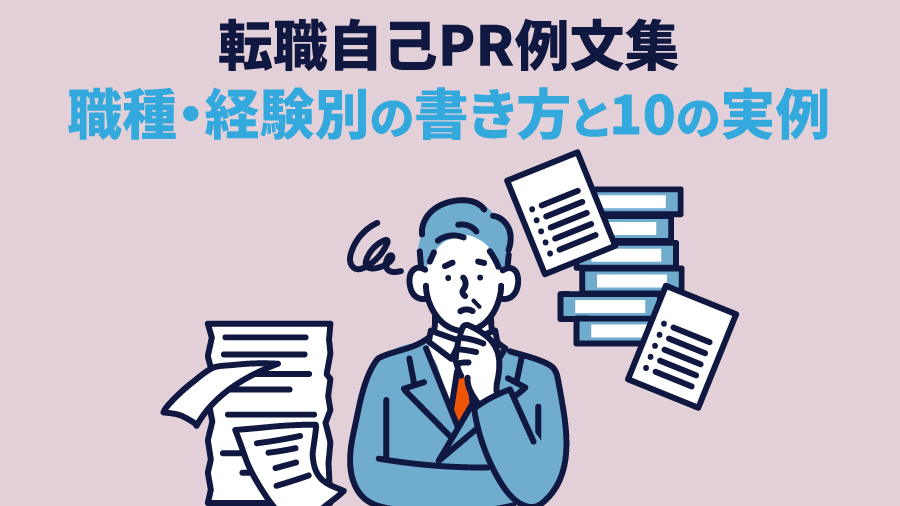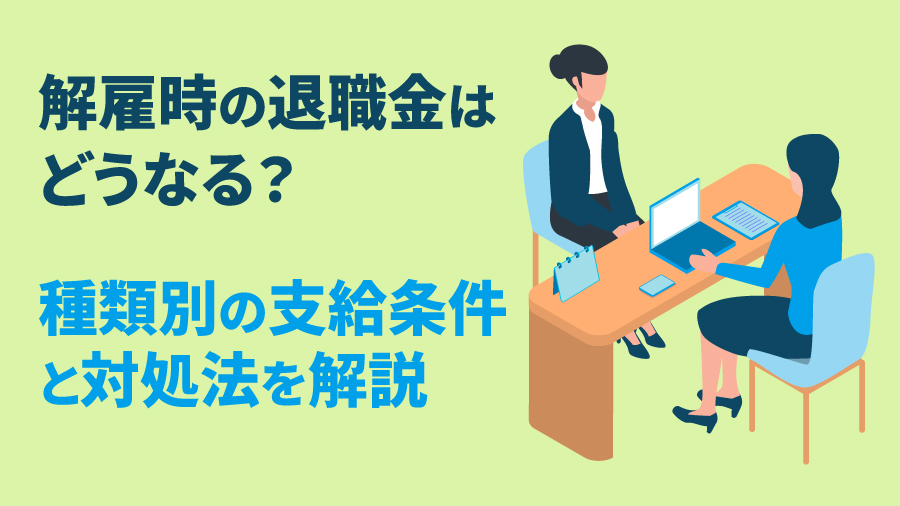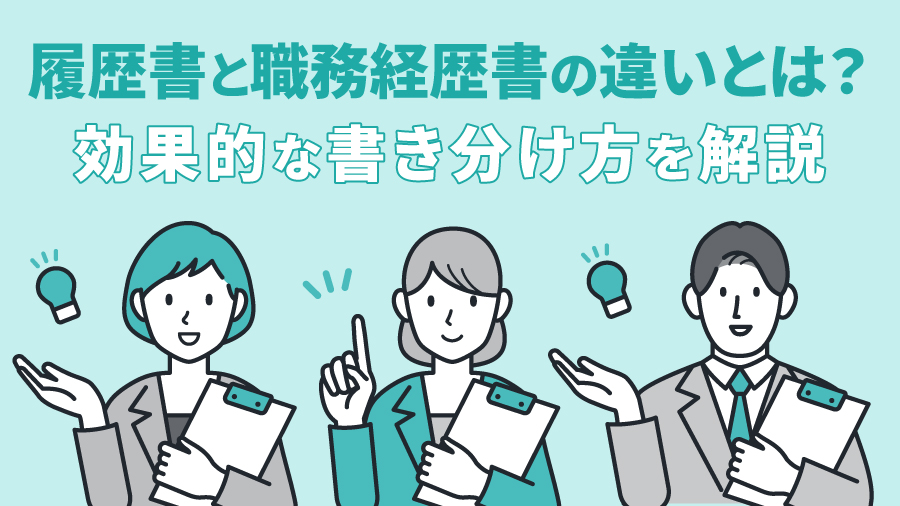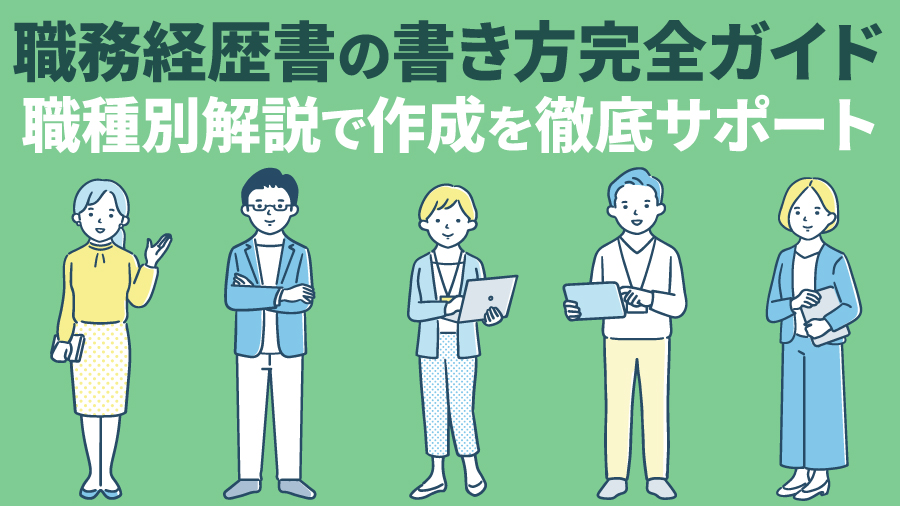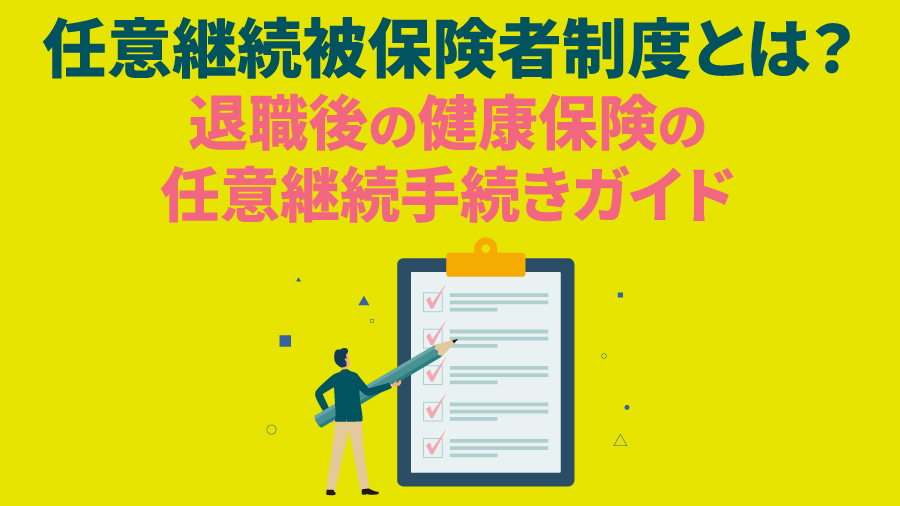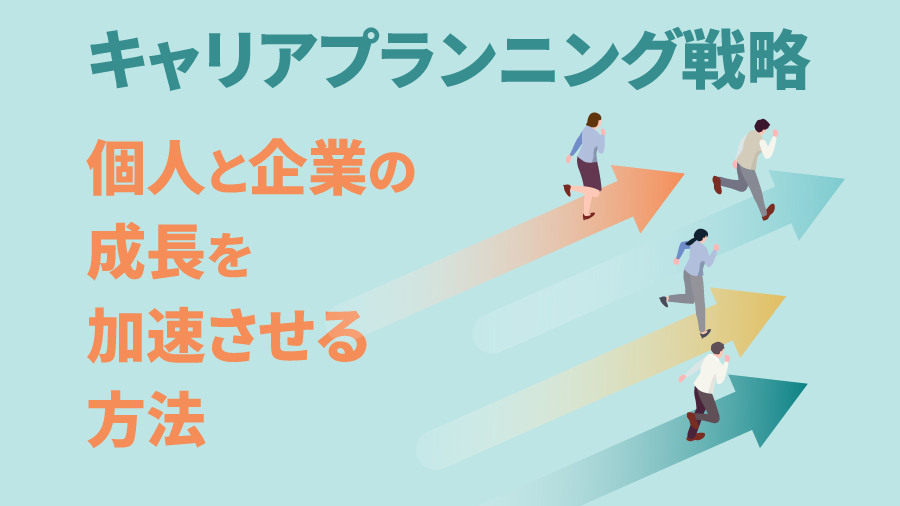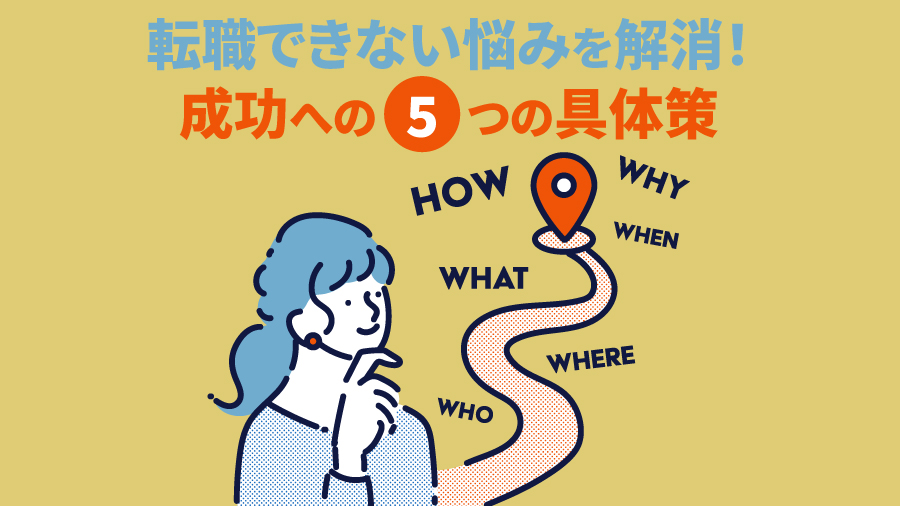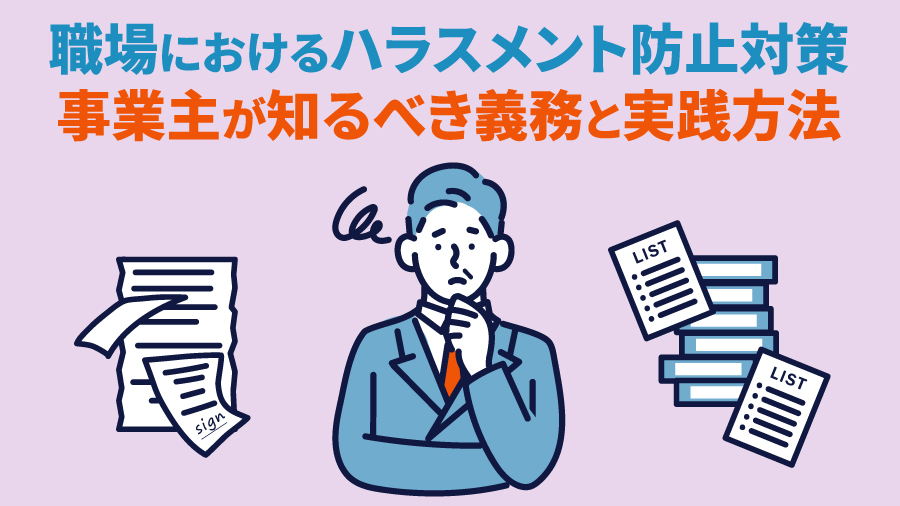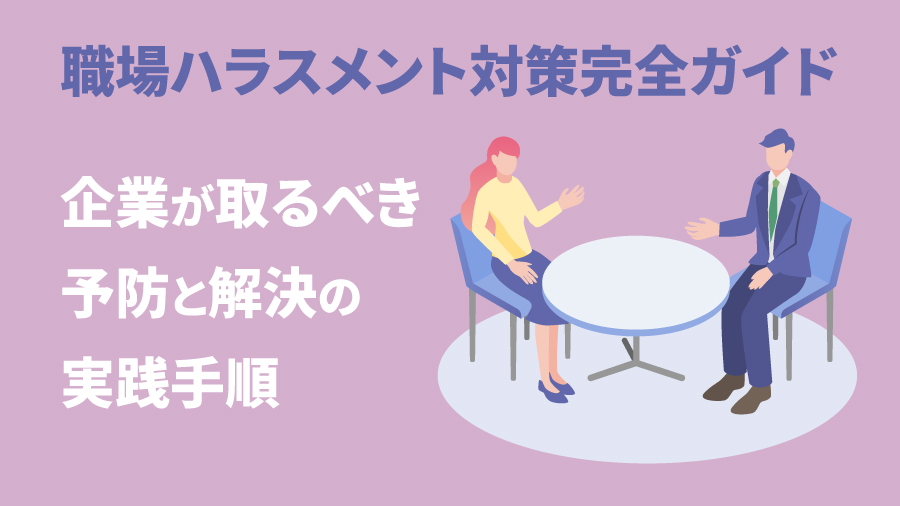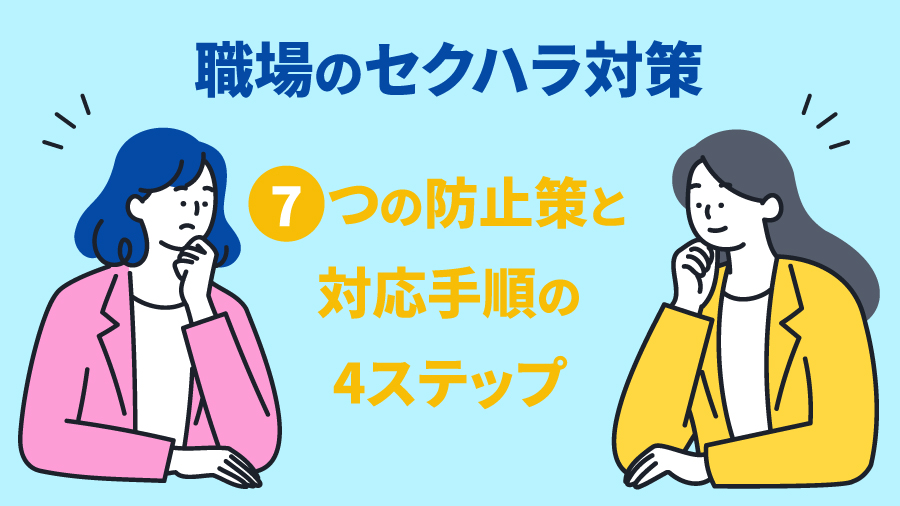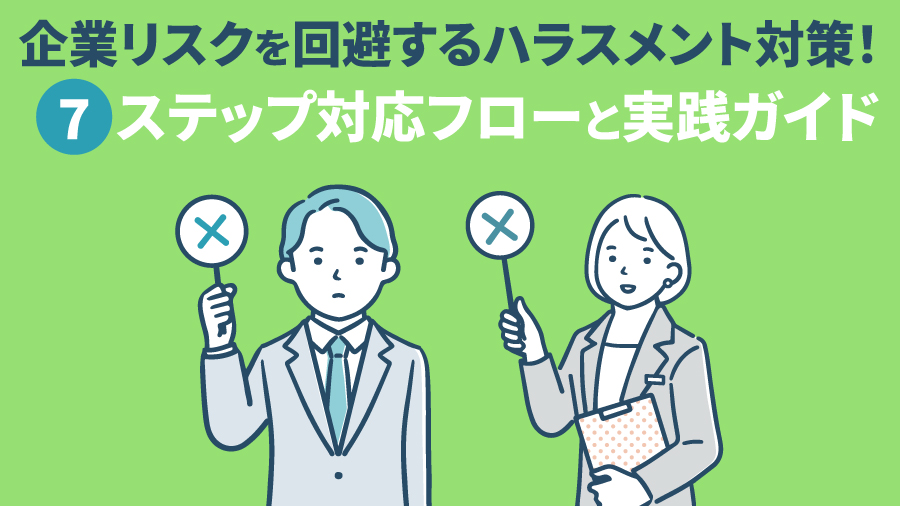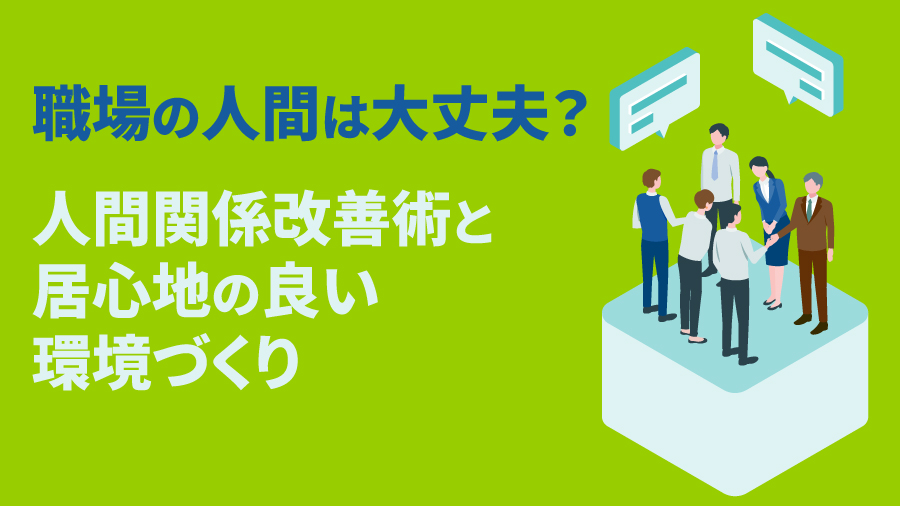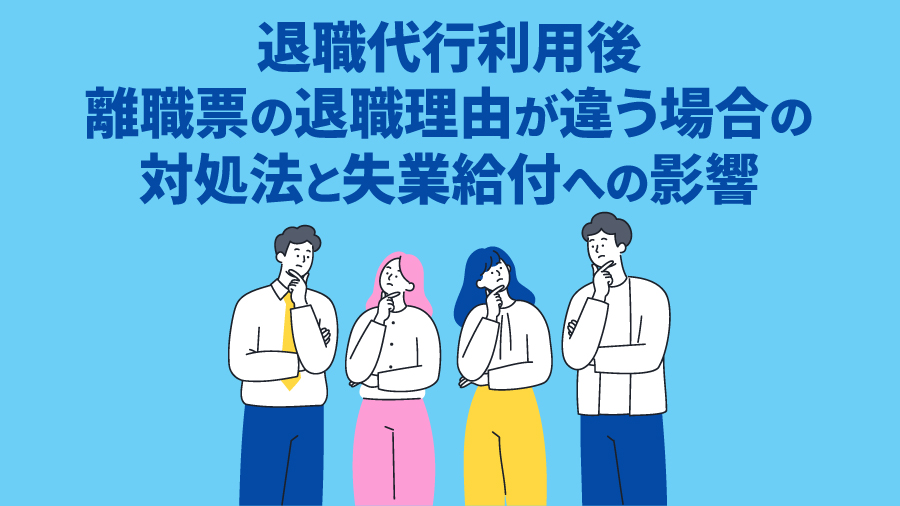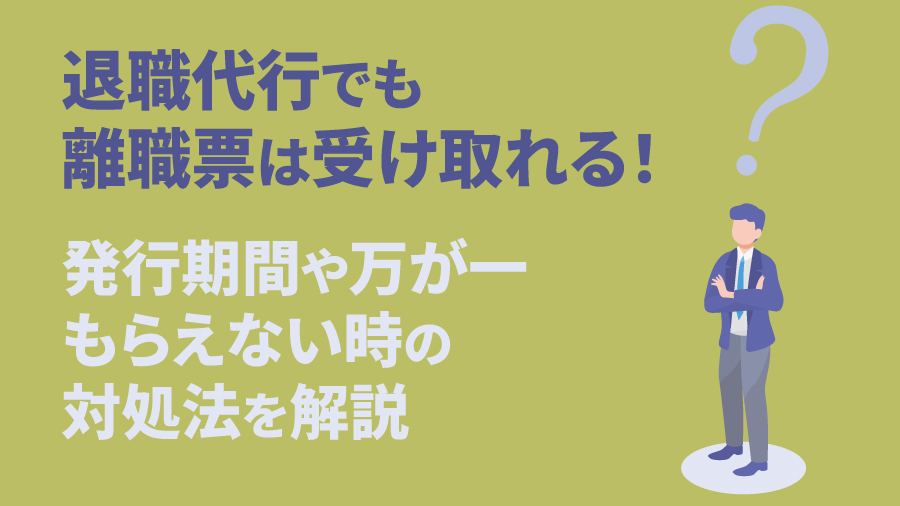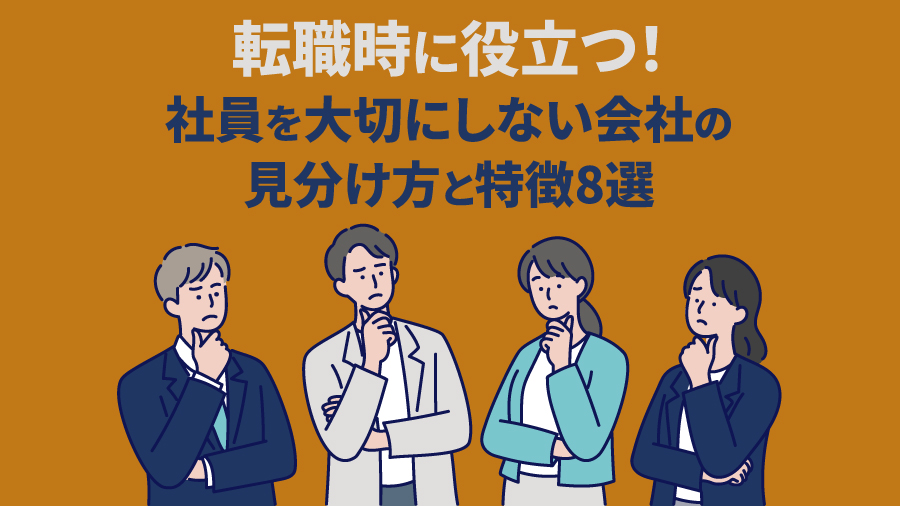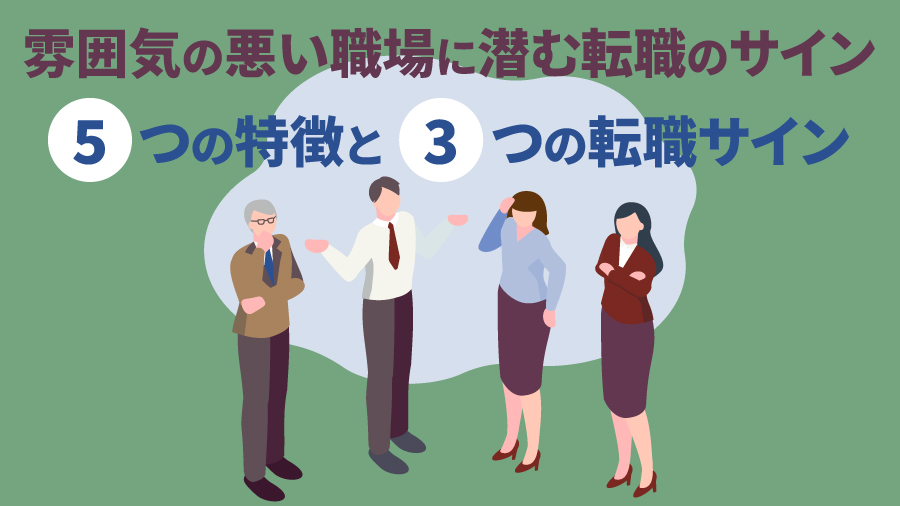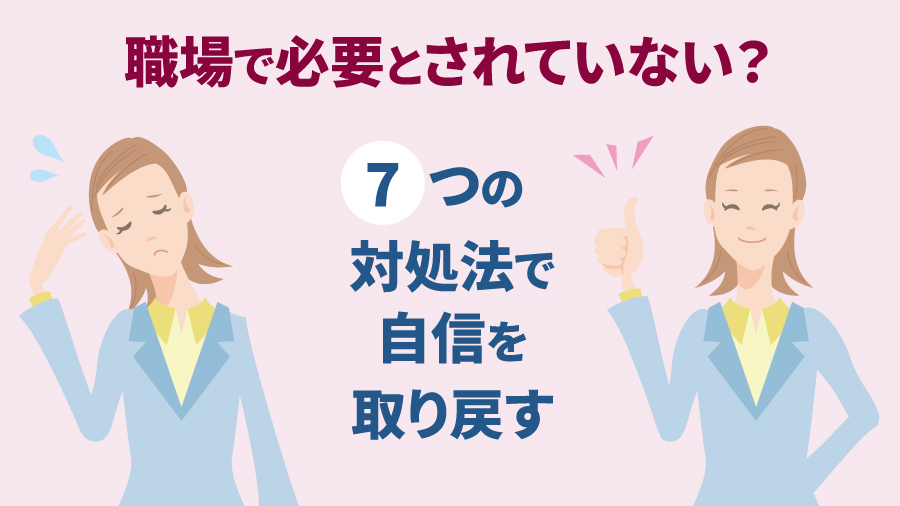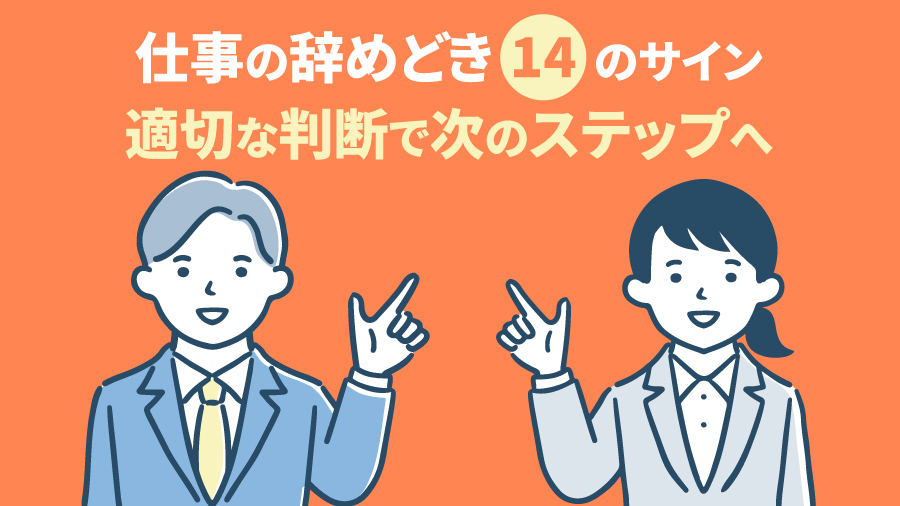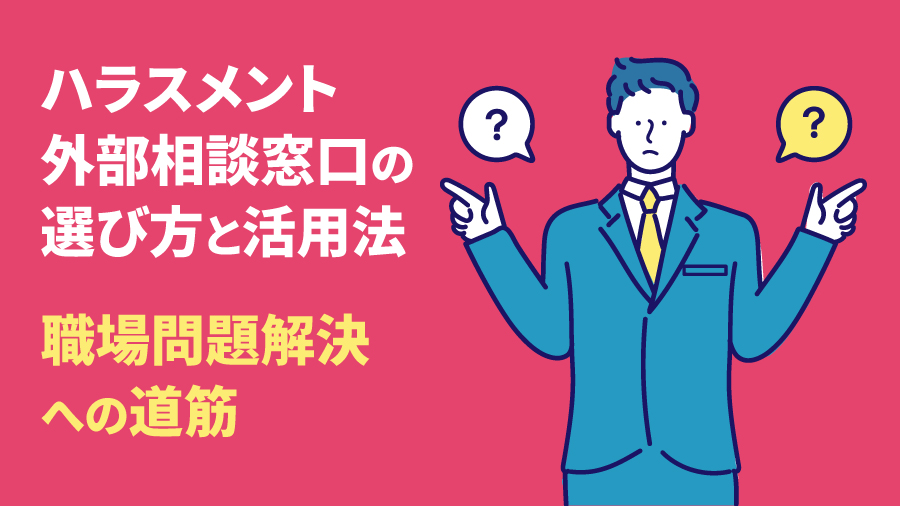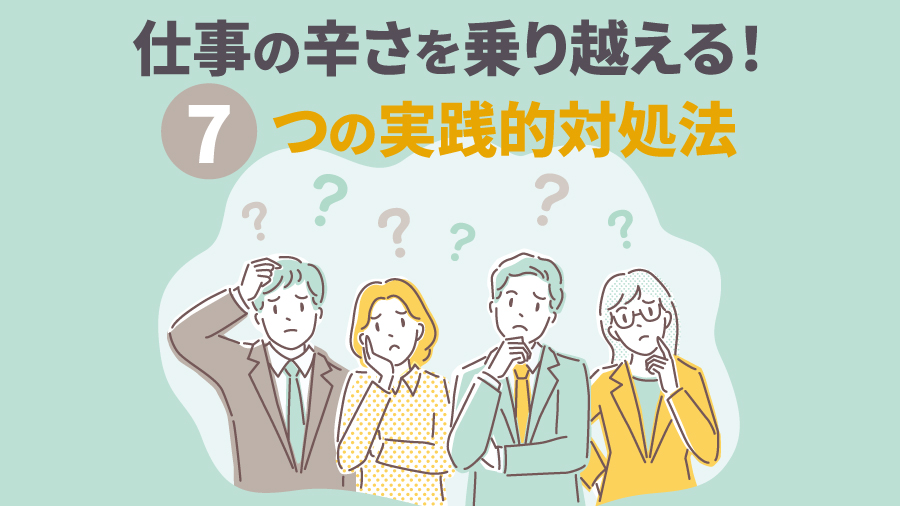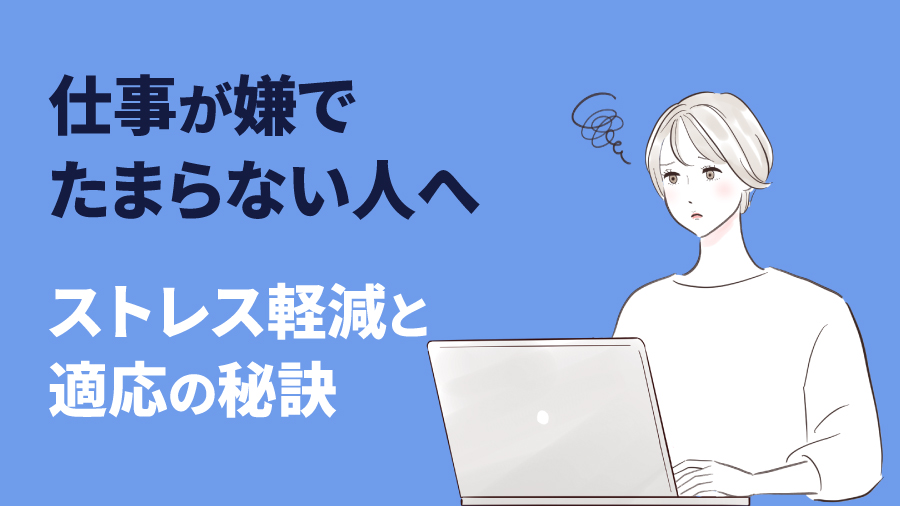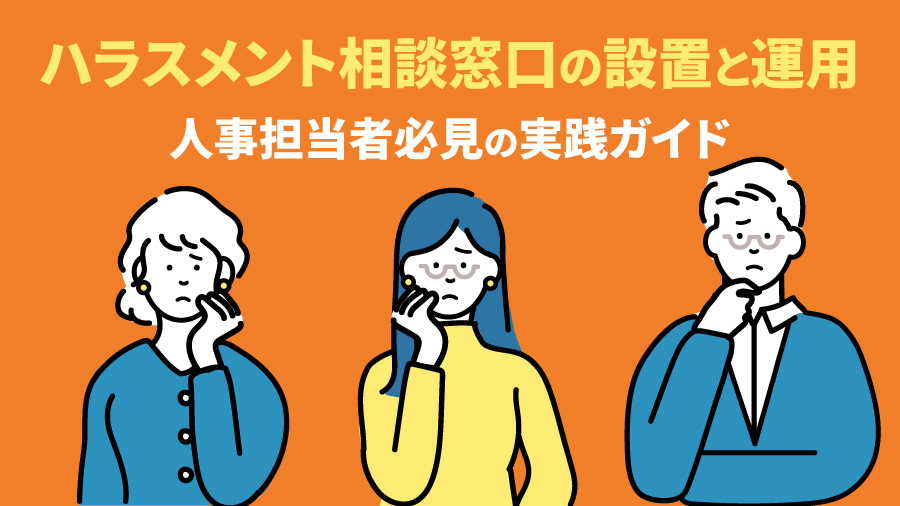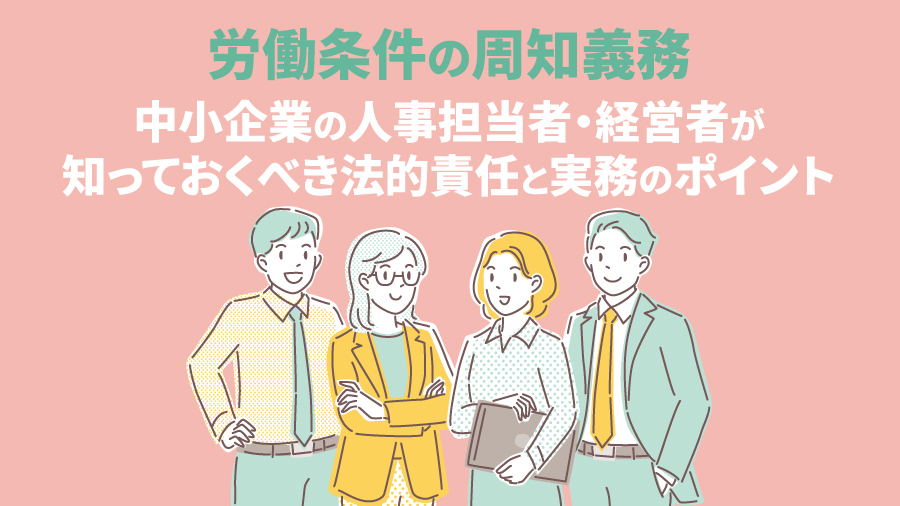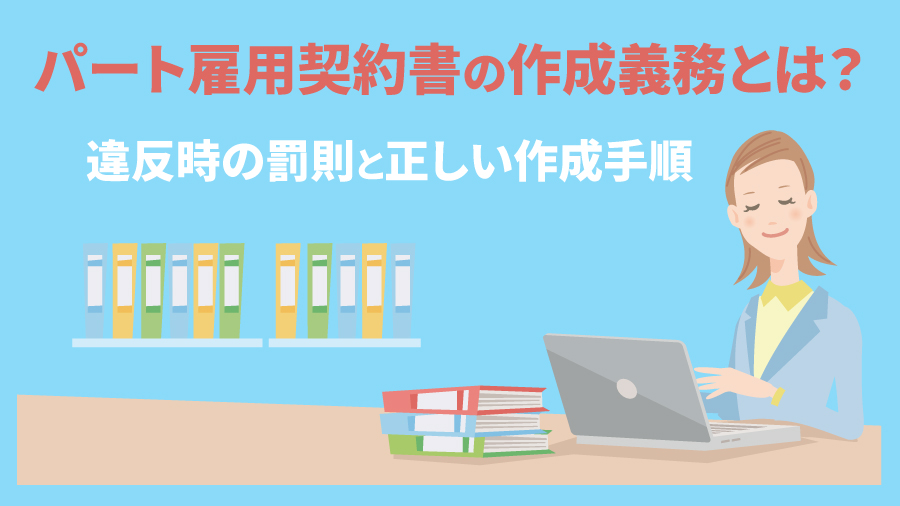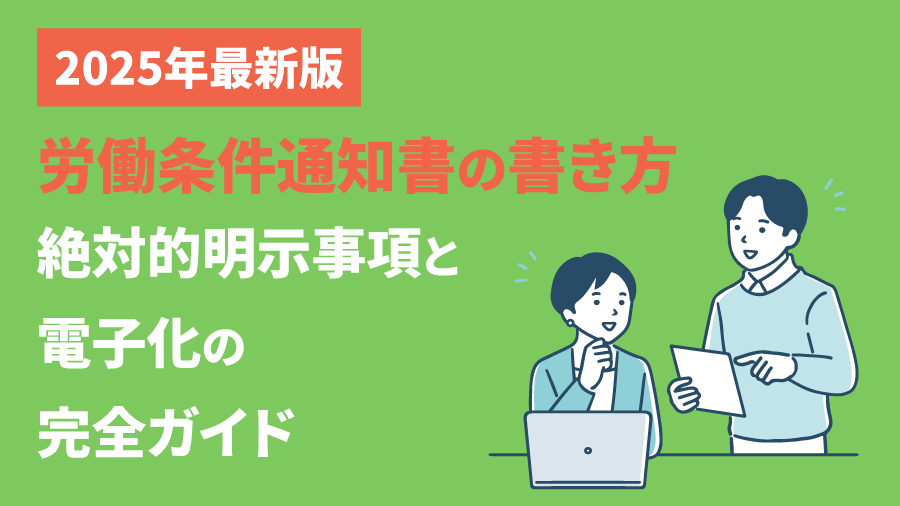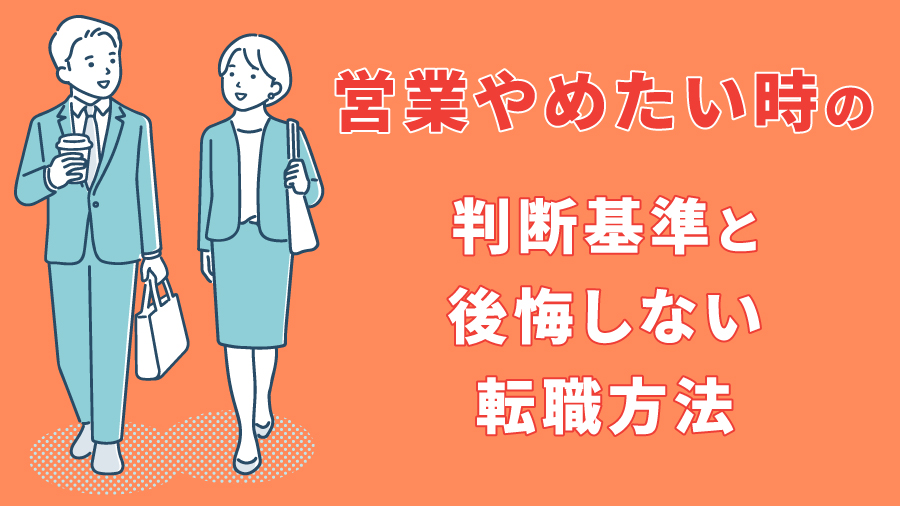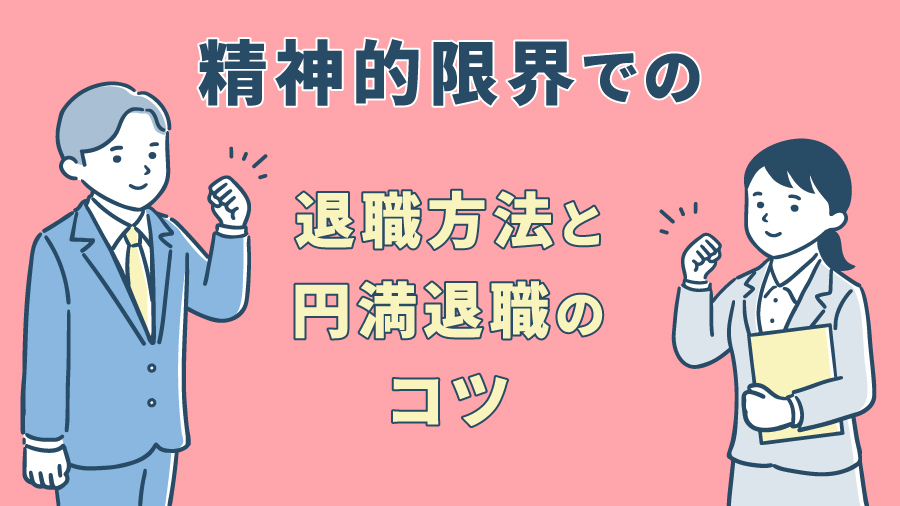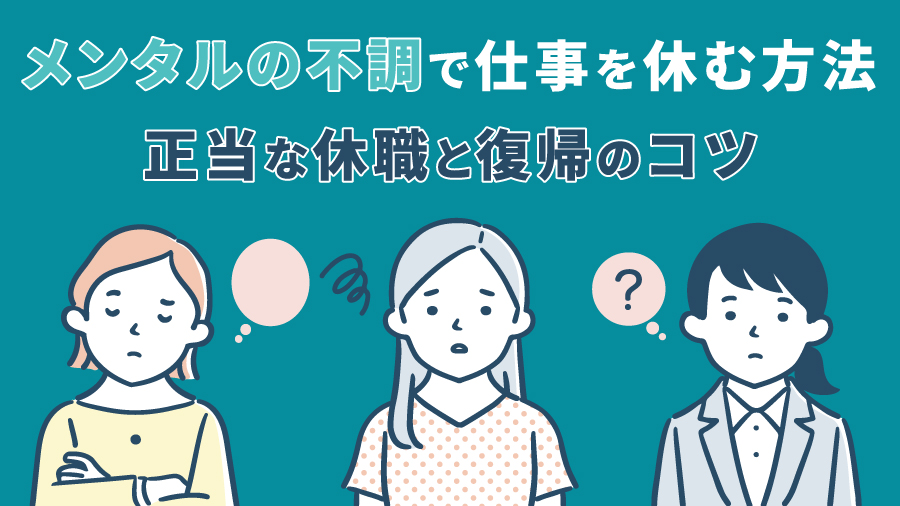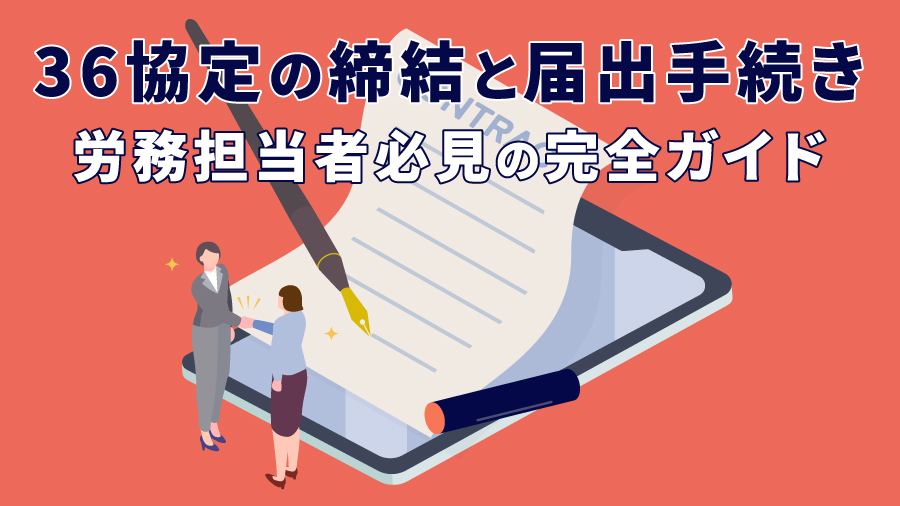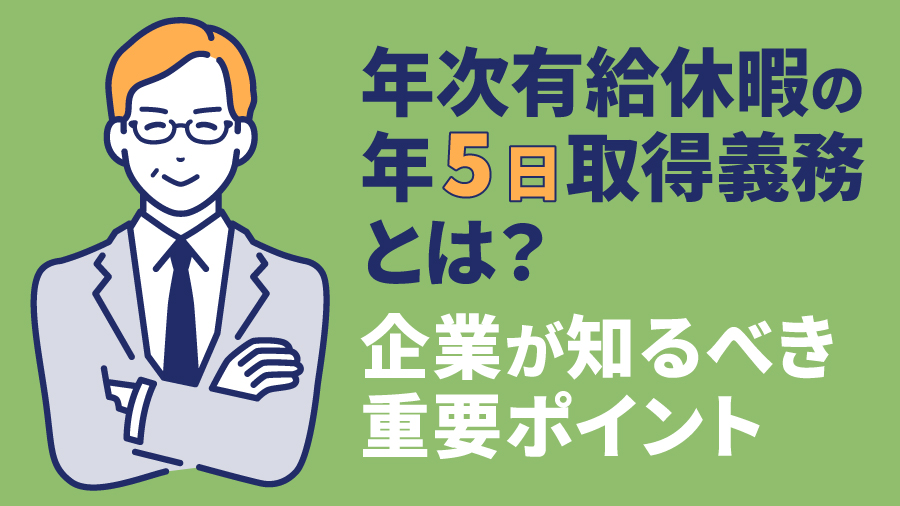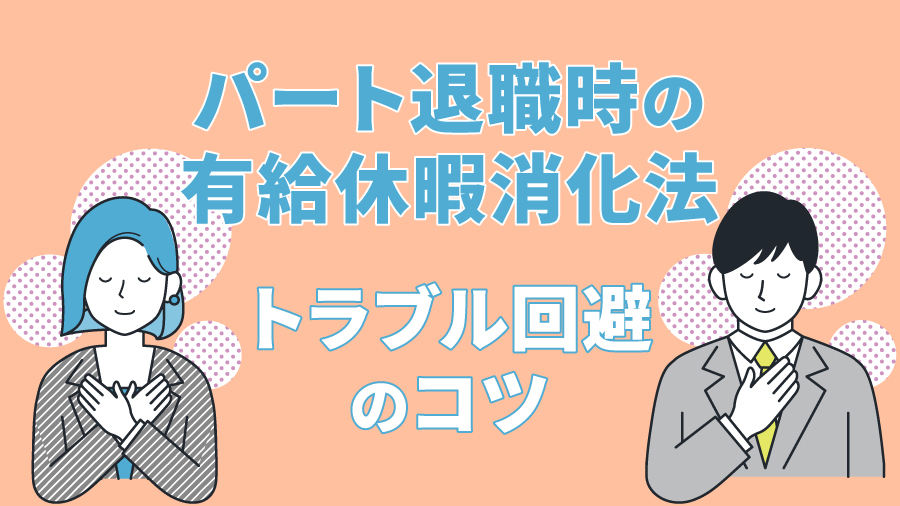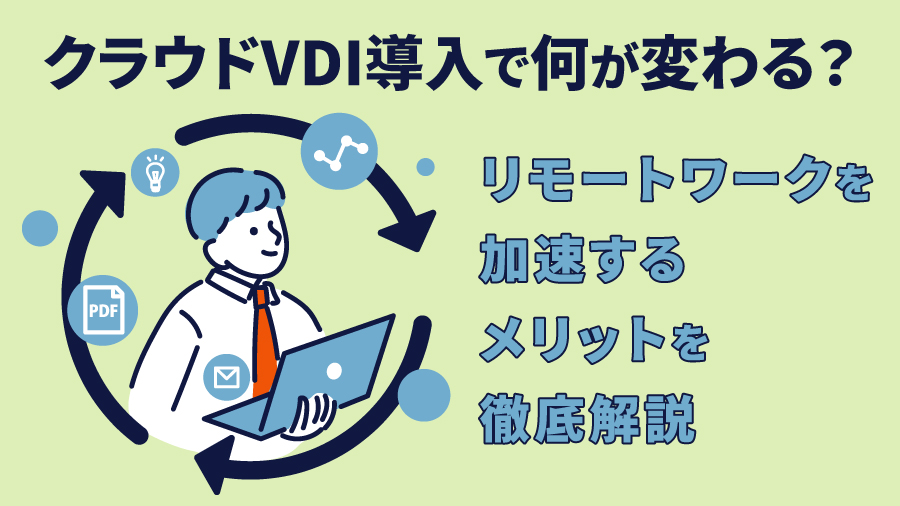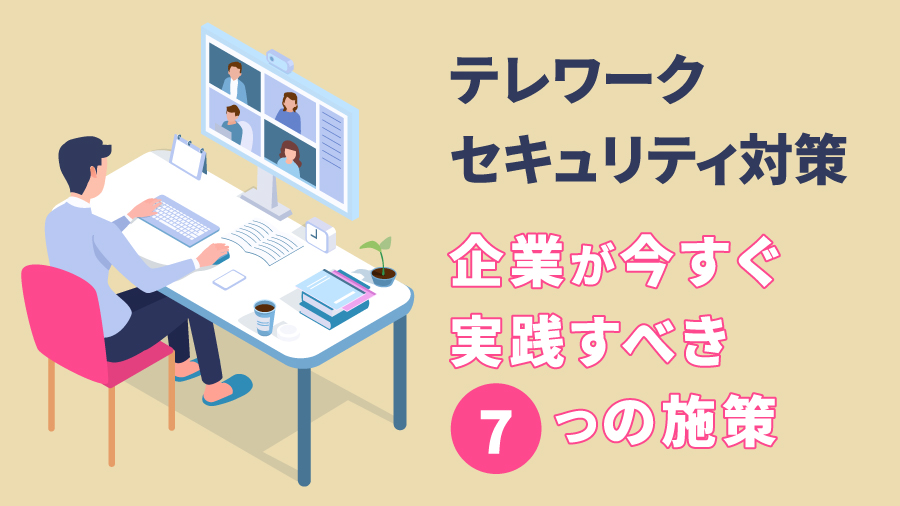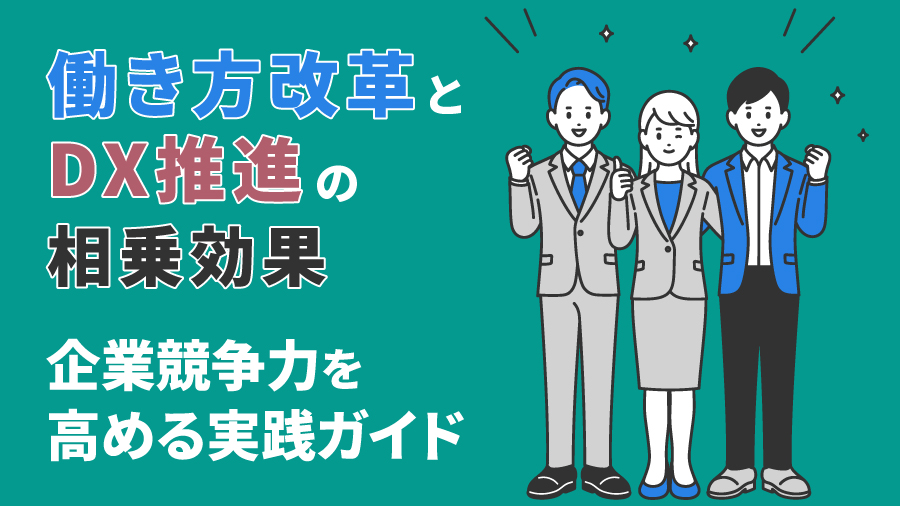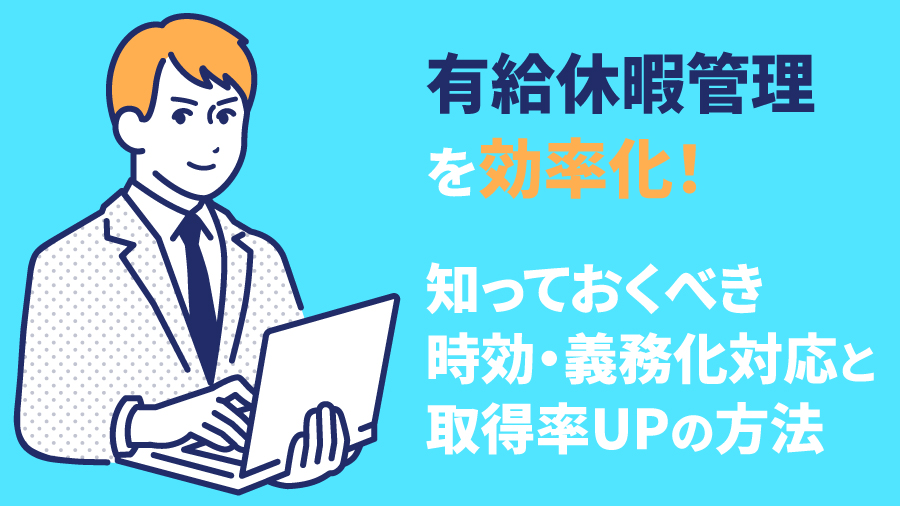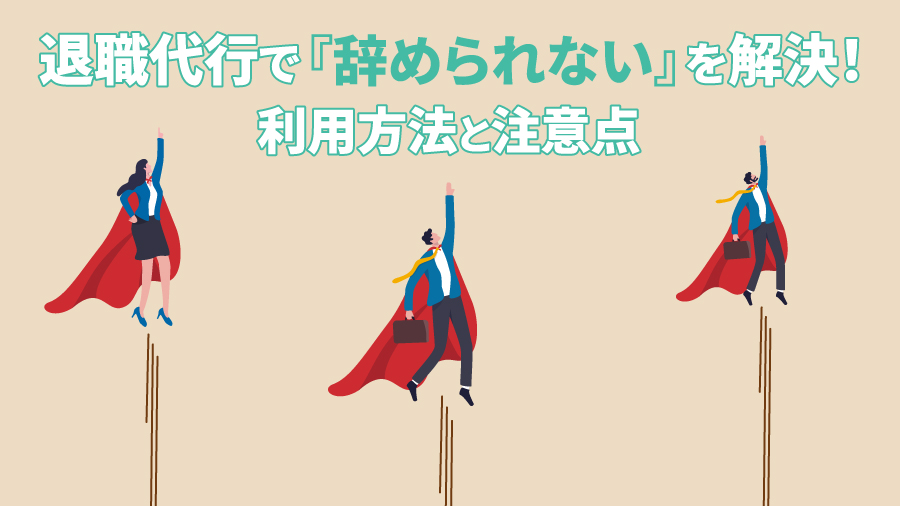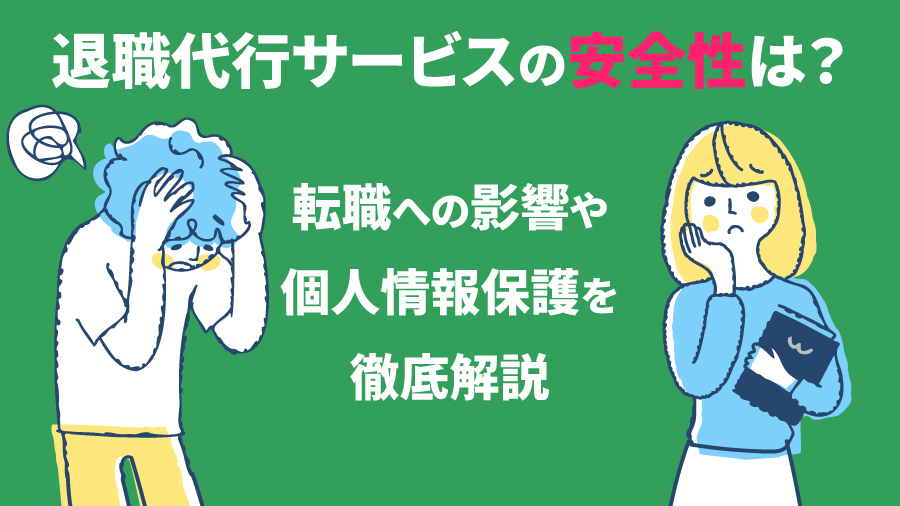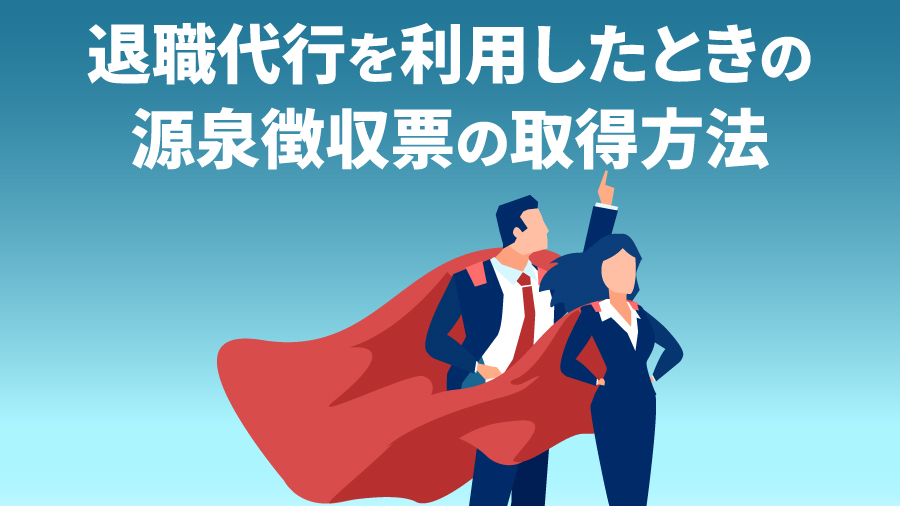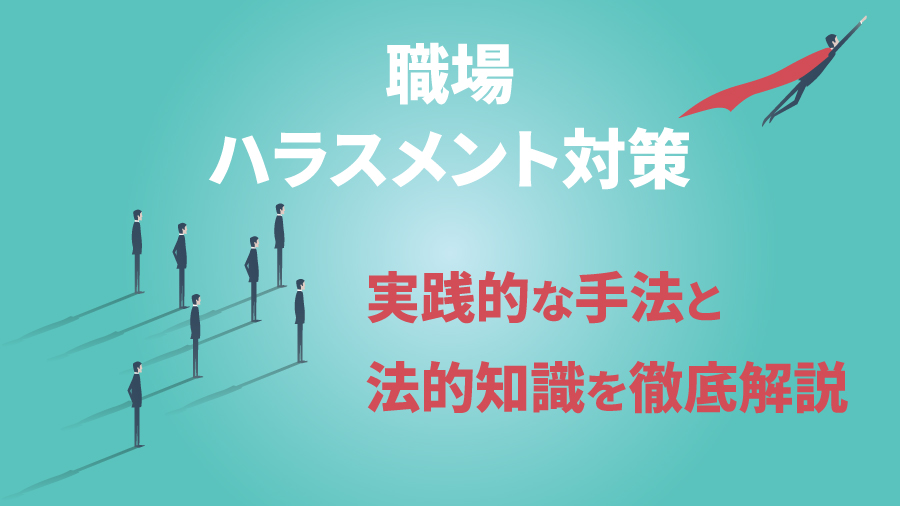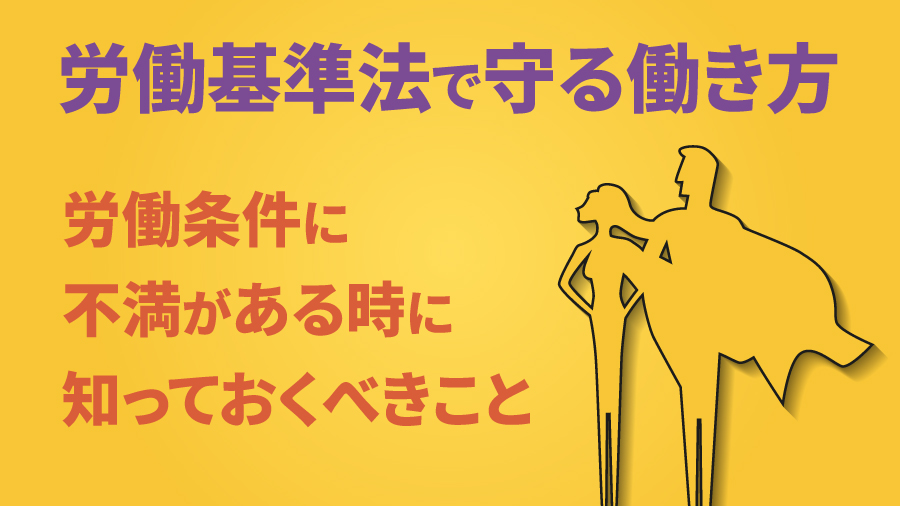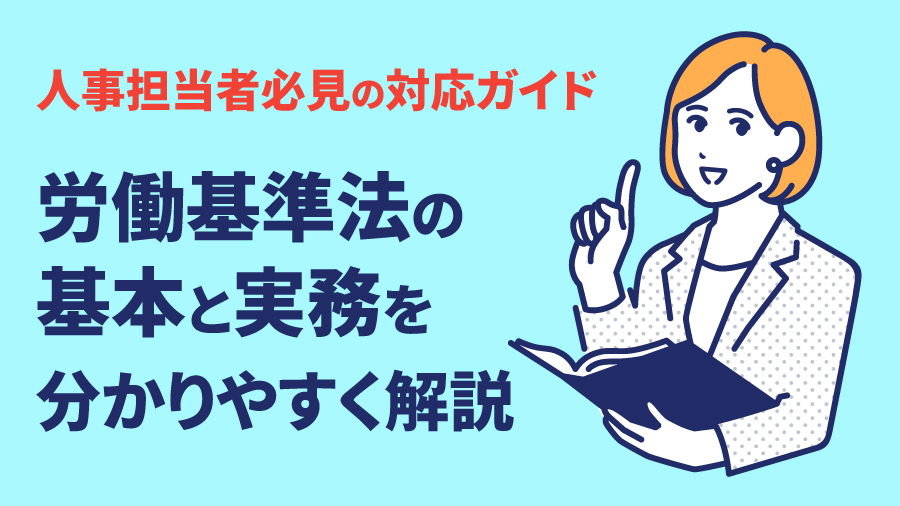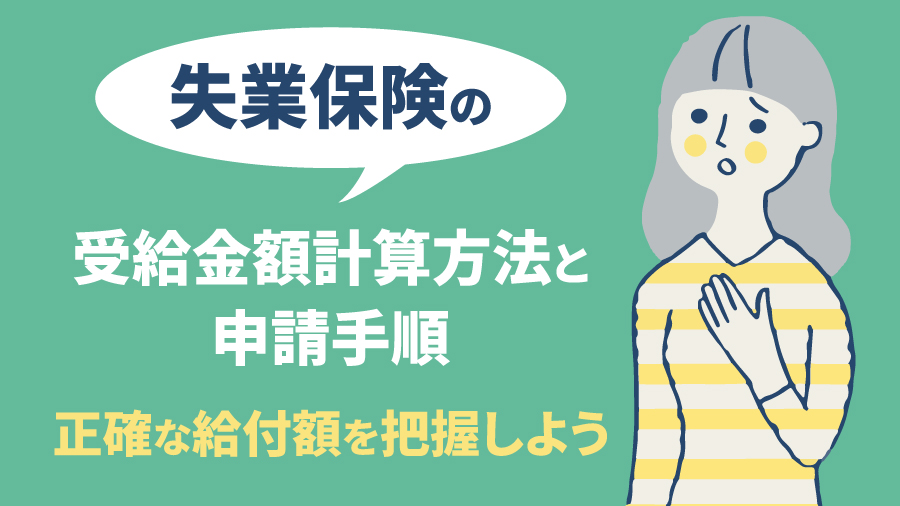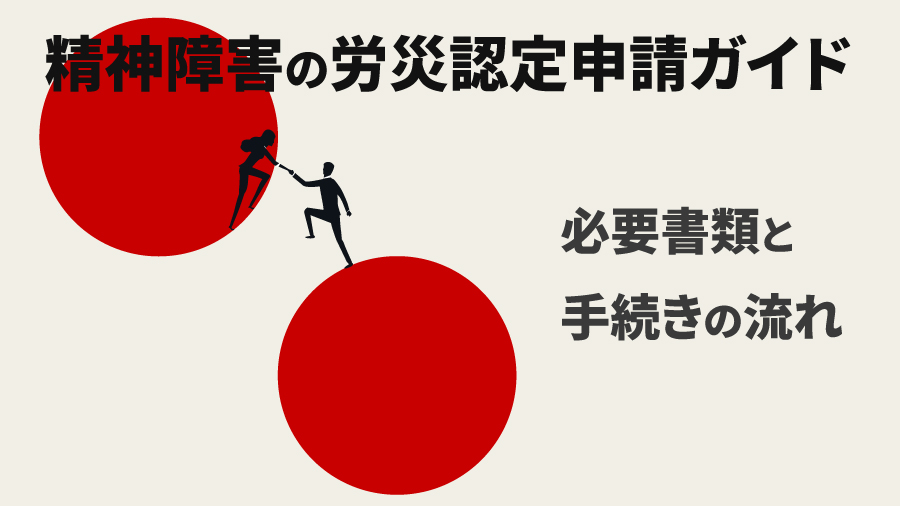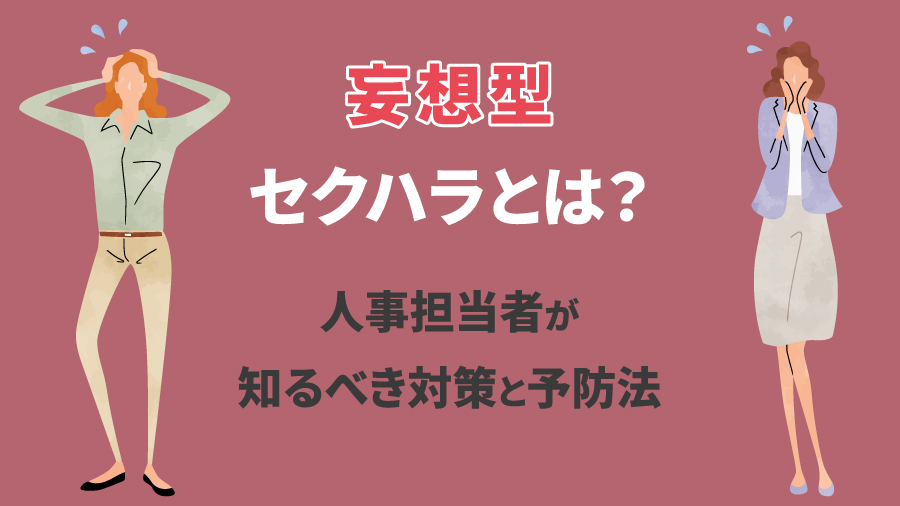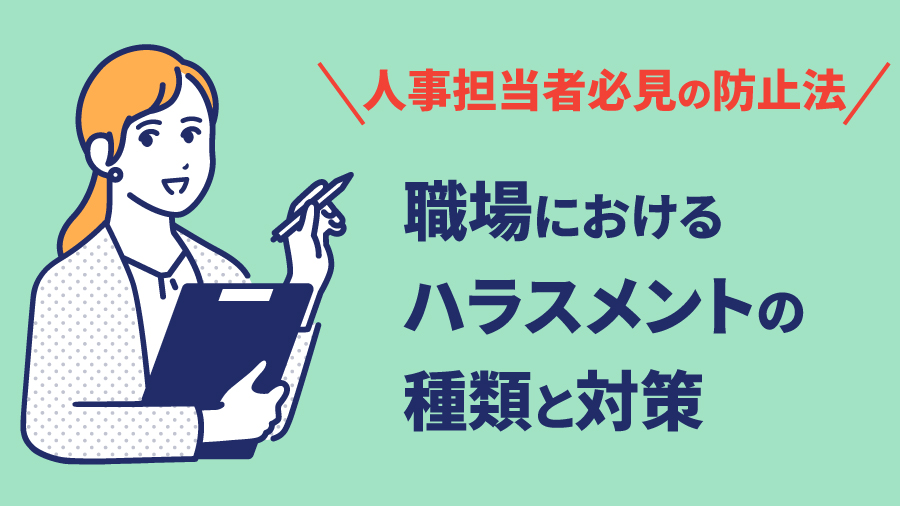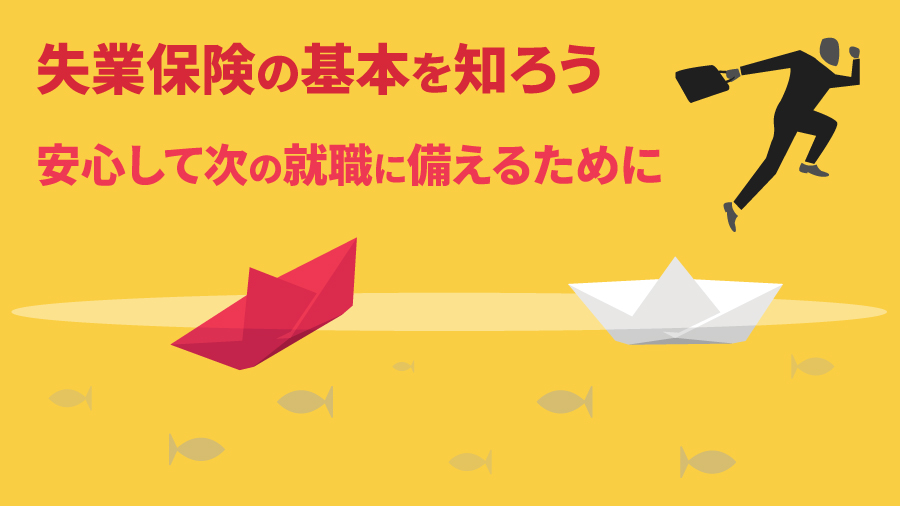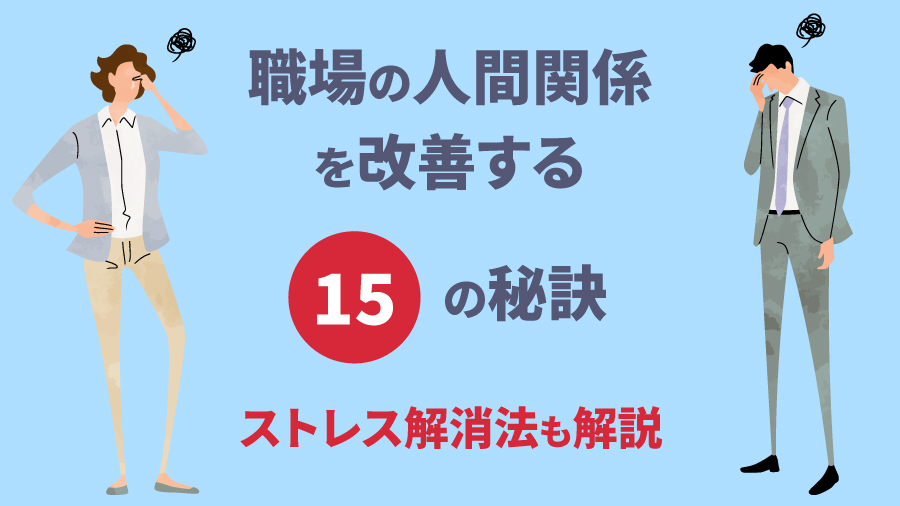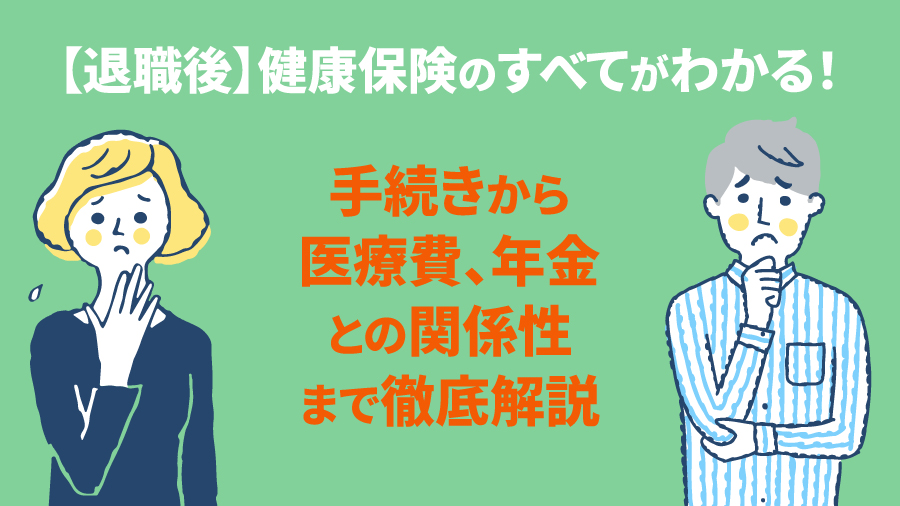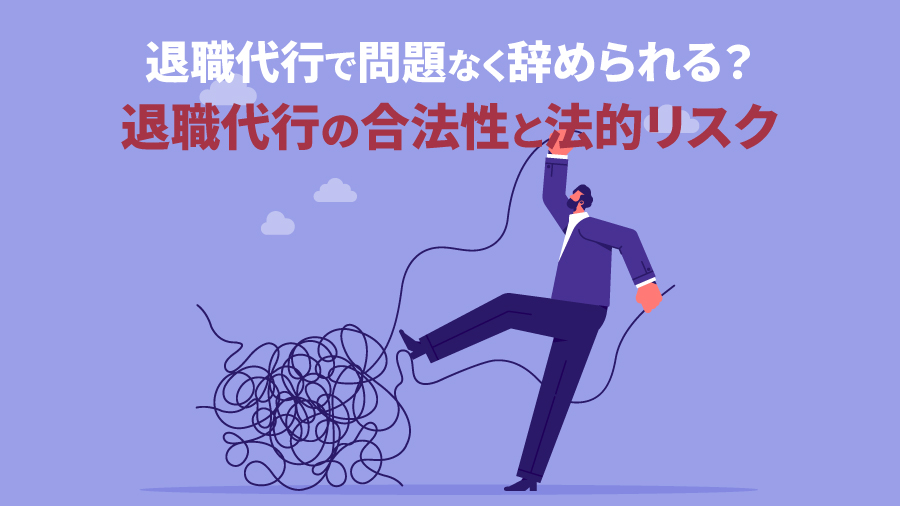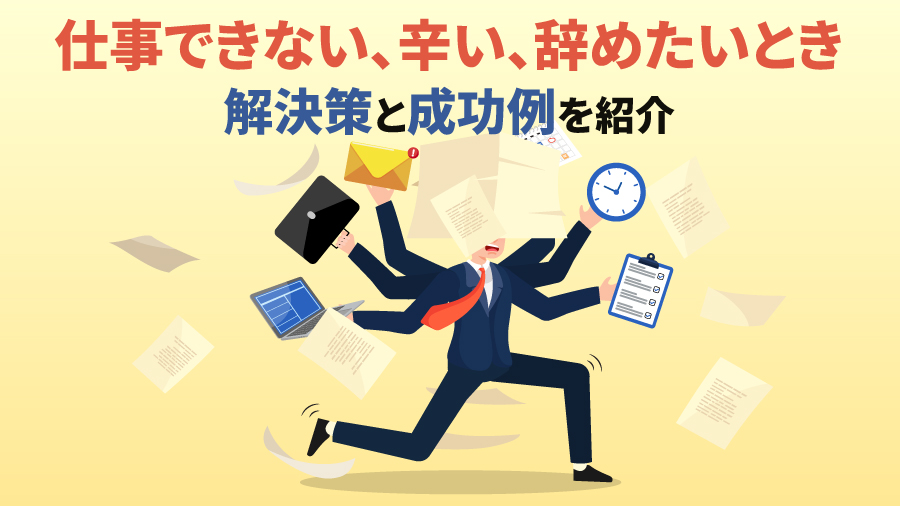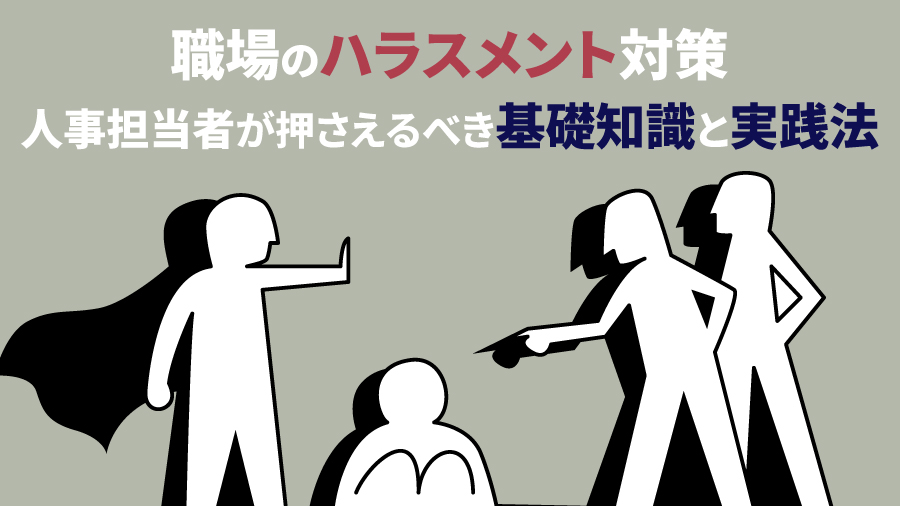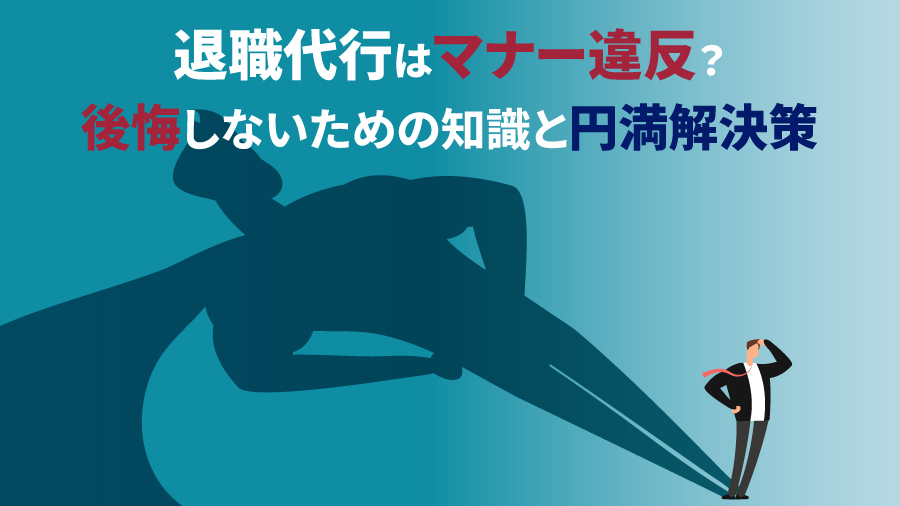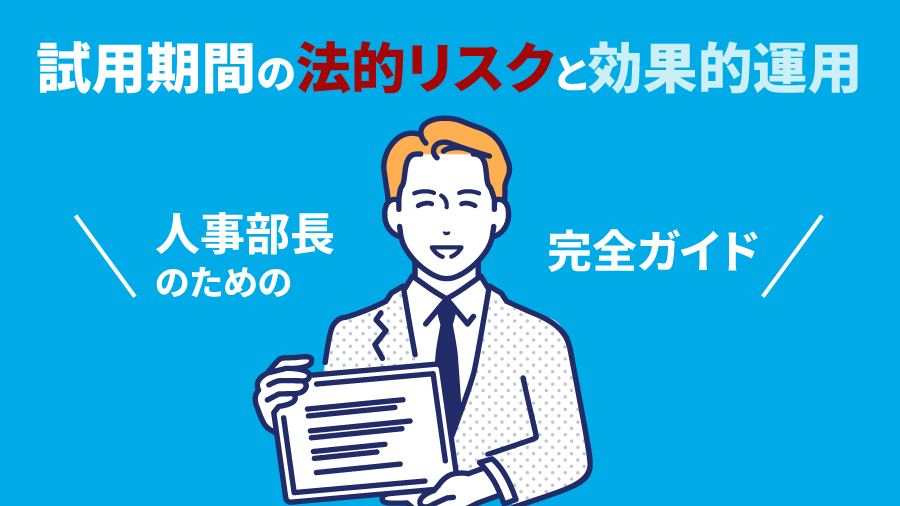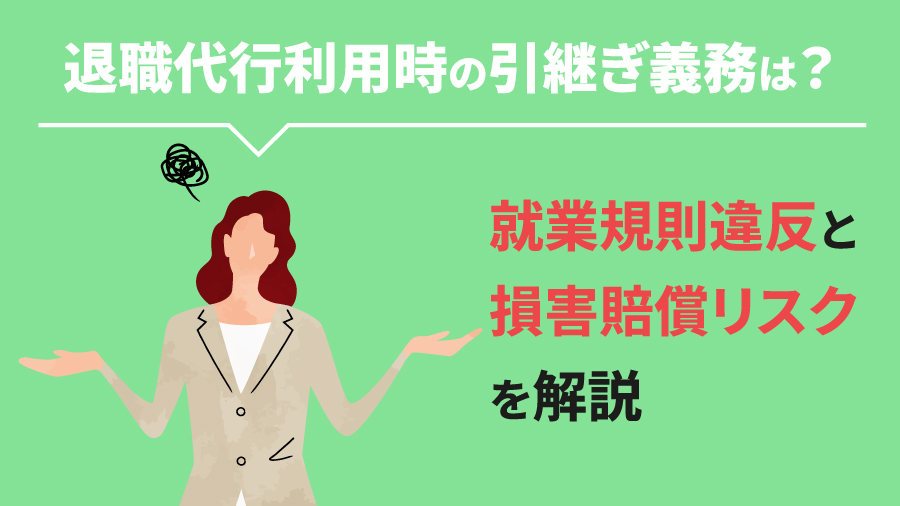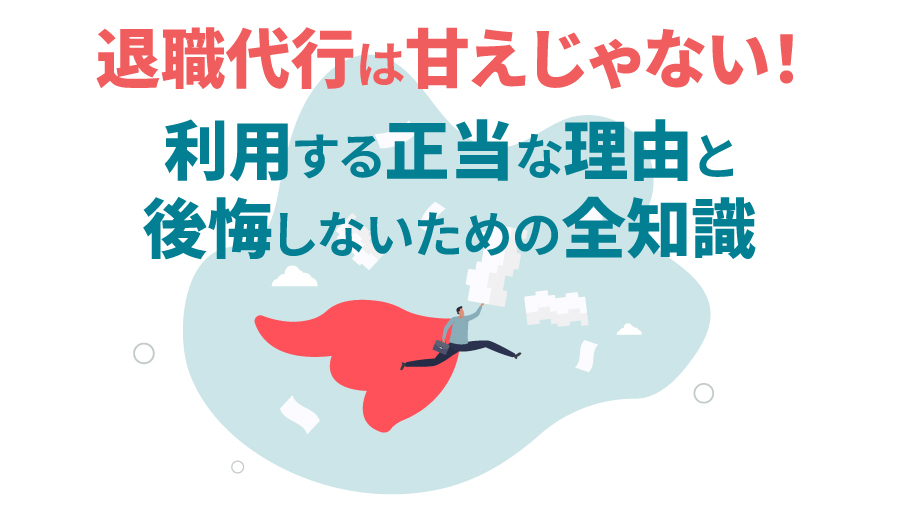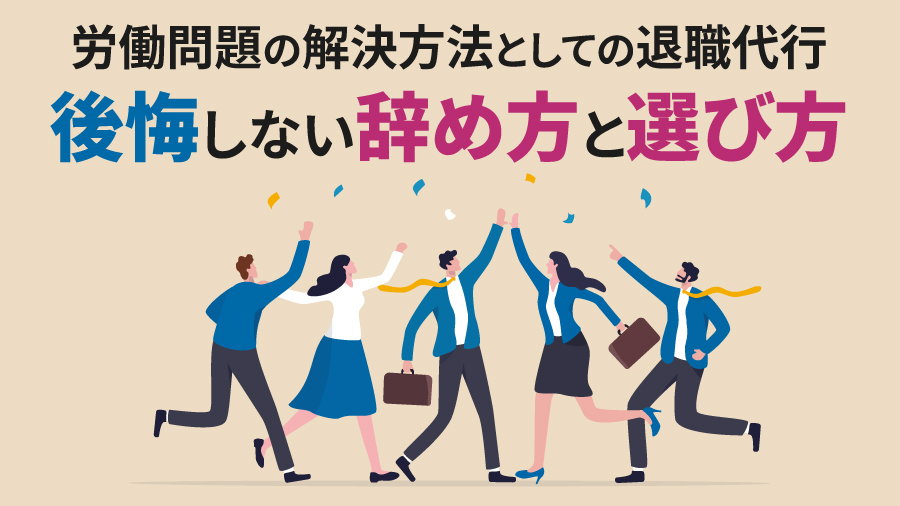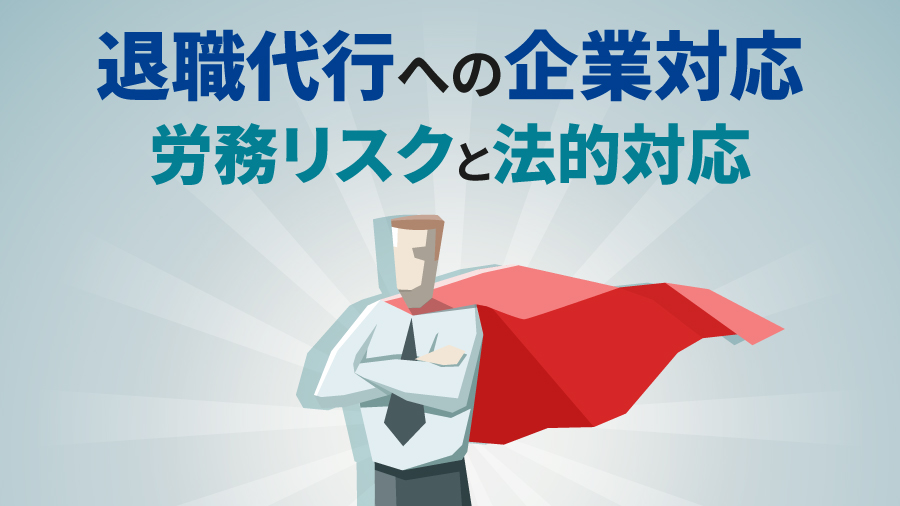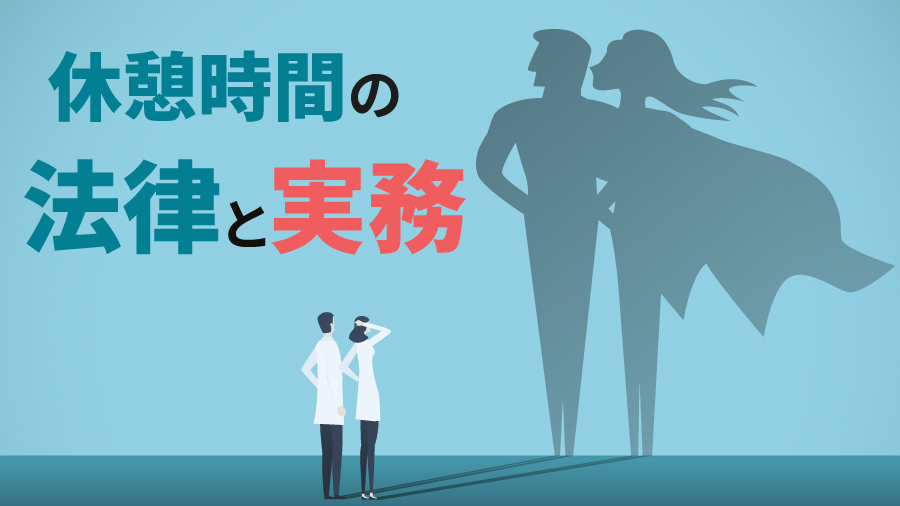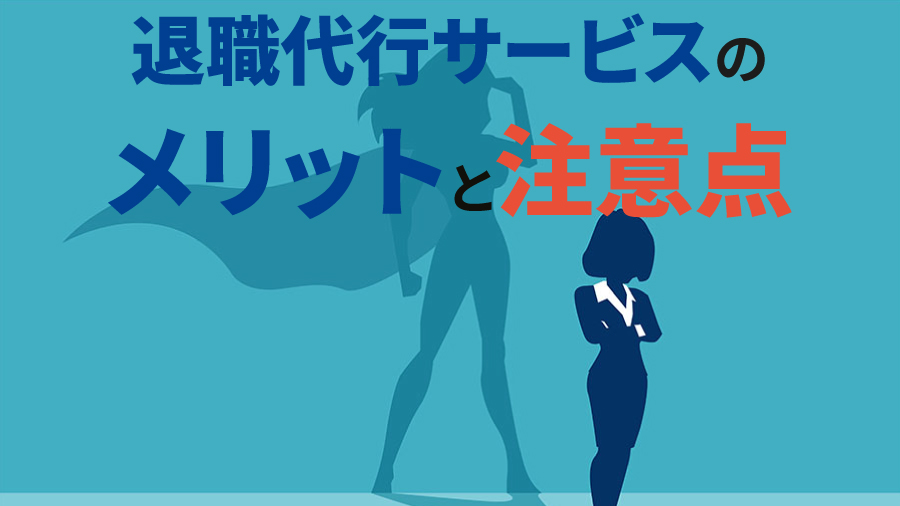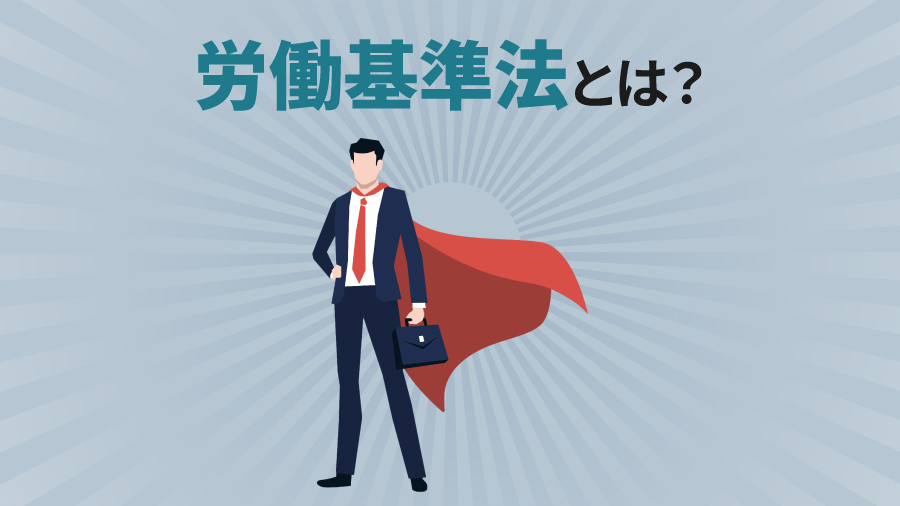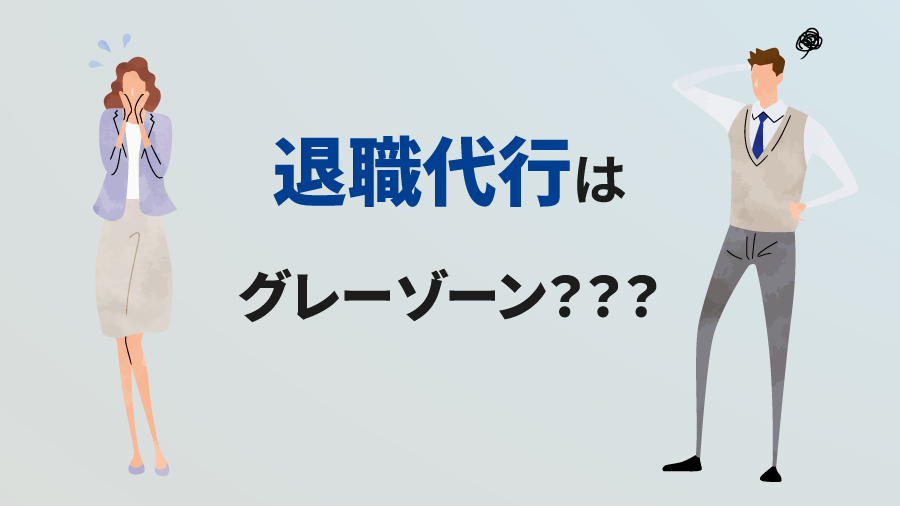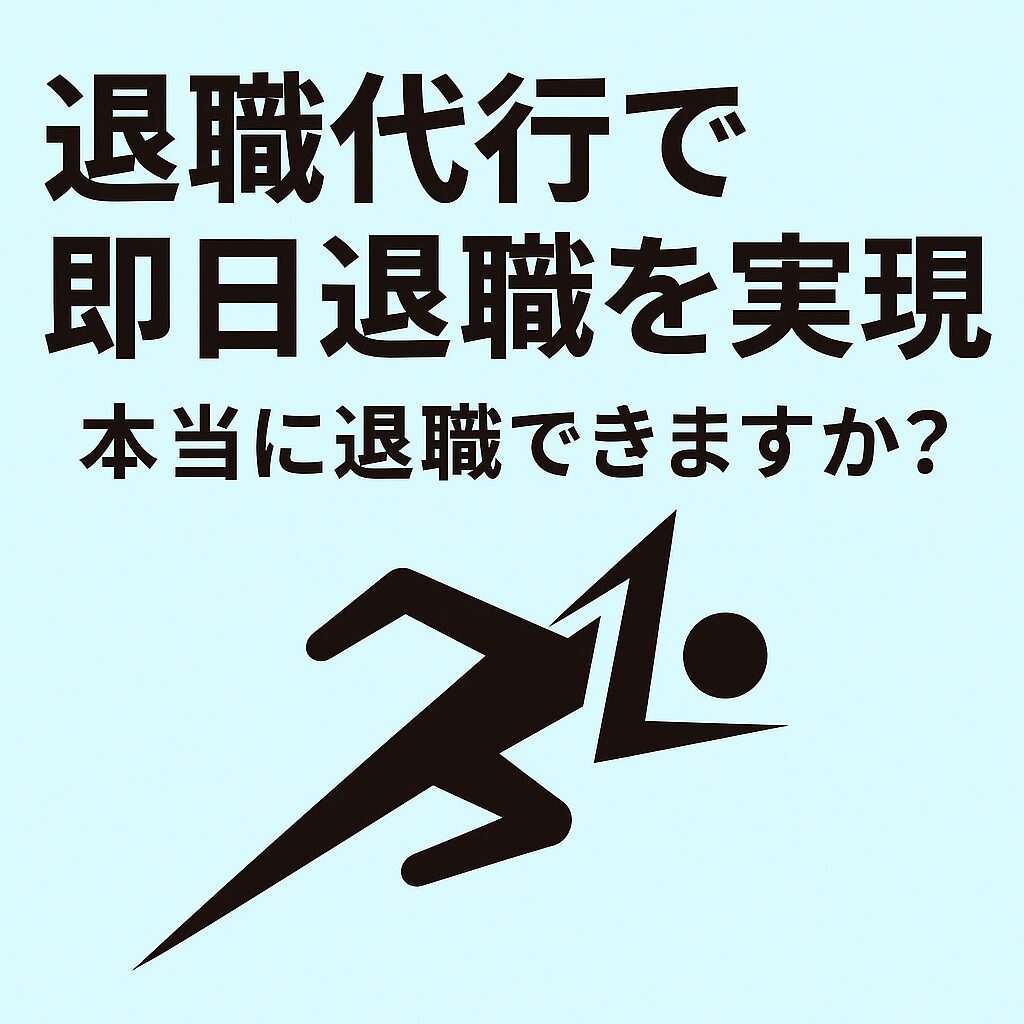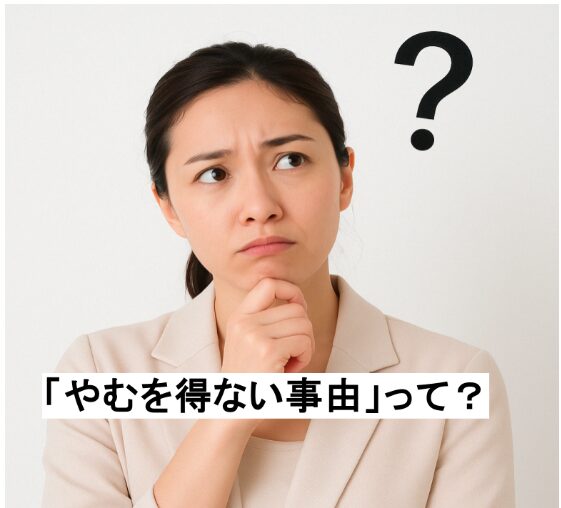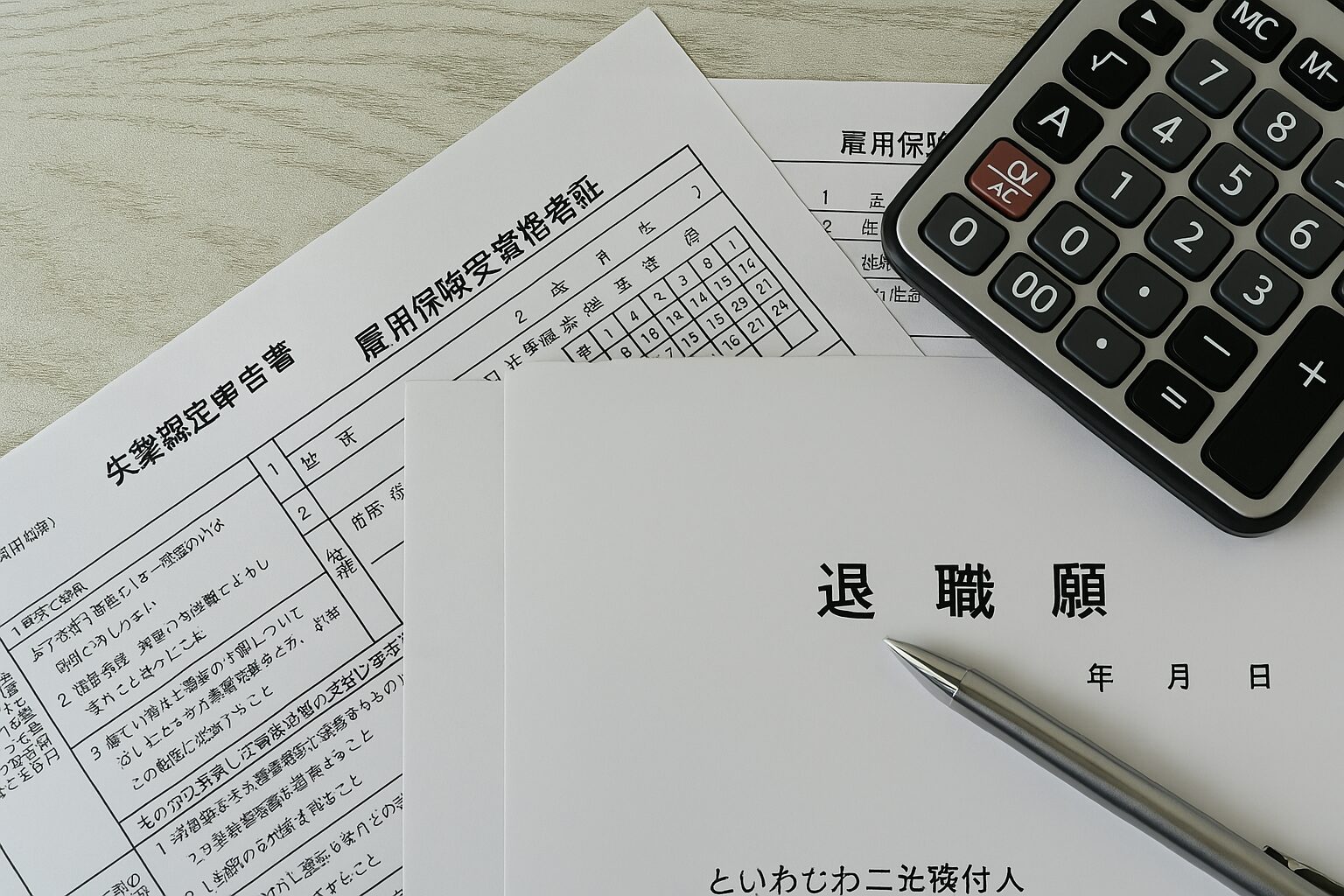-
-
退職後の健康保険料を徹底比較|任意継続と国民健康保険の違いと手続き方法

退職後の健康保険選びは、任意継続か国民健康保険かで迷う方が多いです。本記事では、各選択肢の保険料比較や手続き期限・必要書類を詳しく解説します。さらに、扶養家族がいる場合や収入減少時に有利な選択肢も紹介。退職後の安心を確保するために、最適な健康保険選びをサポートします。
目次退職後の健康保険選びとは?
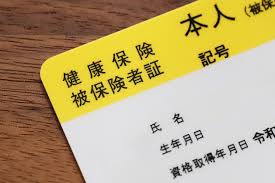
退職後に利用できる健康保険には「任意継続被保険者制度」と「国民健康保険」があります。
それぞれの制度は特徴が異なり、保険料や手続き方法、加入条件も異なります。
ここでは、退職後の生活設計において重要となるこれらの制度について詳しく解説します。
任意継続とは?
任意継続制度は、退職前に加入していた健康保険をそのまま継続できる仕組みで、適用期間は最長2年間です。
加入条件は以下の通りです。
・退職前に2ヶ月以上の被保険者期間がある
・資格喪失日から20日以内に加入手続きを行う(任意継続被保険者資格取得申出書を提出)任意継続では、扶養家族も同じ条件で加入できるため、世帯全体で固定額となる点が特徴です。
ただし、在職時と異なり保険料は全額自己負担となるため、金額が上昇する可能性があります。
短期間の利用や扶養家族が多い場合には特に有利な選択肢となります。
また、扶養家族の数や年齢によっても保険料が変動するため、事前に詳細なシミュレーションを行うことが推奨されます。
国民健康保険とは?
国民健康保険は自治体が運営する公的医療制度で、自営業者や無職者などが対象です。
退職後に会社員としての健康保険から切り替える場合もあります。
国民健康保険制度では、前年所得を基準に保険料が計算されるため、収入減少時には翌年度以降の負担軽減が期待できます。
一方で扶養家族は国民健康保険に個別で加入する必要があり、その分世帯全体の負担増加につながる可能性があります。任意継続と国民健康保険の保険料比較

任意継続と国民健康保険では、年収や家族構成によって有利不利が異なります。
ここでは、それぞれの保険料を比較し、自分に適した選択肢を見つけるためのポイントを解説します。
年収別シミュレーション
年収によってどちらの制度が有利かは異なります。
国民健康保険が前年の所得に基づいて保険料が計算される一方で、任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額に基づいて計算されます。
ここで重要なのは、任意継続の保険料は年収によって上がり続けるわけではなく、標準報酬月額には上限が設定されている点です。
そのため、高年収の方ほど任意継続の方が割安になる可能性があります。
・年収300万円程度の場合
国民健康保険の方が安い
標準報酬月額の上限に達しない・年収600万円程度の場合
任意継続の方が割安になる可能性がある
標準報酬月額の上限に達する可能性がある・年収1,000万円以上の場合
任意継続の方が大幅に安い
標準報酬月額の上限に達するただし、標準報酬月額の上限額は加入している健康保険組合によって異なり、国民健康保険料の計算方法も自治体によって異なります。
上記はあくまで一般的な傾向であり、個々の状況によって最適な選択肢は異なります。
退職前の年収を基に、必ず双方の保険料を詳細にシミュレーションし、ご自身の年収に最適な保険制度を選択してください。扶養家族がいる場合の違い
扶養家族がいる場合には、任意継続が有利になることがあります。
任意継続保険では扶養家族全員分を含めた固定額で済むため、多人数世帯では特にメリットがあります。
一方で国民健康保険では扶養家族も個別で加入する必要があり、その分世帯全体の負担増加につながる可能性があります。
そのため、多人数世帯の場合には任意継続を選ぶことで費用負担を抑えられる可能性があり、一人暮らしや短期間のみ利用する場合には、国民健康保険も検討すべき選択肢となります。
また、扶養家族の数や年齢によっても保険料が変動するため、事前に詳細なシミュレーションを行うことが必要です。
手続き期限と必要書類
手続きをスムーズに進めるためには、それぞれの制度ごとの申請期限や必要書類を正確に把握しておくことが重要です。
ここでは、任意継続と国民健康保険それぞれについて具体的な手順と注意点を解説します。
特に期限切れによるトラブルを防ぐためにも事前準備は欠かせません。
任意継続加入手続き
任意継続への加入手続きは、資格喪失日から20日以内に行う必要があります。
申請先は退職前に所属していた健康保険組合であり、資格喪失証明書・口座振替依頼書・任意継続被保険者資格取得申出書などの書類を提出します。
任意継続保険は、短期間のみ利用する場合に有効であり、その後長期的な視点で国民健康保険への切り替えも検討すべきです。
また、手続きを怠ると申請期限を過ぎてしまい、加入できなくなるリスクもあるため注意してください。
さらに、扶養家族分も同時に手続きを進めておくことでスムーズな移行が可能になります。
事前準備を整えることで短期間の保険空白を防ぐことができます。
国民健康保険加入手続き
国民健康保険への加入手続きは、資格喪失日から14日以内に自治体窓口で行います。
手続きの際には、離職票や本人確認書類など複数の書類を準備します。また、扶養家族分についても別途手続きを行う必要があります。
自治体によって対応方法や必要書類が異なる場合もあるため、事前確認がおすすめです。さらに、一部自治体ではオンライン申請にも対応しているため、自身の住む地域で利用可能かどうか調べておくと良いでしょう。
迅速かつ正確な手続きを行うことで短期間の保険空白期間を防ぐことができます。どちらを選ぶべきか?判断ポイント

任意継続と国民健康保険、それぞれにはメリット・デメリットがあります。
ここでは、自分自身の状況や将来的な見通しを踏まえて最適な選択肢を判断するポイントについて解説します。
収入減少時に有利な選択肢
収入が減少する時には、翌年度以降に負担軽減が期待できる国民健康保険がおすすめです。
国民健康保険では前年所得基準で計算されるため、退職後すぐには反映されないものの、その後の負担軽減効果は大きいです。
一方で固定額制となる任意継続は、短期的なコスト予測がしやすい特徴があります。
そのため、一時的な収入減少であれば任意継続、それ以降長期的な収入変動を見込む場合には国民健康保険というように、状況によって選択肢を使い分けることが重要です。
また、将来的な収入増加を見込める場合には、任意継続が有利になる可能性もあります。
さらに、扶養家族がいる場合には世帯全体での費用負担を考慮する必要があります。
短期間のみ加入する場合
加入するのが短期間になる場合には、固定額制である任意継続がおすすめです。
任意継続では標準報酬月額によって計算されるため、月々の支払い額が一定となり予測しやすいです。
一方で転職活動中など将来的な不確定要素が多い場合には、国民健康保険への切り替えも視野に入れるべきです。
また、一部自治体では短期的な支払い負担軽減策として独自補助金制度なども設けている場合があるため、事前に確認しておくことでより良い判断につながります。
さらに、短期間の保険空白を防ぐためにも手続き期限を守ることが大切です。
まとめ:最適な選択肢で安心を確保しよう
それぞれの制度には特徴と制約があります。
期限内申請や必要書類準備など、基本的な手続きを怠らず進めることで、スムーズな移行につながります。
特に、扶養家族がいる場合や収入減少時には、柔軟に対応できる選択肢を選ぶことが大切です。
自身の状況や将来設計に応じて総合的に判断し最適な選択肢を見つけましょう。
-