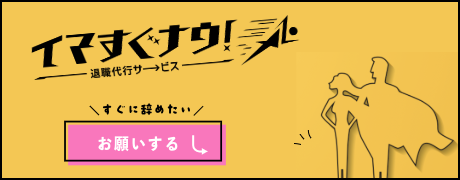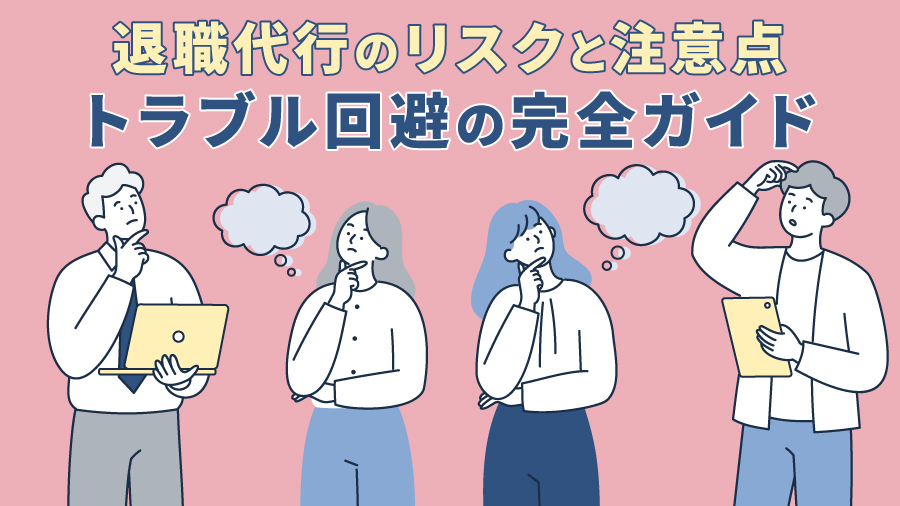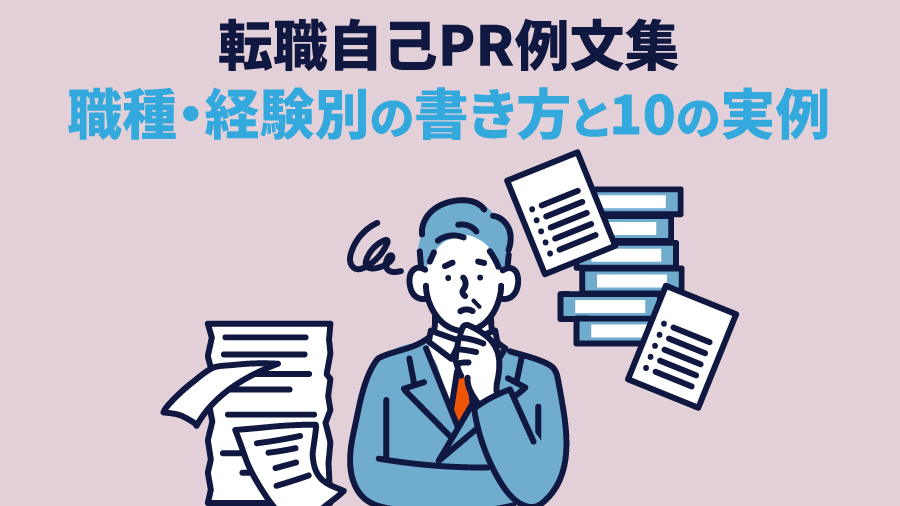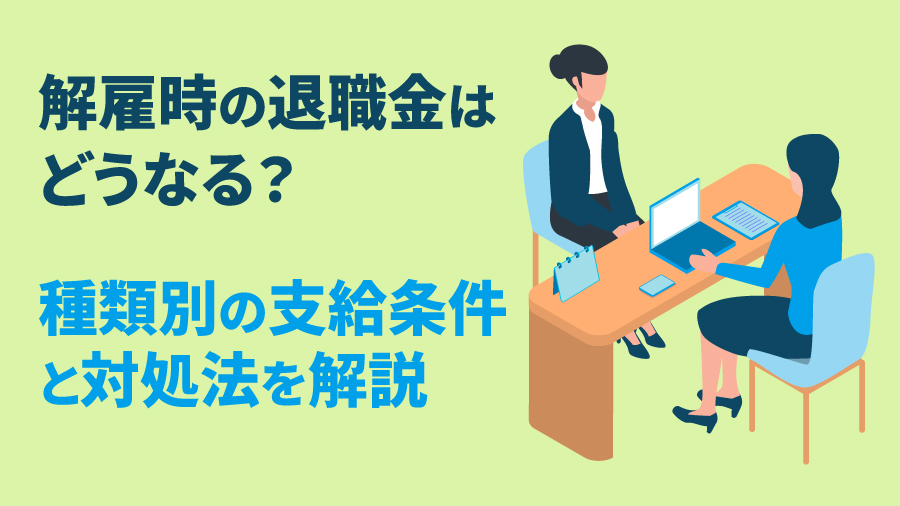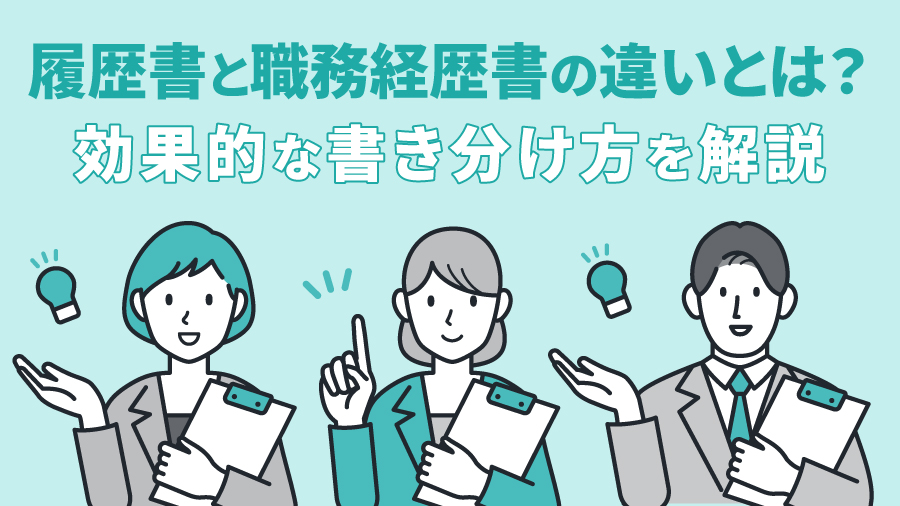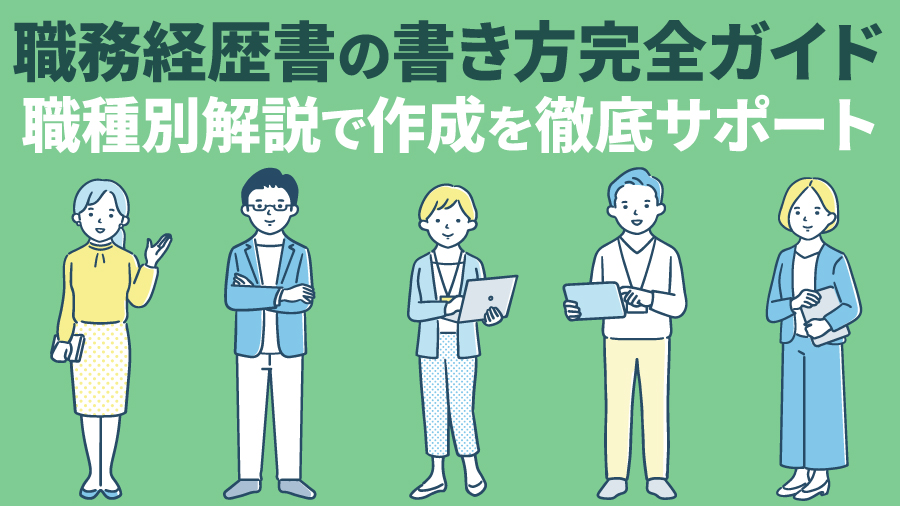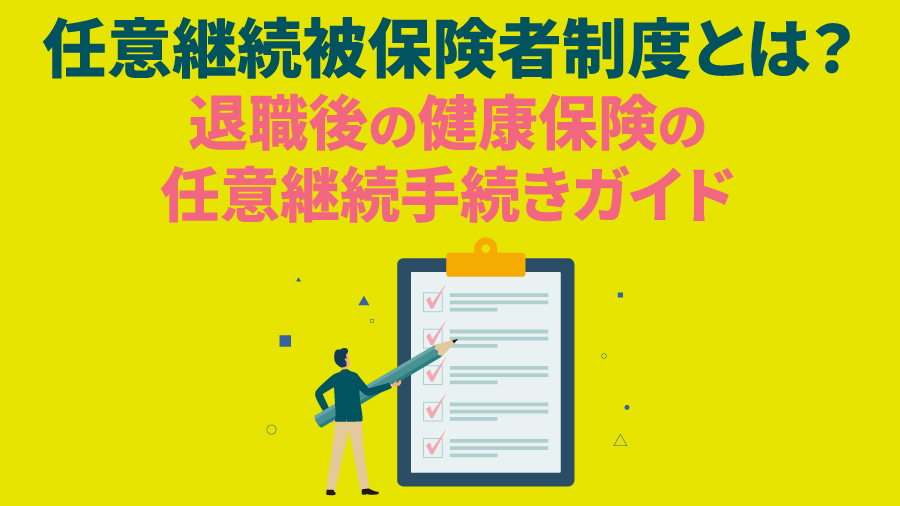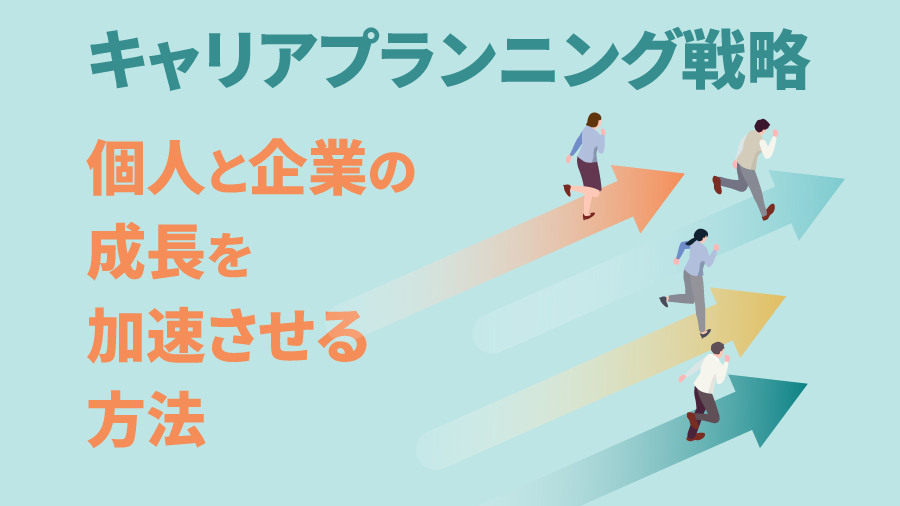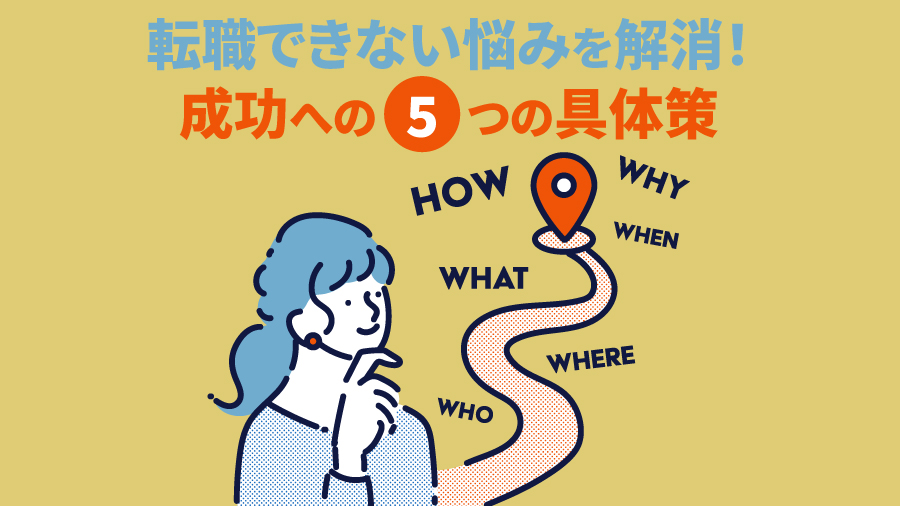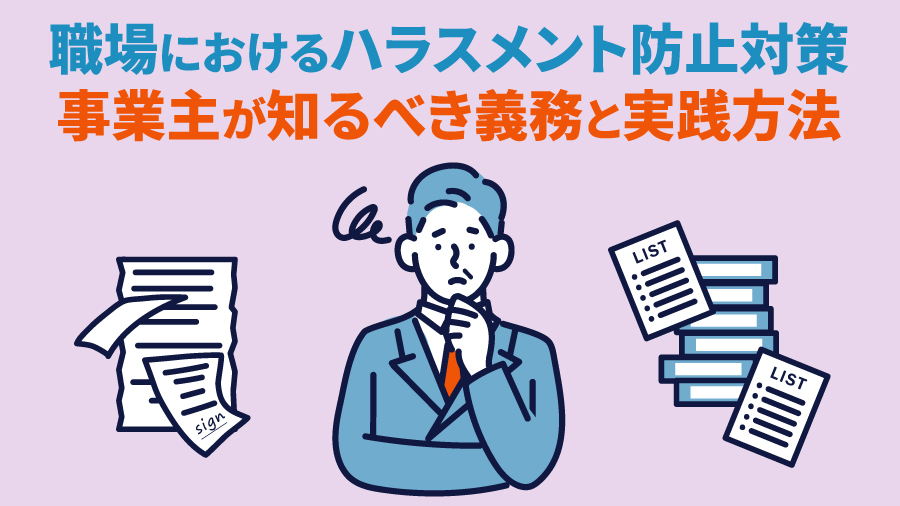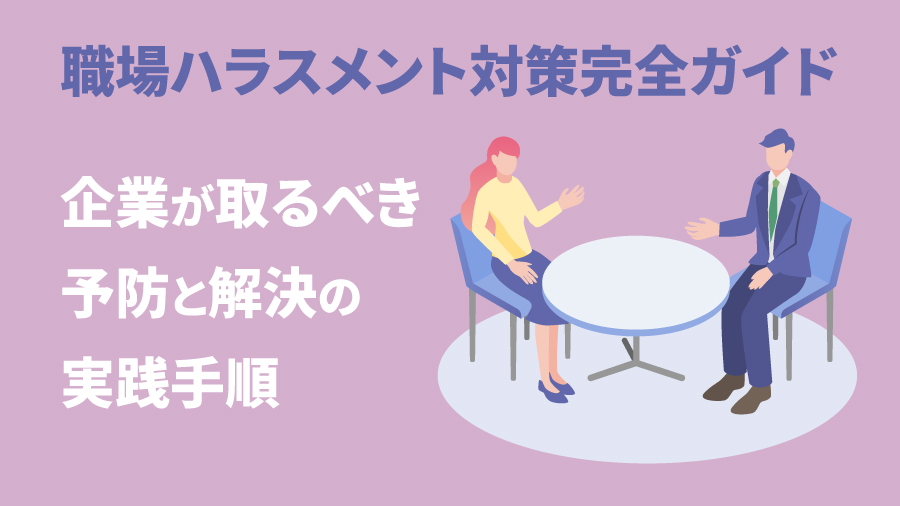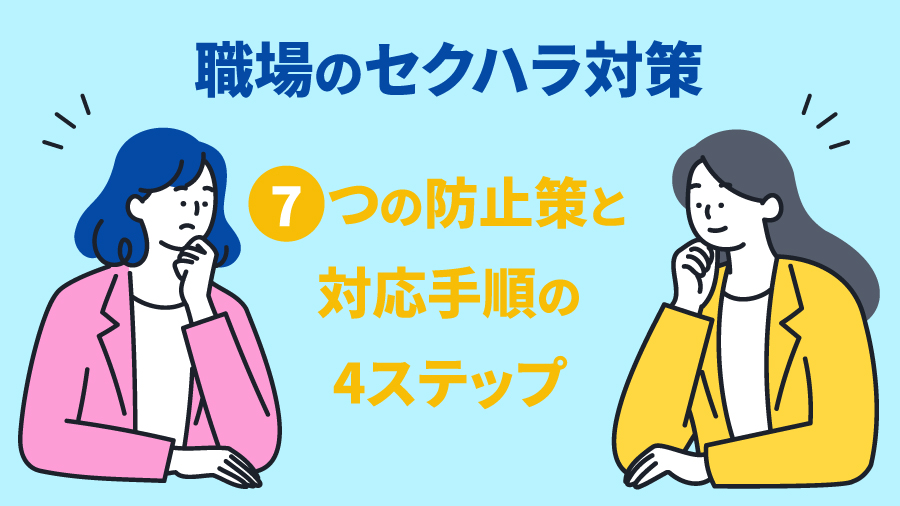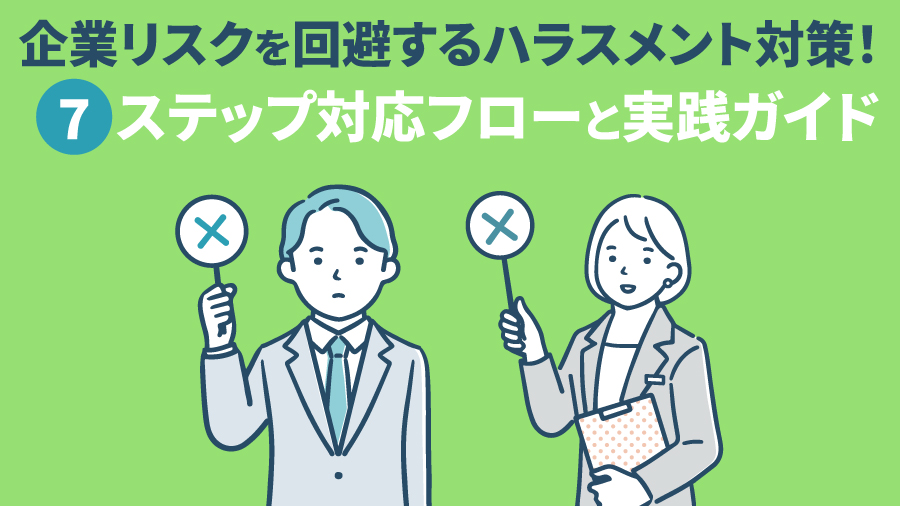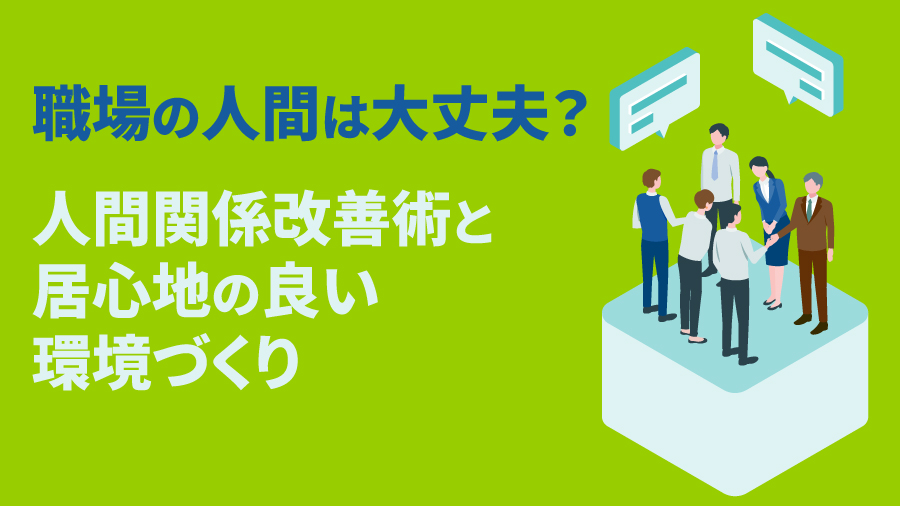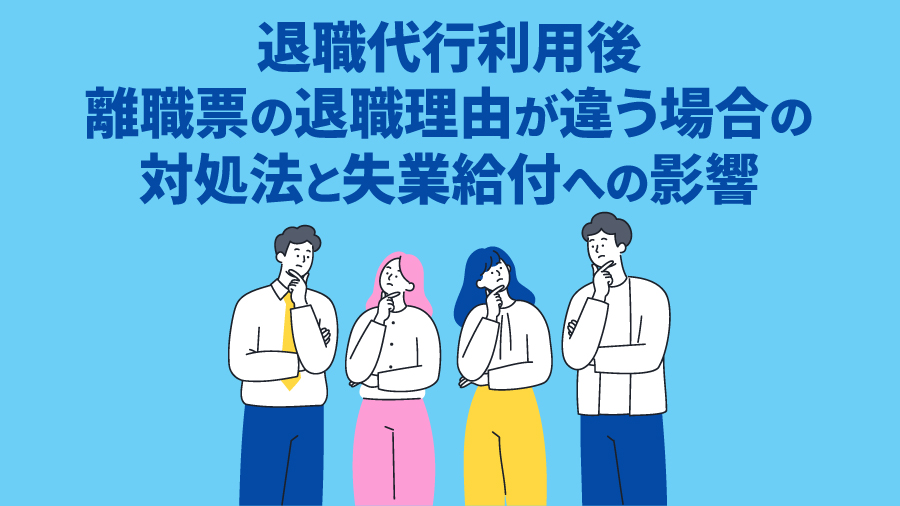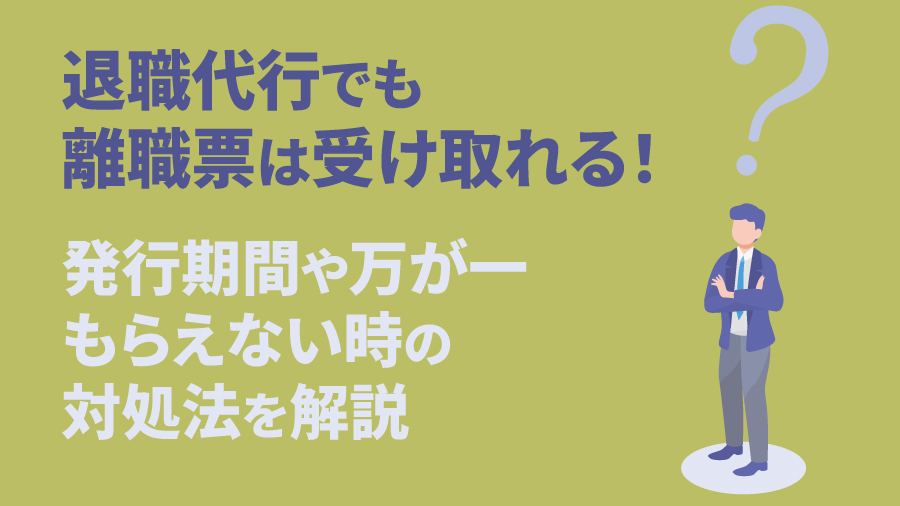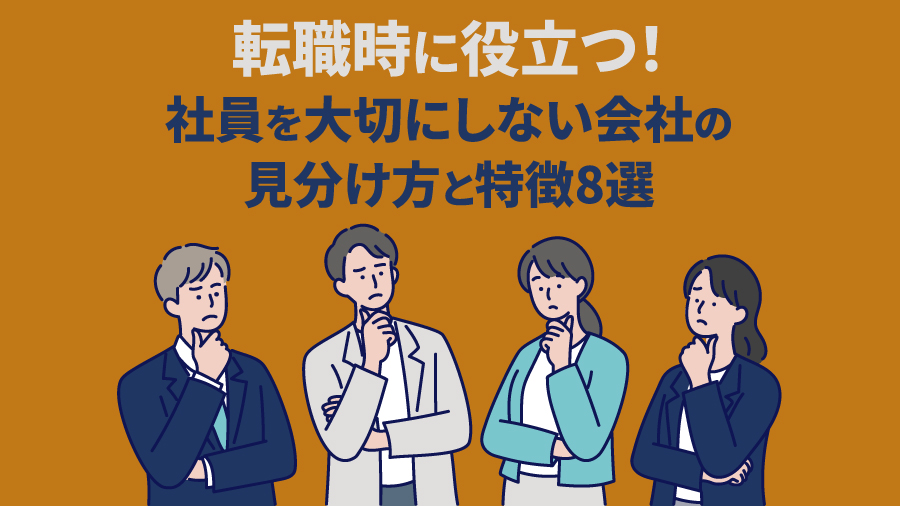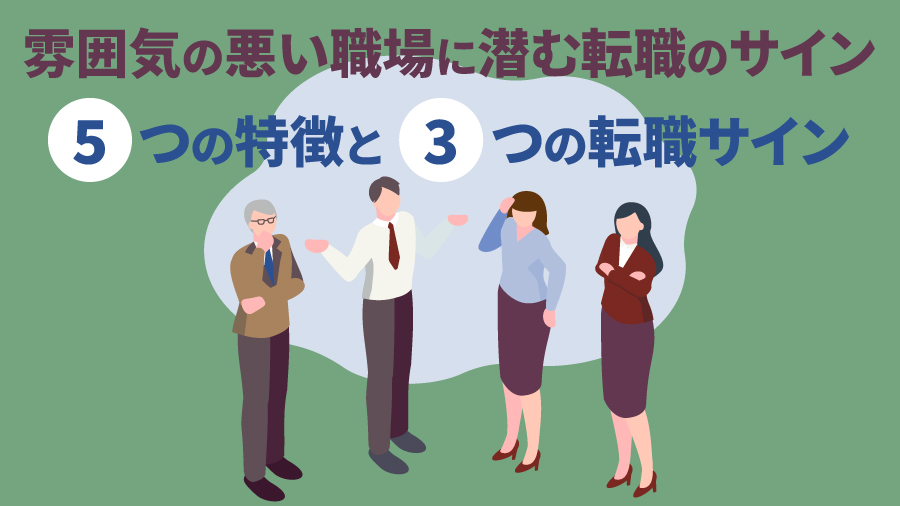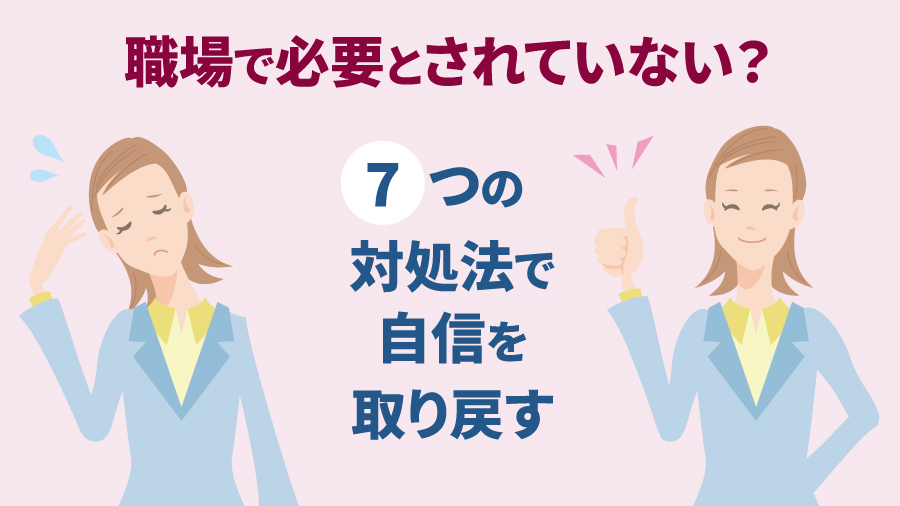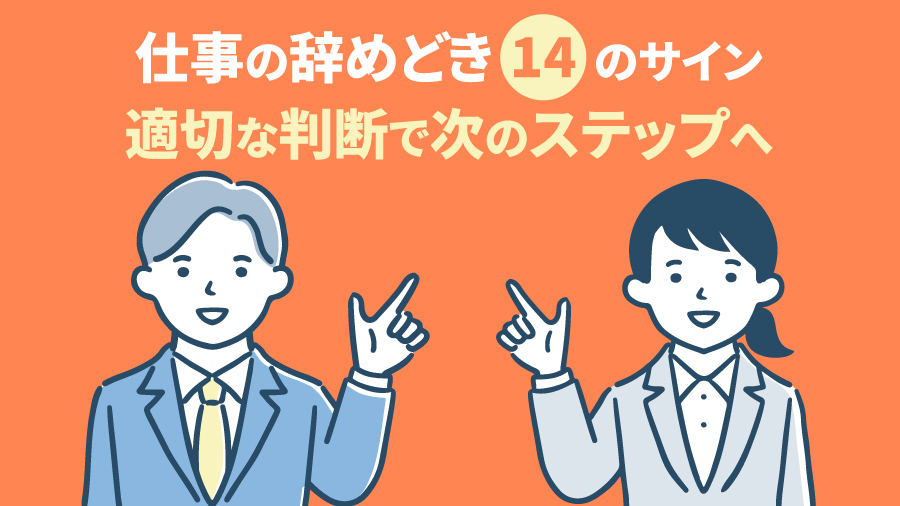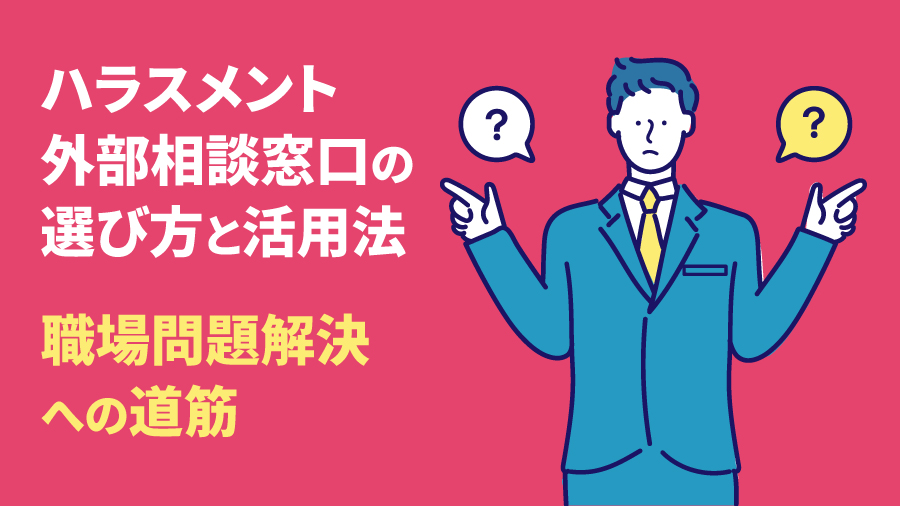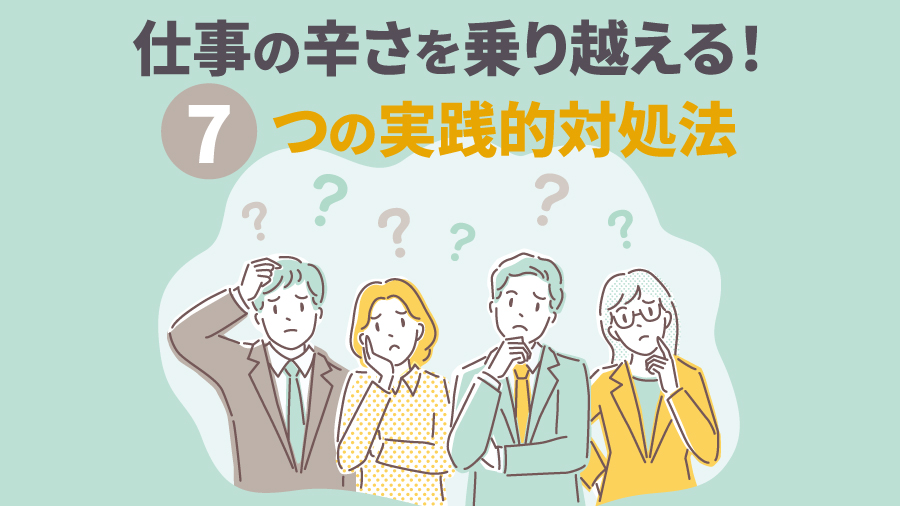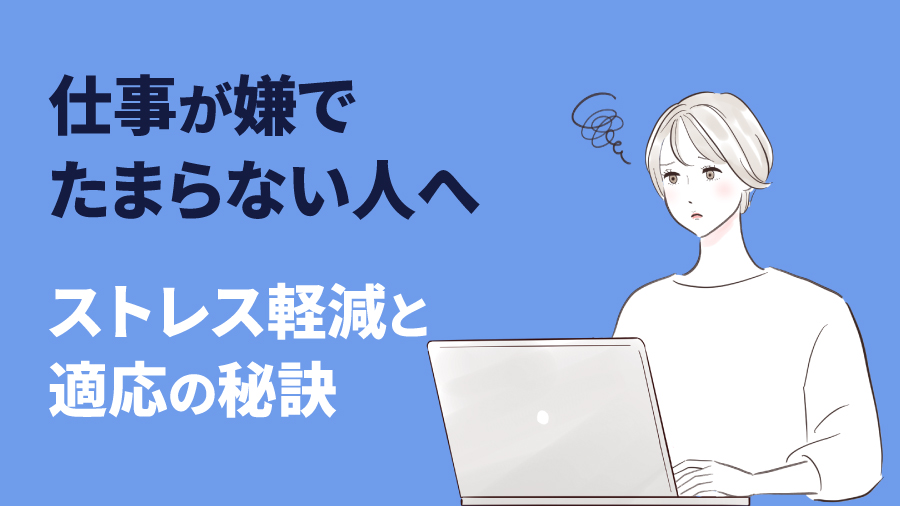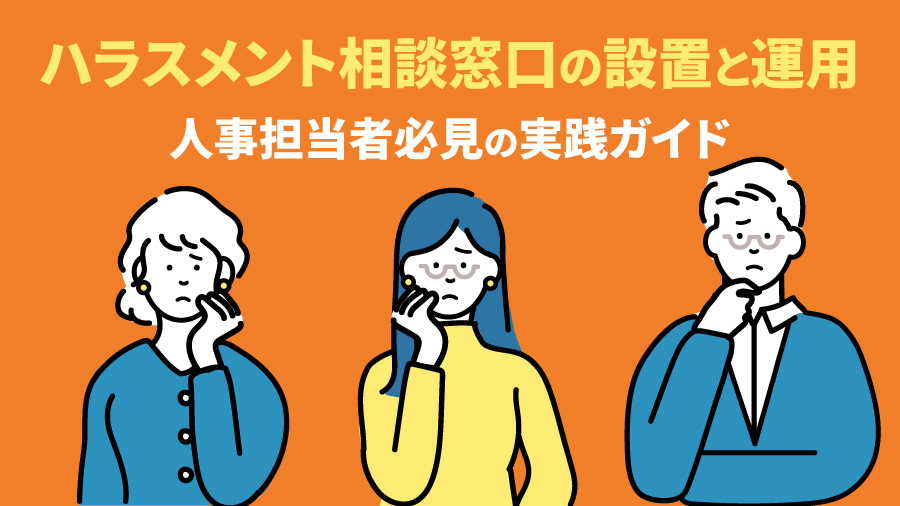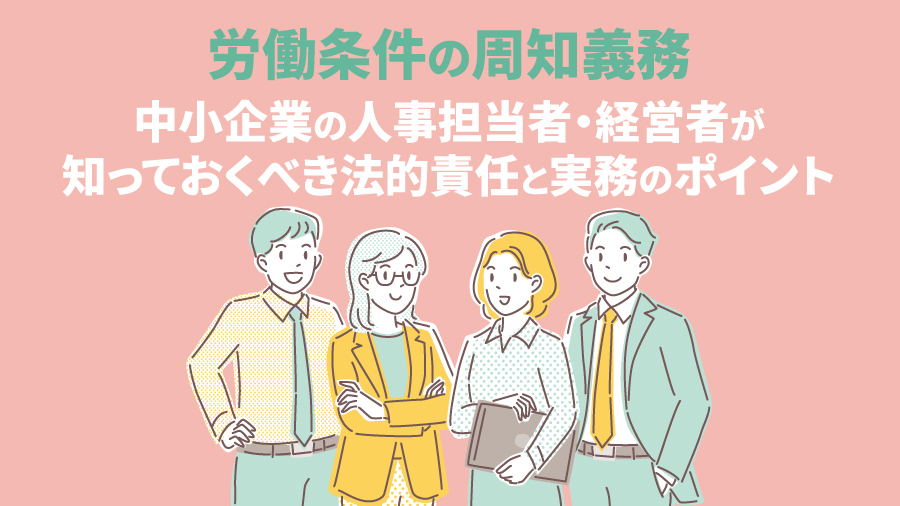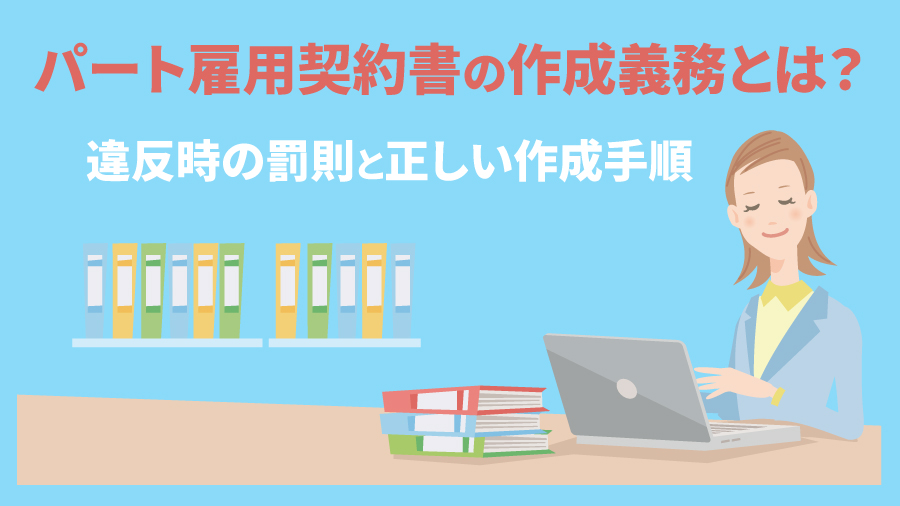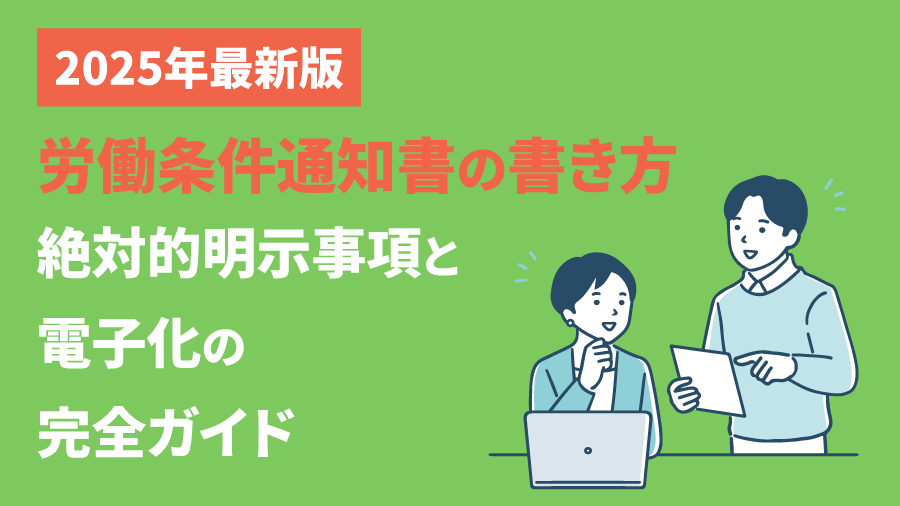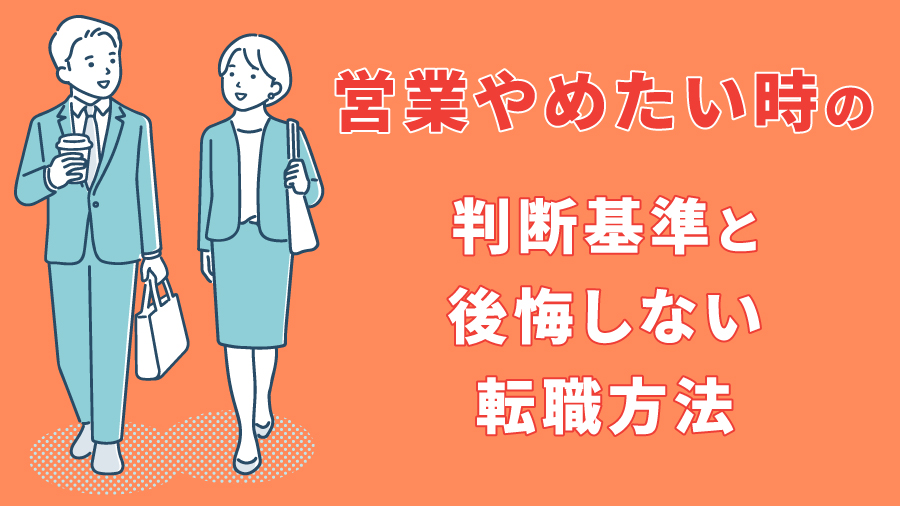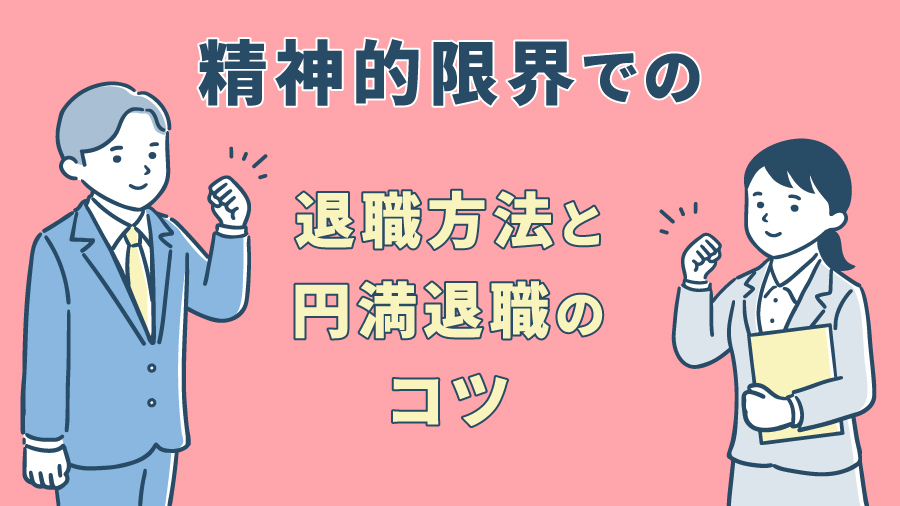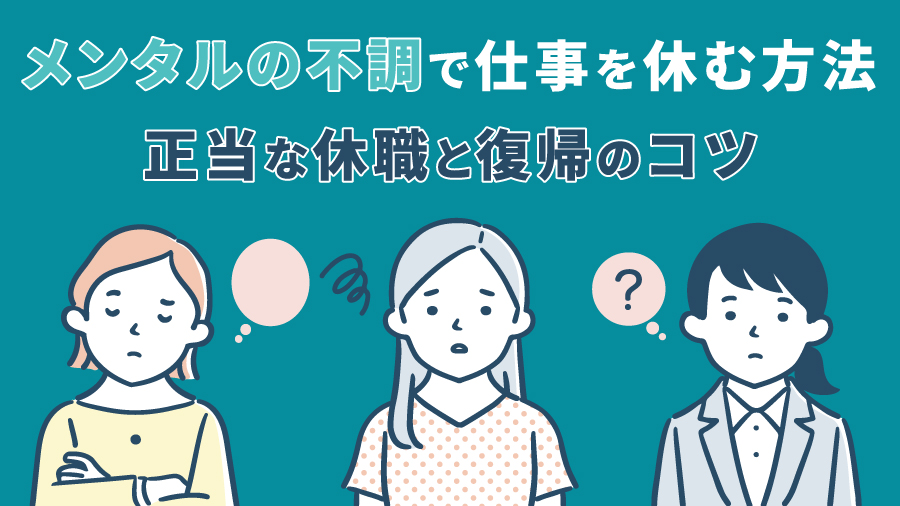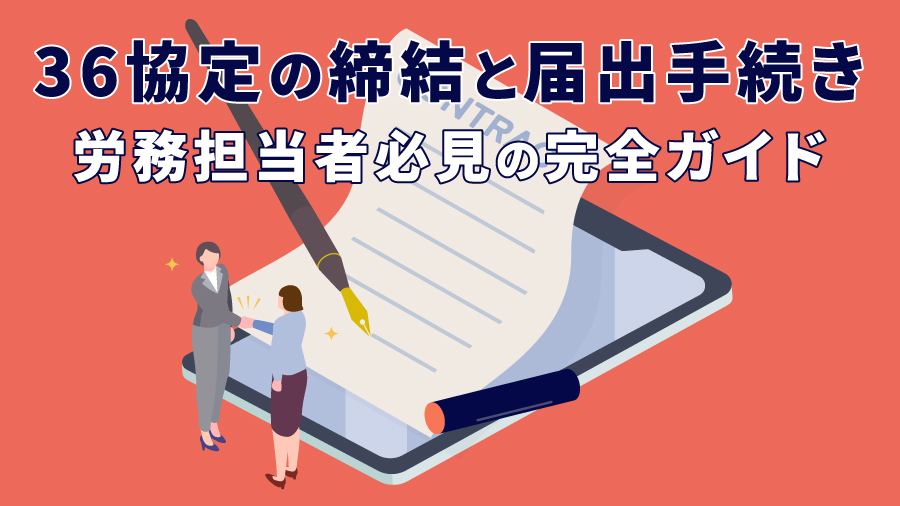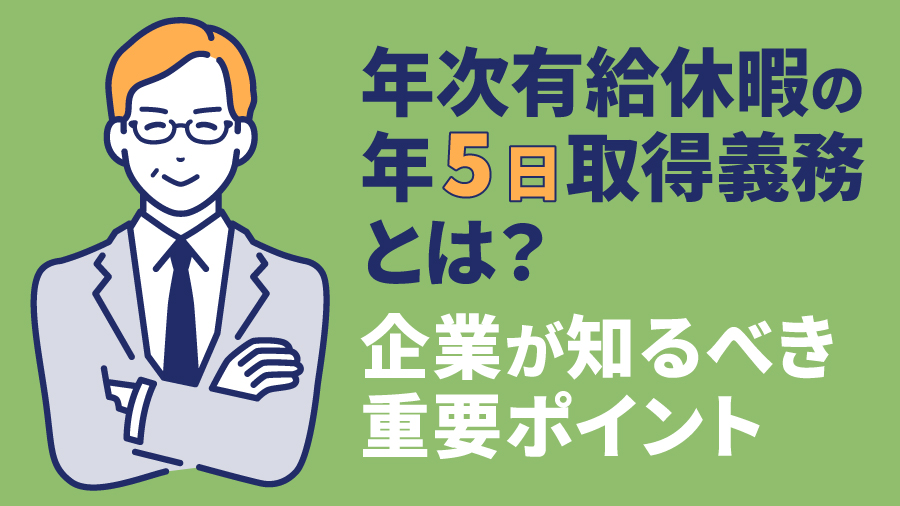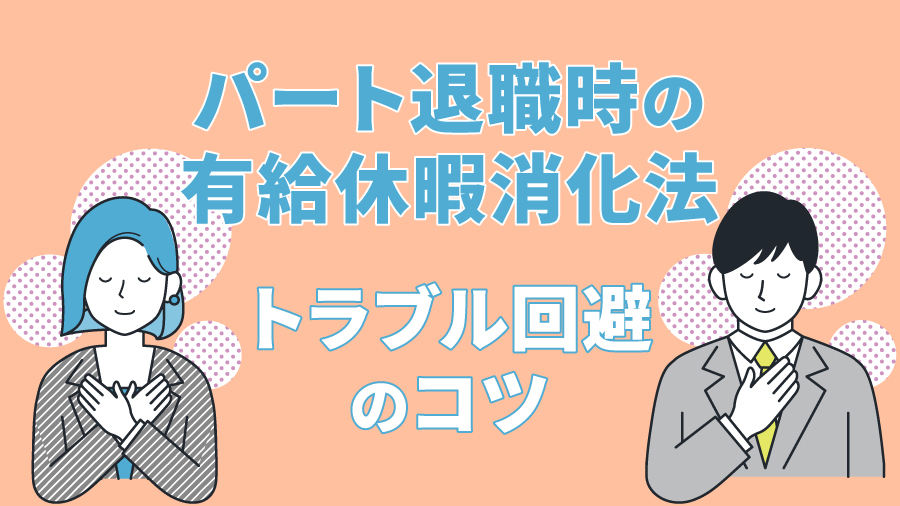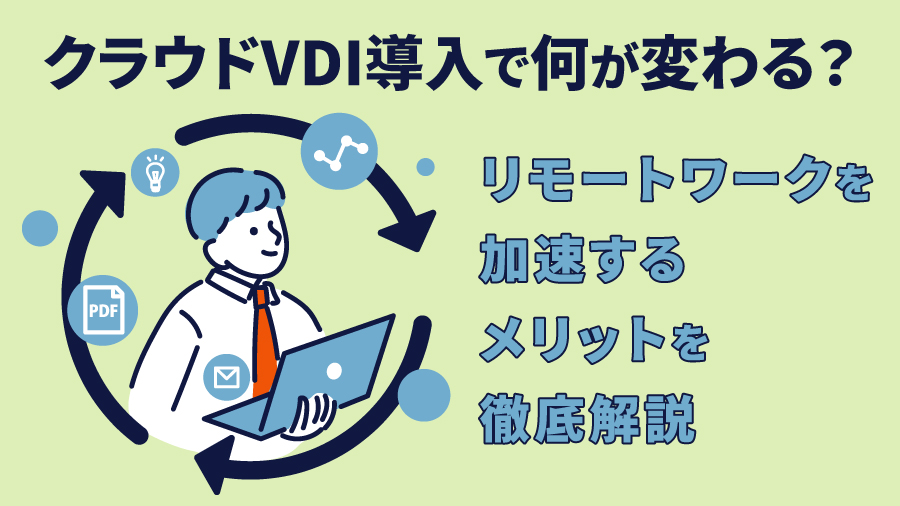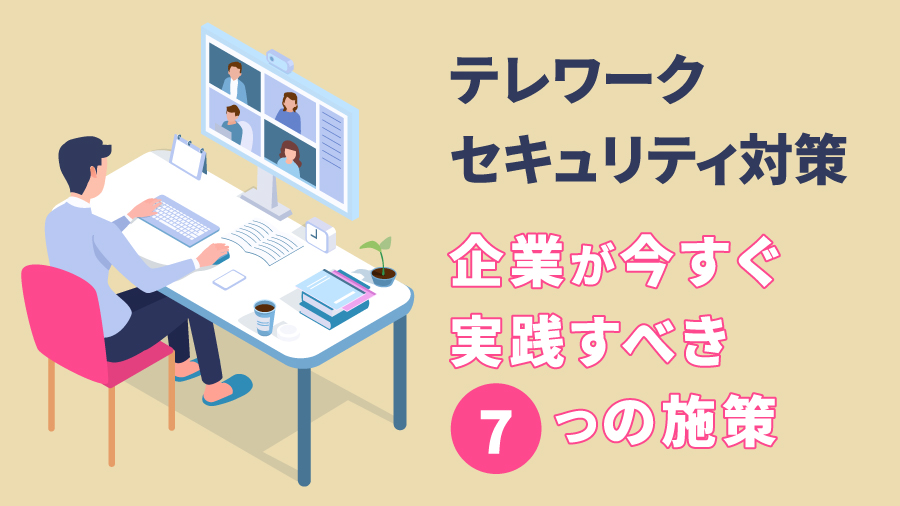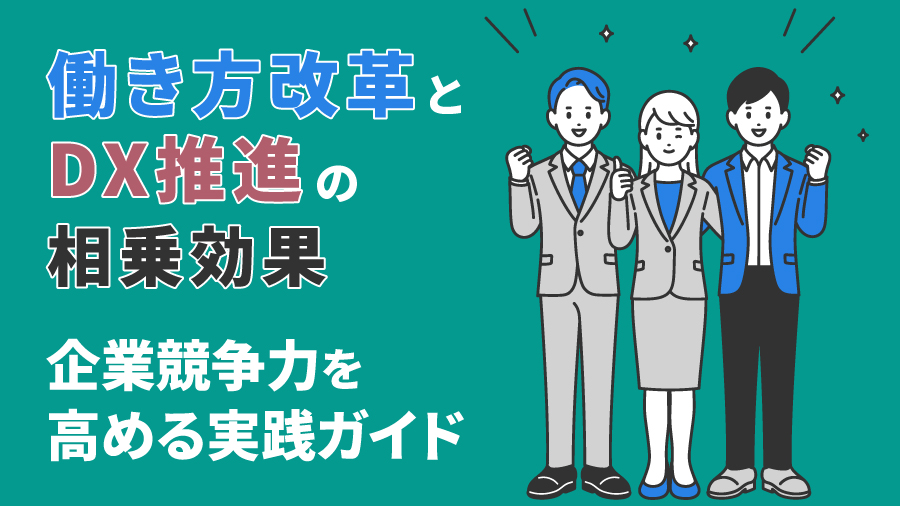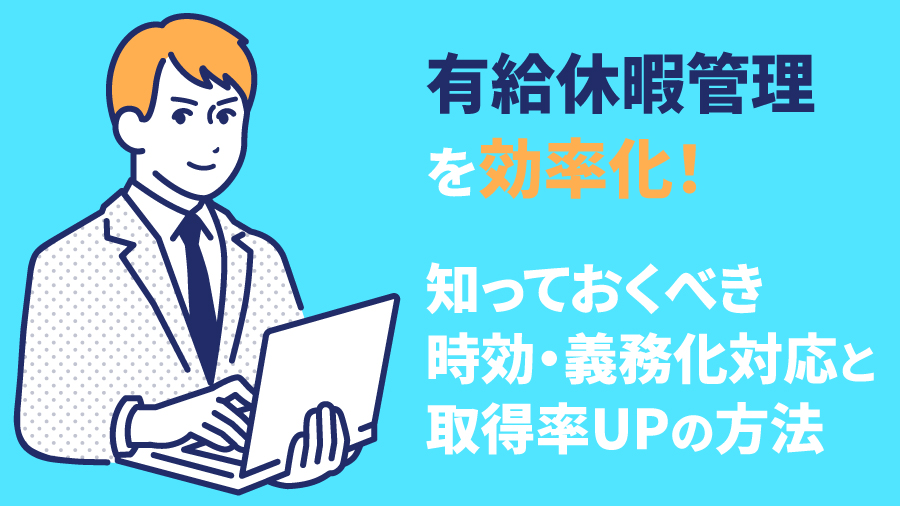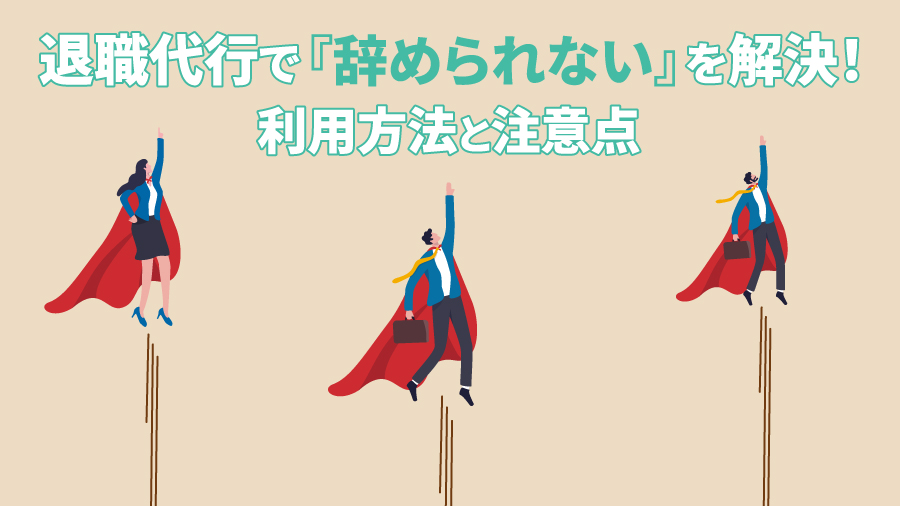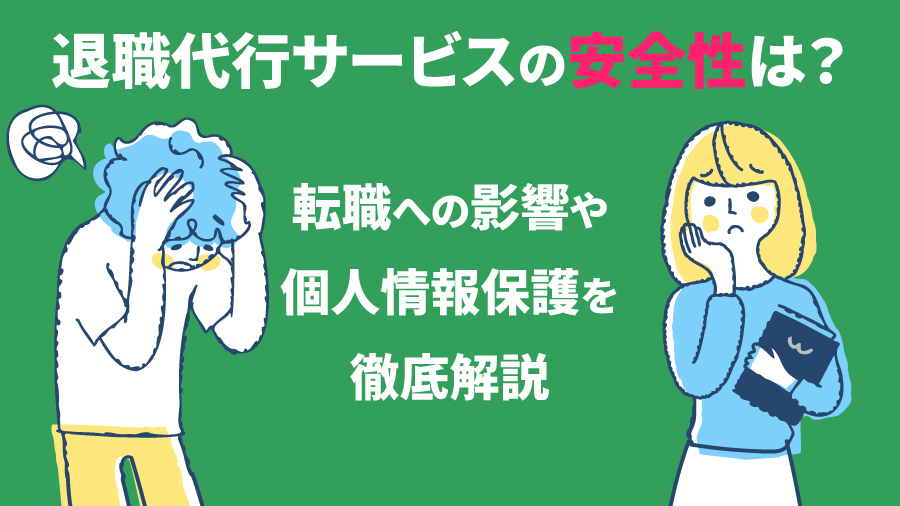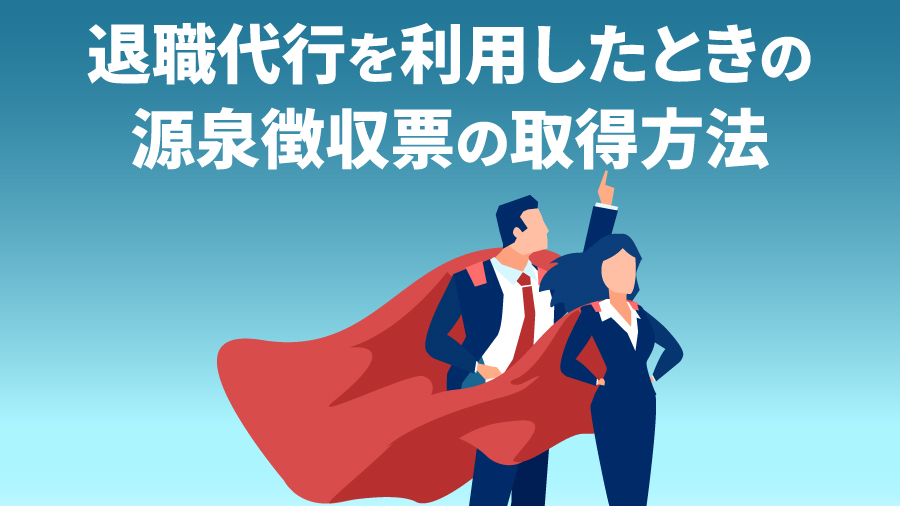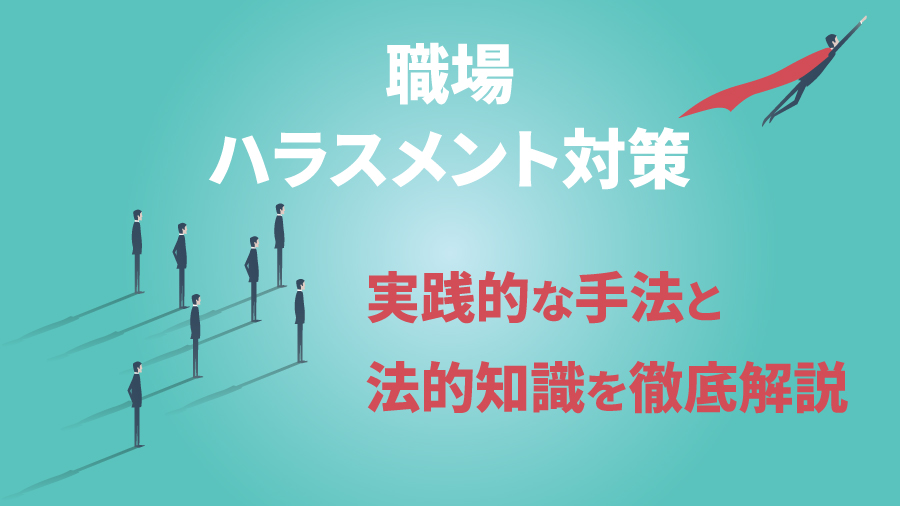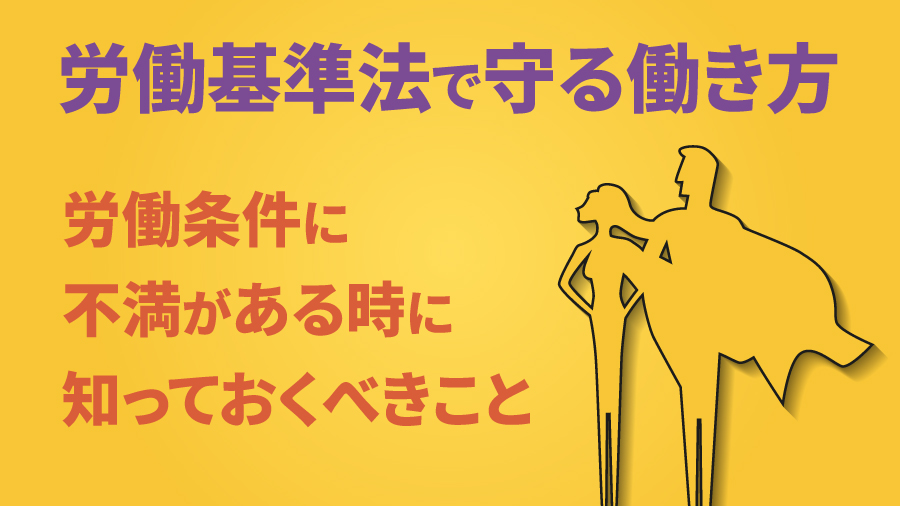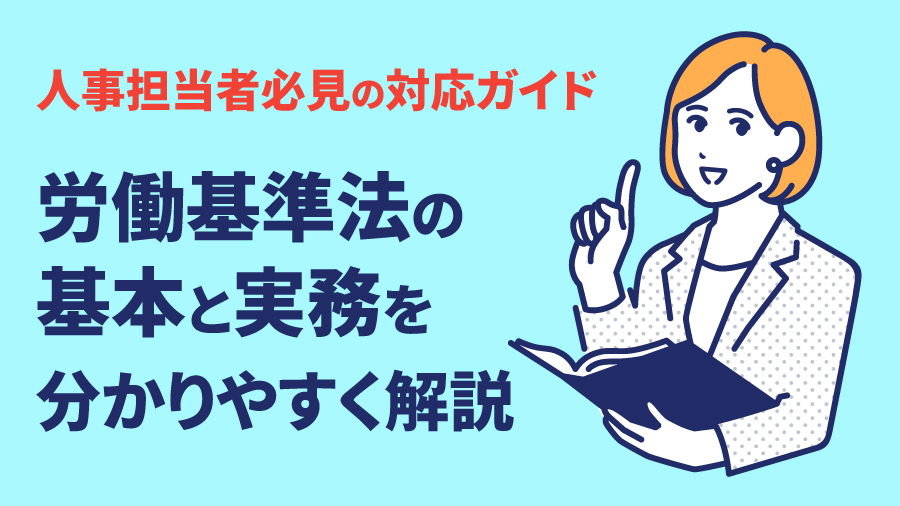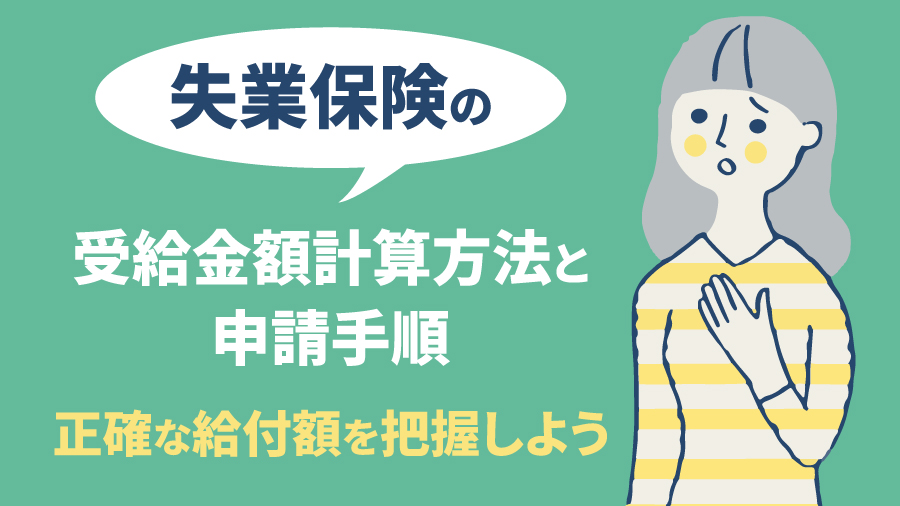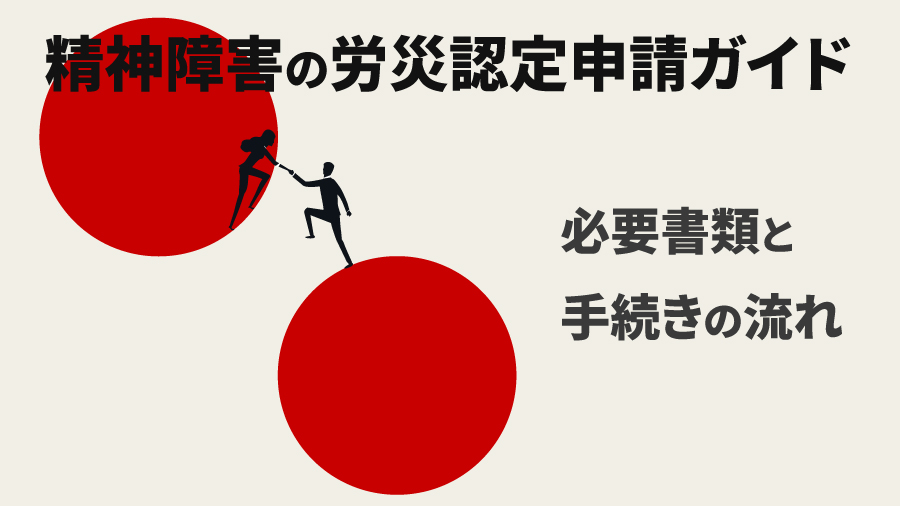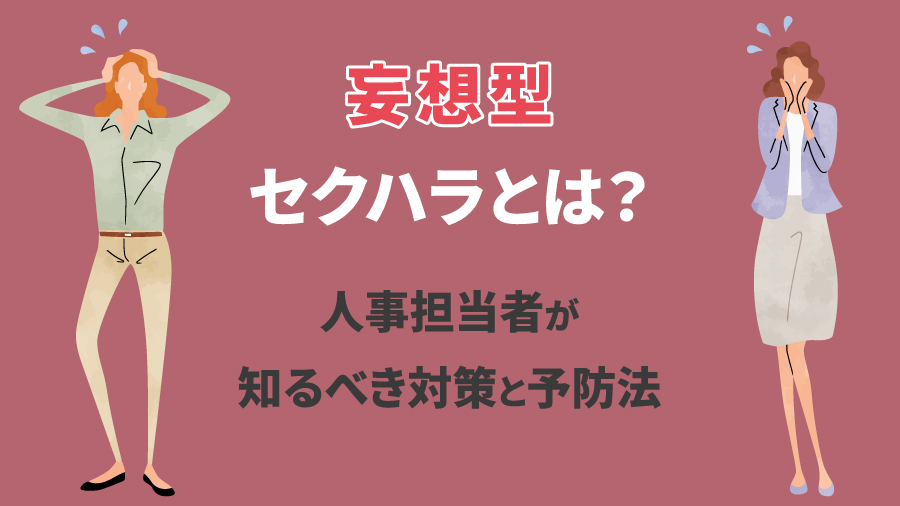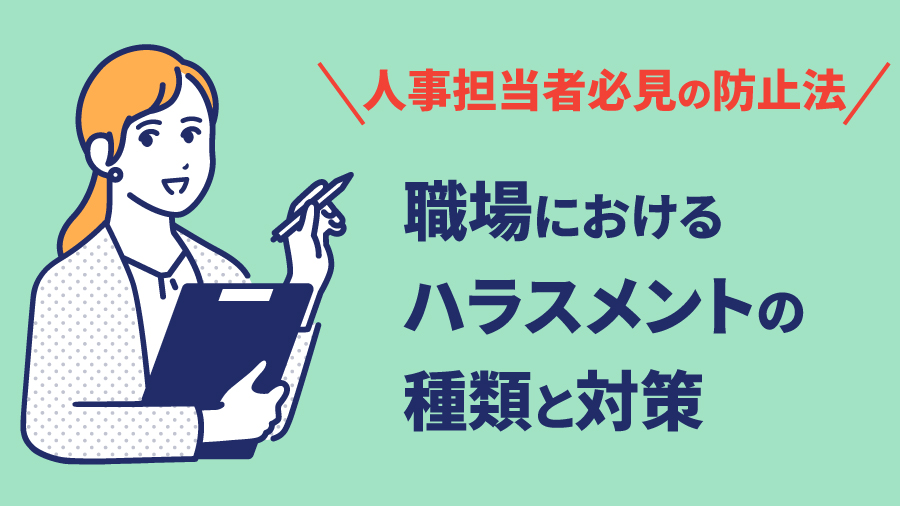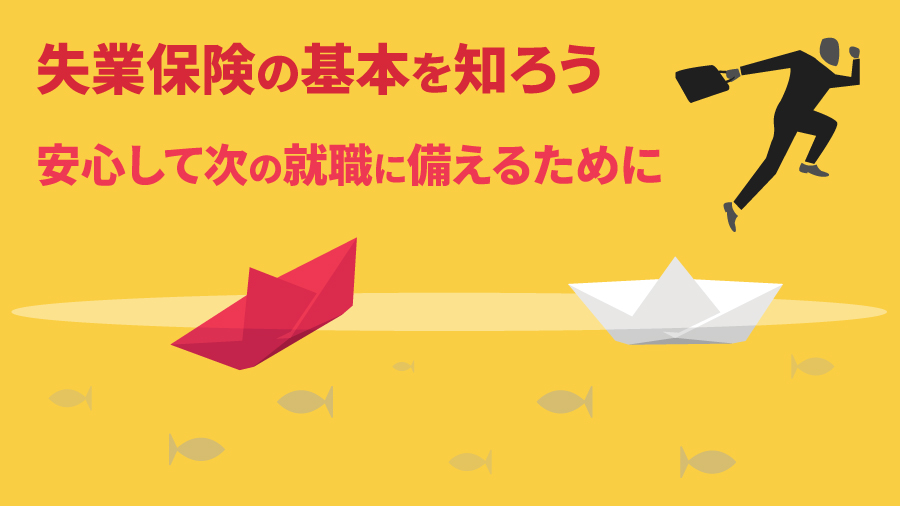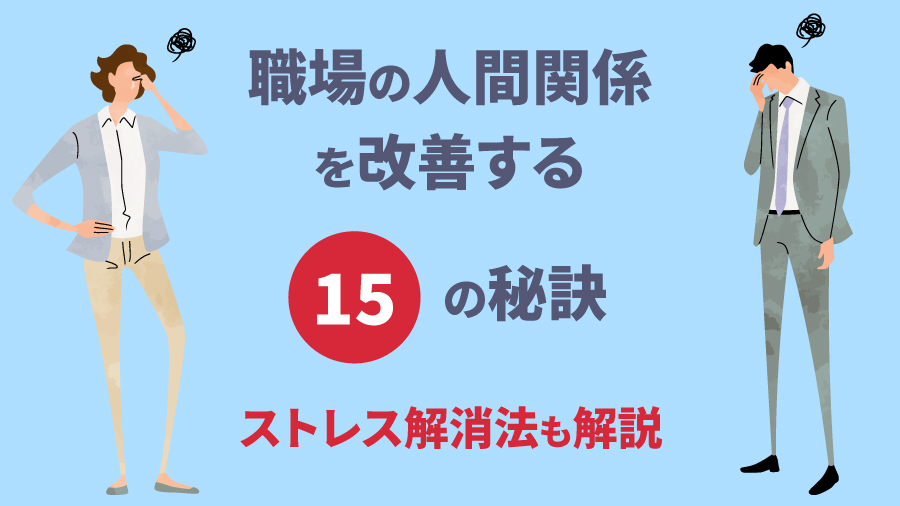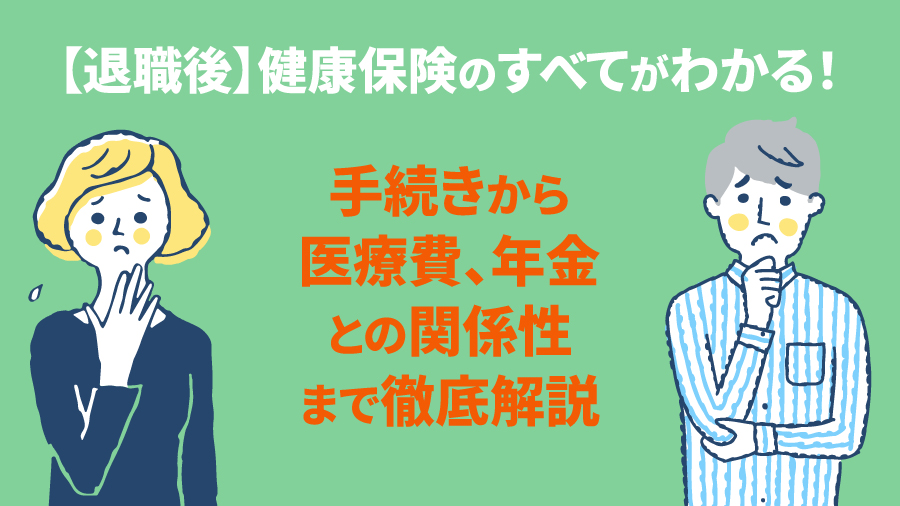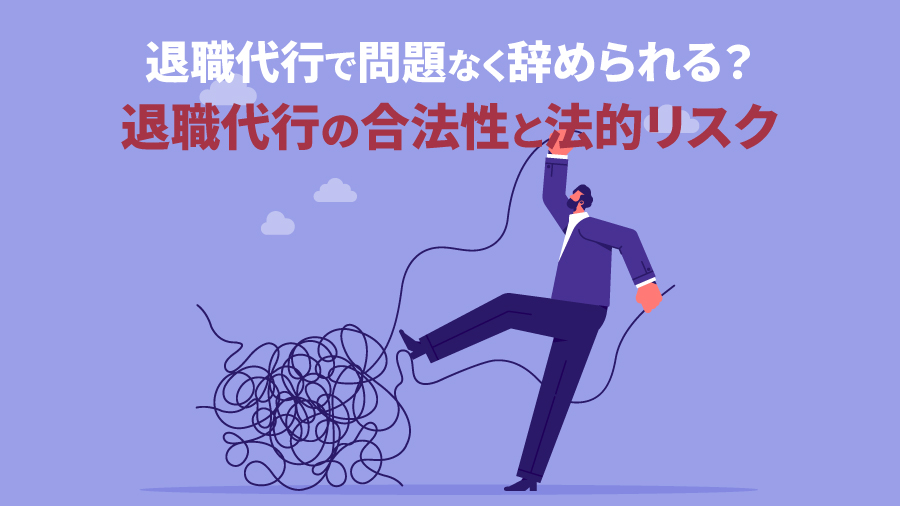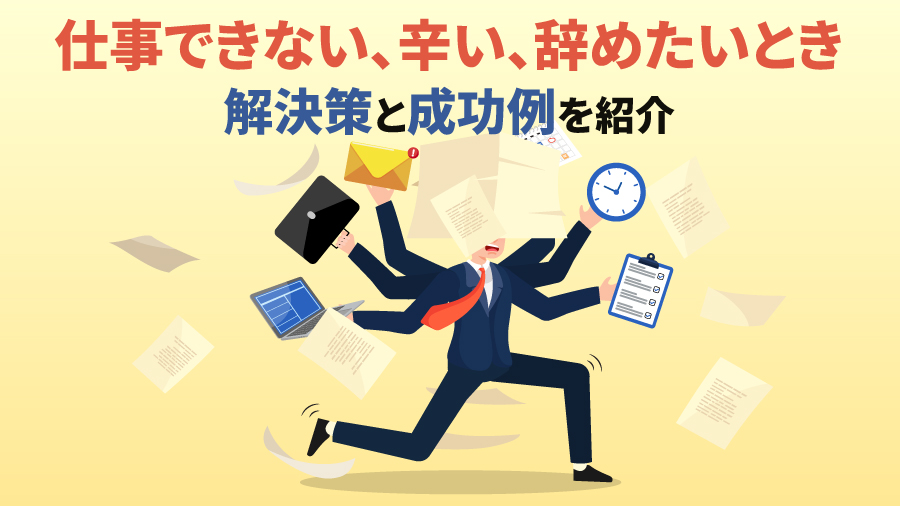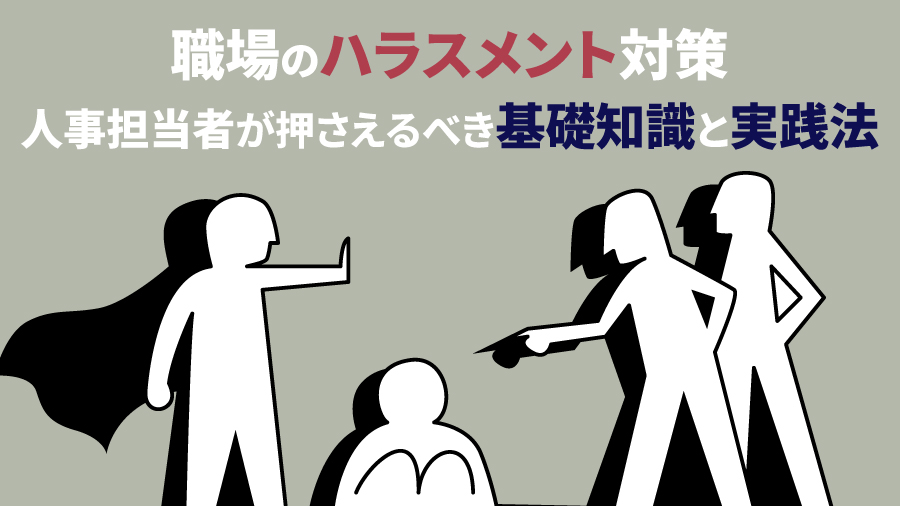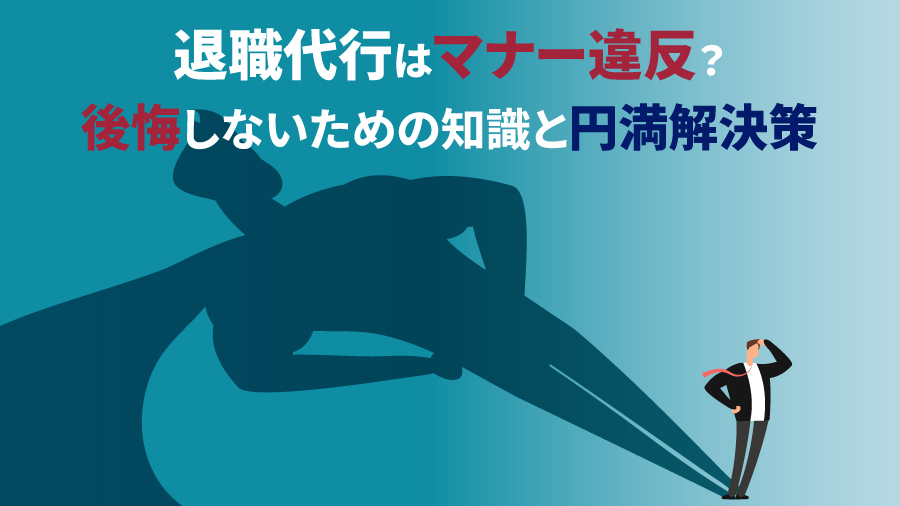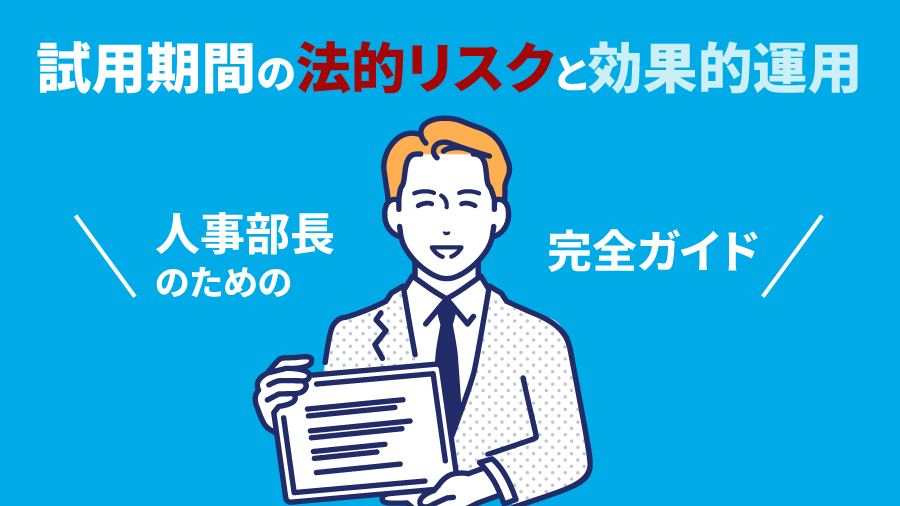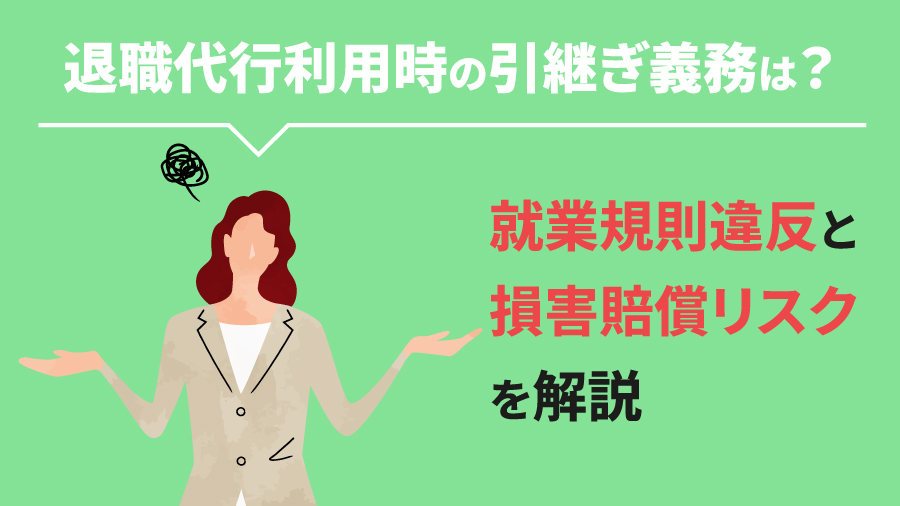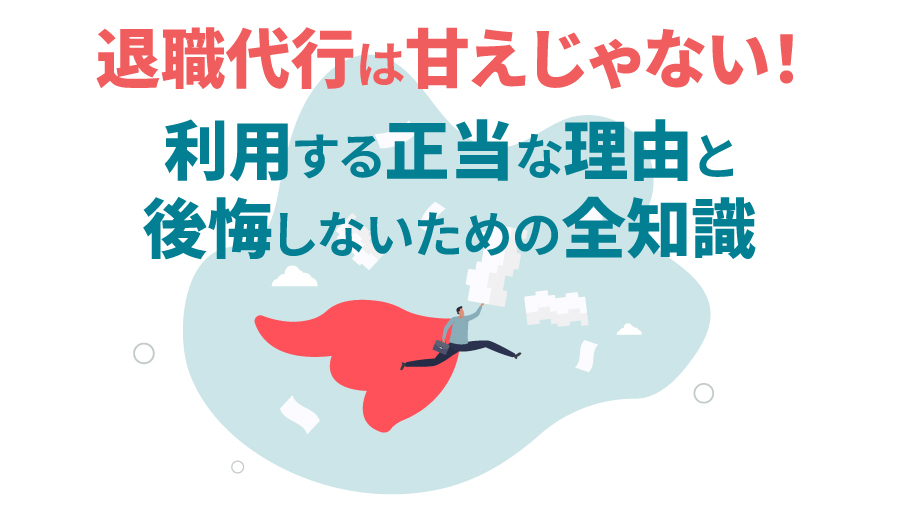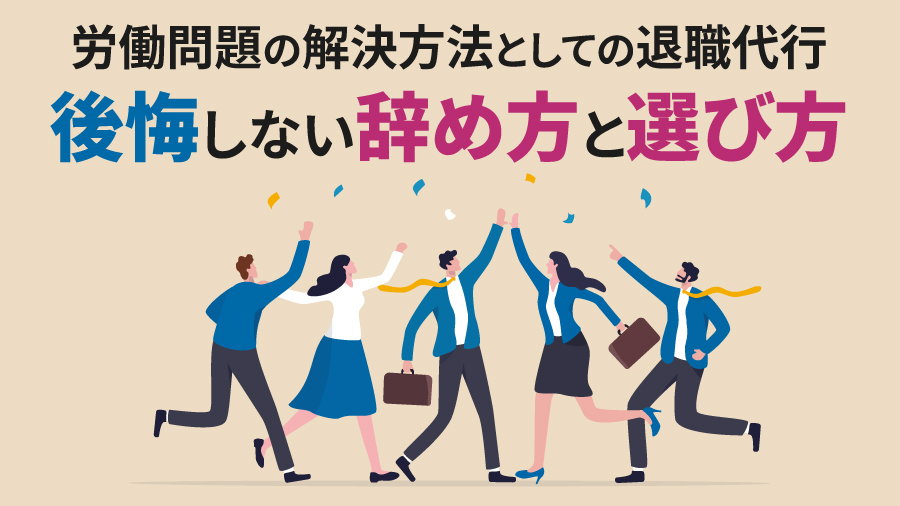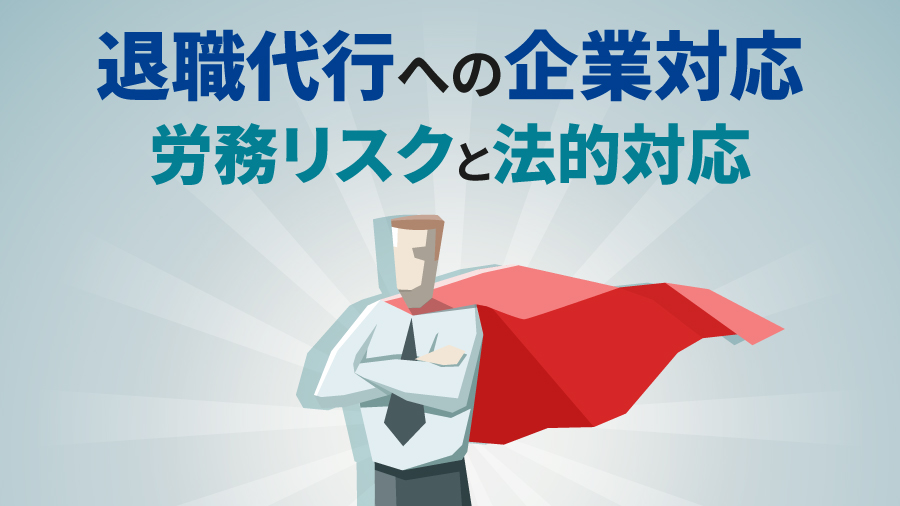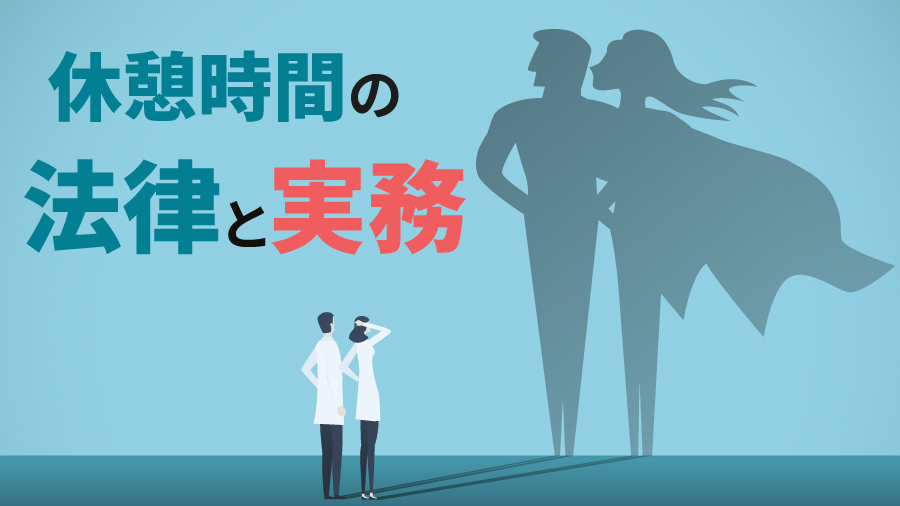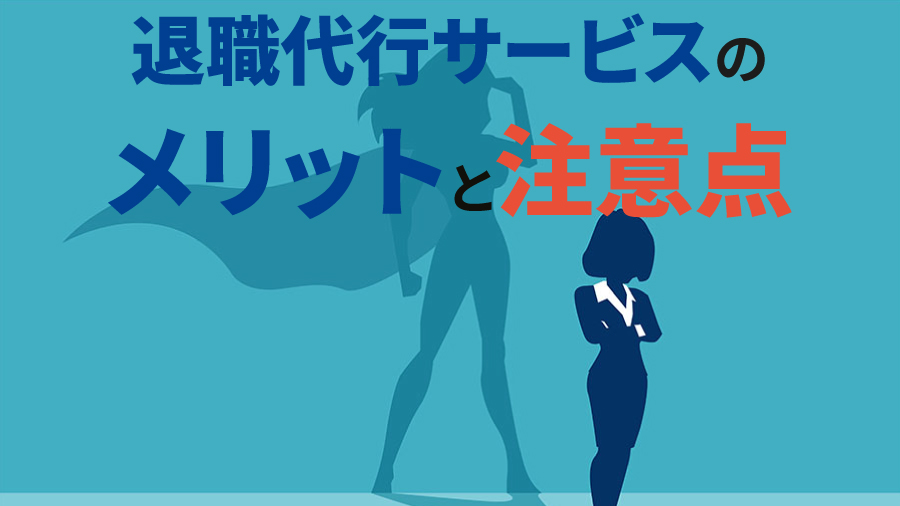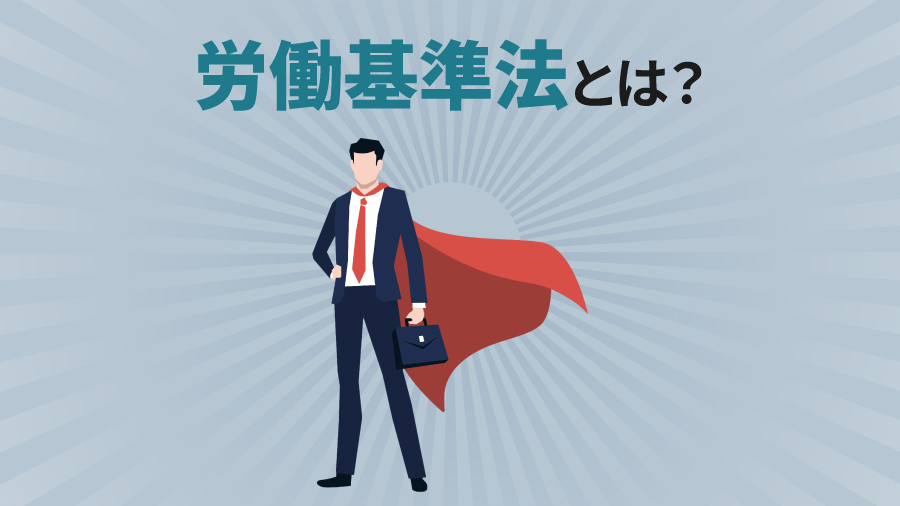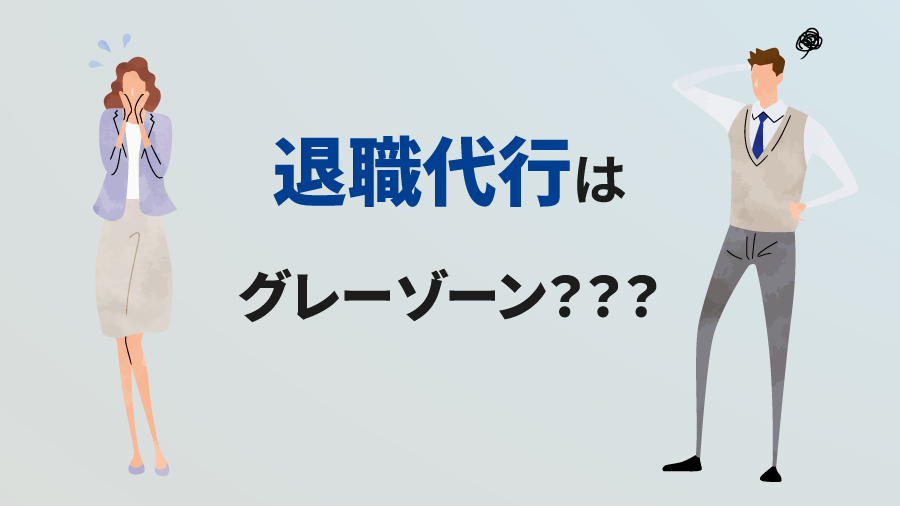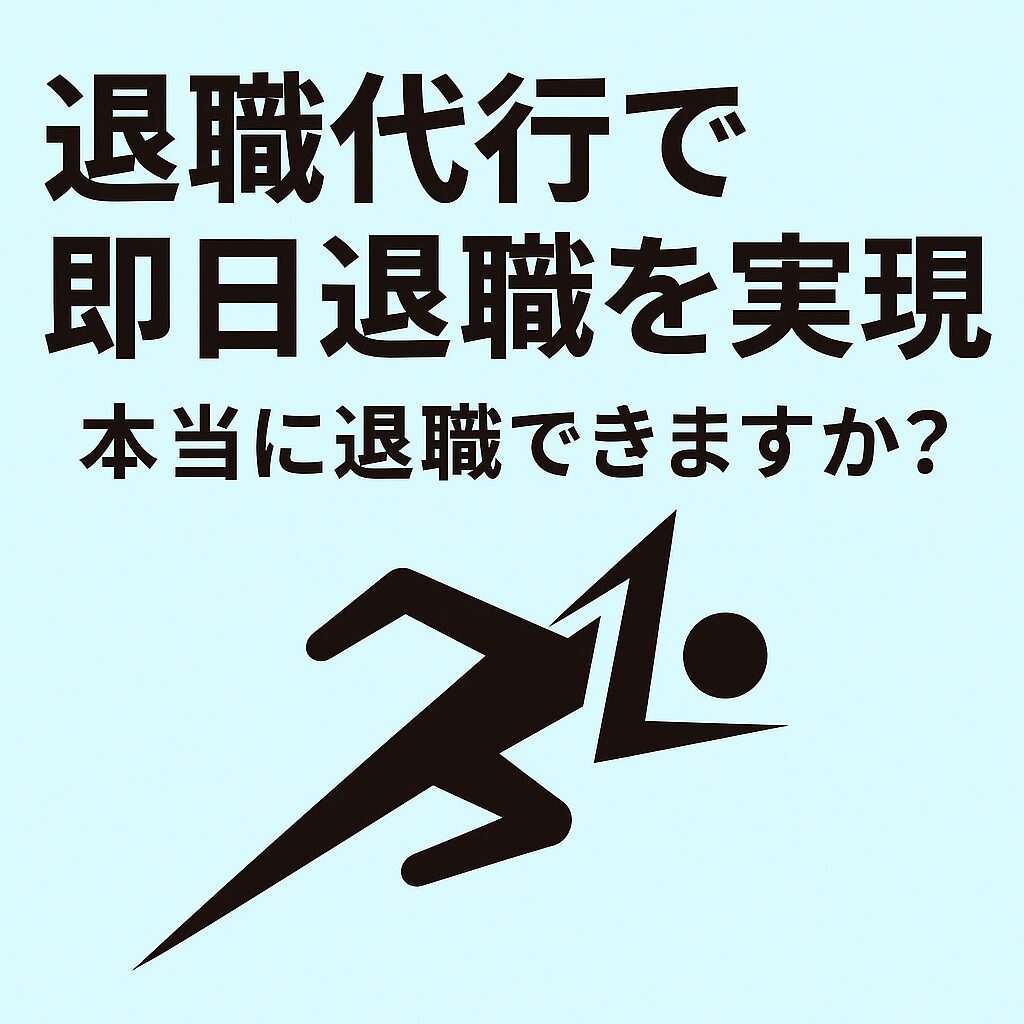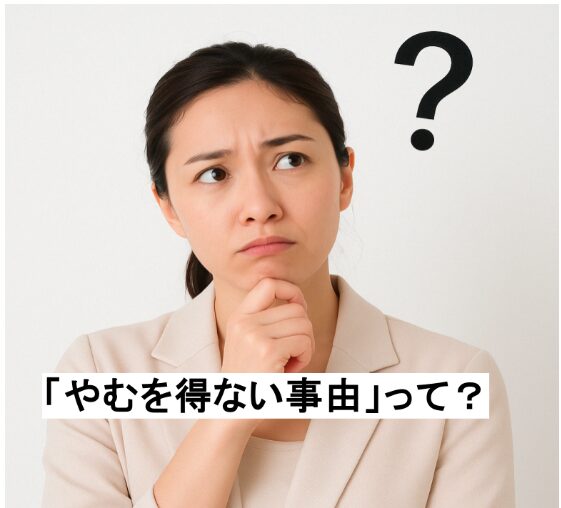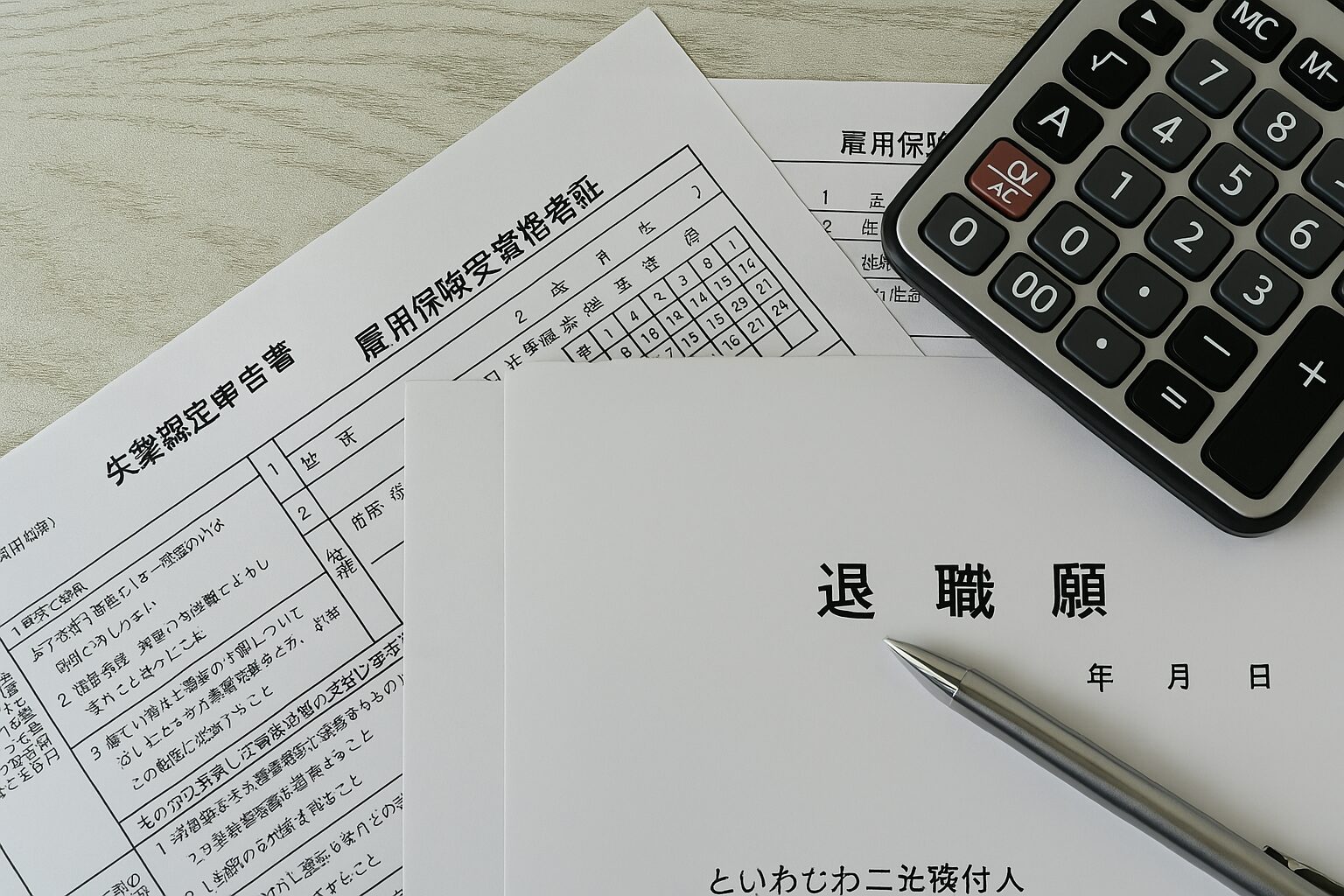-
-
退職代行で即日退職が可能な理由と条件を解説|法的根拠と手続きの流れ

「退職代行というサービスを耳にするが、引継ぎや事前告知なしで即日退職って可能なの?」といった疑問を持つ方も少なくないでしょう。 この記事では、退職代行で即日退職が可能な理由や条件、具体的な手続きの流れ、注意点などを解説します。法的根拠に基づいた情報で、あなたの退職をサポートします。
目次即日退職が可能な法的根拠
民法627条と労働基準法第22条は、労働者が退職を希望する場合において、正当性を担保し、使用者側がそれを拒否できない根拠となる法律です。
以下では、それぞれの条文と実務上の解釈について解説します。
民法627条「14日ルール」の解釈
民法第627条1項では、期間の定めのない雇用契約の場合、退職の申し入れから14日が経過すれば労働契約が終了すると定められています。実務上では、この14日間を有給休暇で相殺することで、実質的に即日退職が成立するケースが多くあります。有給休暇が14日分残っていれば、その期間が法的に必要な予告期間として認められるためです。
有給休暇を即日で申請し、退職日を当日に指定して内容証明で通知を送付すれば、翌日以降の出社義務が免除される可能性があります。これは違法ではなく、労働者の正当な退職権として認められています。
労働基準法が認める退職権
労働基準法においては、労働者が退職を申し出た場合に、使用者がこれを一方的に拒否することはできません。最高裁判例では、退職届が会社に到達した時点で法的効力が発生するとされており、「受理」は形式的な処理に過ぎないとされています。そのため、退職届の不受理を理由に退職を拒否する行為は、法的効力を持ちません。
また、退職意思の伝達が書面または電子メールなど電磁的記録で行われた場合でも、民法上の通知義務は果たされたと認められます。退職代行業者を通じて意思を伝えた場合も、法的には有効な手続きとされています。
退職代行を使った即日退職の手続き
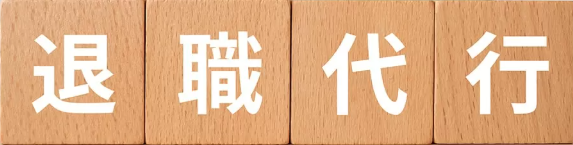
退職代行を利用することで、即日退職を安全かつ円滑に進めることができます。ここでは、手続きを3つのステップに分けてご紹介します。
STEP1:業者選定のポイント
退職代行業者の料金体系には「定額制」と「成功報酬型」があり、定額制の相場は3万円から5万円程度です。定額制は追加費用が発生しない点が特徴であり、予算に不安がある方にも安心です。一方、成功報酬型は退職完了後に追加料金がかかる場合もあるため注意が必要です。
業者を選定する際は、公式サイトで監修者の情報や実績を確認することをおすすめします。
STEP2:退職意思の正式通知
退職代行業者は、依頼者に代わって会社に退職意思を正式に通知します。通知は多くの退職代行業者で、電話やメールで会社の人事担当や上司に連絡を取ります。
通知をする内容は
- 「○○(本人)は、○年○月○日をもって退職する意思を有しており、本日をもってその旨を会社に正式に通知いたします。」
- 「本人は直接連絡が困難なため、当方が代理でご連絡しております。」
- 「退職に必要な書類の送付、給与や有給休暇の精算については、本人の住所に郵送をお願いします。」
になります。
正社員などの期間の定めのない契約であれば、原則2週間前に退職の意思を示せば退職は成立します(民法第627条第1項)。
したがって、会社側の承諾がなくても「通知が到達すれば退職できる」点がポイントです。
STEP3:有給休暇の一括申請
即日退職の実現には、有給休暇の活用が欠かせません。退職代行業者を通じて、未使用の有給休暇を退職日までに一括で申請することで、出社せずに予告期間をカバーすることができます。
有給休暇には2年間の時効があるため、過去に取得していない日数が消滅していないかも確認が必要です。未消化分があれば、退職日までに消化できるよう、会社と交渉しましょう。
残日数の確認には、給与明細や社内システムの履歴を利用し、必要に応じて有給休暇計算ツールの活用も有効です。こうした準備を通じて、スムーズな退職を実現できます。
即日退職の実務上の注意点と対策

即日退職は正当な権利である一方で、実務上のリスクも存在します。ここでは代表的な2つのリスクとその対策を解説します。
退職金減額の可能性
即日退職を行うことで、就業規則に基づいて退職金が減額される可能性があります。これは法律で定められているわけではなく、企業ごとの就業規則や退職金規程に基づき運用されているルールで、予告期間を経ずに退職することで支給額が少なくなる場合があります。
まずは在籍企業の就業規則を確認し、退職金の支給条件や予告義務に関する記載を把握することが大切です。仮に減額が行われた場合でも、その取り扱いに不服がある場合は、労働基準監督署や弁護士に相談して異議申し立てを行うことができます。
証明書発行拒否への対応
退職後に会社が離職票や雇用保険被保険者証、源泉徴収票などの書類を発行しないケースも見受けられます。しかし、労働基準法第22条では、書面請求から7日以内に交付する義務が企業側に課されています。
書類が発行されない場合は、労働基準監督署に相談し、必要に応じて行政書士や弁護士を通じて文書請求を行うことが有効です。また、特定記録郵便や内容証明郵便を利用すれば、請求履歴を証拠として残すことができ、企業側へのプレッシャーにもなります。
このような対策を講じることで、退職後の重要な手続きを円滑に進めることができます。
よくある質問Q&A
退職代行を利用する際には、費用や特殊な状況に関する疑問を持つ方が多くいらっしゃいます。ここでは代表的な2つの質問にお答えします。
Q. 退職代行の費用は自分で全額負担しなければならないのですか?
退職代行の費用は、基本的に利用者ご本人が負担することになります。会社が費用を補助する制度は一般的に存在しないため、利用前に料金の相場や支払方法を確認しておくことが重要です。
料金相場は3万円から5万円程度で、弁護士が対応する場合は10万円前後になることもあります。最近では、後払い対応や分割払い、クレジットカード決済が可能な業者も増えています。
費用の捻出が難しい場合は、以下のような方法も検討してみましょう。- クレジットカードの分割払いを利用する
- 親族や知人に一時的に借りる
- 不要品をフリマアプリなどで売却する
費用の準備が不安な場合は、料金体系が明確で、追加料金の発生しない定額制の業者を選ぶと安心です。
Q. 海外赴任中の即日退職は可能ですか?
海外に赴任中でも、日本国内の企業と雇用契約を結んでいる場合には、日本の労働法が適用されます。そのため、退職の意思を伝え、退職代行を利用することは可能です。
ただし、契約が現地法人とのものであれば、現地の法律が優先される可能性があります。契約書を確認し、不明点があれば専門家に相談することをおすすめします。
まとめ|安全な即日退職のためのチェックリスト

退職代行を利用して即日退職を成功させるためには、事前の準備が欠かせません。以下の7項目を確認し、安全かつ確実な退職を実現しましょう。
確認項目 チェック 雇用契約の形態を確認する 有給休暇の残日数を把握する 退職代行業者の選定基準を明確にする 通知書の文面と送付手段を確認する 退職後に必要な書類の確認をする トラブル発生時の対応先を明確にする 有給消化に向けた交渉方法を確認する これらのポイントを押さえておけば、退職代行による即日退職も安心して実行できます。法律の正しい理解と信頼できる業者の選定を通じて、精神的な負担を減らしながら、新しい一歩を踏み出しましょう。
-