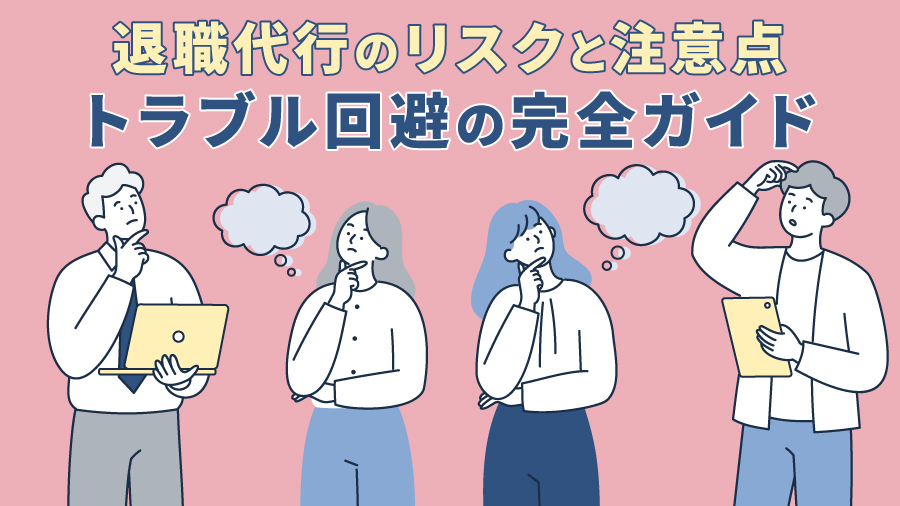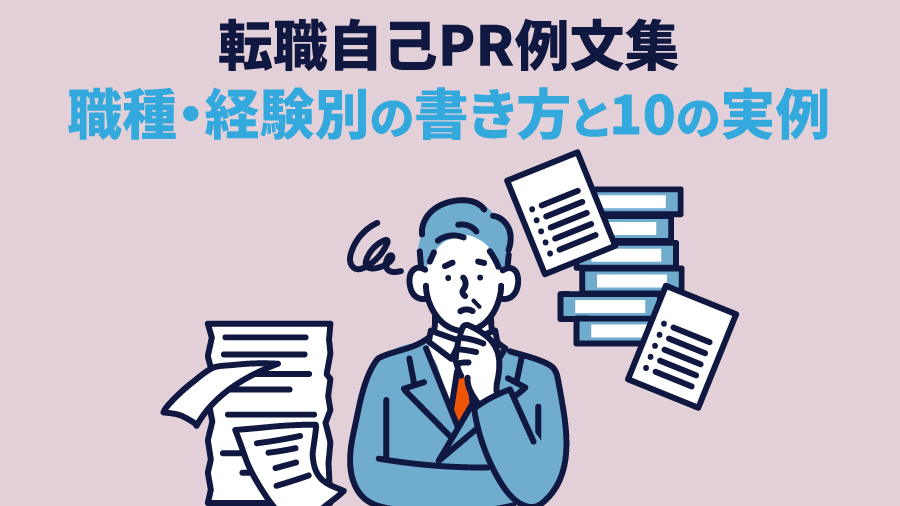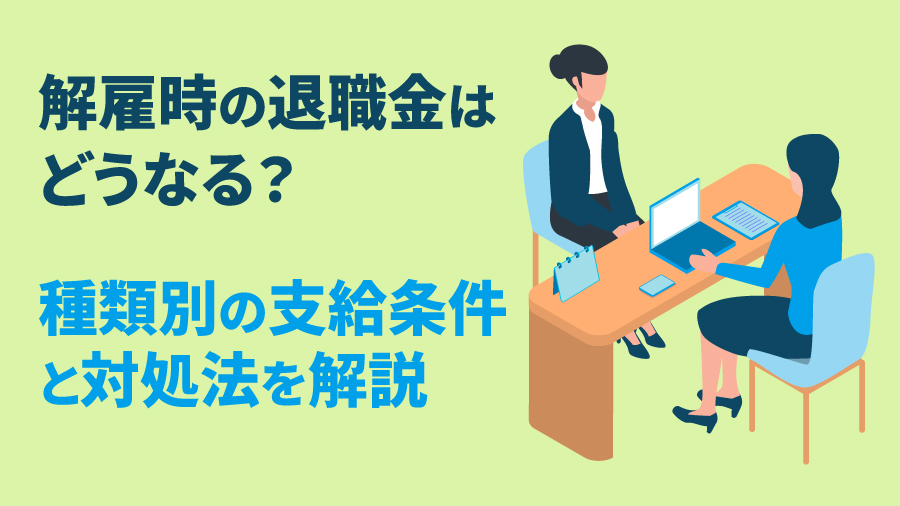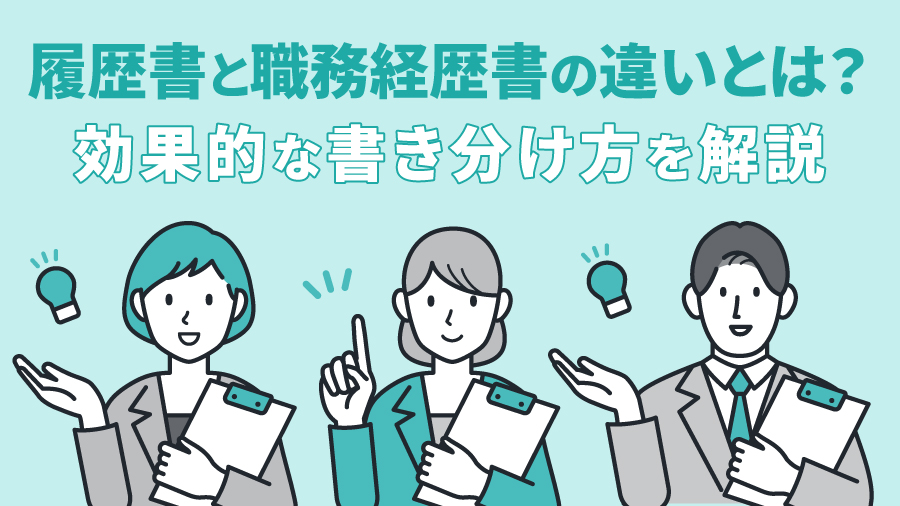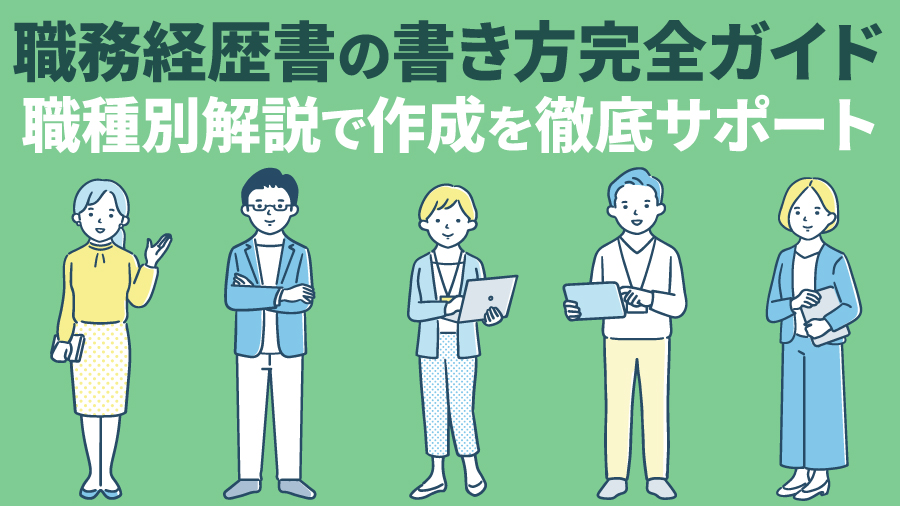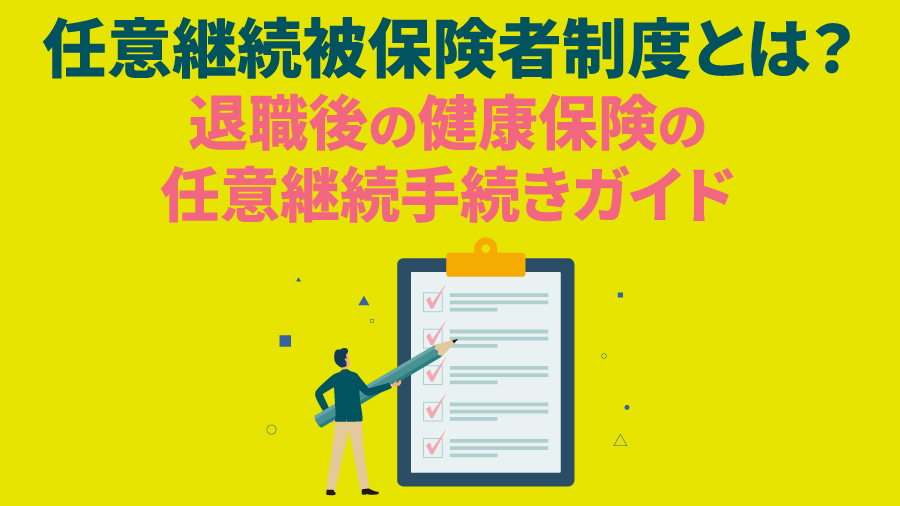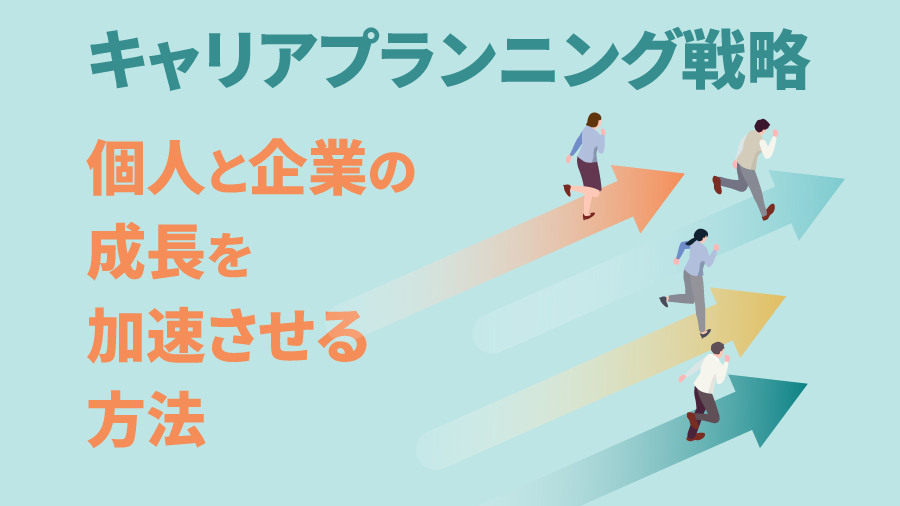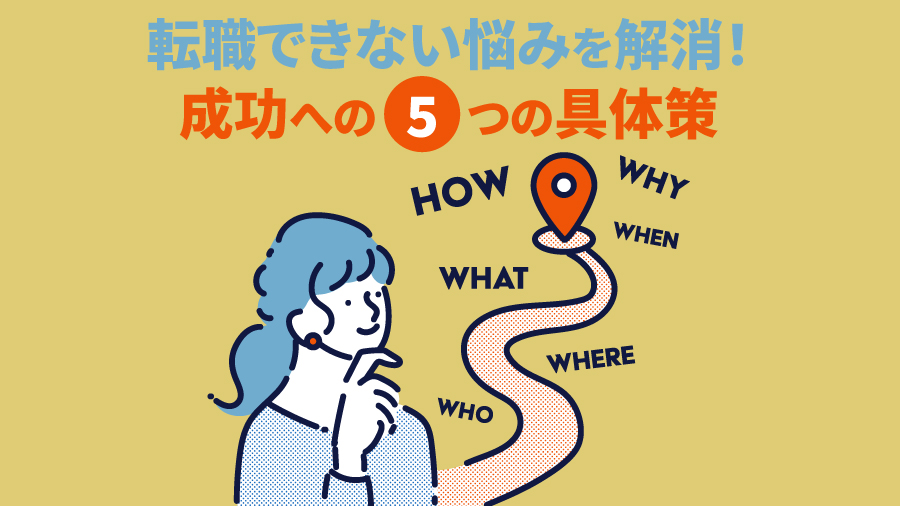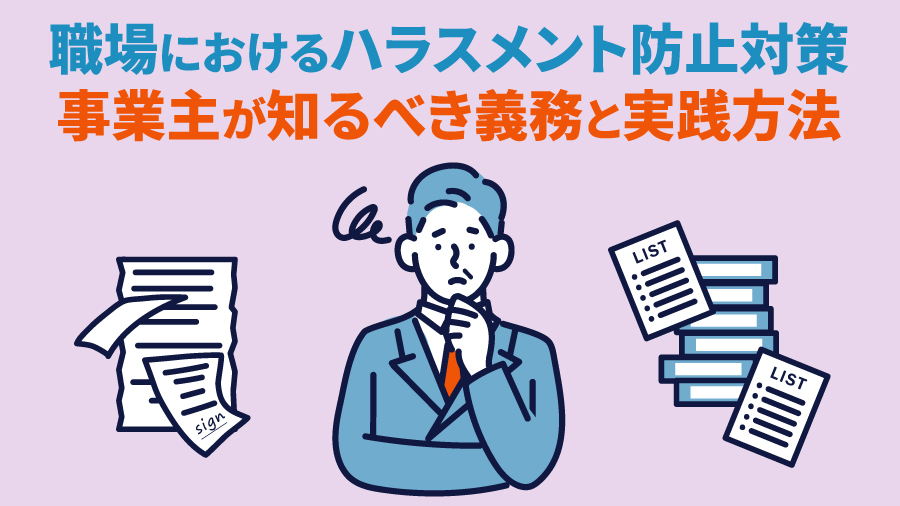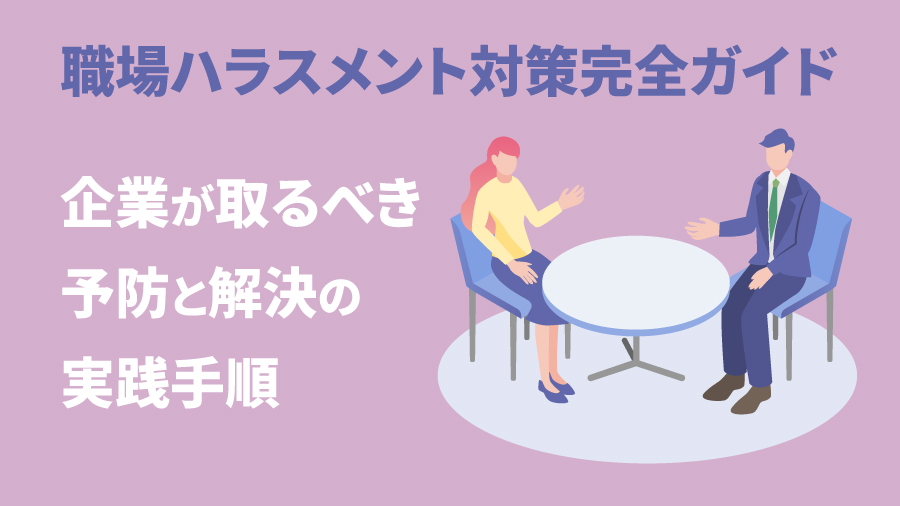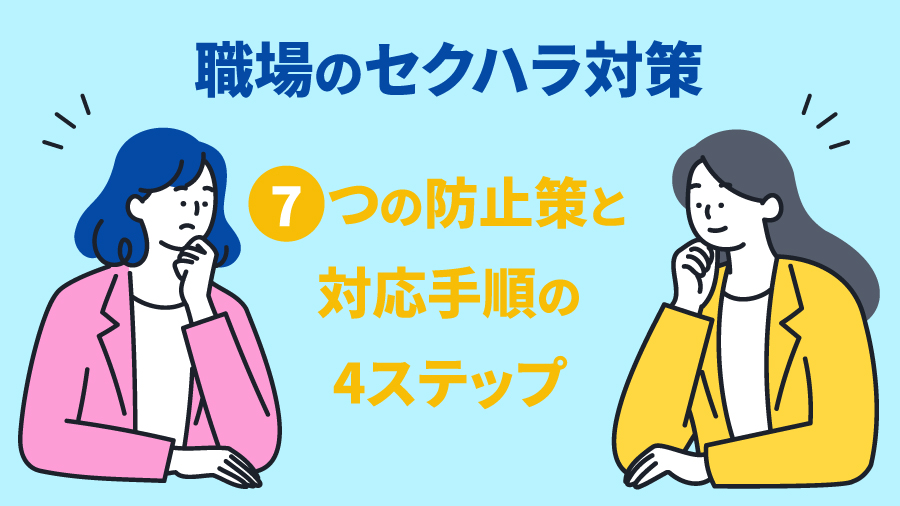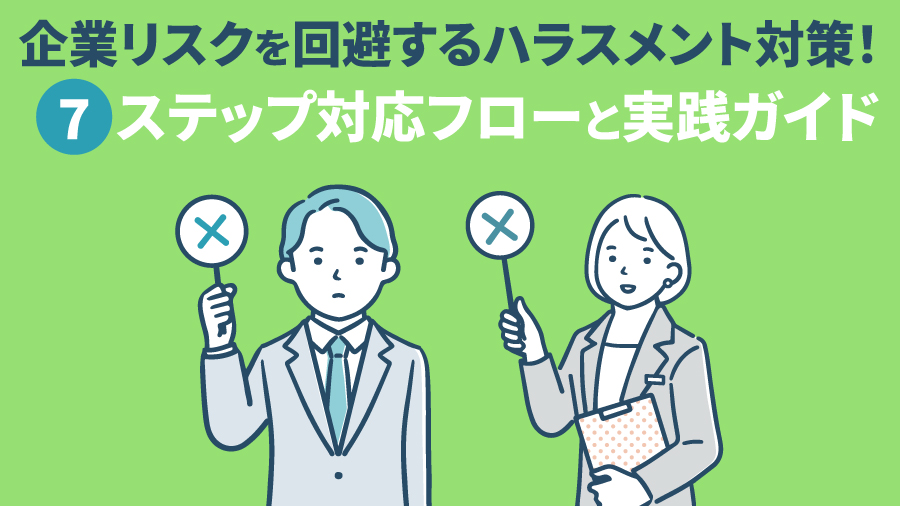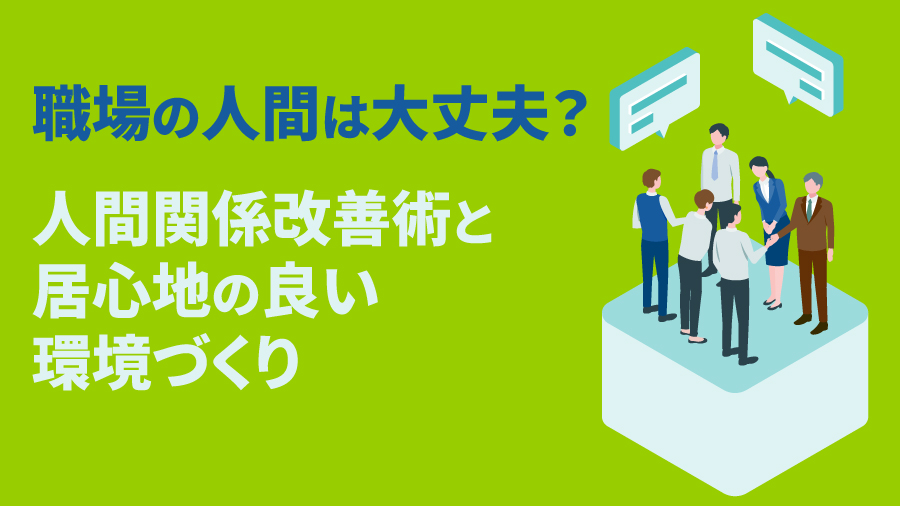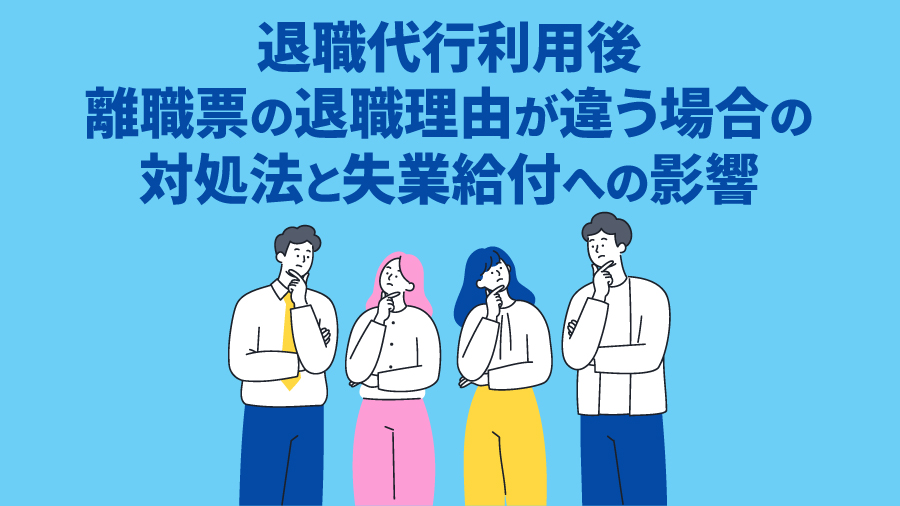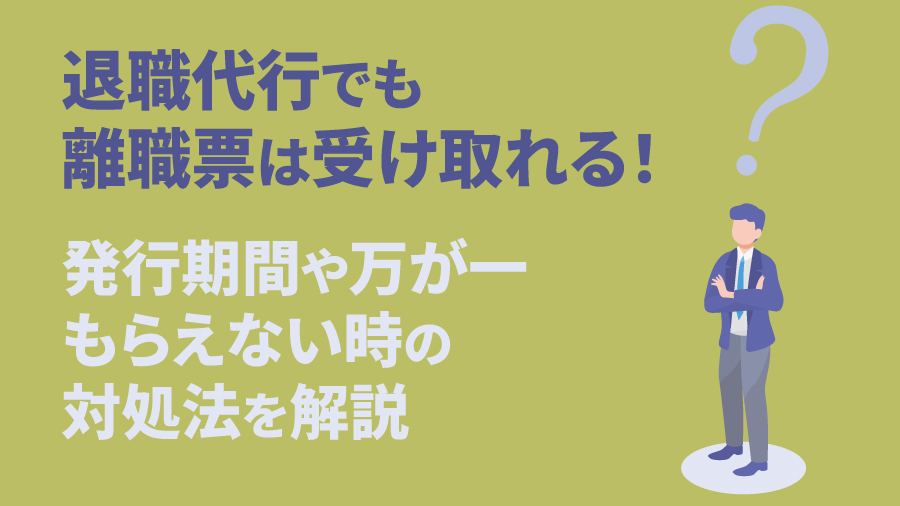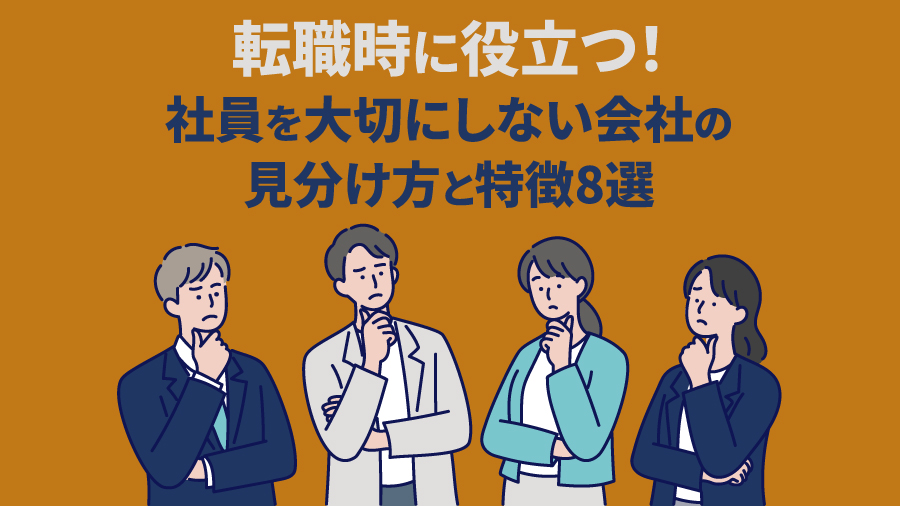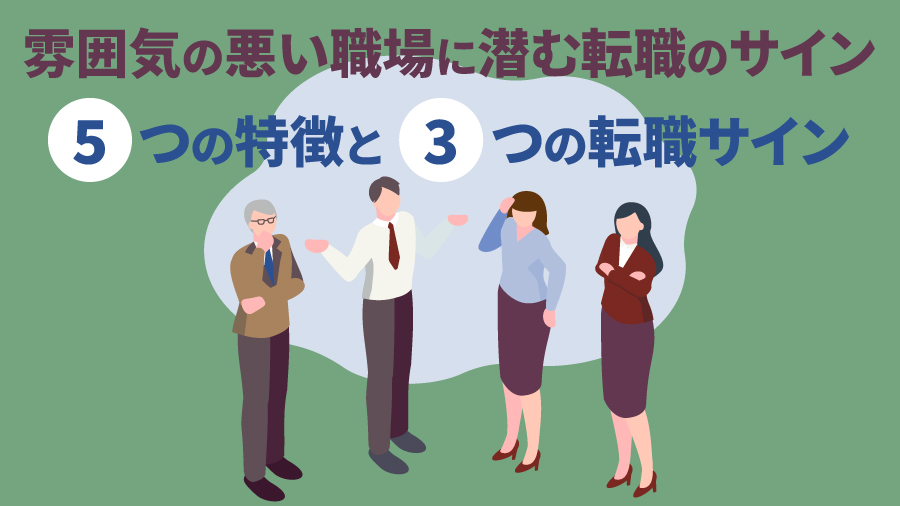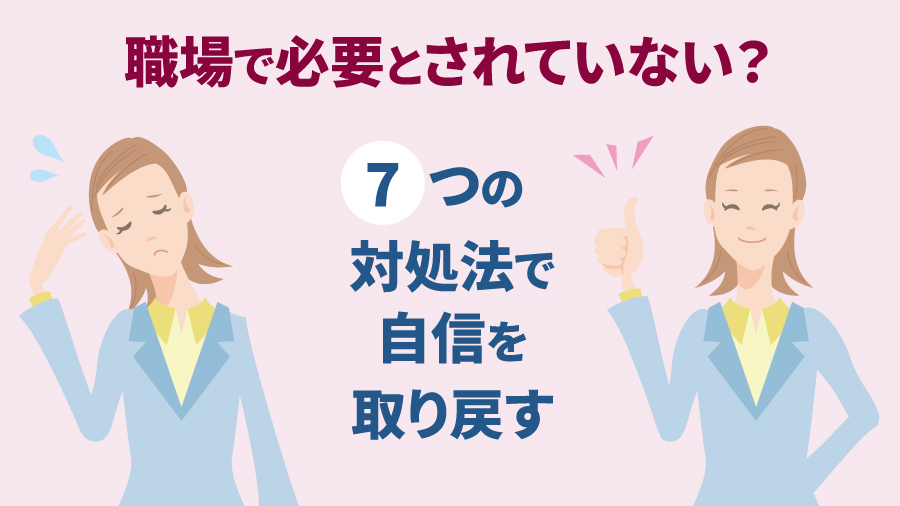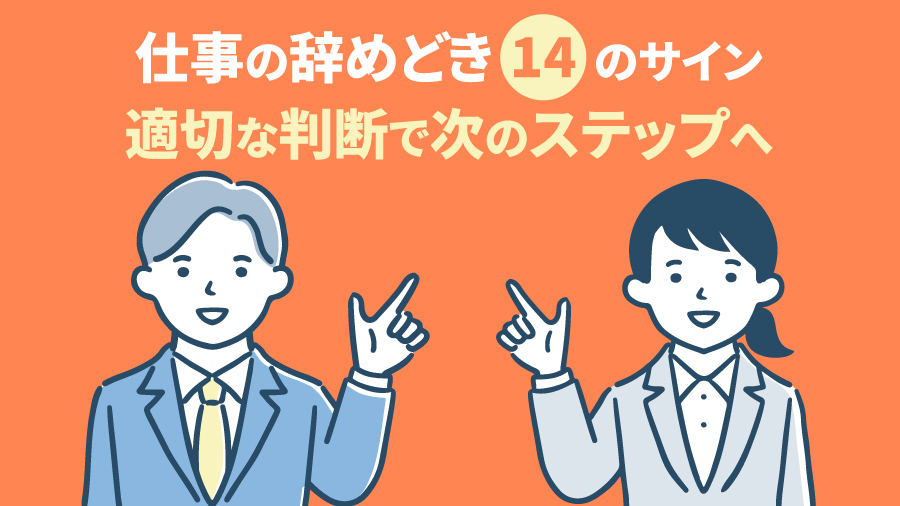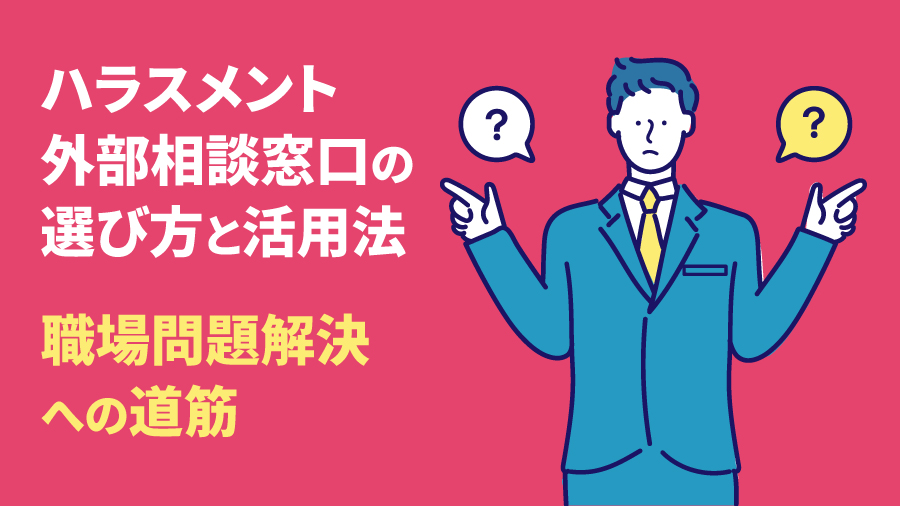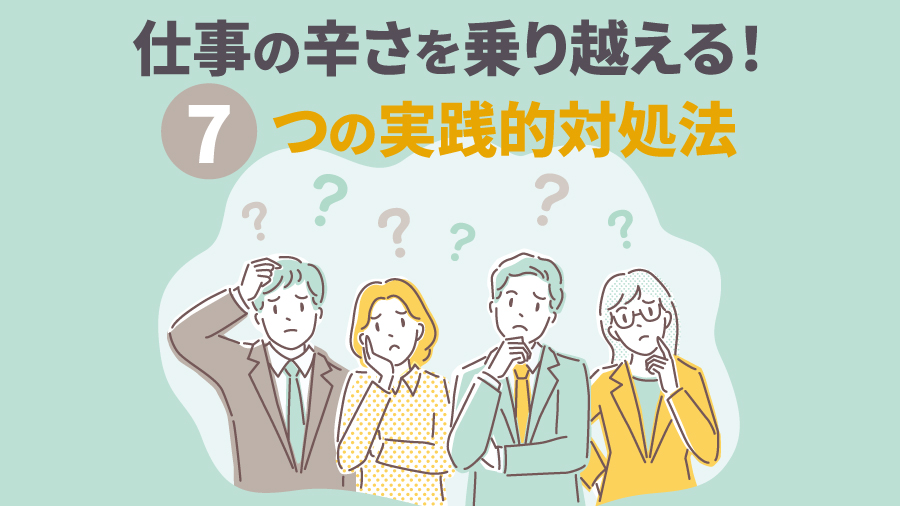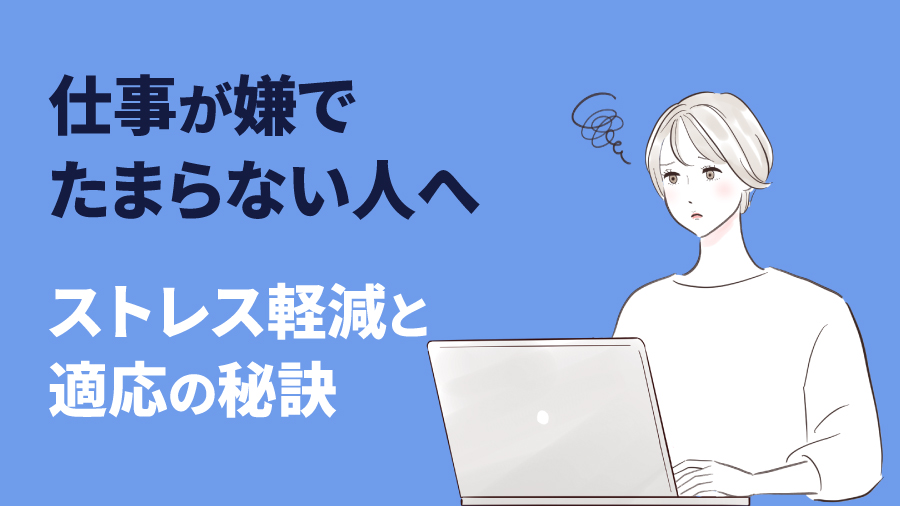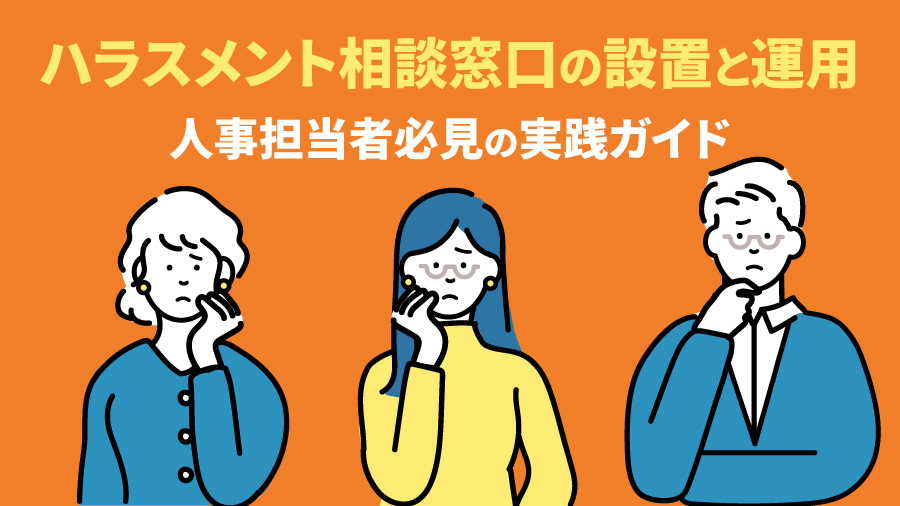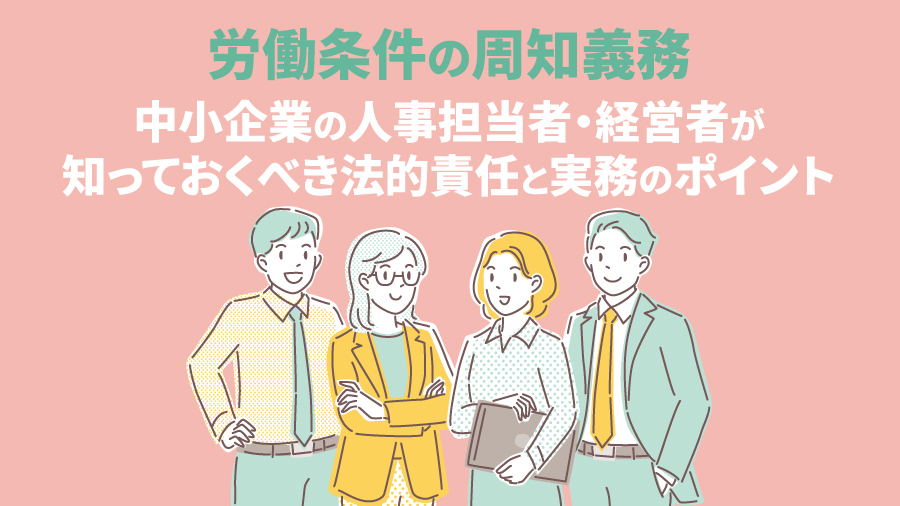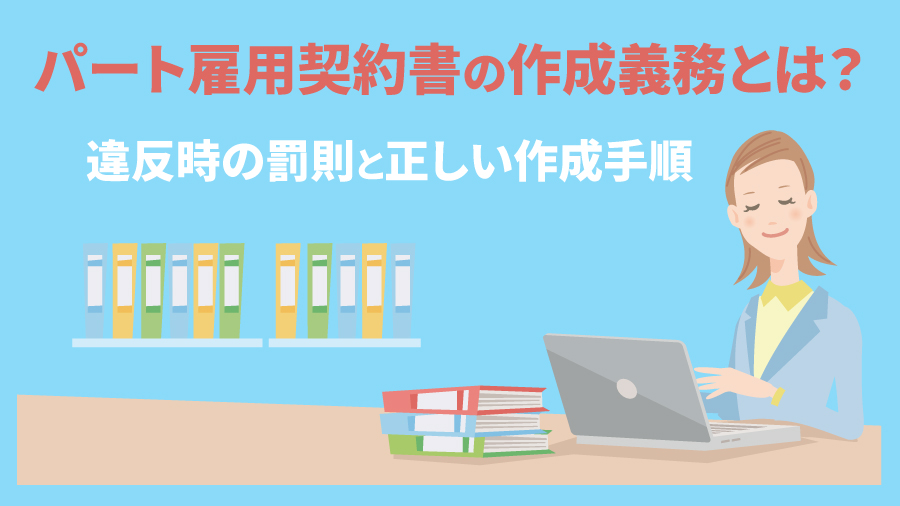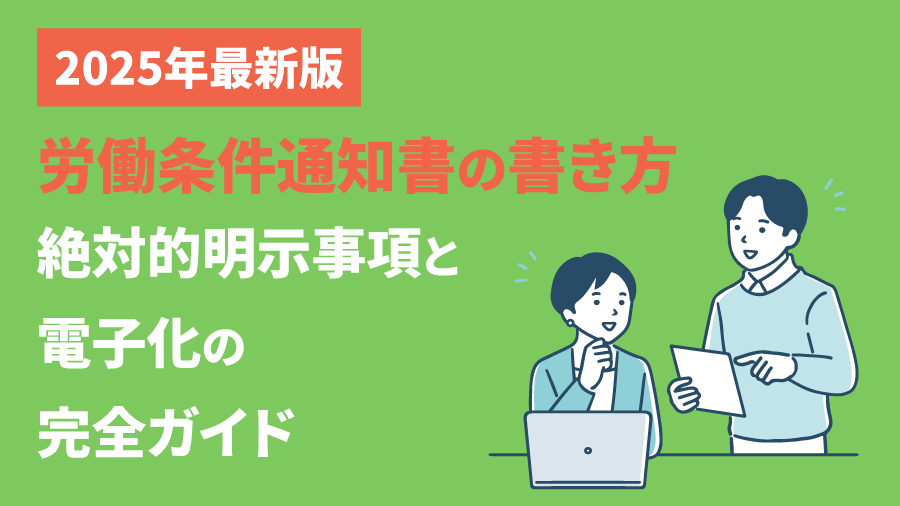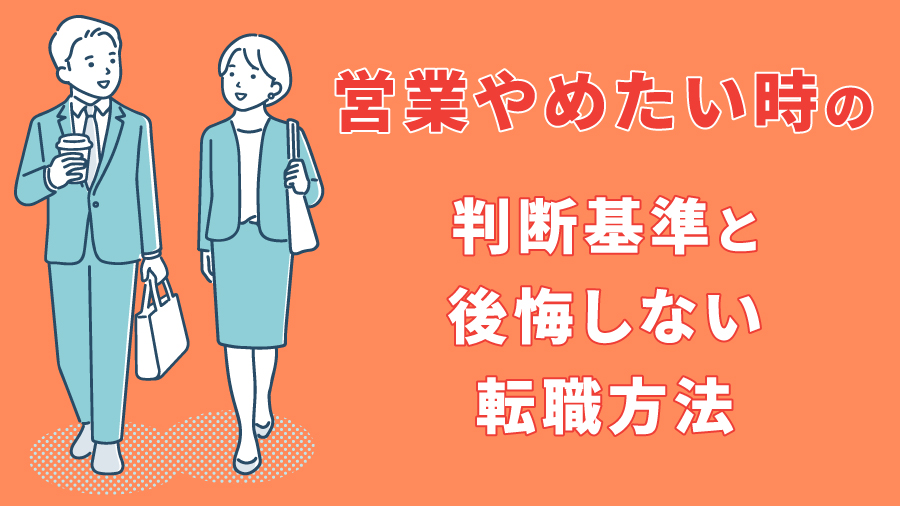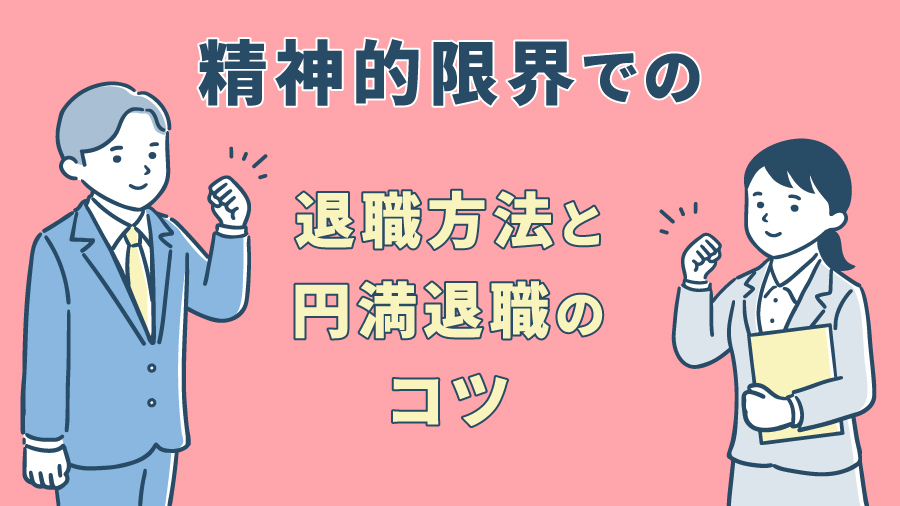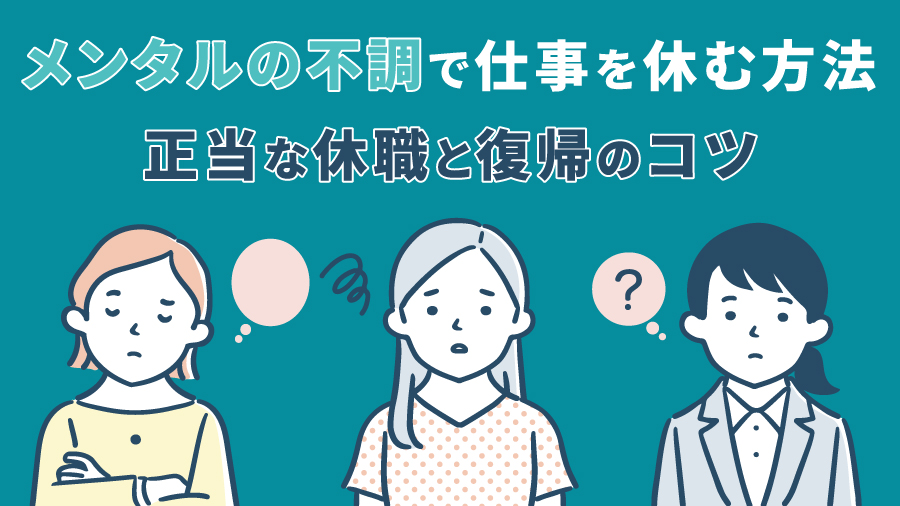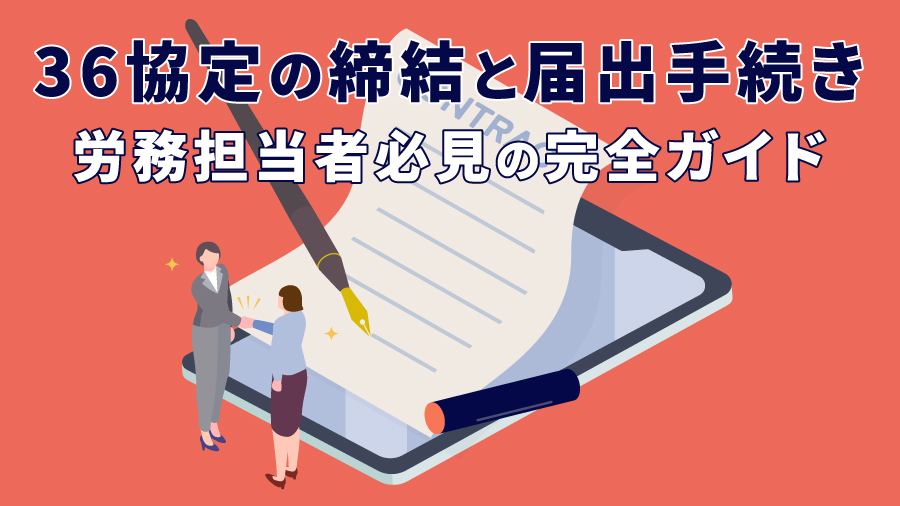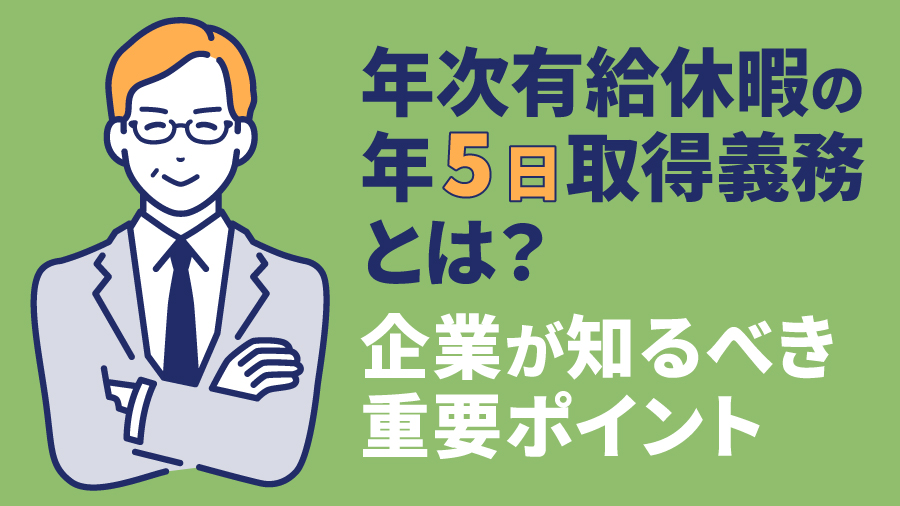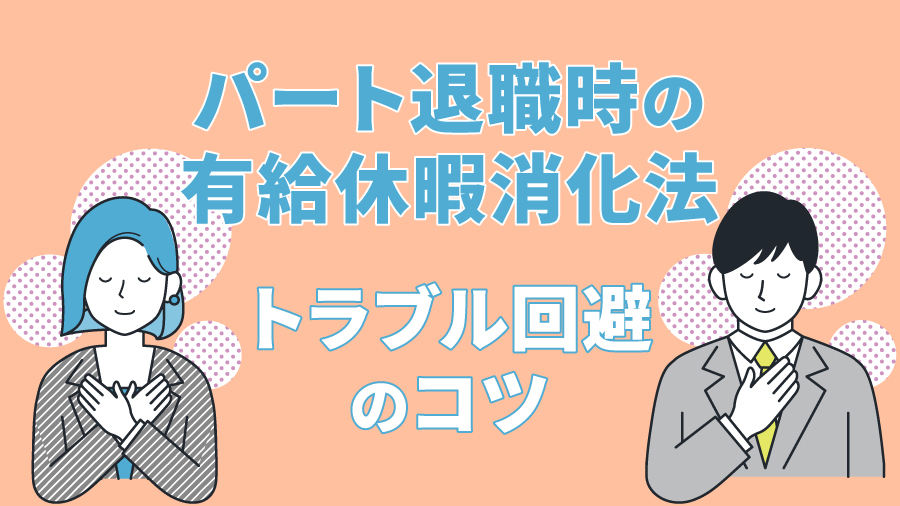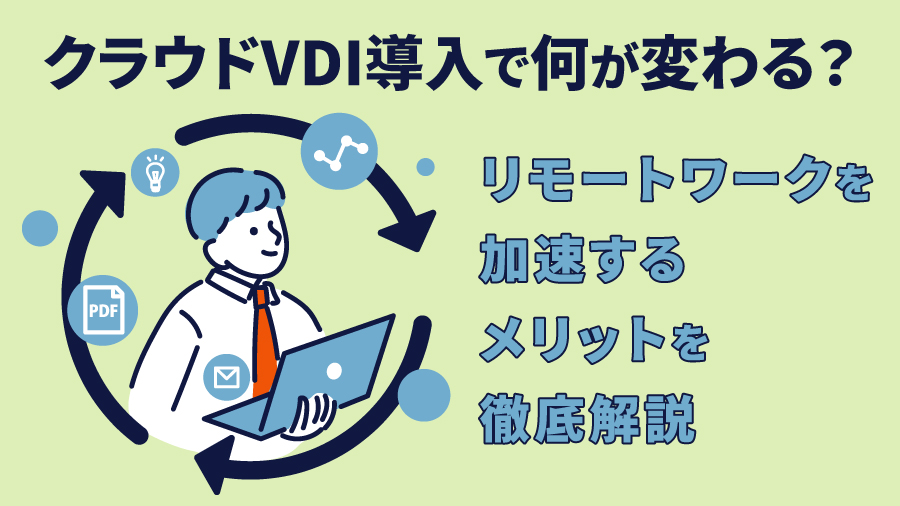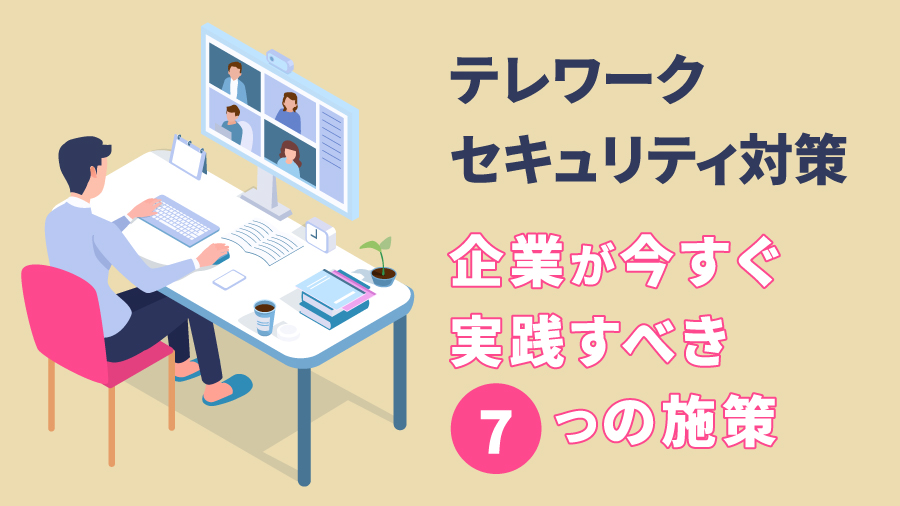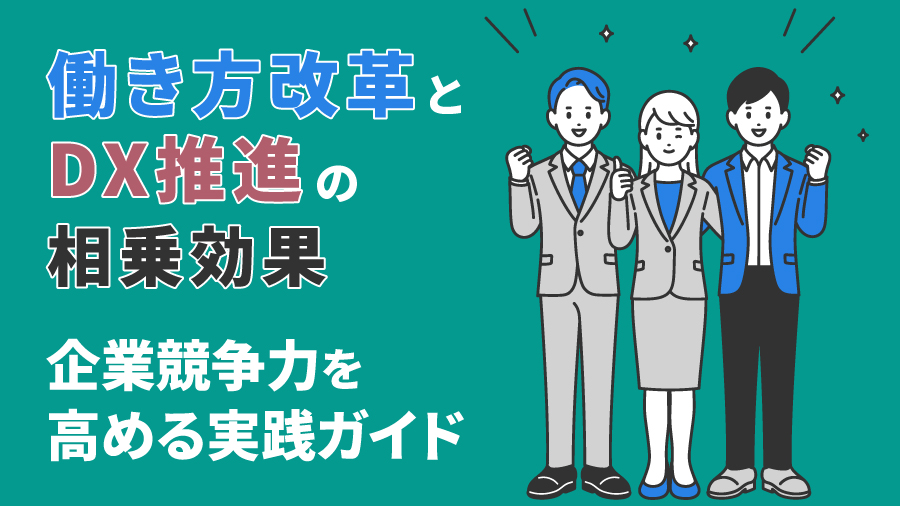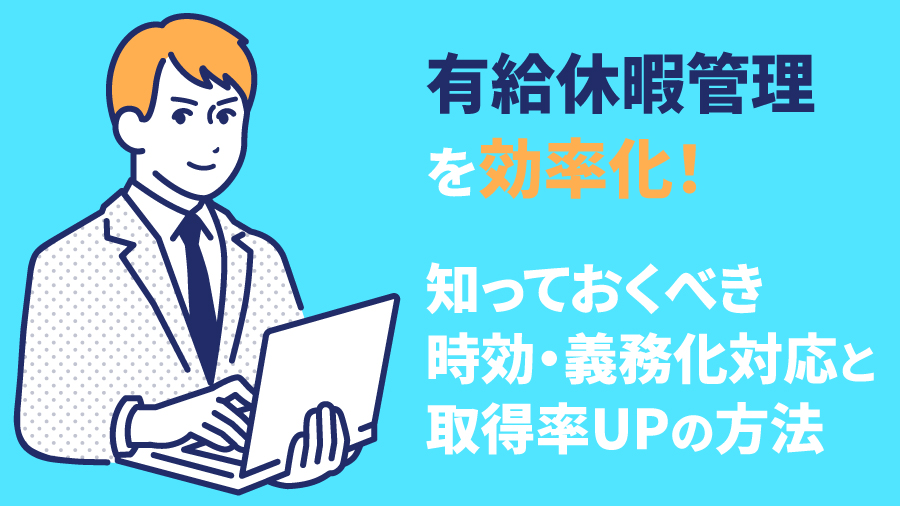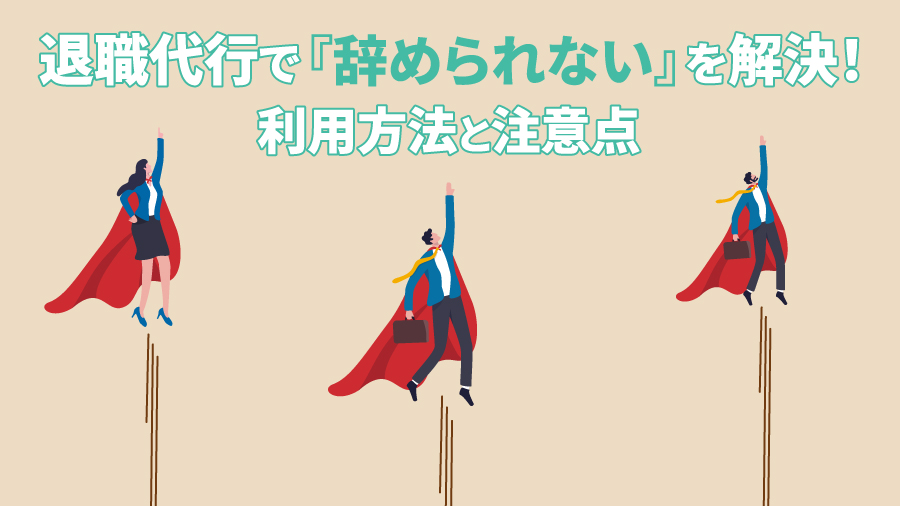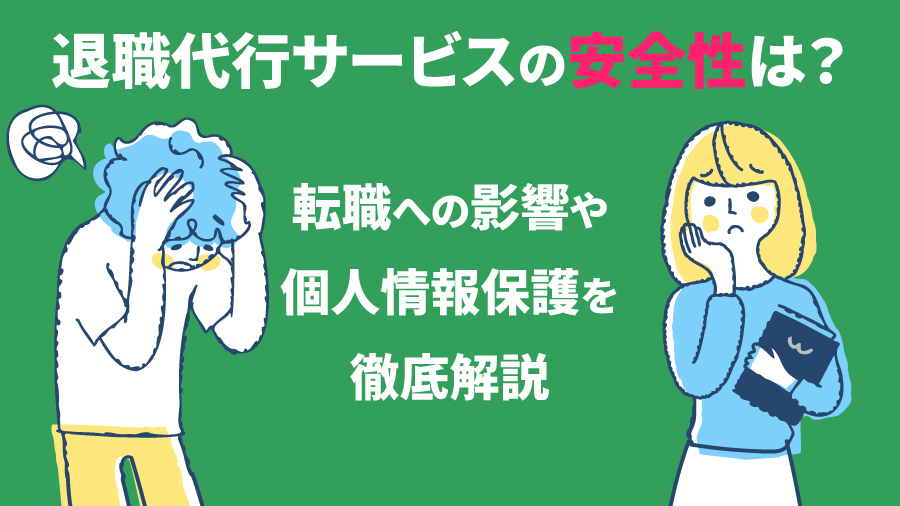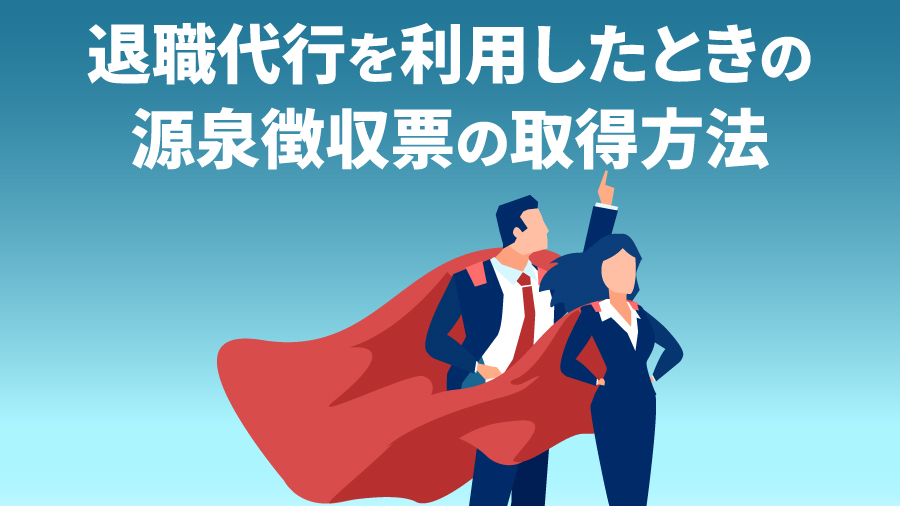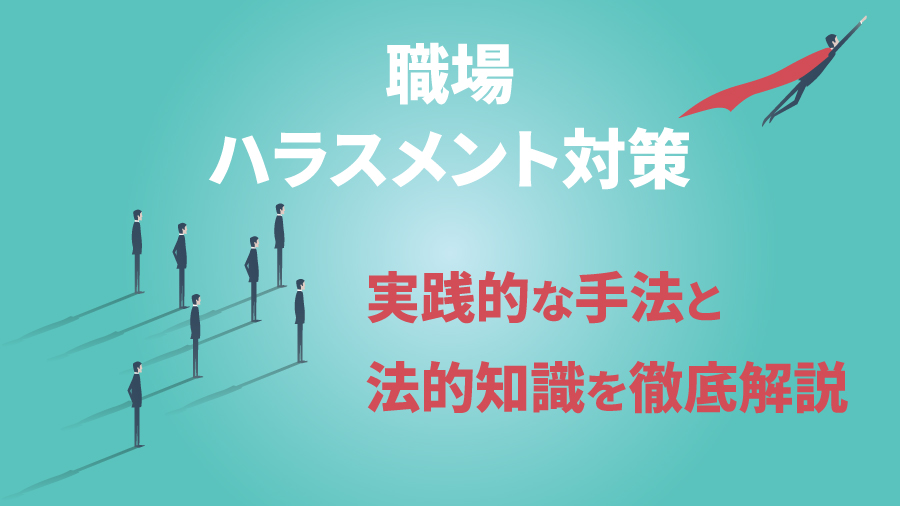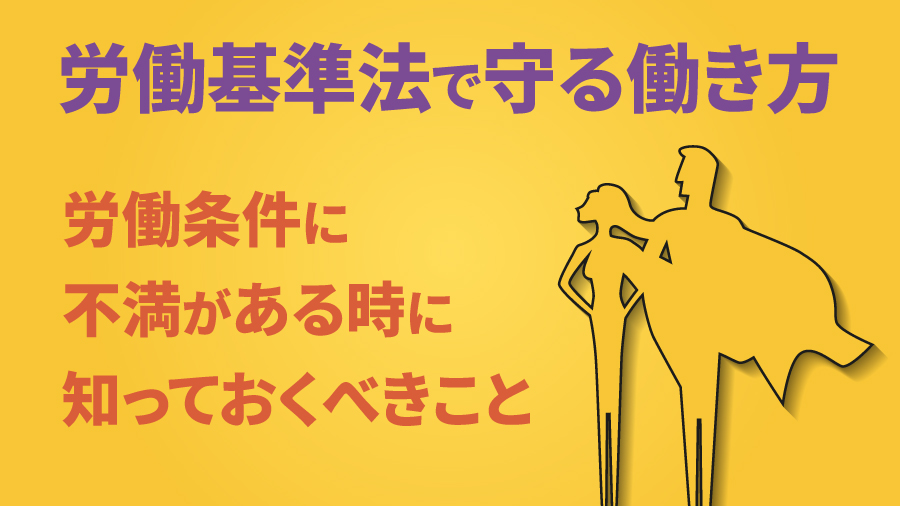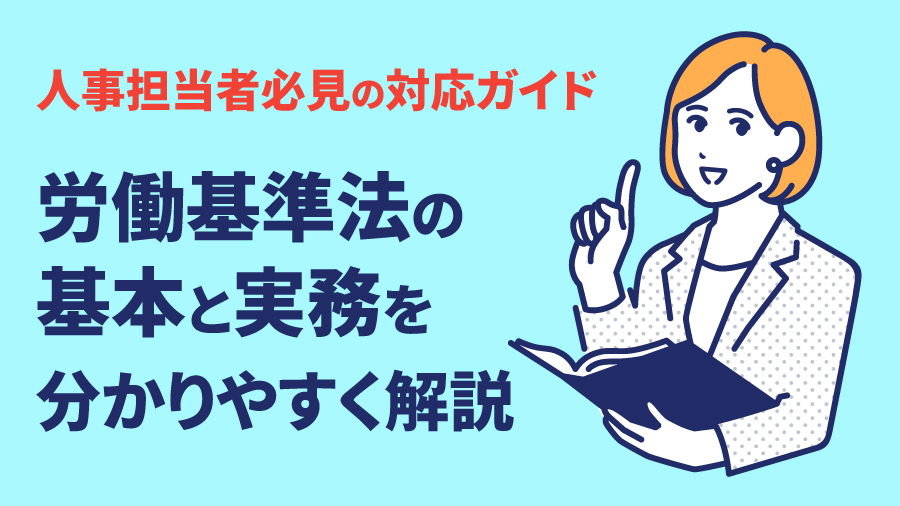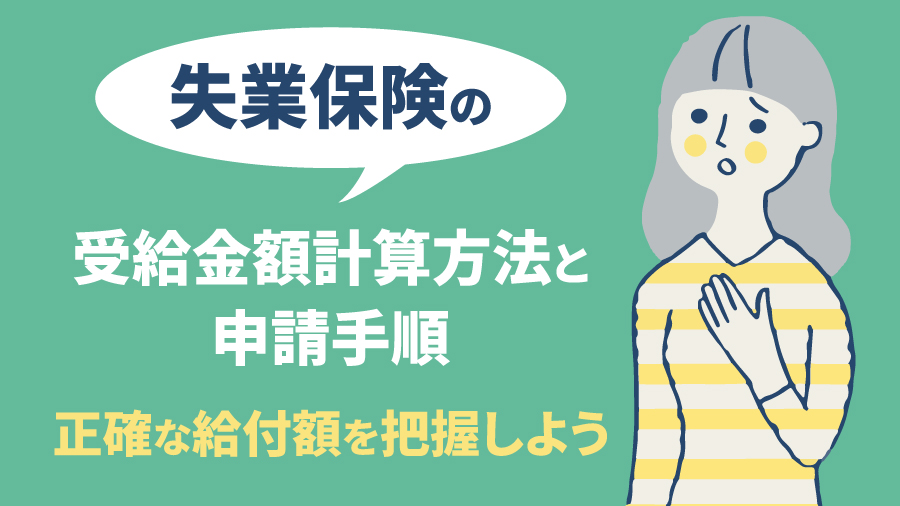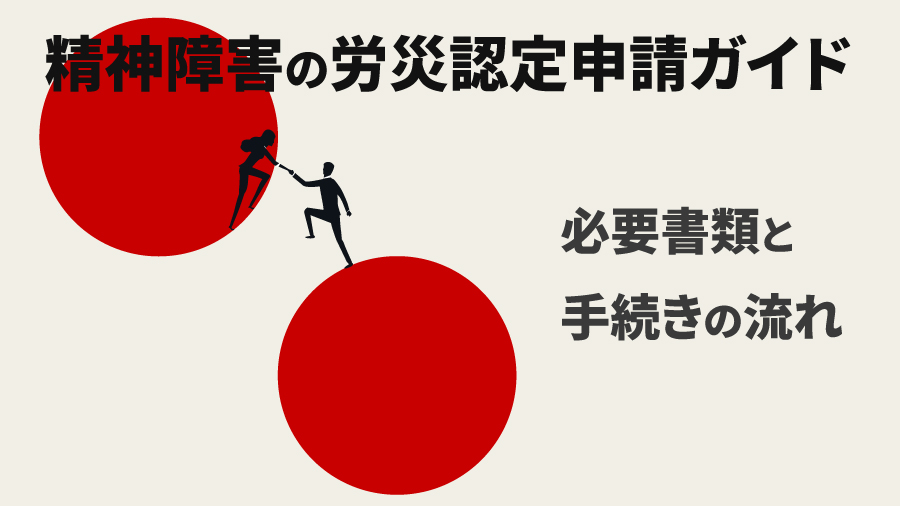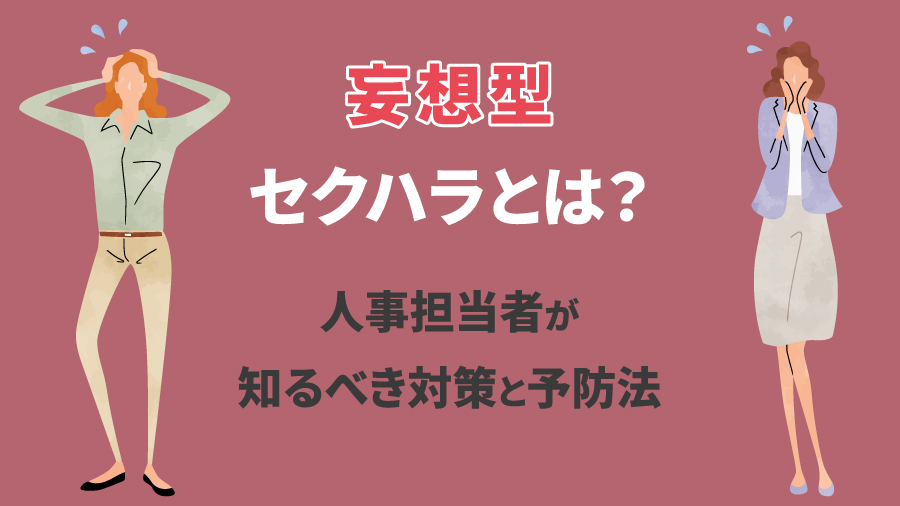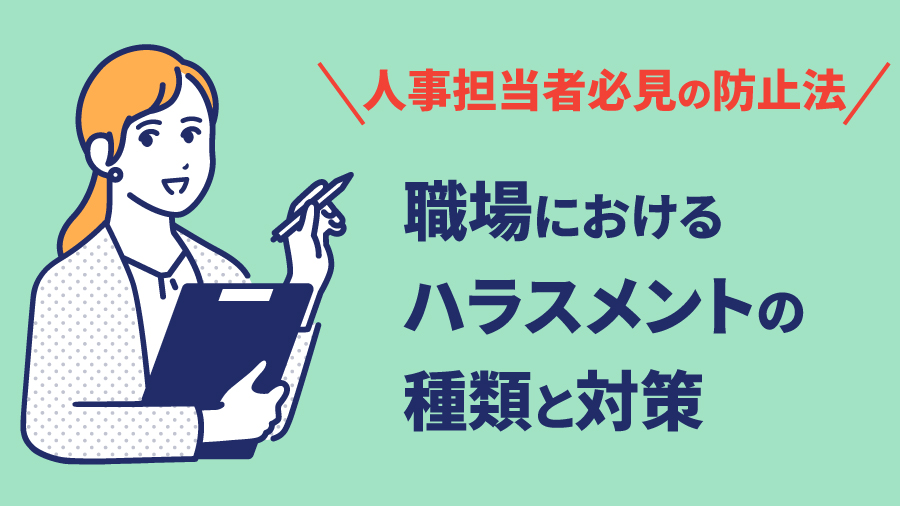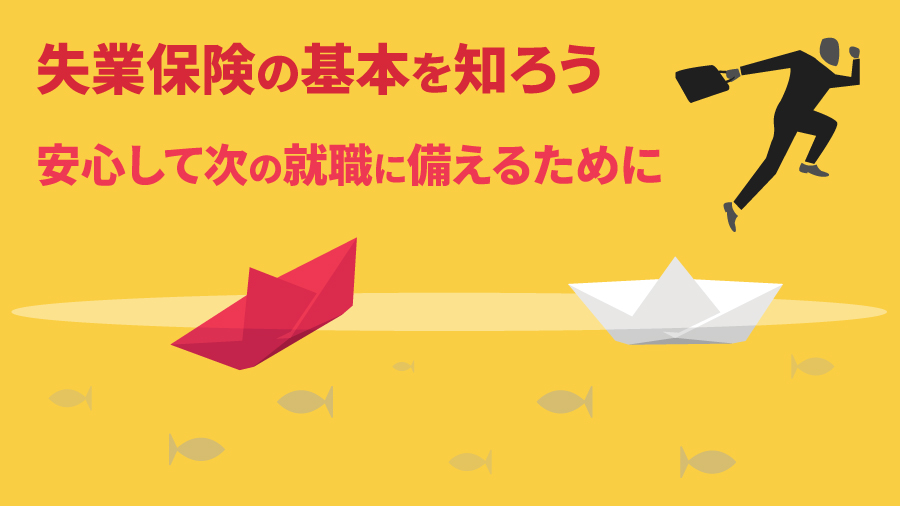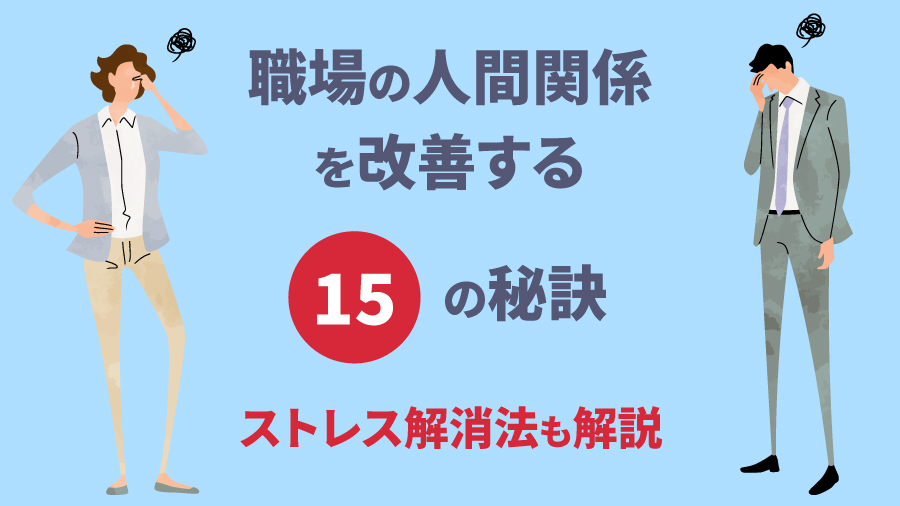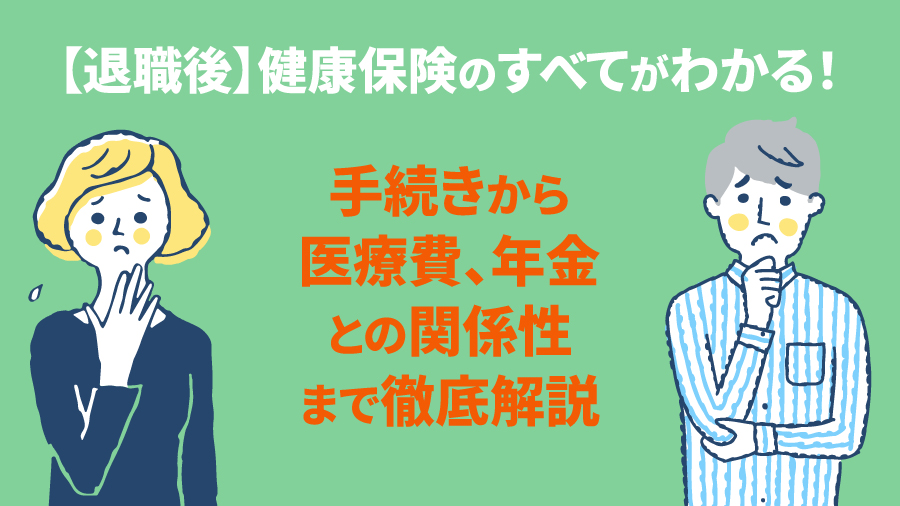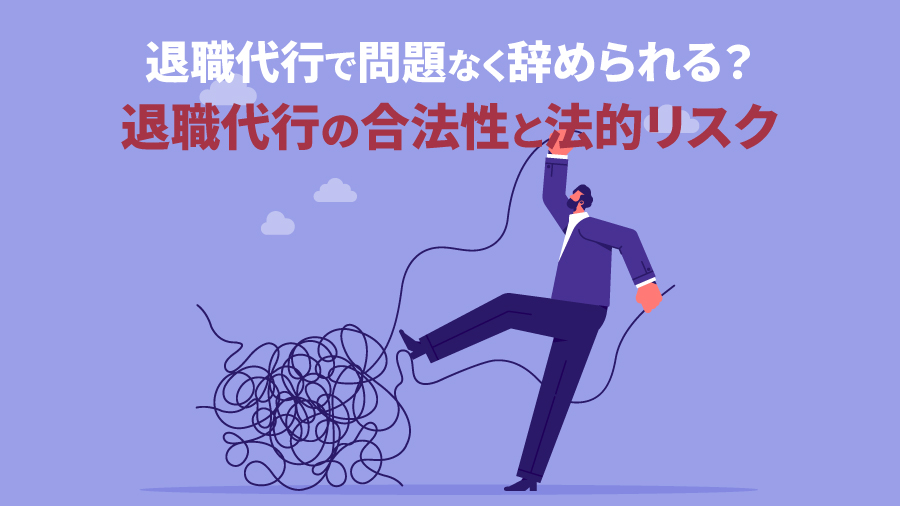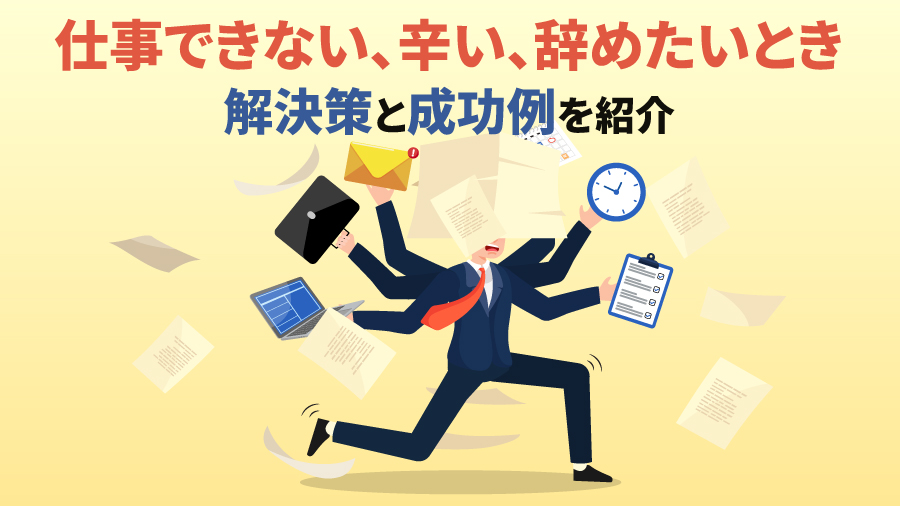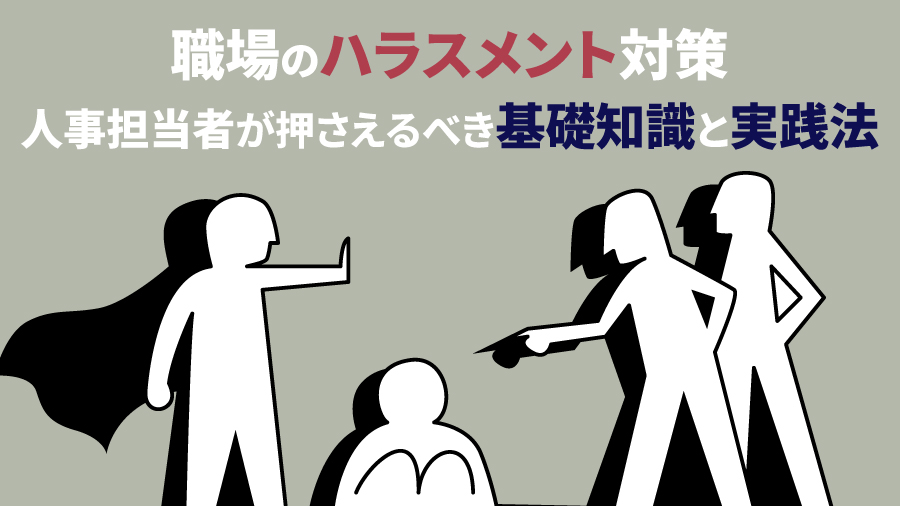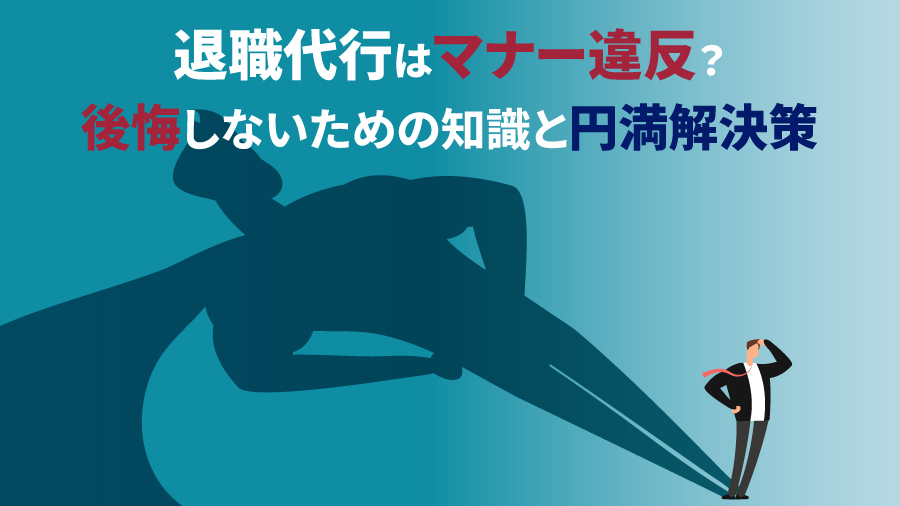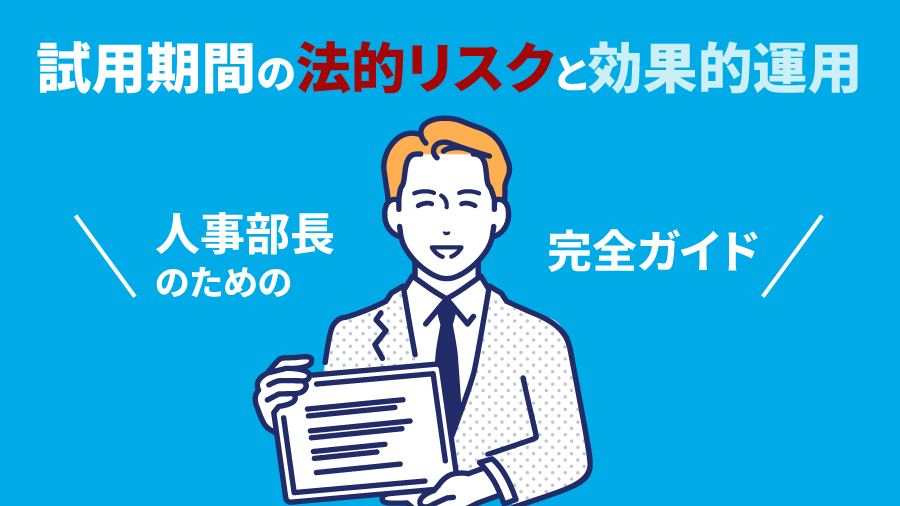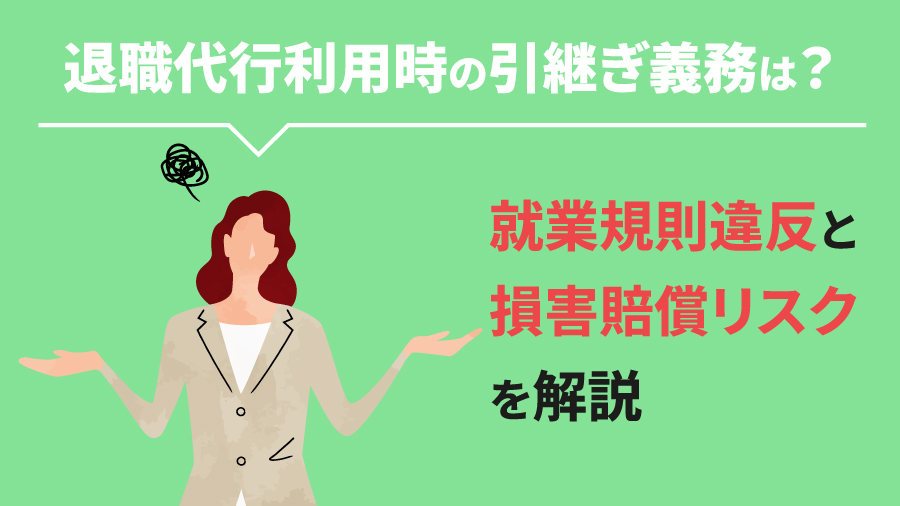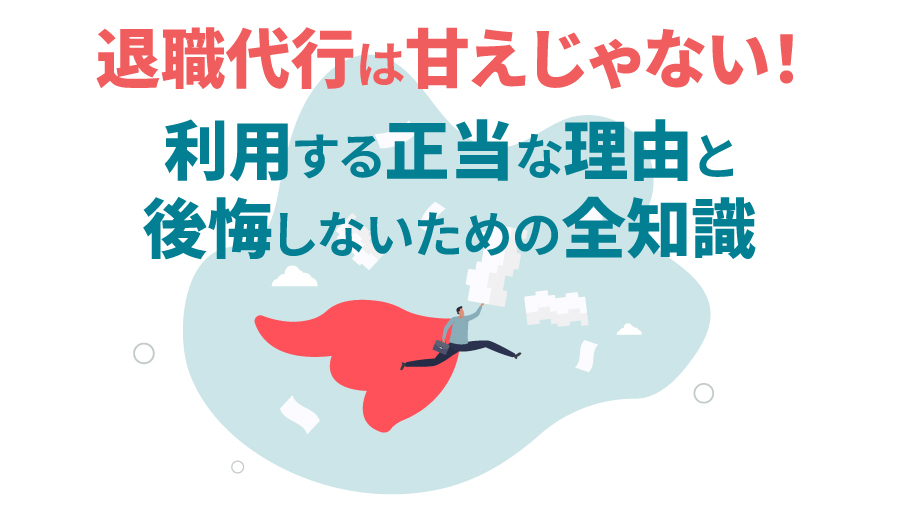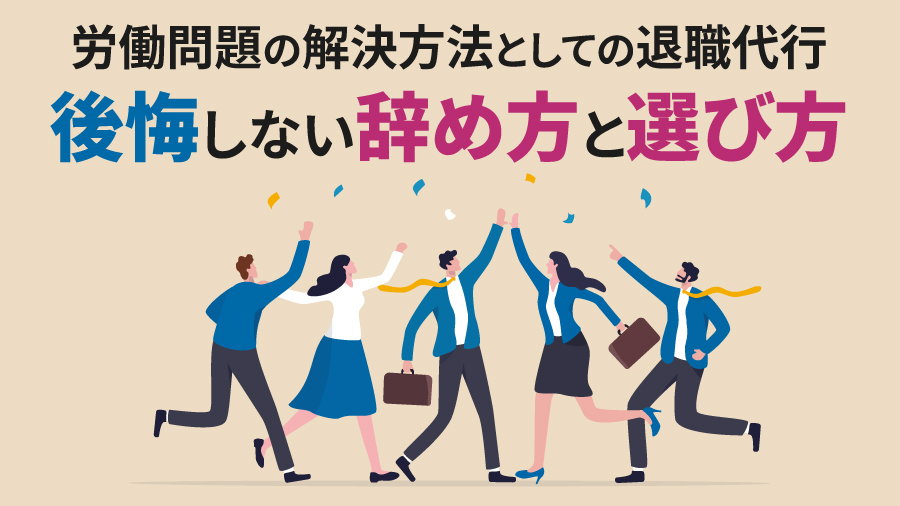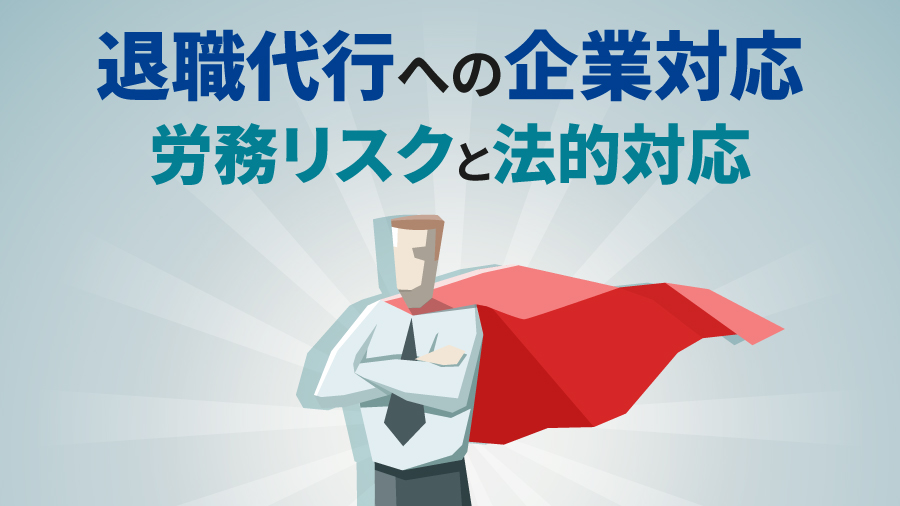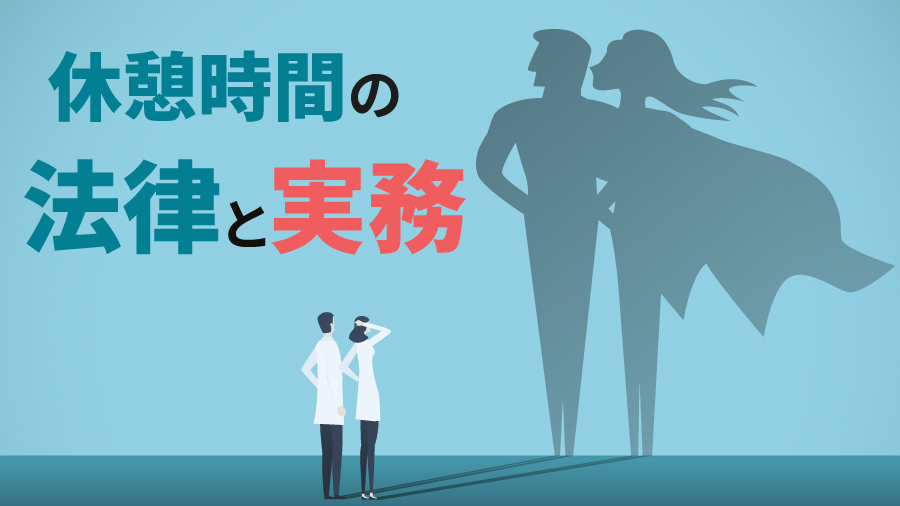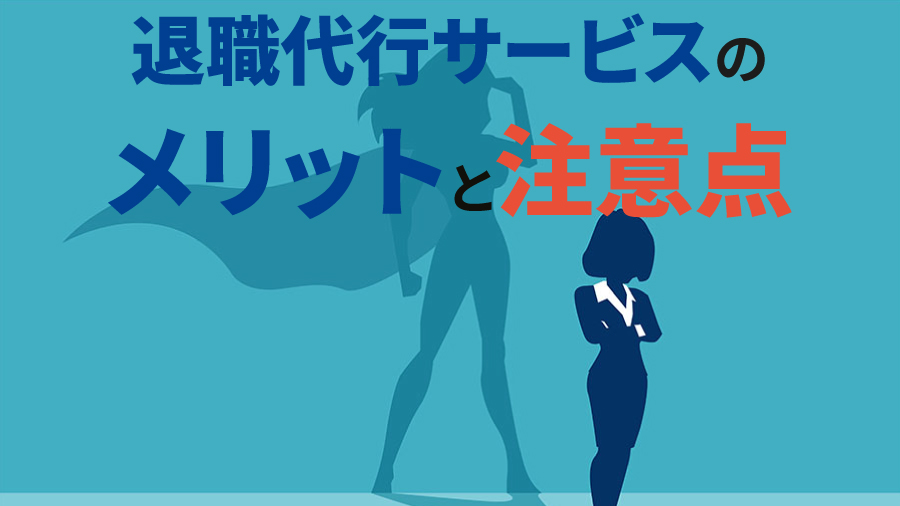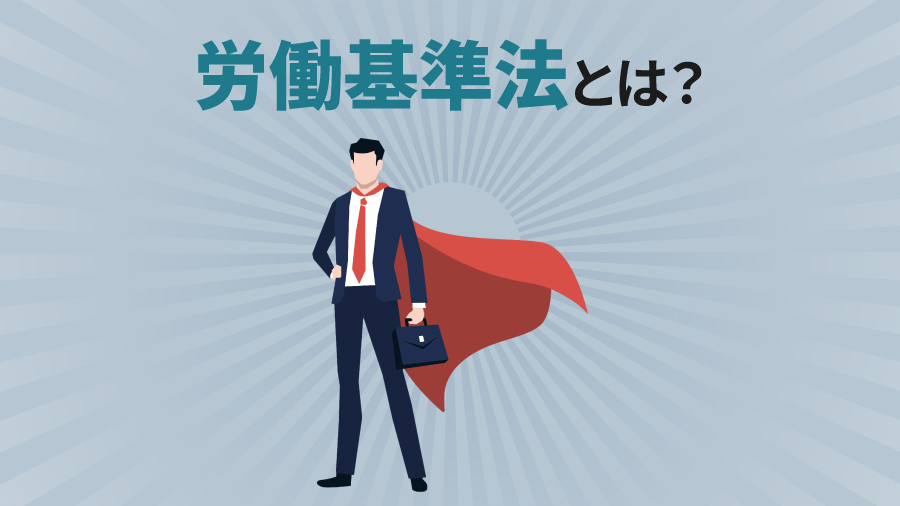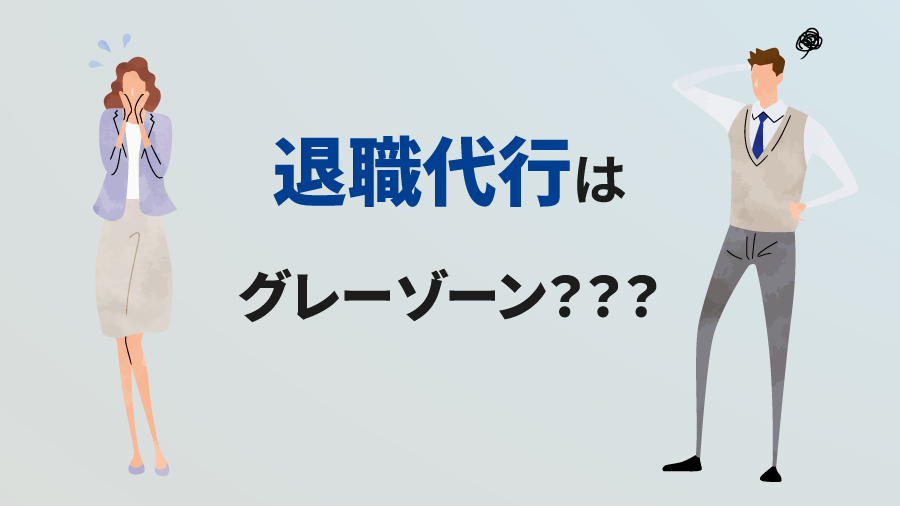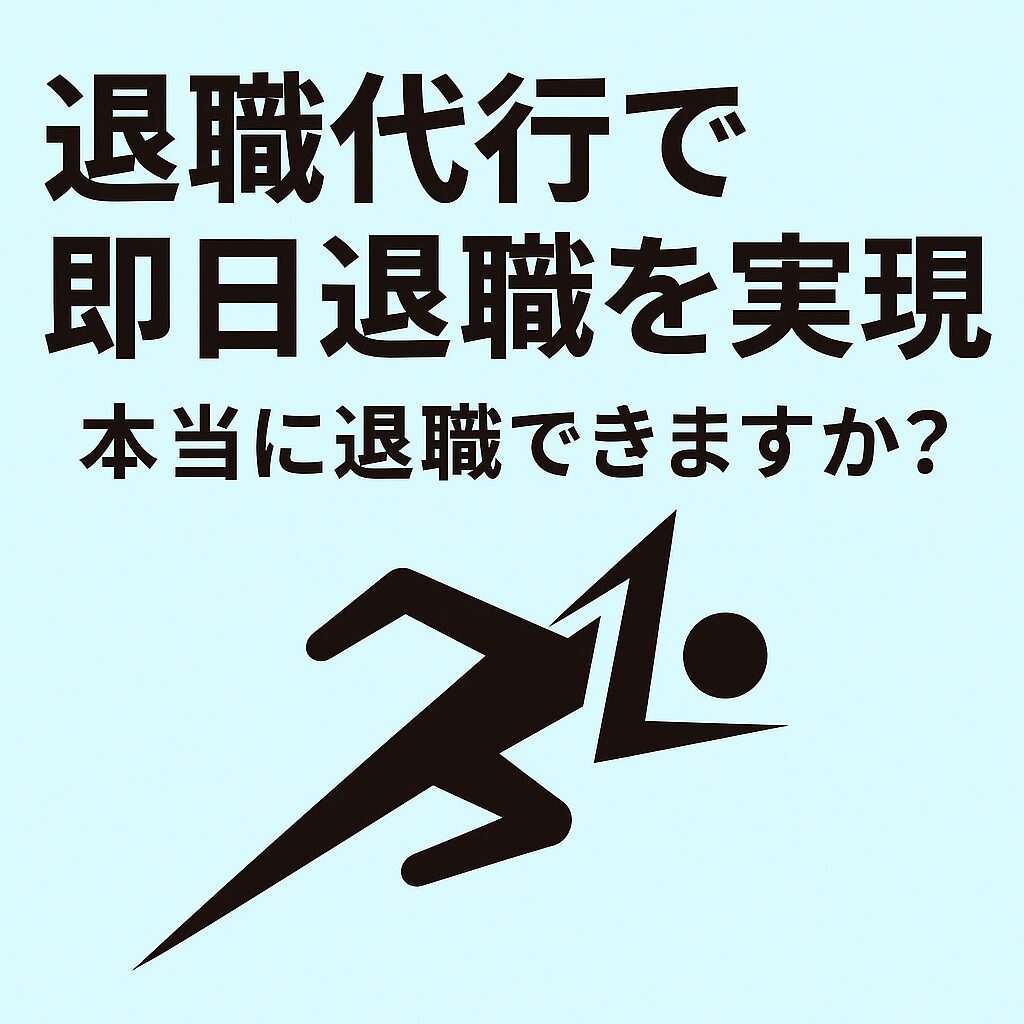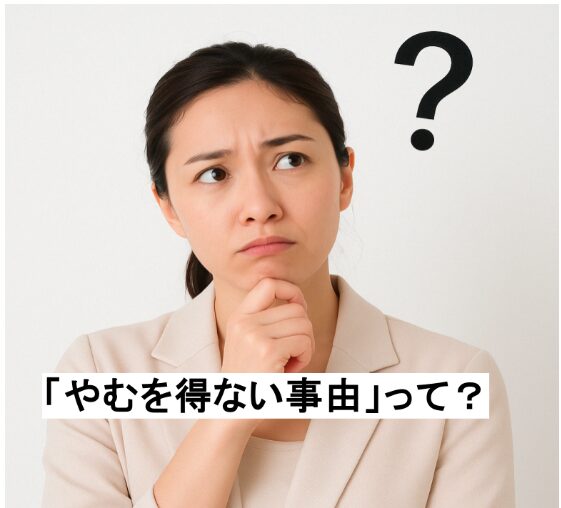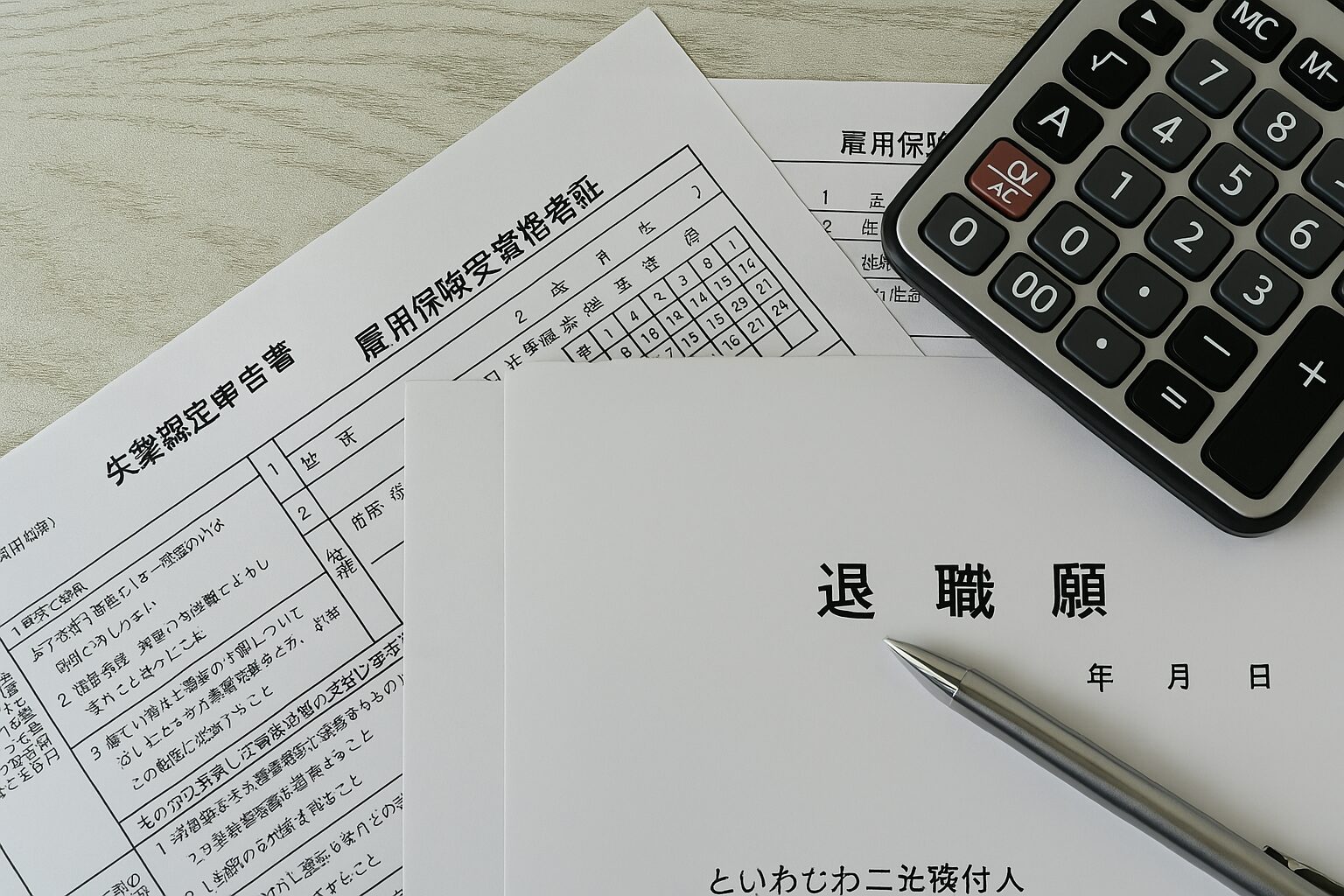-
-
仕事を辞める判断基準|プロが教える後悔しない3ステップ診断法

「このまま仕事を続けるべきか、辞めるべきか」と悩む30代会社員の方へ。本記事では人事コンサルタントが、500件以上の退職相談事例から導き出した客観的な判断基準を公開します。3分でできるストレス診断テスト、退職すべき7つの危険サイン、後悔しないための4ステップ意思決定法を解説。経済的リスク計算式や転職成功確率を高める具体的アクションプラン付きで、感情に流されない理性的な判断が可能になります。
仕事を辞める判断に必要な3要素

退職を検討する際は、感情的な判断ではなく客観的な基準に基づいた意思決定が重要です。
ここでは、人事コンサルタントが500件以上の退職相談事例から抽出した3つの重要な判断要素を紹介します。
これらの要素を総合的に評価することで、より適切な判断が可能になります。
要素1:心理的ストレスの定量化
厚生労働省のストレスチェック基準などを応用した自己診断表を活用し、心理的ストレスを数値化します。
例えば、「1週間に3回以上の不眠」や「1ヶ月で3kg以上の体重変動」などの項目をチェックし、合計スコアが基準値を超えた場合は要注意です。
数値化することで、感覚的な「辛さ」を客観的に評価できます。
また、ストレス要因を「人間関係」「業務負荷」「評価制度」に分類し、改善不可能な要素の割合が70%を超える場合は、退職を真剣に検討する必要があります。
モチベーション低下が継続する環境では、キャリアプランの見直しが必要となります。
要素2:市場価値の客観的評価
スキル診断フローチャートなどを使用し、自身の市場価値を客観的に評価します。
例えば、「プロジェクト管理経験5年以上」の場合、IT業界では平均年収が上昇する可能性が高いですが、製造業では需要が限定される傾向があります。
また、AIを活用したスキルマッチング分析ツールを使用し、転職成功確率を算出します。
この確率が60%未満の場合は、退職前にスキルアップや資格取得を検討することをおすすめします。
キャリアチェンジを考えている場合は、現職で取得可能な資格や経験をリストアップし、市場価値を高める準備をしましょう。
要素3:経済的影響シミュレーション
退職後の経済的リスクを具体的に把握するため、退職金・失業給付金計算と生活費を組み合わせたシミュレーションを行います。
例えば、月々の固定費を1.3倍した金額を6ヶ月分確保することを推奨します。
具体的には、月25万円の支出がある場合、195万円の生活防衛資金が必要となります。
また、失業給付金の受給条件や待機期間を考慮し、「自己都合」か「会社都合」かで準備期間を3ヶ月程度調整することが重要です。
収入途絶リスクを最小化するため、複数のシナリオを想定したシミュレーションを行い、最悪のケースに備えた対策を立てましょう。
退職後の収入構造の変化、生活費の見直し、再就職までの期間など、様々な要素を考慮に入れることで、より現実的な経済計画を立てることができます。
退職すべき7つの危険サイン診断

退職を検討する際、客観的な判断基準として「7つの危険サイン」を活用することで、感情に流されない意思決定が可能になります。
これらのサインは、産業医の臨床データと人事コンサルタントの経験に基づいて策定されており、身体的・組織的な観点から総合的に評価します。
1.身体的危険信号:慢性的な疲労感
慢性的な疲労感が続くことは、身体や心が過剰なストレスにさらされている危険信号です。
例えば、疲れが取れない状態が長く続く、体調不良が長引くなど、身体的な症状が顕著な場合は、退職を検討するべきです。
特に、残業や休日出勤が多く、ワークライフバランスが崩れている場合、心身ともに健康を損なうリスクが高まります。
慢性的な疲労は、免疫力低下やメンタルヘルスの悪化を招き、長期的には重大な健康問題につながる可能性があります。
早期にストレス管理を行い、環境の見直しを検討することが重要です。
2.身体的危険信号:睡眠障害
睡眠障害が続くことは、精神的なストレスが高まっている兆候です。
例えば、毎朝起きられない、夜中に目が覚めて上手く寝られないなどの症状が見られる場合、職場環境が原因である可能性があります。
このような状態が続くと、メンタルヘルスに悪影響を及ぼす可能性があるため、環境の見直しが必要です。
睡眠障害は、集中力低下や判断力の低下を引き起こし、仕事のパフォーマンスにも影響を及ぼします。
ストレス管理やリラクゼーション技法を活用し、睡眠環境を改善することが重要です。また、医師の診断を受けることも推奨されます。
3.身体的危険信号:体調不良
体調不良が長く続くことは、過剰なストレスの影響を受けている証拠です。
例えば、仕事のことを考えるとお腹が痛くなる、出勤前に体調不良になるなどの症状が見られる場合、退職を検討するべきです。
これらの症状は、精神疾患やうつ病のリスクを高める可能性があるため、早期に改善策を講じることが重要です。
体調不良が続く場合、医師の診断を受け、ストレス管理やリラクゼーション技法を活用することが推奨されます。
また、職場環境の見直しやキャリアプランの再検討も必要です。
4.組織的危険信号:人間関係の悪化
会社の人間関係が悪く、仕事が円滑に進まない場合、退職を検討するべきです。
特に、ハラスメントや不適切な扱いを受けている場合、精神的なストレスが高まり、健康に悪影響を及ぼす可能性があります。
人間関係の改善が難しい場合、環境の変更が必要です。
人間関係の悪化は、職場でのモチベーション低下やストレス増加を招き、長期的にはメンタルヘルスに悪影響を及ぼす可能性があります。
早期に問題を認識し、改善策を講じることが重要です。改善が見込めない場合は、新たな環境でのキャリアを検討することも一つの選択肢です。
5.組織的危険信号:評価制度の不透明性
会社の評価制度が不透明で、自分の努力や成果が正当に評価されていないと感じる場合、モチベーションが低下しやすいです。
特に、昇進の見込みがない場合、キャリアの停滞を感じ、退職を検討する理由となります。
評価制度の改善が見込めない場合は、新たな環境での成長を考えるべきです。
評価制度の不透明性は、従業員の満足度低下や離職率の上昇を招く要因となります。
キャリアプランの見直しや新たな職場でのチャレンジが必要です。
また、評価制度の改善を求めるための具体的な提案を行うことも有効です。
6.組織的危険信号:社風と価値観のズレ
会社の社風や価値観が自分と合わなくなった場合、不満やストレスを抱えやすくなります。
特に、倫理観や道徳観に問題がある場合、精神的な負担が増し、退職を検討するべきです。
自分の価値観に合った環境を見つけることが重要です。
社風や価値観のズレは、職場でのモチベーション低下やストレス増加を招き、長期的にはメンタルヘルスに悪影響を及ぼす可能性があります。
早期に問題を認識し、改善策を講じることが重要です。
改善が見込めない場合は、新たな環境でのキャリアを検討することも一つの選択肢です。
7.組織的危険信号:優秀な社員の流出
優秀な社員が次々と辞めていく場合、会社の将来性に不安を感じることがあります。
特に、業績が悪化している場合、退職を検討する理由となります。
優秀な人材が残らない環境では、キャリアの成長が期待できず、退職を考えるべきです。
優秀な社員の流出は、組織全体の士気低下や技術力の低下を招き、長期的には企業の存続に影響を及ぼす可能性があります。
早期に問題を認識し、改善策を講じることが重要です。
改善が見込めない場合は、新たな環境でのキャリアを検討することも一つの選択肢です。
また、社員の流出を防ぐための具体的な対策を提案することも有効です。
メリット・デメリット比較

退職を検討する際、メリットとデメリットを客観的に比較することが重要です。
ここでは、精神面・経済面・キャリア面での影響を分析し、具体的な数値とリスク軽減策を提示します。
この比較表を活用することで、感情に左右されない合理的な意思決定が可能になります。
精神面の影響比較
退職によるストレス軽減効果は多くの人が実感していますが、一方で転職活動中に不安を感じる人も少なくありません。
不安を軽減するためには、認知行動療法を応用した「不安日記」の作成が効果的とされています。
具体的には、不安を感じた出来事を「状況」「自動思考」「感情」「合理的思考」の4項目に分けて記録し、自分の思考パターンを客観視することで、不安をコントロールしやすくなります。
また、日記を通じて不安の傾向を把握し、それに基づいた具体的な対策を講じることも可能です。
さらに、1日10分程度の軽い運動やマインドフルネス(呼吸法や瞑想など)を取り入れることで、気分が向上しストレスが緩和される効果も期待できます。
自分に合ったリラックス方法やストレス対策を見つけておくと、転職活動中も安心して取り組むことができます。
経済的得失分析
転職成功者の平均年収変動は業種によって異なりますが、厚生労働省の調査によると、転職者の38.6%が賃金増加、33.2%が減少を経験しており、年齢によっても傾向が異なります。
空白期間リスクを最小限に抑えるため、失業給付金の受給期間を活用したスキルアッププランが有効です。
具体的なアクションプランとしては、失業給付金の受給開始日から逆算して転職活動のスケジュールを立て、スキルアップと並行して求職活動を行うことが推奨されます。
また、オンライン講座やセミナー参加を通じて、業界の最新動向を把握し、転職先での競争力を高めることが重要です。
キャリアパス比較
職種変更成功者の多くが、退職前6ヶ月間でポートフォリオ作成を行っています。
経歴断絶リスクを回避するため、現職で取得可能な資格や社内プロジェクトの主導経験が有効です。
ある営業職からデータアナリストへ転身した事例では、Python基礎講座修了と社内データ分析プロジェクト参加が採用の決め手となりました。
具体的なアクションとしては、転職先で求められるスキルを3つ以上リストアップし、それぞれに対して具体的な実績や資格を紐づけたポートフォリオを作成することが推奨されます。
また、LinkedInなどのプロフィールを更新し、業界セミナーへの参加を通じてネットワークを拡大することで、スキルミスマッチのリスクを軽減し、新たなキャリアパスの可能性を広げることができます。
後悔しないための4ステップ
退職の意思決定プロセスを体系化することで、感情に左右されない合理的な判断が可能になります。
ここでは、人事コンサルタントが推奨する4つのステップを紹介します。
各ステップには具体的なツールと実践方法が含まれており、順序立てて実行することで、後悔のない決断に近づくことができます。
ステップ1:感情の客観化
「3行ジャーナリング」手法を用いて、感情を「事実」「解釈」「感情」に分解します。
例えば、「上司が書類を投げつけた(事実)→私の能力を否定している(解釈)→屈辱感を覚える(感情)」という構造を可視化します。
3行ジャーナリングを1週間続けることで、感情的要因と客観的事実を分離できます。
さらに、厚生労働省のストレスチェック項目を参考に、1-5のスケールで日々の状態を数値化することで、感情の変動を客観的に把握し、一時的な感情での判断を避けることができます。
また、日記を通じて、感情のパターンを把握し、具体的な対策を講じることができます。
この過程で、退職理由の正当性を客観的に評価し、自己理解を深めることができます。
ステップ2:SWOT分析実践
転職エージェント監修の分析シートを使用し、自身のスキルや経験を「強み」「弱み」「機会」「脅威」に分類します。
例えば、IT技術者の場合、「プログラミングスキル(強み)」「マネジメント経験不足(弱み)」「AI人材需要増(機会)」「年齢制限(脅威)」といった具体例を挙げながら分析します。
各項目に最低3つずつ記入し、それぞれの要素がどのように退職判断に影響するかを検討します。
SWOT分析により、自身のキャリアにおける客観的な立ち位置を把握し、退職後のキャリアプランをより具体的に描くことができます。
また、強みを活かした新たなキャリアパスを模索することで、転職後の成功確率を高めることができます。
ステップ3:シナリオツリー作成
将来の可能性を体系的に整理するため、複数のシナリオを想定した分析を行います。
具体的には「最良ケース」「平均ケース」「最悪ケース」など5つのパターンを設定し、それぞれの発生確率と経済的影響を可視化します。
例えば転職活動においては、成功確率・空白期間の長さ・収入変動幅といった要素を分類し、総合的なリスク評価を行います。
シナリオごとに以下の3段階で分析を進めます。
・シナリオの特定:転職成功/中途採用困難/キャリア変更など現実的なパターンを列挙
・影響度の分類:各シナリオの収入変動幅・期間・スキル要件を数値化
・対策の立案:最悪ケースに対応する貯蓄目標やスキル強化計画を作成表計算ソフトや専用ツールを活用し、5年間の累計収入を現職継続時と比較します。
例えば「転職成功時に想定される収入増加幅」「空白期間中の生活費」などを入力し、異なる条件での試算を並列比較します。
シナリオツリーを作成することにより、感情に左右されない客観的な判断基準が構築できます。
ステップ4:3ヶ月アクションプラン
週次目標管理表を使用し、資格取得・求人応募・面接練習などのタスクを時系列で整理します。
例えば、TOEIC800点取得を8週目、模擬面接実施を10週目と設定し、計画的に準備を進めます。
具体的なアクションプランとしては、1週間ごとのマイルストーンを設定し、毎週日曜日に進捗をチェックします。
また、転職サイトのプロフィール更新や業界セミナーへの参加なども計画に組み込みます。
具体的なアクションプランを立てることで、漠然とした不安を軽減し、退職後の方向性を明確にすることができます。
さらに、週次レビューを通じて、計画の遅れや進捗状況を把握し、必要に応じて調整を行います。
具体的なアクションプランを設定することで、転職活動スケジュールを最適化し、空白期間対策を効果的に実施することができます。
まとめ
退職の判断は、キャリアの重要な分岐点となる決断です。
特に、数値化されたデータや具体的なツールを使用することで、より合理的な意思決定ができます。
退職は「逃げ」ではなく、キャリア構築のための戦略的選択肢の一つです。
自身のキャリアプランに基づいた慎重な判断を心がけ、後悔のない選択をしてください。
-